ある程度の曲尺がある楽曲では
フォルテ以上のダイナミクスの箇所は
一曲の中で何回か出てくるはずです。
それらをどうやって演奏すれば
効果的に聴かせることができるのでしょうか。
ポイントのひとつは
「聴衆の耳を慣れさせない」
ということです。
人間の耳には「慣れ」があるので、
フォルテの音に聴衆の耳が慣れてしまうと
フォルテの効果が活きなくなってしまいます。
◉ フォルテのパッセージの中でも、重みを入れる音と軽く弾くべき音を見きわめる
◉ フォルテ以外のダイナミクスのところで不注意に大きくならないこと
この2つを心がけましょう。
音楽は相対的なものですので、
ある箇所を効果的に聴かせたいのであれば、
その前後を工夫する必要があるということ。
具体例として、オーケストラの「ティンパニ」を挙げます。
ティンパニの「トレモロ(ロール)」はフォルテで演奏すると
とても迫力があります。
しかし、迫力を出す時にずっとロールしていればいいわけではない。
力のある作曲家は、
聴衆の耳を慣れさせないように
必ず間引いたりすることで
叩くところをしぼり込んで効果的に使っています。
作曲されている以上、曲自体は変えられませんので、
「それを演奏における注意点としてやろう」
ということを言いたいのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!
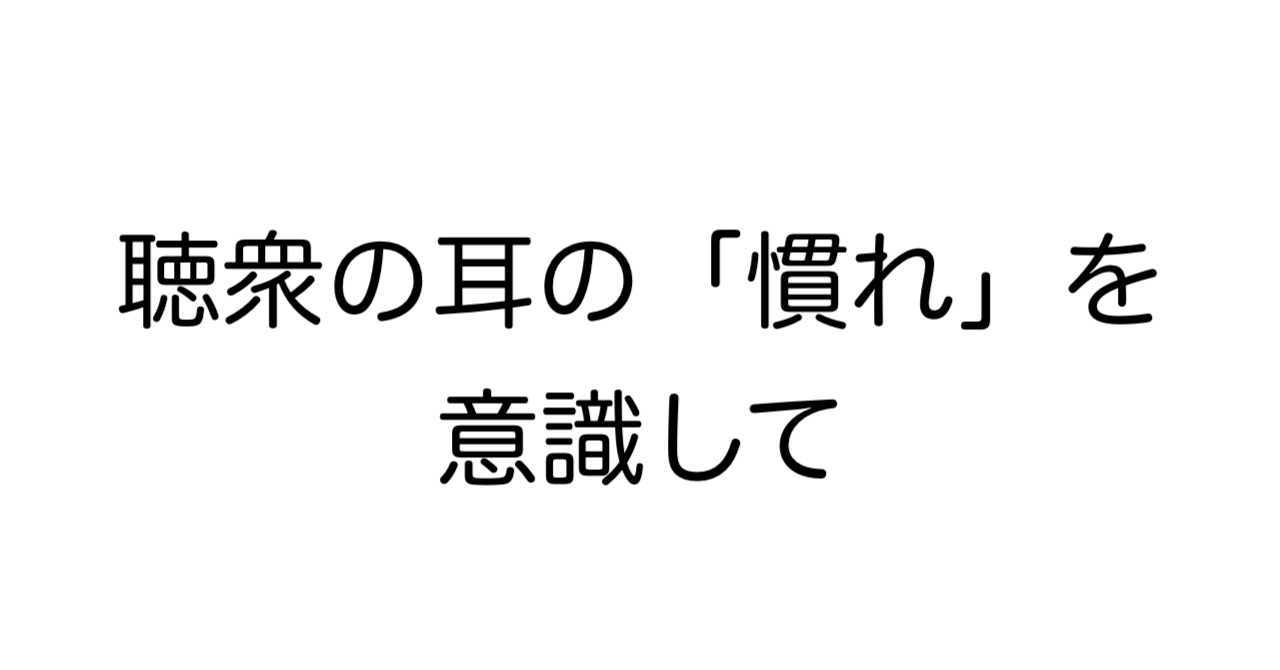
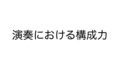
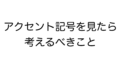
コメント