アクセント記号というと、
「記号が付けられた音を強調して演奏する」
という意味が広く知られています。
もちろんその認識で良いのですが、
ピアノ演奏に余裕が出てきた学習者は
アクセント記号を
「強調する」だけでなく、
「どのような表情で強調すべきか」
ということも考えていきましょう。
具体例を挙げます。
楽曲が変わっても考え方は応用できます。
ショパン「ワルツ第10番 op.69-2」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

カギマークで示した
アクセントが付けられた2つの音を見てください。
「D-Cis」というように
2度音程下がっていく段になっています。
これを見落として
「単に強調して演奏する」
と思ってしまうと
無意味にふたつの同じ強さの音が並んでしまいます。
ここでは、
D音よりもCis音の方が目立ってしまうと音楽的に不自然です。
段になるように
アクセントが付けられた音同士のバランスをとりましょう。
さらに大切なのはここから先。
「どのような表情で強調すべきか」
ということを考えてみましょう。
(再掲)

この楽曲全般で言えることなのですが、
各小節3拍目のアクセント付きの音は
次の1拍目を先取している音です。
シンコペーションのリズムが特徴的。
曲頭のアウフタクトから
早速この特徴が出てきていますね。
そこで、
「強く」というよりは
シンコペーションを伝えてあげる意味でも
「置くようなタッチで重みをいれる」
というイメージを持って打鍵するといいでしょう。
「強く」と思って上からカツン!と打鍵してしまうと、
この楽曲の表情に合わない音色が出てしまいます。
どんな楽曲であっても、
アクセントを見かけた時は
「どのような表情で強調すべきか」
という観点を重視して譜読みしましょう。
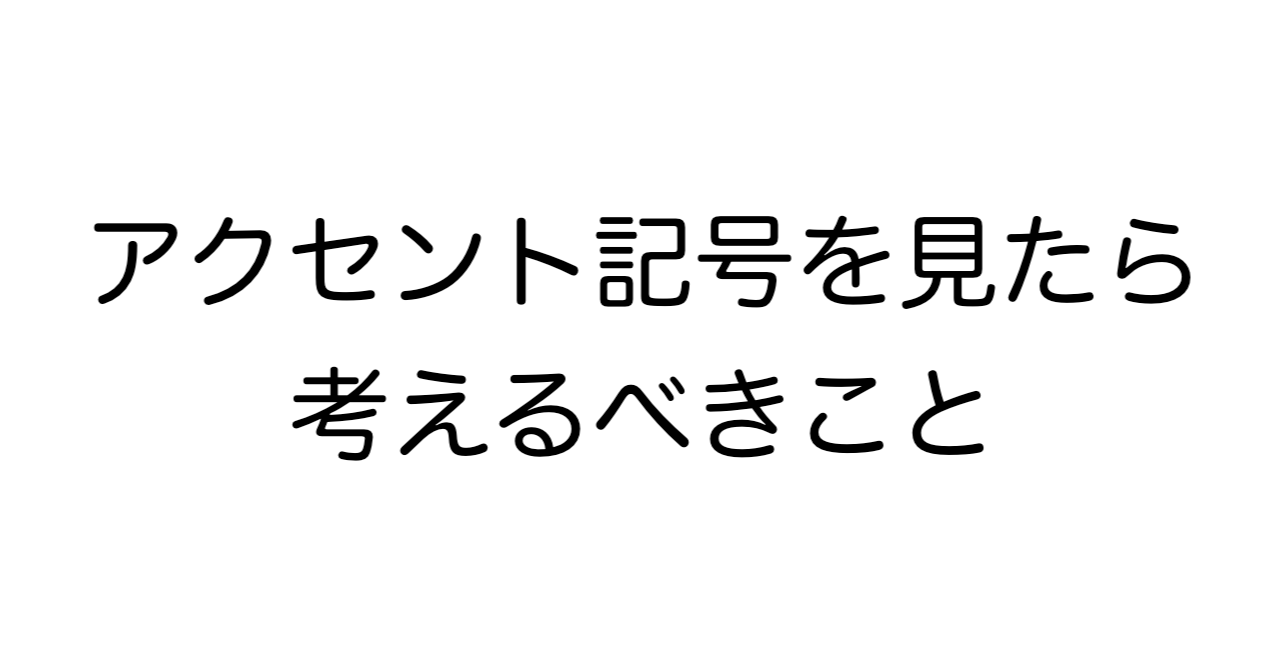
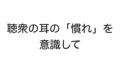
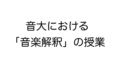
コメント