フレーズ同士の関係分析では、
「対話関係を見つけること」
これがもっとも基本です。
具体例を見てみましょう。
楽曲が変わっても考え方は応用できます。
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-39小節)
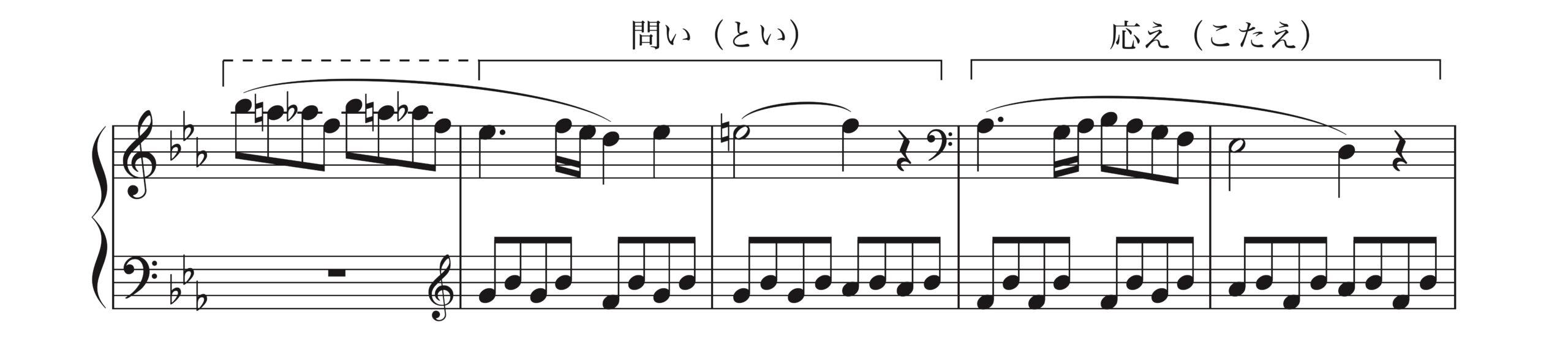
メロディ部分に書かれた
「問い(とい)」と「応え(こたえ)」
に注目してください。
「問い(とい)」
で疑問を投げかけるように提示し
それを解決するかのように
「応え(こたえ)」
が続きます。
このような「問い(とい)」と「応え(こたえ)」
はあらゆる楽曲に出てきますので、
まずはこれを探してみるのが、
フレーズ同士の関係分析としての出発点です。
実は、
新ウィーン楽派などの「無調作品」でも使えることが多い
大事な分析観点です。
(再掲)
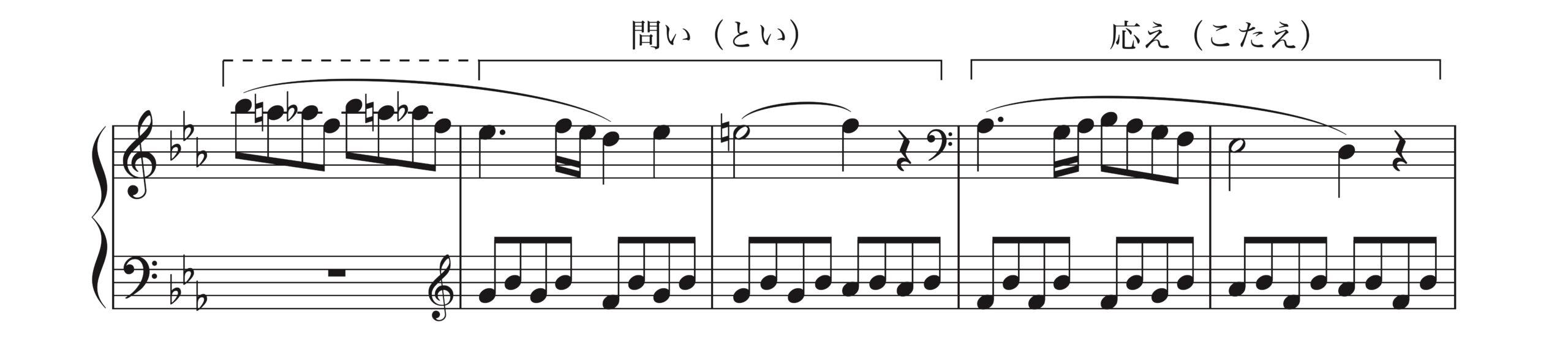
それらのフレーズが
「問い(とい)」と「応え(こたえ)」になっていることを
見分ける方法は
実は「勘(カン)」。
しかし、
今回の譜例のように
「手が交差してメロディを演奏する場合」
この場合には、
「問い(とい)」と「応え(こたえ)」になっていることが多い傾向にあります。
(K.311の第1楽章などでも類似例が出てきます。)
また、今回の譜例のように、
◉ 類似した形のメロディが連続する場合
◉ 音域の離れたメロディが連続する場合
◉ 音域の離れたメロディが連続する場合
これらの場合にも
「問い(とい)」と「応え(こたえ)」
の関係を疑ってみましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
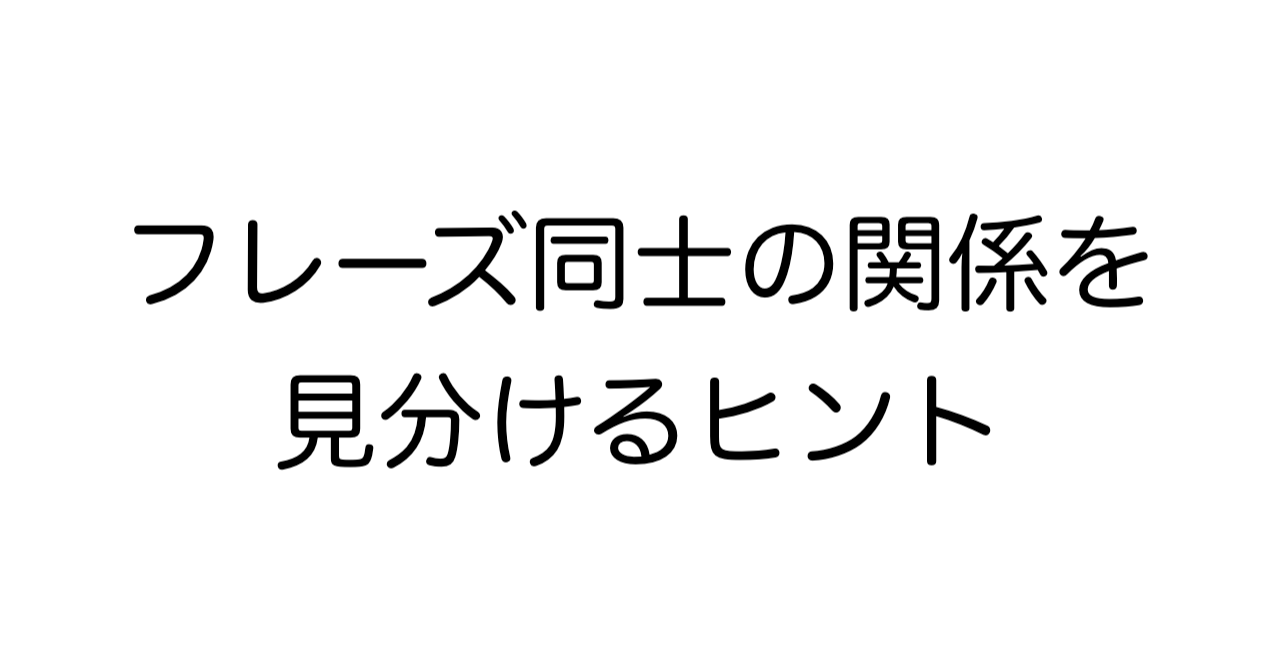
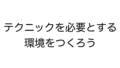

コメント