■時代別に学ぶ「装飾音符の基礎」
♬「拍の前に出す」装飾音符
作曲家や作品によって
装飾音符を「拍の前に出すか出さないか」は異なりますので、
最終的には楽曲ごとに見ていかなくてはいけません。
ただし、全体的な傾向はあります。
ロマン派以降の作品の装飾音符は
基本的には「拍の前に出す」のが慣例となっています。
現代音楽になると、装飾音符の入れ方まで作曲家による指示があることも。
「拍の前」に出す装飾音符で
譜読みのときに意識すべきなのは、
「装飾音符がかかっている先の大きな音符(幹の音)が、原則、時間通りの位置にくる」
ということ。
この幹の音が正しい位置にこないと
曲の骨格がくずれてしまいます。
最終的にどう演奏するのかは奏者に任されていますが、
譜読みの段階では
まず、この時間通りの位置を知っておかなければいけません。
「装飾音符を取り払って練習してみる」
というのも
骨格をつかむためには効果的な練習方法でしょう。
♬ 例外:ショパンの装飾音符
先ほど、
「ロマン派以降の作品の装飾音符は、基本的には拍の前に出すのが慣例」
と書きましたが、
例外を挙げておきましょう。
「ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる」 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社
という書籍には、
以下のように書かれています。
(以下、抜粋 番号は補足)
①
ショパンの前打音奏法の基本的な特徴として
前打音をつねに拍と同時に弾くことが挙げられる。
このことは
彼の弟子の楽譜に
前打音とそれに対応するバスとを結んだ縦の線が
数多く書き込まれていることから明らかである。
②
ショパンが長いトリルを
つねにバスと同時に弾きはじめていたことは
弟子の楽譜へ記された多くの縦の線が示している。
③
ショパンはアルペッジョについても
バスと同時に弾きはじめる方法を用いており、
彼の弟子の楽譜には
そのことを示す縦の線がしばしば書き込まれている。
(抜粋終わり)
この書籍では
豊富な譜例とともに
ショパンの装飾音について解説されていますので、
とても参考になります。
◉ ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社
♬「拍の前に出さない」装飾音符
モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)
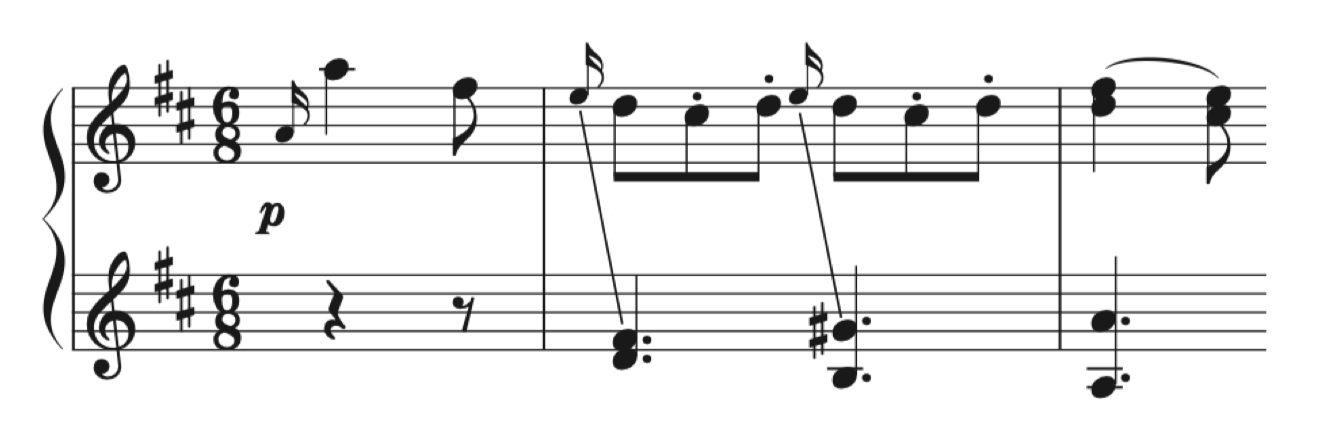
バロックや古典派の作品の装飾音符は
基本的には「拍の前に出さない」のが慣例となっています。
1小節目(アウフタクトは1小節に数えません。)にラインを入れましたが、
このように
装飾音符は前へ出さずに
拍頭の音と合わせて演奏します。
装飾音符は極めて「短く」入れないと
リズムが曖昧になってしまいますので
気をつけましょう。
♬ モーツァルトの装飾音符の勉強方法
以前の記事で、
レオポルド・モーツァルトが書いた「ヴァイオリン奏法」という本をご紹介しました。
こちらを参考にするのはもちろんオススメですが、
他にも、
「奏法譜から学ぶ」
という勉強方法もあります。
ヘンレ版の「モーツァルト ソナタ集」では、
別紙で「装飾音符の奏法譜」が付属してきますので
それを参考に勉強できます。
エルンスト・ヘルトトリッヒの校訂による
1977年に出版されたものが
現在出回っているもの。
ただし、応用できるようにするためには
そのまま弾くのではなく
「どのように装飾を入れているのかつぶさに研究してみること」
これが重要。
それによって、
「こういうパターンの時はこのように装飾音符を入れればいいんだ」
などと自分の糧にしていくことができます。
ヘンレ版などの「信用のある版」による奏法譜だからこそ
取り組んでみる価値はあるでしょう。
◉ モーツァルト: ピアノ・ソナタ集 第1巻/ヘンレ社/原典版
◉ モーツァルト: ピアノ・ソナタ集 第2巻/ヘンレ社/原典版
◉ レオポルトモーツァルト ヴァイオリン奏法 [新訳版]
♬ なぜ?「トルコ行進曲」の装飾音符の疑問
モーツァルト「ピアノソナタ第11番 K.331(トルコ行進曲付き) 第3楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

このように、
16分音符で弾く音符が装飾音符で書かれていて
「なぜ?」
と思ったことはありませんか?
これには研究があり、
「非和声音は拍頭につけるときには大きい音符でつけてはいけない」
という習慣がこの時代にあったと
音楽学で明らかになっています。
モーツァルトの装飾音について
さらに本格的に学びたい場合は、
以下の書籍を参考にしてください。
◉ 新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
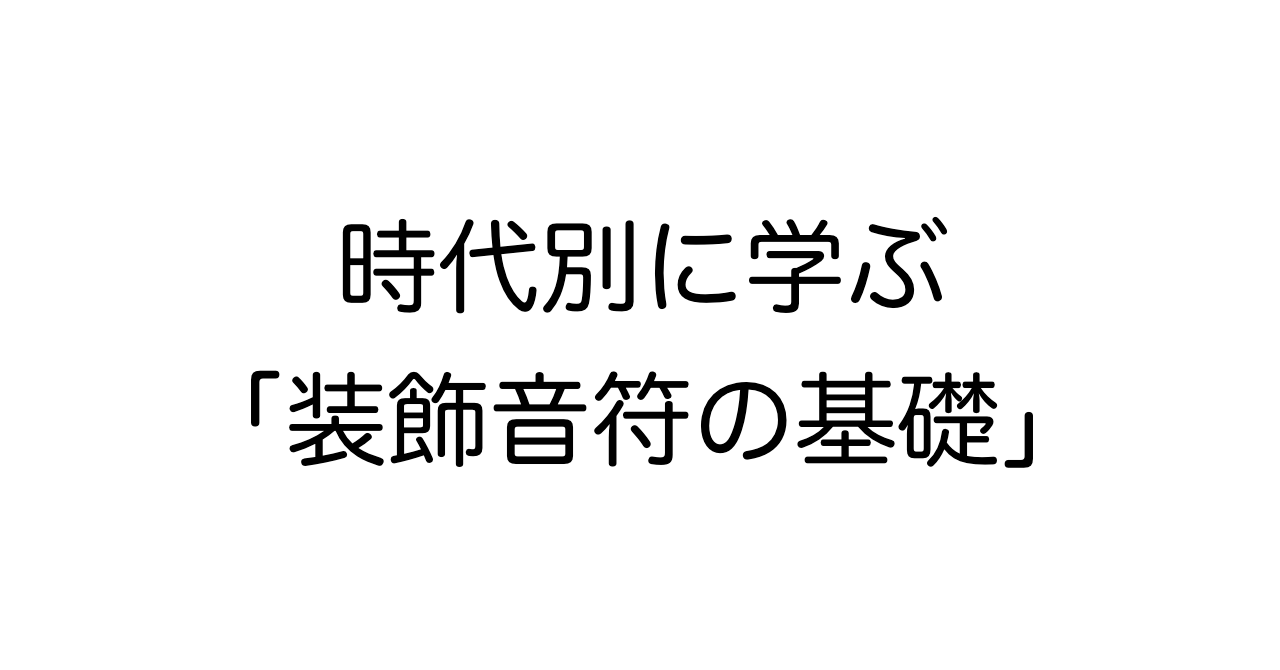



![レオポルトモーツァルト ヴァイオリン奏法 [新訳版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41tO+Sxr+-L._SL160_.jpg)

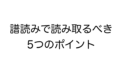
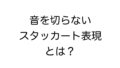
コメント