「ピアニストからのメッセージ 演奏活動とレッスンの現場から」
ボリス ベルマン (著)、阿部 美由紀 (翻訳) 音楽之友社
の記述によると、
ピアニストのブレンデルは
「Musical Thoughts and Afterthoughts」という著作の中で
以下のように解説しているそうです。
(以下、抜粋)
(ピアノで)ホルンの高貴で豊かな、幾分ベールがかかったような『ロマンティックな』音を出すには、
腕を緩めて手首をしなやかにしておく必要がある。
ホルンのダイナミクスの幅は pp から f に及ぶが、常にソフトペダルを使用すること。
腕を緩めて手首をしなやかにしておく必要がある。
ホルンのダイナミクスの幅は pp から f に及ぶが、常にソフトペダルを使用すること。
(抜粋終わり)
最後の、
「常にソフトペダルを使用すること」
というのは
考えてみるべきテクニック。
弱奏のときに
音量サポートや音色づくりとして
ソフトペダルを取り入れることは
普段からあると思います。
一方、逆の発想として
「強奏のときの音色づくりとしてソフトペダルを取り入れる」
というのが
抜粋文章のやり方で狙われていることのひとつ。
「弱音器」「弱音ペダル」などという言葉に左右されすぎず、
強奏で使うことも引き出しへ入れておくと
音色の幅が広がるでしょう。
◉ ピアニストからのメッセージ 演奏活動とレッスンの現場から ボリス ベルマン (著), 阿部 美由紀 (翻訳) 音楽之友社
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
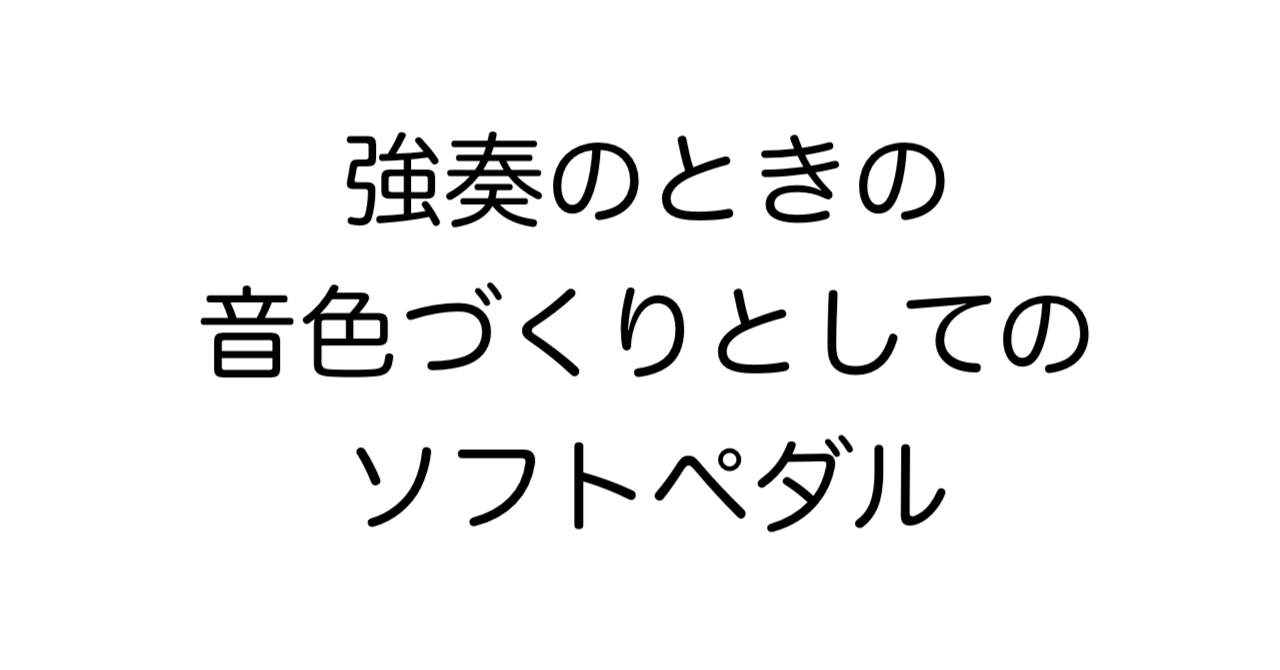

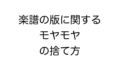
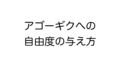
コメント