先日のブログで以下のことを書きました。
「出したい音(色)を自分の中で鳴らすこと」
「出したい音(色)を自分の中で鳴らせるようになる」ために必要なのは、
「ピアノが出せる音(色)の可能性をひとつでも多く知っておくこと」
そして、
「一曲を深く学ぶこと」
これが欠かせません。
では、
「ピアノが出せる音(色)の可能性をひとつでも多く知っておくこと」
この部分を伸ばすためには
どのような勉強方法があるのでしょうか。
ピアノについて詳細に書かれた書籍を読むのもいいですが、
それ以外に効果的なのは、
「”オケ中ピアノ” がある楽曲を聴いてみる」
という方法。
「オケ中ピアノ(おけなかぴあの)」
というのは、
オーケストラの中に
「数あるパートのうちのひとつとして」
ピアノが取り入れられている場合の
ピアノパートの呼び方です。
「ピアノ協奏曲」は
オーケストラの中にピアノが存在しますが、
ピアノが主役なので
通常は「オケ中ピアノ」とは言いません。
なぜこういった呼び名がついたのでしょうか。
実は、
ピアノという楽器はオーケストラの中においては
「編入楽器扱い」です。
つまり、
通常のオーソドックスなオーケストラでは
ピアノには席が与えられていないのです。
そこで、
作曲家の意志によって
「編入楽器として変則的にピアノを入れている」
というわけなのです。
「オケ中ピアノが存在しない楽曲」が多いのも
こういった理由から。
ではなぜ、
「”オケ中ピアノ” がある楽曲を聴いてみる」
という方法が
「自身がまだ把握していないピアノの可能性を知るためにできる勉強方法」
として有効なのでしょうか。
それは、
「ピアノソロ楽曲の場合とは根本的に違う役割が与えられていることが多いから」
という理由。
もう少しわかりやすく解説します。
ピアノは
◉ 一度に多くの音を出してハーモニーを聴かせる
◉ バスラインを奏でる
など、
さまざまなことを一度にできます。
一方、
これらのことは
オーケストラの各楽器が力を合わせれば
どれもできてしまうことなのです。
では、
「オーケストラにはできなくてピアノにだけできること」
は何であるのか考えてみてください。
答えはシンプル。
「ピアノという楽器自体の音色を聴かせること」です。
オーケストラはどんなに力を合わせても
ピアノと同じ音色を出すことはできません。
「オケ中ピアノ」としてのパートは
「ピアノという楽器自体の音色を聴かせること」
に主眼が置かれている場合が多いので、
当然ながら
ピアノソロで多く使われるような
「アルペジオ伴奏」
「メロディ演奏」
だけでなく、
「打楽器的な奏法でピアノの音色を強調する」
「あえてピアノの最高音域や最低音域の音を聴かせる」
などといった使い方が多くあるのです。
ピアノソロ楽曲だけを聴いていては
なかなか耳にできないピアノの使い方を
知ることができるでしょう。
また、
「楽器の王様」
「オーケストラ」
などと呼ばれることが多い「ピアノ」という楽器でさえも
オーケストラの中では
「意外と聴こえてきにくい」
ということに気づくことができると思います。
“オケ中ピアノ” がある楽曲を聴いてみることで
ピアノについてさらに詳しくなりましょう。
繰り返しますが、
「出したい音(色)を自分の中で鳴らせるようになる」ために必要なのは、
「ピアノが出せる音(色)の可能性をひとつでも多く知っておくこと」
これにあります。
「オケ中ピアノ」で調べれば
具体的な楽曲がたくさん出てきますが
曲頭からピアノが登場する、
ドビュッシー : 交響組曲「春」
などは
ピアノの音もはっきり聴こえるのでオススメ。
音源だけで聴いてもいいですが、
ピアノの楽譜が読めれば
オーケストラの楽器の楽譜も半分以上は読めるので
スコアを片手に聴いてみるのも勉強になるでしょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
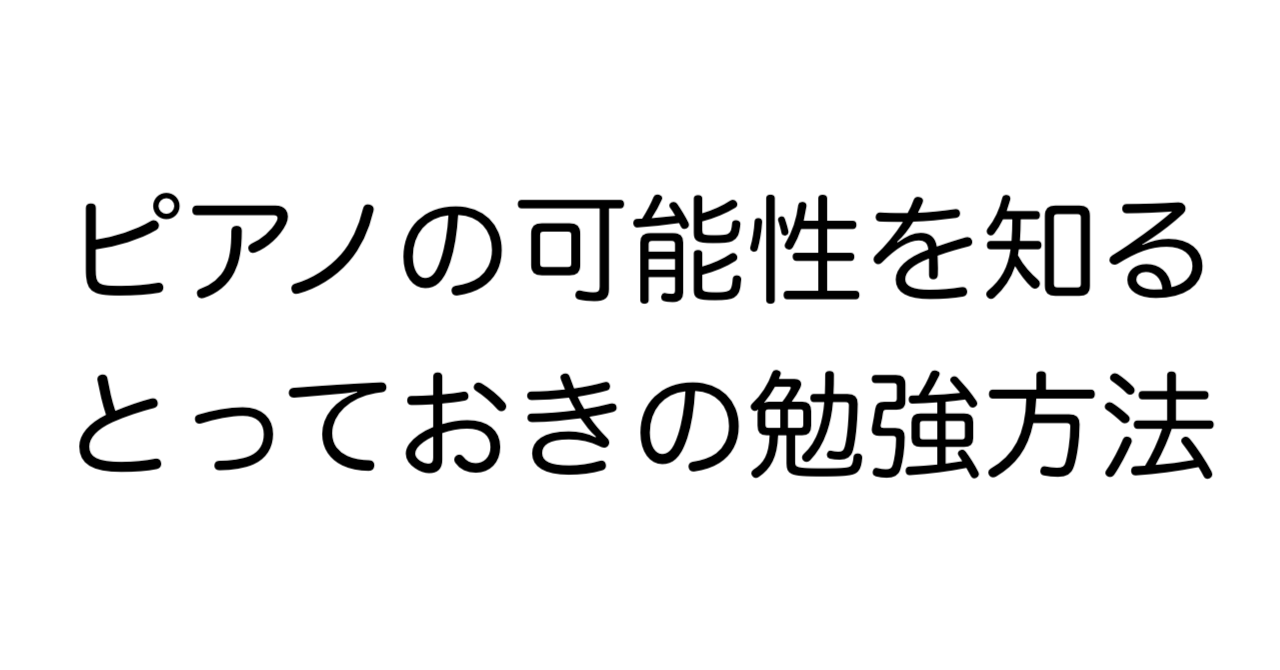
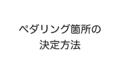
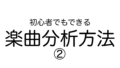
コメント