具体例を挙げます。
楽曲が変わっても考え方は応用できます。
モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)
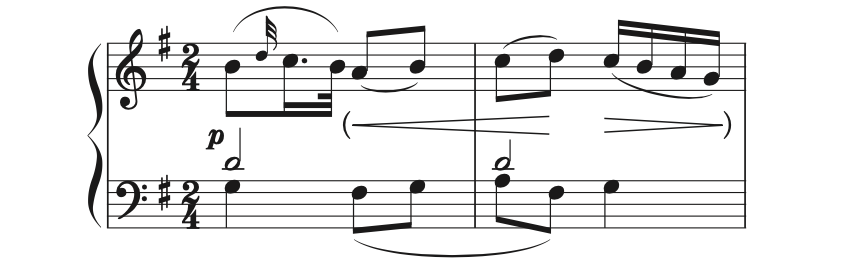
括弧つきのダイナミクスの松葉は
原曲には書かれていません。
しかし、
音楽の方向性を考えると
実際にはこのように演奏するべきです。
一般的に、
作曲家自体が絶対に表現して欲しいと思っていることは
ダイナミクス指示を書いてくれていますが、
それ以外の
フレージングから読み取れる今回のような部分は
演奏者自身が表現していかなくてはいけません。
読み取るポイントとしては、
「楽式論」で「重心」などの項目を学ぶことがいちばんですが、
メロディを口で歌ってみるだけでも
どこにヤマやタニを作ればいいか判断できるはず。
そのフレーズがヤマなのかタニなのかを、
ダイナミクス指示で書かれていなくても読み取ることが重要。
そして、こういったことも譜読みのうちに含まれる。
ダイナミクス指示で書かれていなくても読み取ることが重要。
そして、こういったことも譜読みのうちに含まれる。
全部均等の「1拍子の集合」
みたいに演奏してしまわないように注意しましょう。
◉ 楽式論 石桁真礼生 著(音楽之友社)
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
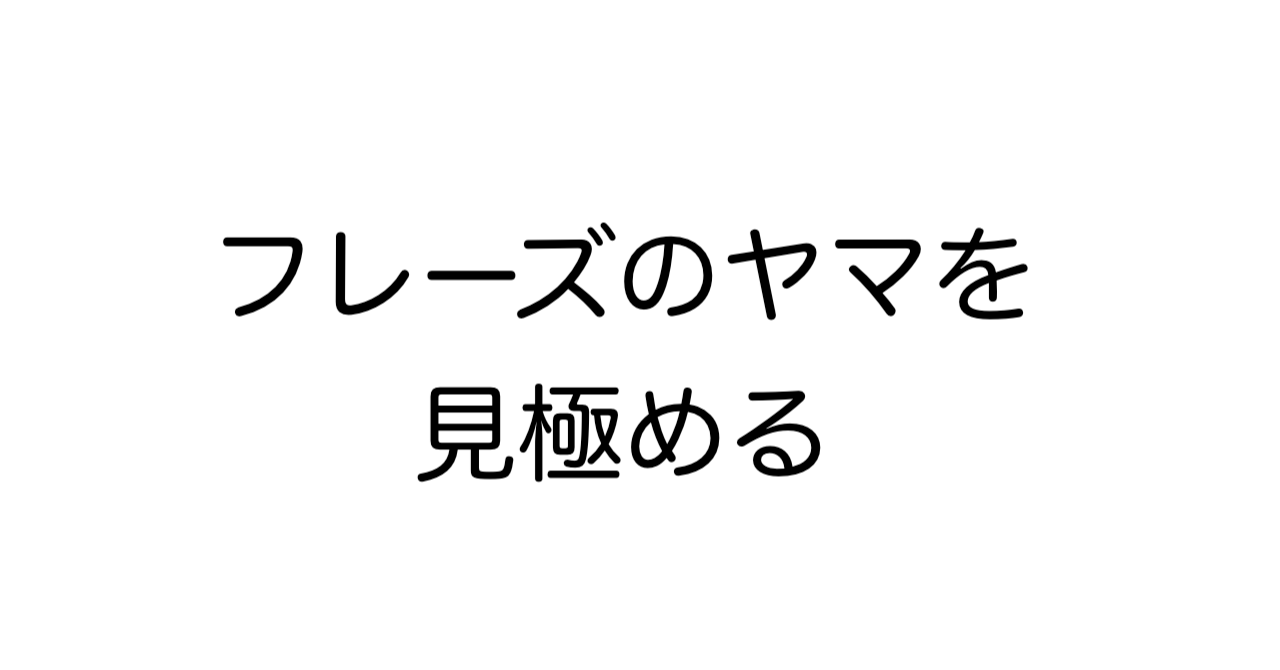

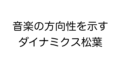

コメント