多くの学習者に共通するクセのひとつに気づきました。
「高音域の細かく動くパッセージを見ると、いつもキラキラした音質で弾いてしまう傾向がある」
ということです。
例えば、
通称、「黒鍵のエチュード」
の高音域でしたら
キラキラした明るい音で演奏してもいいでしょう。
しかし、次の譜例の場合でしたらどうでしょうか。
ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」
譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)
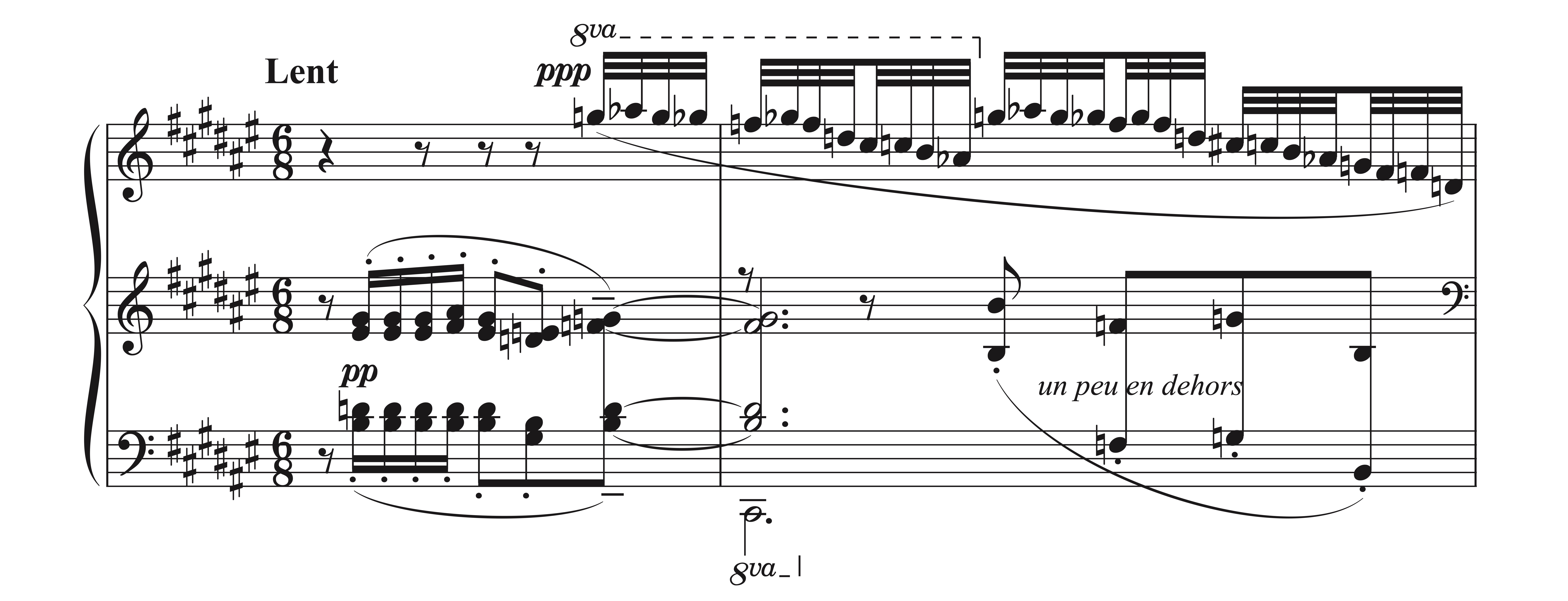
1小節目の後半から
「32分音符による高音域パッセージ」が出てきます。
「月光の降りそそぐ」
というタイトルにあるように
この動きは
「月光が降り注いでいる様子」
を描いていると考えてもいいかもしれません。
キラキラしている月光もあるかもしれませんが、
ここでは
「ppp という非常に抑制されたダイナミクス」や
「その他のパートの在り方」から察すると
「妖艶な雰囲気をもった、曇った音色」
で演奏する方がベターだと感じます。
もちろん正解はありません。
ここでお伝えしたいのは、
譜読みの段階において
「この楽曲の、この箇所にふさわしい音色とは?」
という視点を必ず持つべきだということです。
特に「高音域の細かく動くパッセージ」というのは
キラキラした音質を連想させる傾向があるため
音色がいつでもどんな楽曲でも同じになってしまわないように
注意する必要があります。
テクニック的には、
ざっくりとではありますが
次のようなことが言えます。
◉ 指を寝せ気味にして打鍵速度をゆっくりめに弾くと、曇りがかった音が出る
「楽曲にふさわしい音色を考えて、それを表現する」
というのは、
指が速く動くかどうかというのとは
別の観点で必要なテクニックです。
音楽で大切なのは
「音の高さ」や「リズム」だけではありません。
多くの学習者がこれらばかりを気にしています。
しかし、
これらの必要性の把握と同時に
「音色」という観点を持つことが
上級レベルへ達するための超重要ポイントなのです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
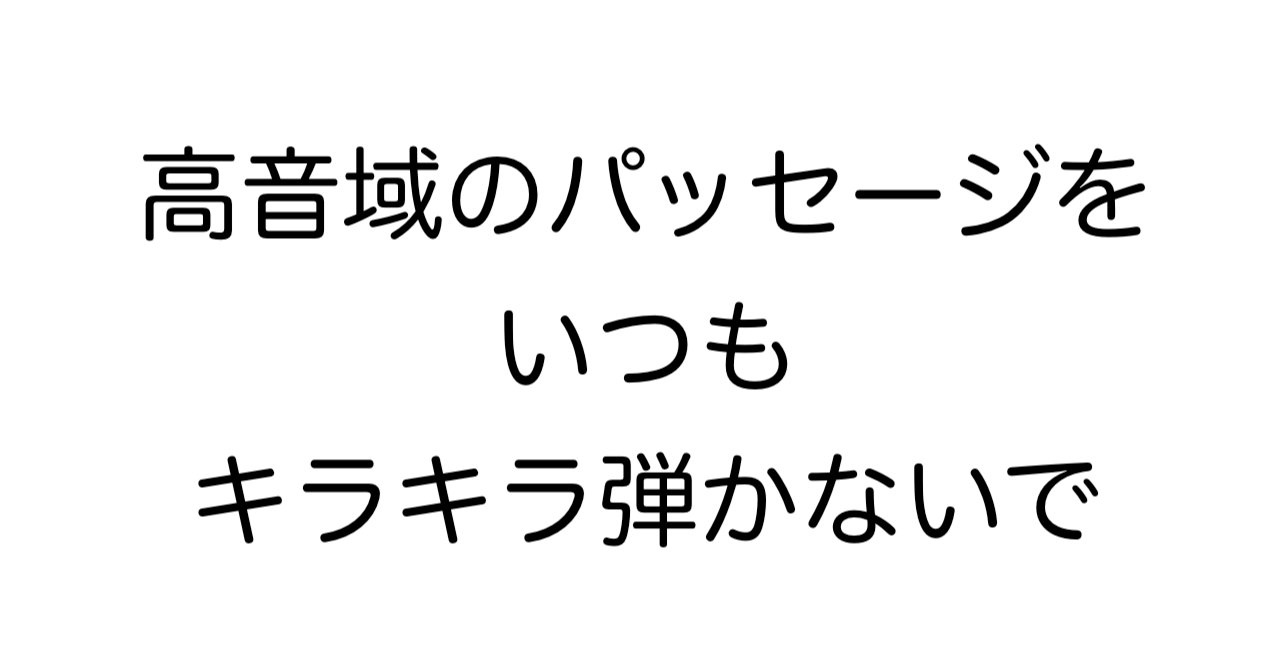
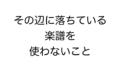
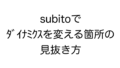
コメント