具体例を挙げます。
楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。
ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 雪の上の足跡」
譜例(PD作品、Finaleで作成、7小節目)

ご覧の通り、
ここでは背景としての伴奏が消え入り、メロディがsoloになります。
このような表現は
同楽曲だけでも数回出てきます。
また、
古典派の作品はもちろん
シェーンベルクのピアノ曲などの
あらゆる作品でも登場する書法です。
演奏ポイントは、
「伴奏部分の消し方の工夫」です。
打ち直して勢いよく消す楽曲は例外ですが、
譜例のようにタイで伸ばされているケースでは、
「バッと切らないこと」
これが重要です。
いきなり音響が無くなると音楽的ではありませんし
直後の休符も活きません。
(再掲)

「ペダリング」に注意し、
ダンパーペダルを徐々に上げていくことで音響をコントロールしましょう。
「余韻も含めて音価分の長さになるようなイメージ」
これを目指すと、音楽的に消え入ります。
ちなみに、
少し高度な考え方ですが
上級を目指す方にはぜひ知っておいていただきたい内容があります。
(再掲)

譜例で1拍目裏からはメロディのsoloになりますが、
「聴衆の耳には、1拍目表までで消えた音響の印象がそれ以降も残っている」
という事実を知っておきましょう。
この残像をうまく利用して作曲された作品が
特に近現代では何作品もあるのです。
今は、雑学程度の認識で構いません。
学習が進んでくると
これがいかに音楽の印象を左右しているかに
気が付くときがくるはずです。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
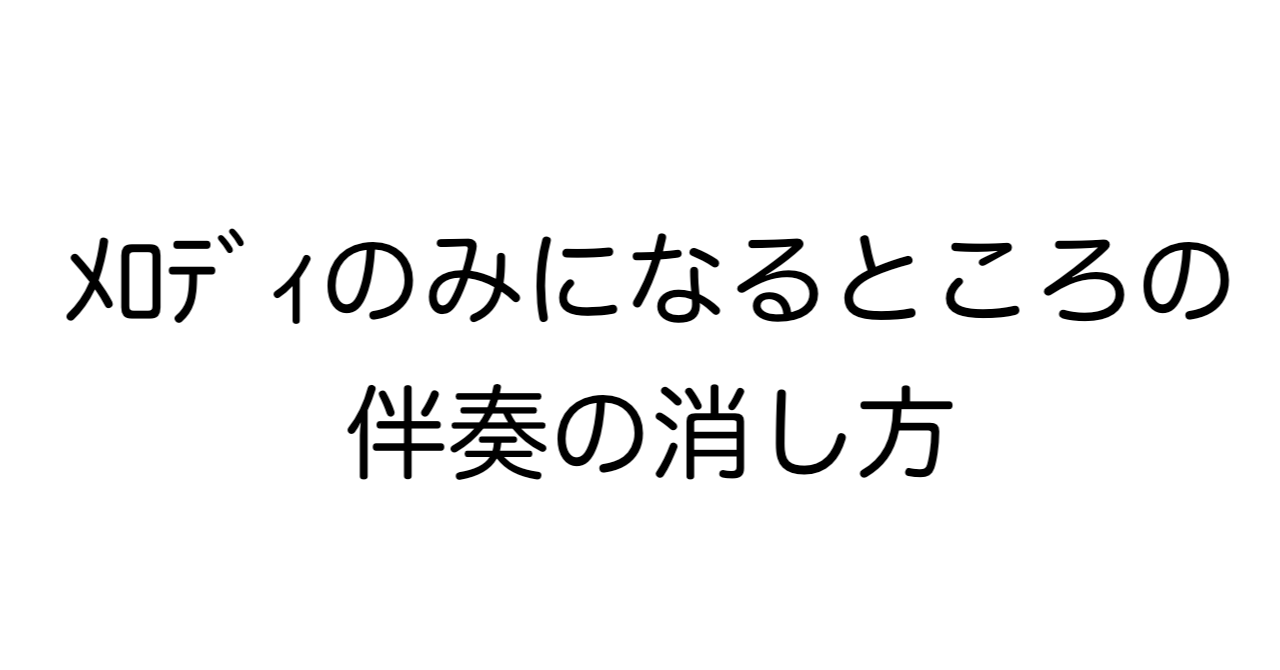
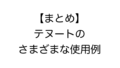
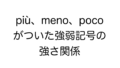
コメント