【ピアノ】テヌートの連続とレガートの違いとは?演奏法と使い分けのポイント
► はじめに
音楽演奏において、テヌートとレガートの違いは非常に重要であり、特に「テヌートの連続」と「レガート」は、一見似ているように見えて、実は全く異なる演奏表現となります。
本記事では、その違いを詳しく解説していきます。
► テヌートの連続とレガートの違い
‣ 結論:テヌートとレガートの本質的な違い
・テヌート:各音を保持しながらも、音と音の間に微細な切れ目を入れる
・レガート:音と音を完全につなげて演奏する
‣ 譜例で見る違い
譜例(Finaleで作成)
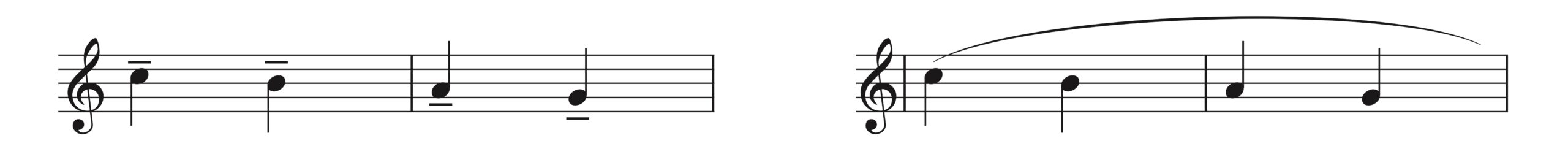
左:テヌートの連続
右:レガートのスラー
これら2つの奏法は、同じように見えて全く異なる演奏方法を示しています。
► 原則としてのテヌートの演奏法
テヌートの連続では、以下の点に注意して演奏しましょう:
1. 音の保持
・各音符の長さをしっかりと保つ
・音をギリギリまで意識的に維持する
2. 音の区切り
・音と音の間に「紙一枚分」の隙間を入れる
・各音の終わりは、はっきりと切る
3. 音の強調(解釈による)
・各音をやや強調する
・音の始まりを明確に
► 楽器別のテヌートの演奏方法
‣ ピアノの場合
「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社
という書籍に、以下のような記述があります。
テヌート記号がついた音が連続している場合、レガートのとき程は音をつながない。
レガートでは、上腕の動作およびダンパーを静かに下げることによって、音をつなぐ。
それに対してテヌートの場合、ダンパーは自由にストンと落下させる。
このことによって、音と音の間にテヌート独特のわずかな切れ目を作り出す。
(抜粋終わり)
この文章から読み取って欲しいのは、「各音の間の消え際は、割とバッサリいっている」ということ。
「音の長さを保ち終えたら、バッサリ消す」
このニュアンスが、テヌートのイメージに近いものとなります。
‣ 弦楽器の場合
・テヌートは、弓を一音ごとに返す奏法で演奏
・弓の動きを止めずに、かつ、弓を返さないと「スラー表現」になる
‣ 管楽器の場合
・テヌートは、タンギング(舌による音の区切り)を使用し、「ダーダー吹き」と呼ばれる奏法で演奏
・スラーがかかっていると、「タンギングし直さないで演奏する」という意味になる
► 補足:マルカートとスラーの関係
マルカートはスラーと相反する性質を持っています。以下の理由から、通常、力のある作曲家はマルカートとスラーを同時に使用しません:
・音楽表現の明確さが失われる
・演奏者に混乱を与える可能性がある
・音楽の意図が不明確になる
譜例(Finaleで作成)
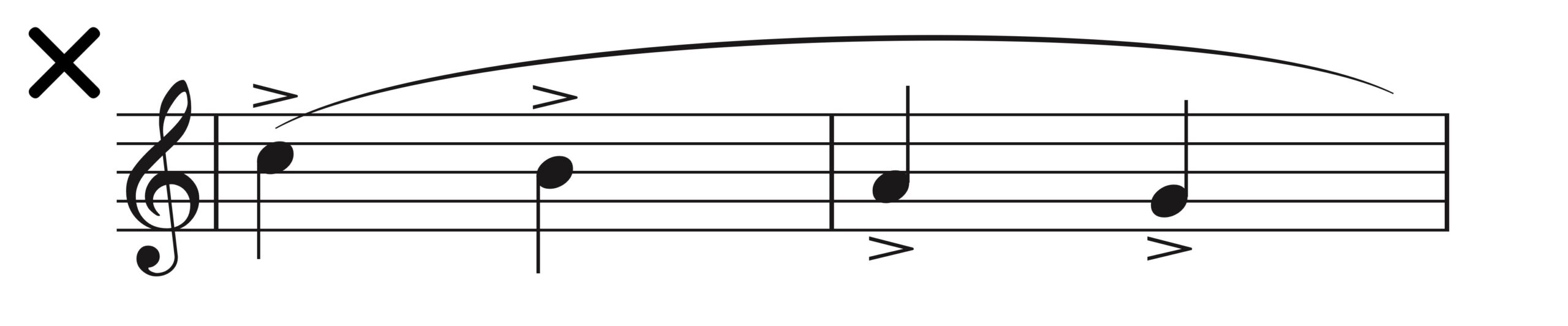
► まとめ:演奏のポイント
テヌートの連続を演奏する際は:
・音の長さをしっかり保つ
・音と音の間に微細な切れ目を入れる
・必要に応じて、各音を適度に強調する解釈をとる
これらの要素を意識することで、テヌートの持つ特徴的な表現を実現できます。
・シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社
► 関連コンテンツ
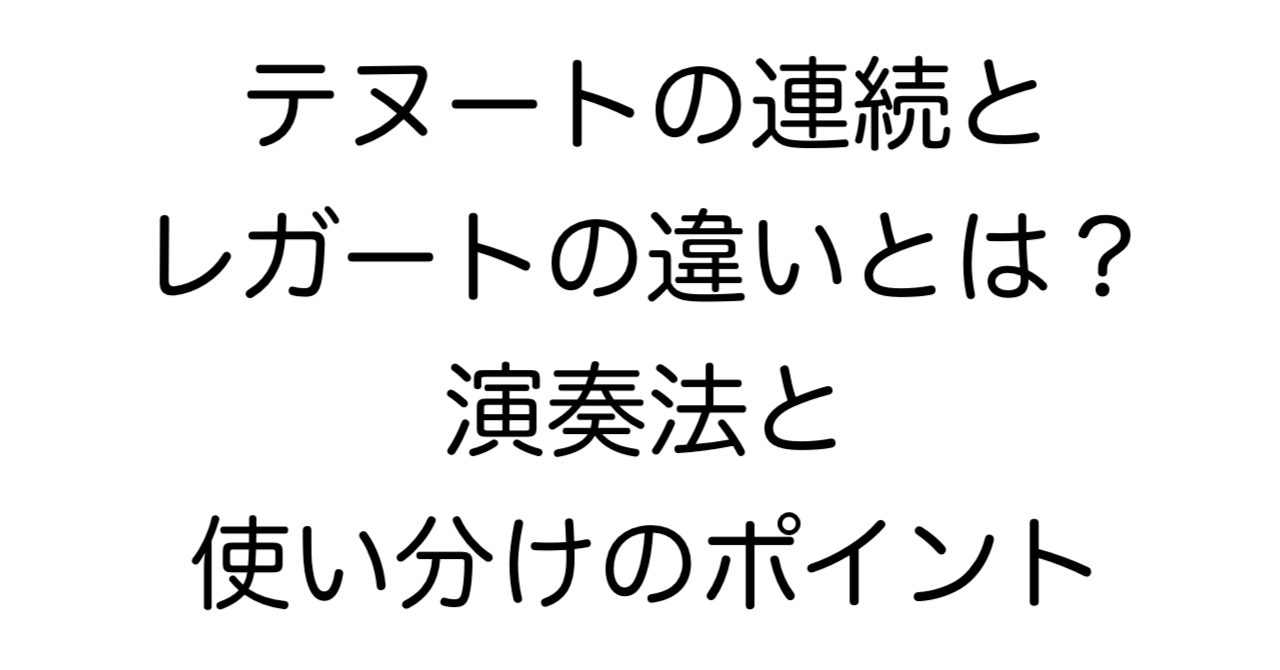

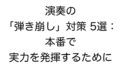
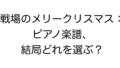
コメント