【ピアノ】別声部へのタイを活用したアレンジテクニック
► はじめに
ピアノアレンジにおいて、同音の連打を避けながらハーモニーを豊かに表現したいという場面は頻繁に訪れます。特に、メロディラインで使用した音符を直後の内声部でも響かせたい場合、そのまま演奏すると不自然な連打となってしまい、音楽的な流れが損なわれることがあります。
そこで有効なのが「別声部へのタイ」というテクニックです。この手法は、メロディ声部から内声部へタイを伸ばすことで、連打を避けながらも必要なハーモニーを維持できる優れた技法です。本記事では、この実用的なアレンジテクニックについて、具体例を交えながら解説していきます。
► 別声部へのタイを活用する
‣ 連打を避けつつ、ハーモニーを得る
譜例(運営者が作成した楽曲教材)

レッド音符で示したE音へのタイ処理を詳しく見てみましょう。ここでは以下のような音楽的判断が働いています:
問題の認識:
・直前のメロディでE音が演奏されている
・作曲上、直後の内声部にもE音の響きが欲しいと感じた
・しかし、E音が連打されるサウンドは気になるので避けたかった
解決策の実装:
・メロディのE音から内声部のE音へタイで接続
・連打のサウンドを回避しながら、ハーモニー上必要なE音を維持
・音楽の自然な流れを保持
次の小節のレッド音符で示したA音の処理も同様の原理に基づいています:
問題の認識:
・このレッド音符A音は、第9音(9th)にあたるハーモニー構成音
・作曲上、コードネーム「Gadd9」のサウンドが欲しかった
・直前のメロディでもA音が演奏されている
・しかし、A音が連打されるサウンドは気になるので避けたかった
解決策の実装:
・メロディのA音から内声部のA音へタイで接続
・連打のサウンドを回避しながら、ハーモニー上必要なA音を維持
・音楽の自然な流れを保持
実際の音響効果
これらのテクニックの効果は、以下の音源で確認できます(57秒辺りから)。
‣ 実はクラシック作品にも出てくる
J.S.バッハ「シンフォニア 第14番 BWV800」
譜例(PD作品、Sibeliusで作成、7-8小節)

一例ではありますが、この作品においても、別声部へのタイが効果的に使用されています。レッド音符で示した部分では、ソプラノ声部からタイが引かれています。
この楽曲の特徴:
・全声部が独立した「線」として構成されている
・「メロディ+伴奏」ではなく、対位法的な声部進行
・各声部の独立性が重要視されている構造
本来はタイにしないほうが声部の独立性が感じられます。J.S.バッハが何を意図したのかは正確には分かりませんが、「線×3」の音楽なので、上記の別例で取り上げた「和声を得るため」のタイとは考えにくいでしょう。
鍵盤楽器の特性との関係
鍵盤楽器というのは、その構造上、同音連打が苦手な楽器です。その欠点を補うことを考えると、「別声部へのタイ」は創作上使い道が広いのです。
► 実践的な応用方法
別声部へのタイが効果的に機能する条件は、以下の通りです:
メロディ・ハーモニー的条件:
・メロディ声部と直後の内声部で同音が連続する
・その音がハーモニー上重要な役割を果たしている
・連打による音響的な問題が気になる
演奏技術的条件:
・指使いの合理化が必要
・より滑らかな声部進行を求める
響きへの配慮:
・ハーモニーバランスへの影響を音を出して確認
・タイにせず再打鍵したほうが響き自体は厚くなることを踏まえて、比較検討
► 終わりに
「別声部へのタイ」は、ピアノ音楽の作曲や編曲における実用的かつ効果的なテクニックです。このテクニックを習得することで:
・演奏技術的な問題や連打サウンドの懸念点を解決しつつ、使いたい響きを得ることができる
・ジャンルレスで幅広く応用できる
重要なのは、ただ単に技術的な問題を解決するだけでなく、音楽的な表現力を高める方法として活用することです。実際の創作において、このテクニックを積極的に取り入れてみてください。
関連内容として、以下の記事も参考にしてください:
・【ピアノ】初心者からステップアップできるアレンジテクニック集
・【ピアノ】ピアノアレンジの手順:全体ざっくり作成 vs 細部集中 どちらを先行させるのが得策か
・【ピアノ】ピアノアレンジの質を高める「原曲理解」と楽曲分析の重要性
・【ピアノ】ドミナントの第3音を美しく響かせるコツ:創作と演奏の両面によるアプローチ
・【ピアノ】ロー・インターヴァル・リミットとは?:作曲と演奏に役立つ音楽理論
・【ピアノ】演奏者のための音楽理論学習法:4つのポイント
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
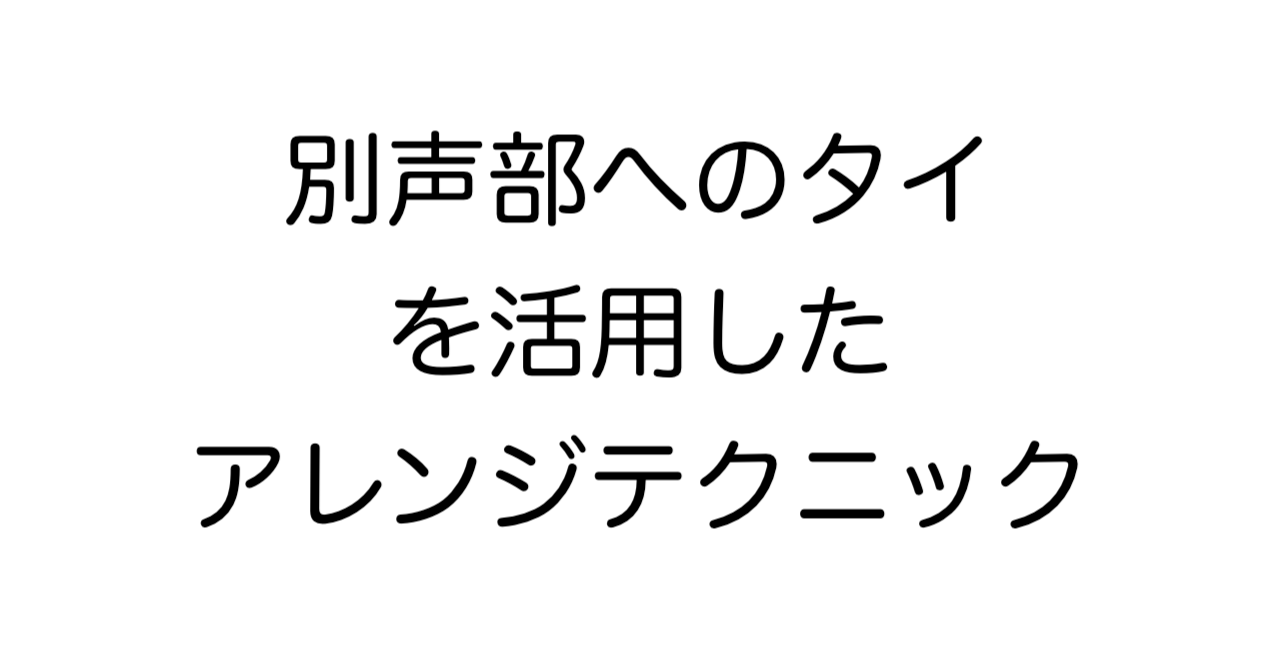
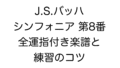
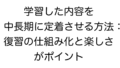
コメント