【ピアノ】「ピアノ音楽事典 演奏篇」レビュー
► はじめに
本書は、ピアノ演奏と指導に関する膨大な知識を体系的にまとめた、「事典」の名に相応しい一冊です。特に指導者にとっては手放せない一冊となるでしょう。注目したいのが、独立した項目として設けられた「運指法」の章です。
・出版社:全音楽譜出版社
・初版:1981年
・ページ数:587ページ + 別冊付録240ページ
・編集顧問:井口基成、野村光一、安川加寿子
・対象レベル:初中級~上級者
・ピアノ音楽事典 演奏篇 / 全音楽譜出版社
► 内容について
‣ 分担執筆の強み
本書は、各分野を代表する研究者、演奏家、教育者による分担執筆形式を採用しています。これにより、単一の著者ではカバーできない広範囲かつ専門性の高い内容が実現されています。
‣ 構成と内容の充実度
本書は圧倒的な情報量と網羅性が特徴の一つです。主要な構成は以下の通りです:
1. ピアノ音楽の歴史的概観
ピアノに関して幅広い時代を俯瞰できる内容となっています。ピアノとピアノ音楽の歴史、ピアノ演奏史、現代のピアノやピアニストの歴史的文脈などが収載されています。
2. 時代別演奏法
バロック、古典派、ロマン派、近現代という時代区分に沿って、それぞれの様式的特徴と演奏法が詳述されています。各時代の代表的作曲家の演奏法概論も含まれており、実践的な知識が得られます。
3. 指導法
本書で最も価値ある部分の一つです。運指法、ピアノ伴奏、ツェルニーの段階的学習法、クラーマーやクレメンティの奏法、さらにはアメリカのピアノ教育まで、多角的な視点からピアノ指導法を学べます。
‣ 特筆すべき「運指法」の項目
本書で特に注目したいのが、独立した項目として設けられた「運指法」です。運指に特化した専門書が少ない中で、これは非常に貴重な資料と言えるでしょう。
運指法の内容:
・ピアノ演奏における運指法の役割
・運指法の歴史的考察
・作曲家が遺した運指法
・初歩の段階における運指法
・演奏における運指法の原則
– メロディを美しく歌わせるための運指法
– アウフタクトを持つメロディの運指法
– アーティキュレーションと運指の関係
– 同型反復と運指の関係
– リズムとの関係
– テンポとの関係
– 半音階の運指法
– 3度の運指法
– 6度の運指法
– 左右対称のフレーズ
– 替手について
興味深いのは、ベートーヴェンのソナタなどについて、ビューロー、シェンカー、シュナーベル、アラウといった著名音楽家の運指を比較分析している点です。これにより、同じ楽曲でも解釈によって運指がどのように変わるかを具体的に学ぶことができます。
‣ 別冊付録「ピアノ誌上ゼミナール」の価値
240ページにも及ぶ別冊付録は、本編に劣らない価値を持っています。J.S.バッハからドビュッシーまで、各時代の代表作品について、その分野の専門家が実際の楽譜に赤字で注釈を加えながら詳細に解説しています。
収載作品:
1. J.S.バッハ インヴェンションとシンフォニア より 3声のシンフォニア 第1,2,9,10,12,13番:市田儀一郎
2. モーツァルト ソナタ K.331、幻想曲 K. 397:深沢亮子
3. ベートーヴェン ソナタ Op.13 悲愴:井内澄子
4. ベートーヴェン ソナタ Op.57 熱情:種田直之
5. シューベルト 即興曲 Op.90-4、楽興の時 Op.94-1:笠間春子
6. ショパン バラード 第1番 Op.23、エチュード Op.10 Op.25:山崎孝
7. シューマン 謝肉祭 Op.9:辛島輝治
8. リスト メフィスト・ワルツ:米谷治郎
9. ブラームス ラプソディ Op.79-.2、インテルメッツォ Op.117-2:北川正
10. ドビュッシー 版画:井上二葉
各専門家が自身の得意分野を担当していることで、それぞれの作品について深い洞察を得ることができます。
► 使用上の注意点
一点注意すべきは、「資料篇」の部分では1981年当時の情報(各音楽大学の教員一覧など)が含まれており、現在では参考にならない部分があることです。しかし、演奏法や指導法といった普遍的な内容については、今なお色褪せることのない価値を持っています。
► 終わりに
本書は特に「運指法」に関する詳細な解説と、別冊付録の実践的な演奏解釈指導において、貴重な知識源となっています。ピアノを真剣に学ぶ方や指導に携わる方は一度手にとってみてください。
・ピアノ音楽事典 演奏篇 / 全音楽譜出版社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
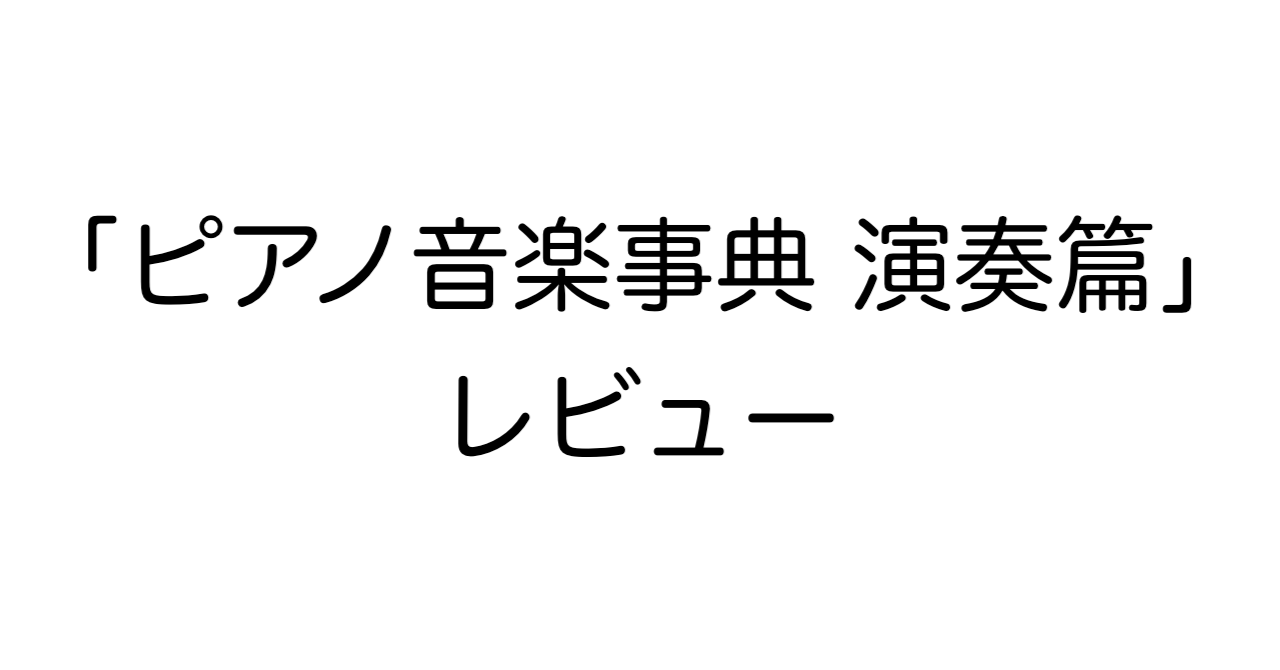

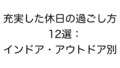

コメント