【ピアノ】ハノンをいつから始める?失敗しない導入時期と練習方法
► はじめに
多くのピアノ学習者が悩むのが、ハノン練習曲の開始時期。「早すぎも遅すぎも良くない」と言われますが、具体的にいつ始めればいいのでしょうか。
本記事では、ハノンを効果的に導入するためのポイントを詳しく解説します。
► ハノン練習曲の理想的な開始時期
‣ 導入時期の具体的な目安
【最短時期】
・ブルグミュラー25の練習曲に入る段階
・全音ピアノピースの難易度Bがまだ少し難しい程度
【標準時期】
・ツェルニー30番に入る段階
・全音ピアノピースの難易度Bが無理なく弾ける程度
重要ポイント
バイエル(および同程度の曲集)を学習中の段階では、まだハノンの導入は控えましょう。
‣ 独学の場合の注意点
独学で学習されている方は、以下の点に特に注意が必要です:
・最短時期(ブルグミュラー導入時)での開始は、経験者のアドバイスを受けられる環境がある場合のみ推奨
・基本的な奏法が身についているか、客観的な確認が重要
・必要に応じてオンラインレッスンなどでの確認も検討
ハノンで学習するのは基礎技術であり、楽曲解釈ではありません。一度間違った方向で癖づいてしまうと修正するのが大変になります。そこで、普段は独学でも「ハノン学習の方向性のチェック」として、経験者のワンポイント指導を受ける機会を作れるとベストです。
► 開始時期で失敗しないための3つのポイント
‣ 1. 早すぎる開始のリスク
避けるべき状況
・指をベタっと伸ばしたままの演奏が習慣化している
・腕に余計な力が入った状態での演奏
・基本的な運指の理解が不十分
ハノンの特徴である「音型の反復練習」は、良い習慣も悪い習慣も強化してしまいます。最低限の奏法が定着していない段階での開始は、望ましくない癖を固定化するリスクが高くなります。
‣ 2. 遅すぎる開始のデメリット
ハノンで学べる重要なテクニック:
・トレモロ・トリル
・スケール・半音階
・アルペジオ
・3度・6度・オクターブ
・同音連打
・5本指の平均的な基礎練習
これらのテクニックは、実際の楽曲演奏に必要不可欠です。中上級レベルに進む前に、体系的な練習を通じて身につけておくことが望ましいでしょう。
テクニックというのは表現したいものがあってこそですが、「出てきたときや使いたいときにいつでも使える」というのは大事な部分です。
‣ 3. 他の教材とのバランス
以下の教材とハノンを同時期に使用する場合は、内容の選択に注意しましょう:
・ピッシュナ
・コルトー
・ベレンス
基本原則
似たような目的の練習は分散させず、一点集中で取り組むことで効果を最大化します。
有益な課題組み合わせ例
以下の異なる視点での練習曲のセットは、併用することで効果を上げることができます:
・ハノン「第39番 全調スケール」
・コルトー「4本の指の練習-1本の指を持続(指の均一と独立)No.2a-2e」
► 効果的なハノン練習の始め方
「まずは第1番に集中する」
・1日10-15分程度
・テンポは♩= 60 から開始
・両手練習は片手が完璧になってから
ハノンの後半部は、学習者の手の大きさなどによって体感難易度が大きく変わるので、まずは第1番から始めるのが「どんなレベル」「どんな年齢」の方にとってもスムーズに導入できるポイントとなります。
► 終わりに
ハノン活用のヒント:
・最低でもバイエル修了程度の演奏技術が身についてから開始
・第1番から丁寧に練習
・単発でもいいので、できる限り経験者のアドバイスを受ける
本記事は、ピアノ学習者がハノンを効果的に活用できるよう、筆者の経験と専門知識をもとにまとめたものです。個々の状況に応じて、柔軟に対応するようにしましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
・SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
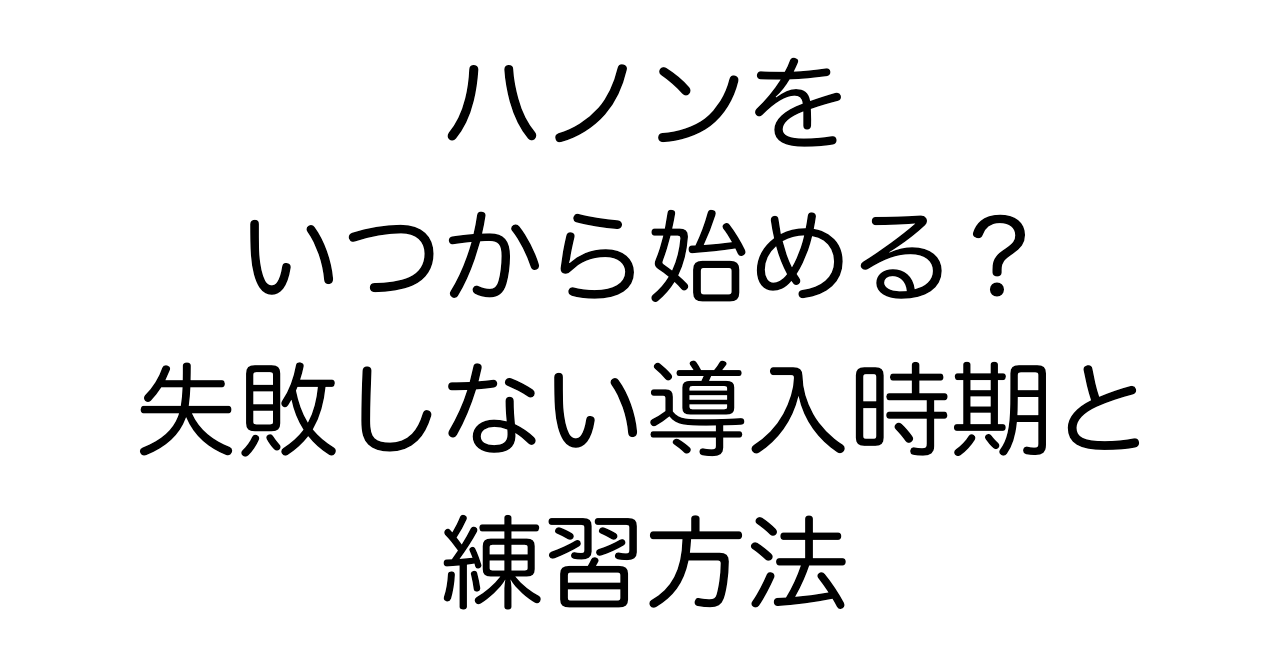

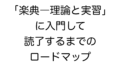
コメント