【ピアノ】拍に入らない音符列を音楽的に演奏する:拍感を崩さないテクニック
► はじめに
クラシック音楽の演奏において、楽譜に記された音符を機械的に再現することは、真の音楽表現とは異なります。
特に、テンポが速く、複雑な音符列が存在する作品では、単純に拍に当てはめようとすると、音楽の本質を失いかねません。
本稿では、拍に入りにくい音符列を、いかに音楽的に、そして作曲家の意図に沿って演奏するかについて、具体的な楽曲例を通じて解説します。
► 具体例と考察
‣ 具体例①:プロコフィエフ「ピアノソナタ第1番」─ 32分音符の挑戦
プロコフィエフ「ピアノソナタ第1番 ヘ短調 作品1」
譜例(PD作品、Finaleで作成、134小節目)
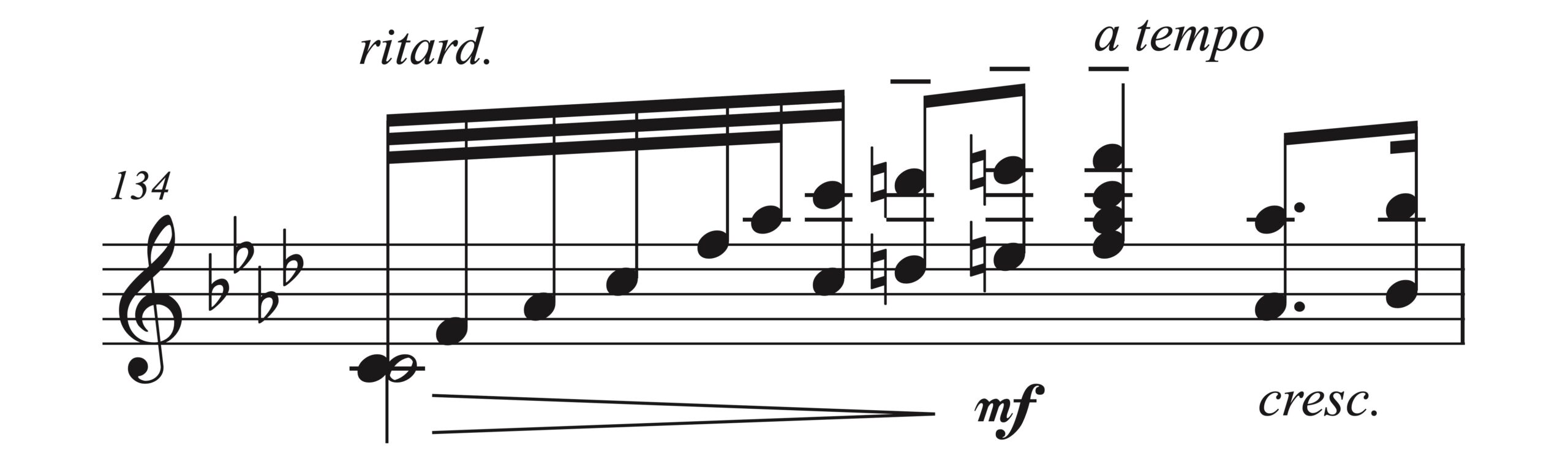
プロコフィエフは ritard. を書いてくれていますが、楽曲の速度指定はAllegroなので、ここで出てくる32分音符は頑張っても拍へ入れるのは困難です。
ほとんどの楽曲では前後関係のこともあり「両手で分担すること」も難しいでしょう。
結論的には拍を広げるしかないのですが、そのやり方が重要。
ただ単にゆっくりにして「取って付けたように」弾くのではなく、「イーチ・ニ・サン・シ」というように、「拍を引き伸ばしているイメージ」を持って演奏するのがポイント。
そうすることで、出てくるサウンドは違和感のないものになります。
「引き伸ばしても、自分の中の拍感覚までは放棄しない」
これは、特に中級以上になってくると必須。上記譜例よりももっと極端な
・絶対に拍に入らない極端な跳躍
・絶対に拍に入らない細かなパッセージ
なども多く出てくるからです。
‣ 具体例②:ベートーヴェン「熱情」─ 大きな跳躍と拍感の維持
ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 熱情 ヘ短調 op.57 第1楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、コーダの入り)
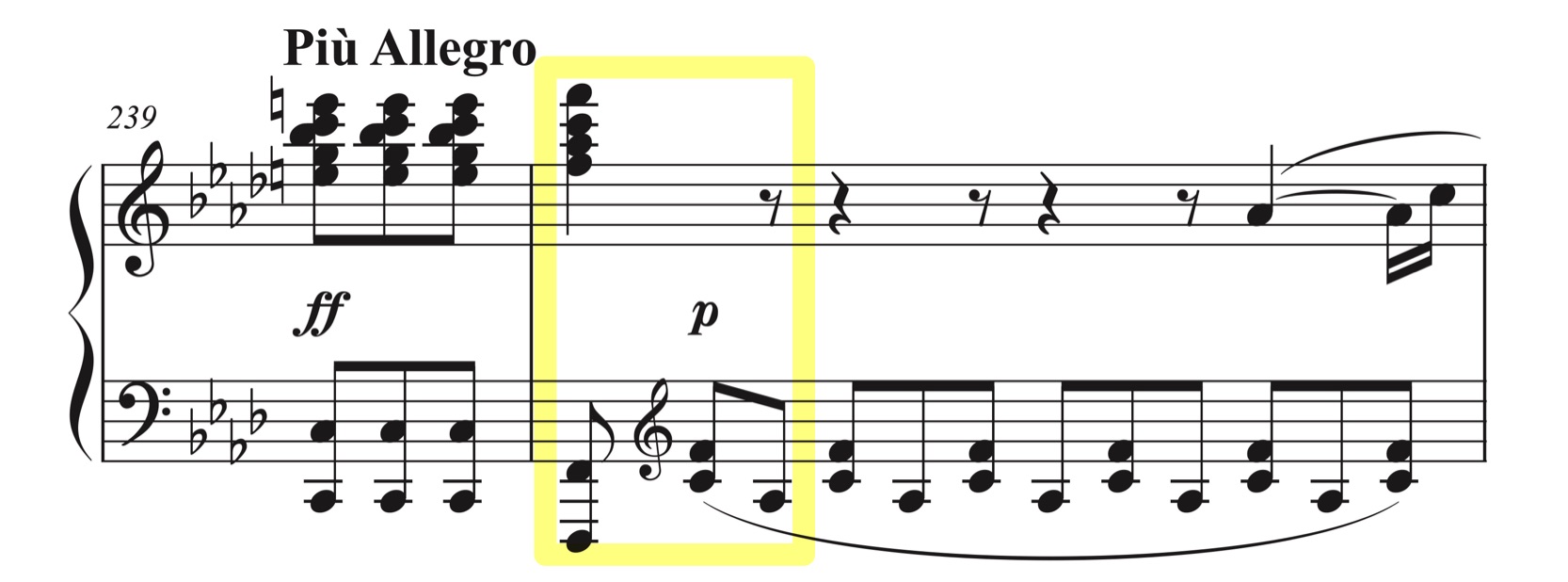
黄色マーカーで囲った箇所は演奏の仕方に注意が必要。
このような「急速かつ大きな跳躍」では、手の移動に時間を要することで拍の感覚が大きく崩れてしまう可能性があるからです。
拍の感覚が無くなると、音楽の骨格が崩れてしまいます。
理想的には「瞬時に手を移動させてもミスしないように練習する」のが望ましいのですが、もう一つの選択肢があります。
前項目でも解説したように、多少引き伸ばしてでも1拍目を意識して演奏するという方法。
つまり、「イーチ・ニ・サン」というように、1拍目がやや広がっていることを踏まえてその拍を作る。
そうすることで、2拍目以降も崩れずに安定するのです。
これをせずに1拍目を曖昧に弾いてしまうと、たいてい2拍目も失敗してしまいます。
‣ 具体例③:ベートーヴェン「第18番ソナタ」─ 12連符と即興性の表現
ベートーヴェン「ピアノソナタ第18番 変ホ長調 作品31-3 第1楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、53-57小節)
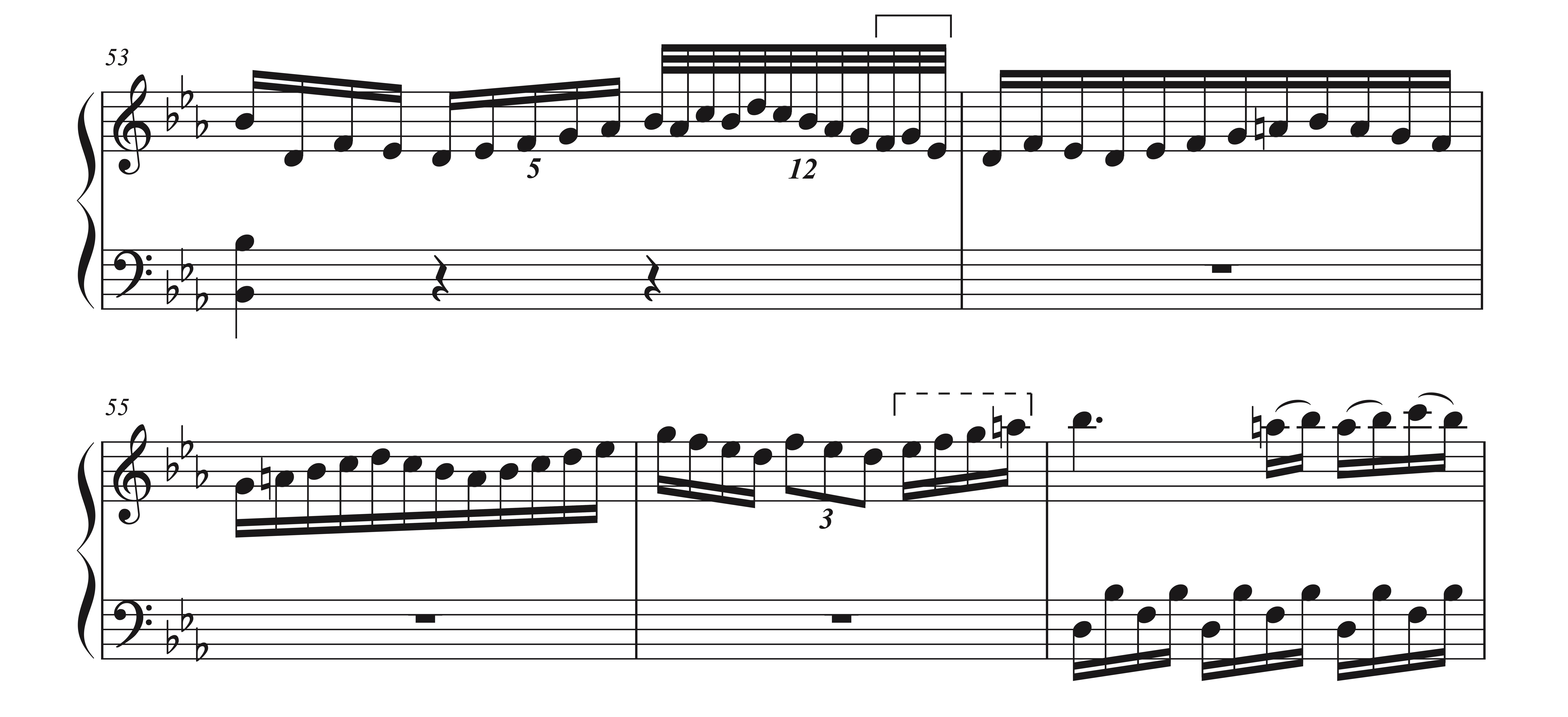
53小節3拍目には「12連符」が出てきますが、この楽曲のテンポはAllegroなので、インテンポで拍へ入れることはできません。
仮に入れられる超人的なテクニックを持っていたとしても、前後関係からすると機械的に聴こえるだけなので、やめた方がいいでしょう。
ではどうすればいいかというと、やはり前項目と同様。
拍を引き伸ばしている感覚を持ちながら演奏するようにしましょう。
53小節目を「イチ・ニ・サーーン」というように、「サン」を引き伸ばす意識を持つ。
絶対に「サン」の感覚を放棄しないでください。
それをしてしまうと、次の小節の「イチ」が崩れます。
それに、拍を意識しておくと、仮に「暗譜」がとんでしまったとしてもいずれかの拍頭から弾き始められるので、そういった点でもメリットがあります。
(再掲)
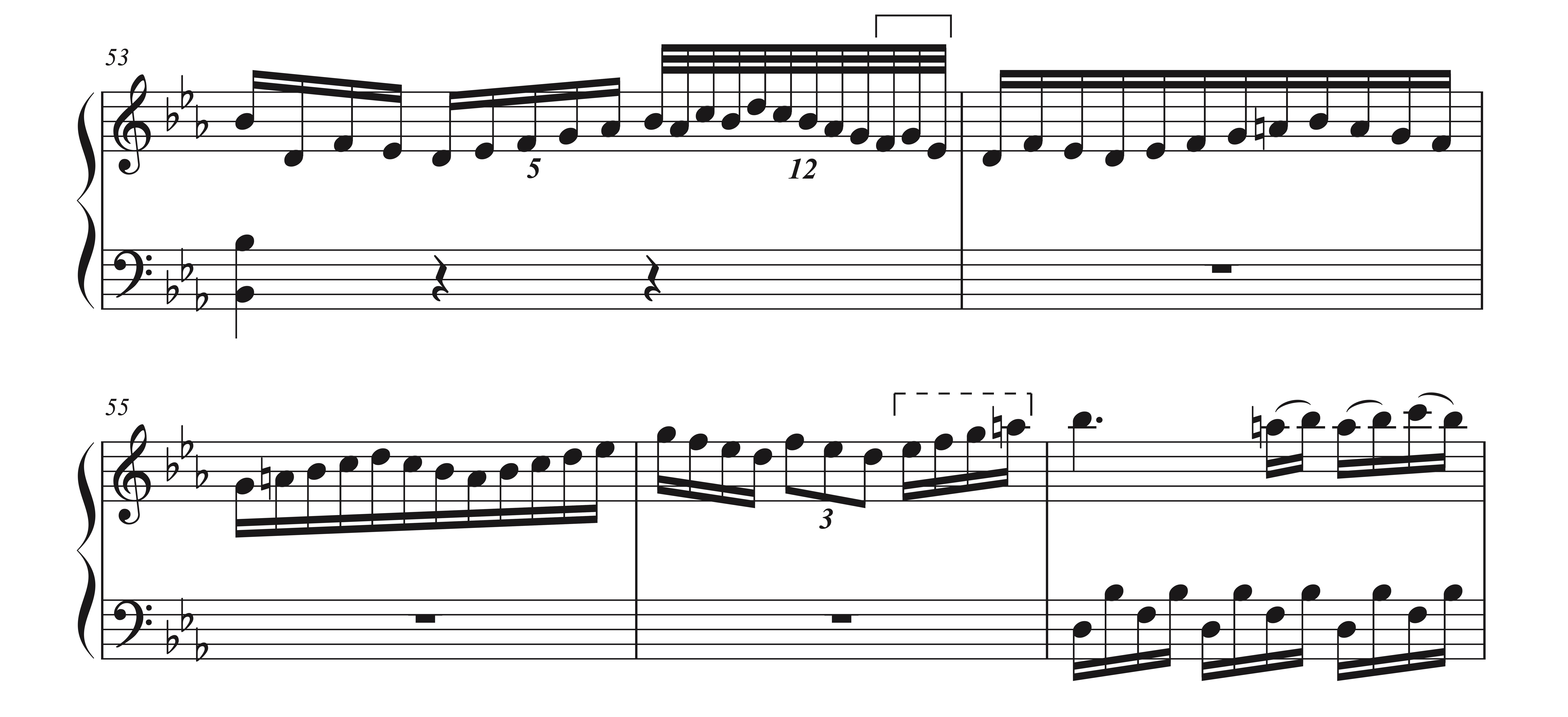
12連符の後、54小節目で通常の16分音符に戻るので、普通に演奏するとテンポ感が変わりすぎてギクシャクします。
ここでは12連符の最後の3つの音をテヌート気味にやや引き伸ばして演奏するようにすると、54小節目へ違和感なく連結できるでしょう。
実線カギマークで示した3つの音のこと。
57小節目から通常の「メロディ+伴奏」の音楽へ戻ります。
こういう場合、その直前の点線カギマークで示した16分音符を使って57小節目からのテンポを作ってしまうといいでしょう。
‣ 考察:作曲家の意図を読み解く:楽譜の奥にある音楽性
(再掲)
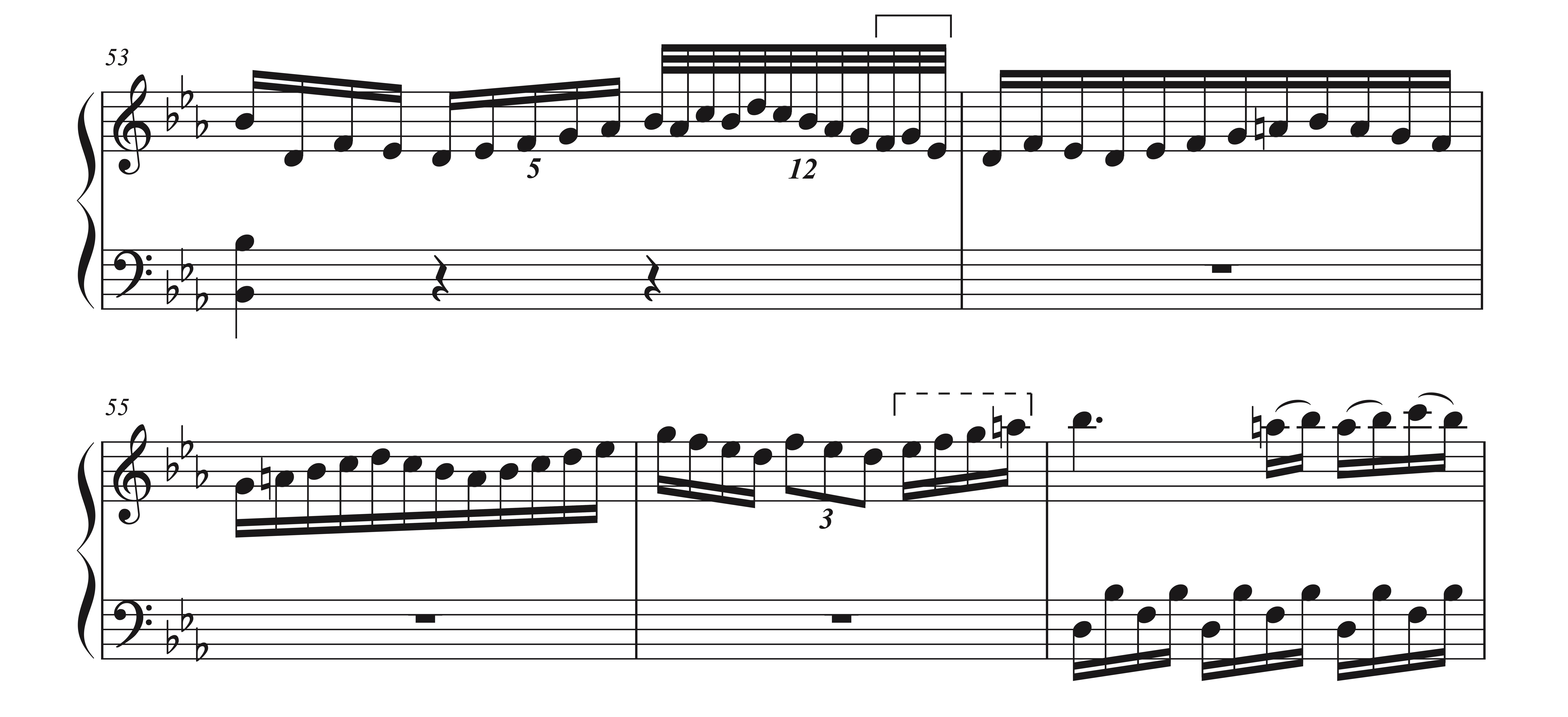
なぜ、ベートーヴェンは、拍に入らないような12連符をわざわざ書いたのでしょうか。
あくまでも予想ですが、そのヒントは54-55小節にあると考えます。
54-55小節は、各拍ごと連桁(れんこう)が分断されずに全ての16分音符がつながっていますね。
つまり、53-56小節あたりは「即興的な自由さ」をイメージしていたのではないかと感じるのです。
そう考えると、12連符が出てくることも納得できなくはありません。
ではなぜ、53小節目と56小節目は連桁が分断されているのかというと、これらの小節は各拍ごとに音価が異なるので、つなぐと単純に見にくいからでしょう。
正解はベートーヴェンにきかないと分かりませんが、こういったことを考えながら巨匠の作品と向かい合うのは楽しいと思いませんか。
一種の「再現芸術」ともいえるクラシック音楽だからこそ感じることができる楽しみです。
► 終わりに
拍感を保ちながら、音楽の流れと表現を大切にする。このようなアプローチを大切にしましょう。
特に中級以上になってくると、上記譜例よりももっと極端な
・絶対に拍に入らない極端な跳躍
・絶対に拍に入らない細かなパッセージ
なども多く出てきます。
▼ 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
・SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
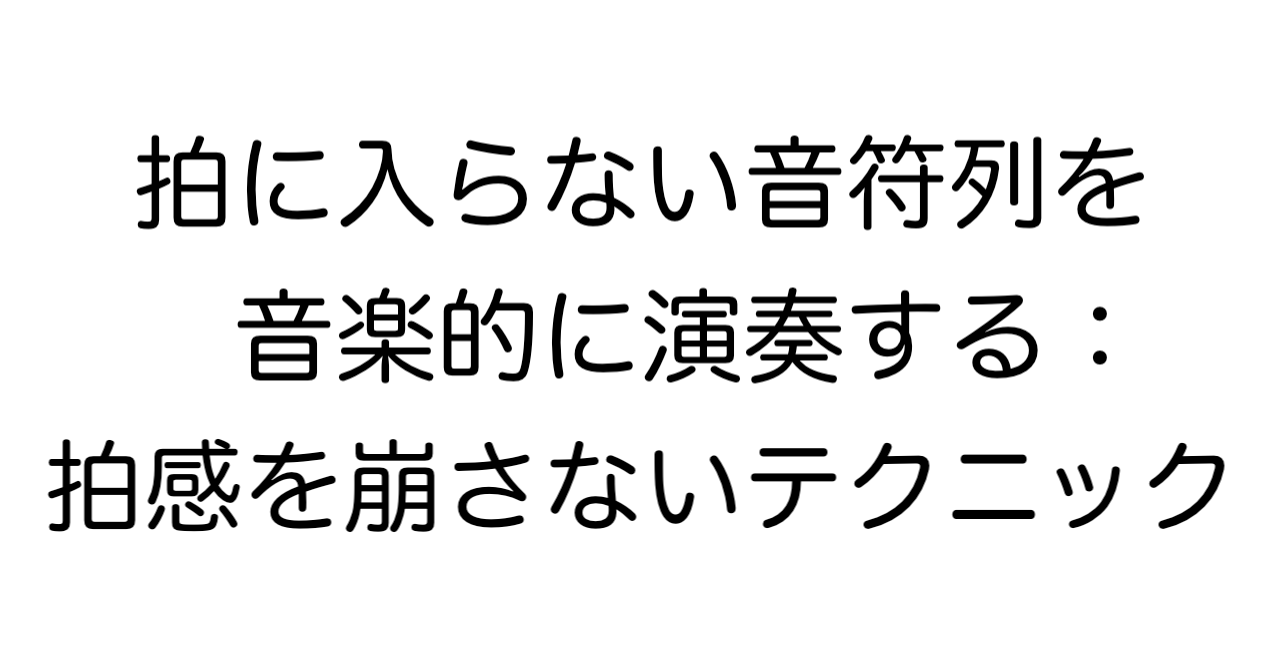
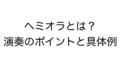
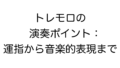
コメント