【ピアノ】楽曲分析が深まる、エバーグリーン作品の選び方と実践例
► はじめに
‣ 楽曲分析の重要性
楽曲分析(アナリーゼ)の力が上がると、楽曲の全体像はもちろん、細部までを音楽の成り立ちから理解できるようになります。単純に楽曲理解が深まるだけでなく、演奏方法を考えていくヒントにも使えます。
‣ エバーグリーン作品を選ぶ意義と特徴
楽曲分析の方法が分かってきたら、あとはとにかく手を動かして分析してみるに限ります。当然、今弾いている作品を分析するのがおすすめですが、同じ楽曲を長期間練習することもあるため、別に分析する教材を選ぶ必要もあります。
そのようなときには、エバーグリーンな作品を選曲するようにしてみましょう。
エバーグリーンな作品とは簡単に言うと、以下のようなものです:
・いわゆる「名曲」と言われ、一定の評価が定着している作品
・作曲に詳しい人物が「良く出来ている」と太鼓判を押している作品
・自身が以前に演奏で取り組んだ作品
これらは「エバーグリーン」つまり、いつまで経っても価値が薄れない重要な作品です。
なぜこのような作品を選ぶといいのかというと:
・一定の評価があり、作曲クオリティの低い作品を選んでしまう可能性が低い
・よく知られている作品のため、取り組み始めるハードルが低い
・よく知られている作品のため、知人を巻き込みながら学習することもできる
これらのような利点があるからです。
ある意味、例外として注目して欲しいのは、自身が以前に取り組んだ作品。このような類の作品は、仮に楽曲が佳作でも、自分にとってはエバーグリーンなレパートリーです。将来また再チャレンジするときに使える糧にもなるので、当時気づかなかった情報をたくさん拾うつもりで、分析してみましょう。
‣ レベル別おすすめ作品リスト
初級:
・J.S.バッハ : 2声のインヴェンション
・ブルグミュラー25の練習曲
・モーツァルト : ピアノソナタ K.545
他
中級:
・ベートーヴェン : 初期のピアノソナタ
・ブラームス : 3つの間奏曲 Op.117
・シェーンベルク : 6つの小さなピアノ曲 Op.19
他
上級:
・シューベルト : ピアノソナタ 第21番 D 960
・シューマン : クライスレリアーナ Op.16
・ドビュッシー : 前奏曲集 第2巻
他
これらの作品以外にも、上記エバーグリーンの自主定義に属するあらゆる作品をおすすめします。
► 実践例①:初級編
‣ シューマン「兵士の行進」のワンポイント分析例
ユーゲントアルバムはシンプルな教材ですが、小さな発見がたくさんあることに驚くことでしょう。
例えば、以下の譜例を見てください。
シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)より 兵士の行進 Op.68-2」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、17-22小節)

イエローマーカーの終わりの音とグリーンマーカーの始まりの音は、付点8分音符による団子和音でまとめられていて、声部分けされていません。しかし、複声部になっているのです。
21小節目へ矢印で示したようなA音からE音へ跳ぶメロディではない、ということに注意しましょう。新たなメロディのフレーズの始まりは、あくまでもグリーンのラインの部分からです。
‣ 初心者が見つけやすい分析ポイント
(再掲)

楽曲分析の初心者でも、メロディラインに関連するつなぎ目であれば気づきやすいでしょう。
この譜例の場合のポイントは、17-18小節でも「Re – Mi – Fa – Mi – Re」というメロディが出てきていることを意識することです。そうすると、グリーンのラインの最初のReは、「一番上にある音ではないけれどもメロディの一端なのではないか」と勘づくことができます。
‣ 演奏への活かし方
演奏上どうすればいいのかというと、黄色の最後のA音と黄緑の最初のD音を同じくらいのバランスで弾けばOKです。新たなメロディの始まりで聴こえて欲しいD音は、左手パートでもオクターヴユニゾンで補強されているため、やや大きめに聴こえるからです。
ここでは「オクターヴユニゾンになっている」と分析で見抜くことも、演奏解釈を助けます。
この作品で見たような、団子和音でまとめられていて声部分けされていない例は、同じユーゲントアルバムの第1曲「メロディー」などでも見られます。
► 実践例②:中〜上級編
‣ ショパン「エチュード Op.25-7」のワンポイント分析例
先ほどシューマンの初級作品で取り上げたのと同様の手法が使われている、中〜上級作品の分析例を見てみましょう。
ショパン「エチュード Op.25-7」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

3/4拍子になってすぐのところにある小音符E音は、先行フレーズの終結音。一方、直後のオクターブ上のE音は、後続フレーズの開始音。
ショパンは、このように装飾音符を2つのフレーズの接続として使用するやり方を時々用いました。音楽にちょっとしたうねりが生まれる書法です。
‣ メロディの跳躍に注目すると発見がある
譜例では、つなぎ目の装飾音符のところに大きな跳躍があります。当然、世の中には大きな跳躍をするメロディもありますが、実は例外も多いのです。つまり、メロディの跳躍に注目すると、本例のように2つのメロディのつなぎ目が見つかることもあります。
先ほどのシューマンの例にもメロディの跳躍があって、そこがつなぎ目となっていました。
‣ 演奏への活かし方
(再掲)

分析の結果、小音符という「拍の中へ入れて数えない、ある意味イレギュラーな音符」をつなぎ目としていることが分かりました。それを踏まえると、おそらくショパンは、このような書法をとることによって、音楽のうねりの表現、そして、後続フレーズの歌心あふれる連結を望んでいたと考えられます。わざわざ曖昧な音符をつなぎ目に使ったわけなので。
そこで、演奏面ではリズムを厳格に弾き過ぎず、3/4拍子になるところでややテンポを広げてもいいと考えられます。
► エバーグリーン作品での学習プロセス
雰囲気を感じていただくためにワンポイント分析を行いましたが、実際には、以下のようなプロセスで学習を進めていくことをおすすめします。
‣ プロセス一覧
1. 選曲段階
・以前弾いた曲など、分析に取り組みたいエバーグリーン作品のリストアップ
・分析学習ポイントの確認
・1曲選択
2. 初見分析
・全体構造の把握
・調性など基本情報の確認
・主要テーマの抽出など、大掴みな分析
3. 詳細分析
・和声進行や声部の動きなど、細部の分析
・その他、搾り取れるだけの発見をして、すべて書き出す
4. 演奏との結びつけ
・分析結果を演奏に活かすポイントの整理
・実際の演奏での試行
・気づきの記録
※ このプロセスを1サイクルとして繰り返す
► 終わりに:どんな学習レベルの作品でも、必ず発見がある
・いわゆる「名曲」と言われ、一定の評価が定着している作品
・作曲に詳しい人物が「良く出来ている」と太鼓判を押している作品
・自身が以前に演奏で取り組んだ作品
本記事の最初で自主定義したこれらのエバーグリーンな作品であれば、仮にどんな学習レベルの作品であっても、必ず発見があります。それを自分自身がエバーグリーンな気持ちで掘り起こすことができるかどうかです。
本記事で扱った、シューマン「兵士の行進」について学びを深めたい方へ
・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン 兵士の行進】徹底分析
► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
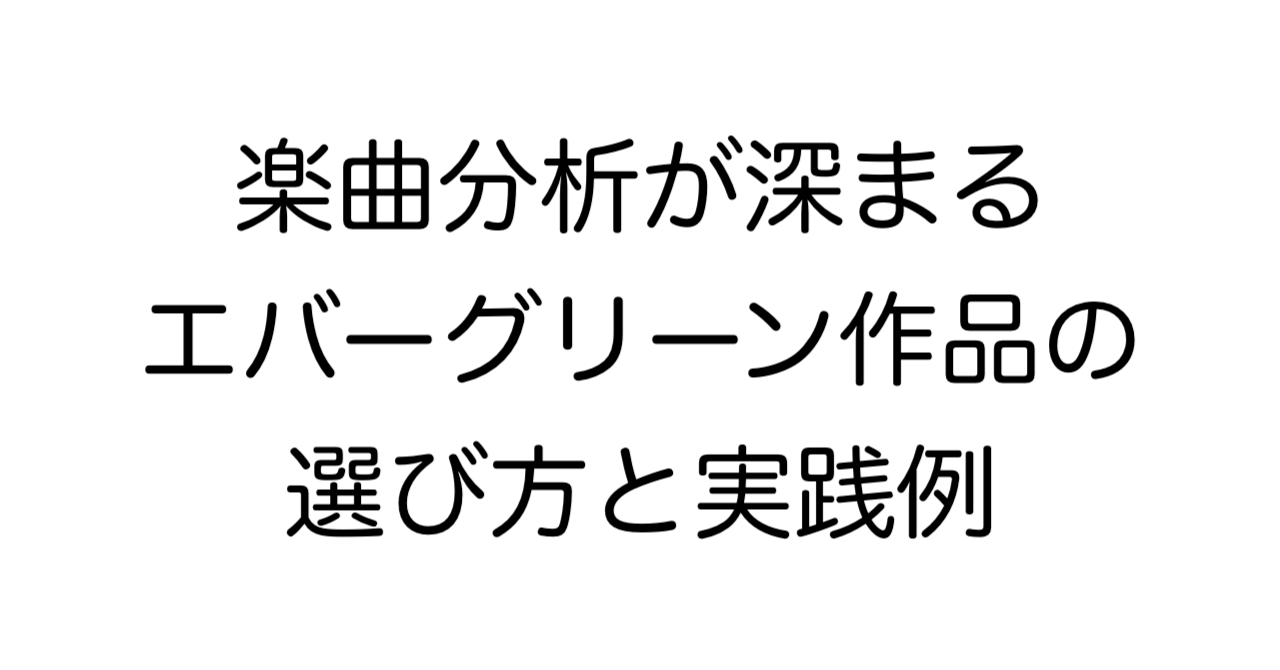

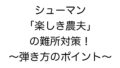
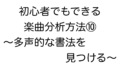
コメント