【ピアノ】陥りがちな「叩く奏法」の改善ガイド
► はじめに
ピアノ演奏において、美しい音色は最も重要な要素の一つです。しかし、多くの演奏者が気づかないうちに「叩く奏法」に陥っています。
本記事では、音質を改善するためのテクニックについて詳しく解説します。
► A. ピアノ演奏における音質の基本
‣ 1. なぜ、自分の音の汚さに気づけないのか
人間、良くも悪くも「慣れ」というものにコントロールされて、その度が過ぎると「当たり前」になっていきます。
ピアノで言うと、言い方は良くありませんが、びっくりするくらい音が汚い演奏を耳にすることもあります。長年、力で弾いたりペダリングへの意識がなかったりして今の音が当たり前になり、汚いことに気づいていないのでしょう。
録音して聴いても自分で気づかないのであれば、一時的に他者に頼るのもアリです:
・信頼している力のある先生
・独学の場合は、信頼している上手な友人
これらのような方から一度でも音質の荒さを指摘されたら、必ず、以後意識してみてください。
叩いて割れた音は、近くで聴いていると大きな音に聴こえて、一瞬「カッコいいかも」などと思ってしまいそうになりますが、完全な幻想です。上手なピアニストでそういった音を出す方はほとんどいません。
ff と書いてあるからといって、力と音量でやったらうるさいに決まっています。作曲家は何かの表現として ff を書いているわけなので、楽曲に応じてそれを想像し、真上から力で叩くような「とても強く」にしないことが重要です。
音をキレイにしたい場合は、まずは、今までの自分が持っている「汚くない」の基準をいったんフラットへ戻してみることから始めてみてください。そして、自分の音をよく聴く。そうすると、汚くない音を出すべく無意識に身体の使い方をコントロールするようになるので、改善へ向かいます。
‣ 2. 叩く奏法が音楽に与える悪影響
一部の現代曲で作曲家が指示しているような場合を除き、原則、大きな音を出そうとして鍵盤を叩くことはマイナスでしかありません。
衝突の反発で力の多くがなくなってしまったり、響きが散らばってしまい美しい音が出ないというのは当然ですが、もっとそれ以前の根本的理由があります。
叩くと、指が鍵盤に強くぶつかることによる騒音や、鍵盤が鍵床へぶつかる大きな騒音がたつからです。
普段ピアノを弾いていると、こういった騒音・雑音はピアノの音にごまかされて気づきにくいのですが、実際は相当大きな音がたっています。
時々、楽器演奏不可物件でヘッドフォンを使って練習していたら、楽器自体の音は漏れていないのに演奏時の物音がうるさくて苦情になった、という話を耳にしませんか。普通に弾いていてもそうなので、叩くクセがある演奏者の場合、その騒音のすごさは計り知れません。
叩いたときの指が鍵盤にぶつかる音は、ステージ上で聴くと顕著です。たとえ楽器の音がフォルテで鳴っていても騒音は聴こえてきますし、その騒音がピアノの音自体にも少なからず悪影響を与えています。
もう一つ、叩くときは大抵高くから打鍵することになるので、純粋に音を外しやすくなります。
だからこそ、大きな音を出したいときであっても、鍵盤の近くから「重さ」を使って打鍵することで、高さがなくても重厚な音を出せるようにするテクニックが求められるわけです。
► B. 打鍵の仕組みと奏法
‣ 3. 高くからの打鍵が音量と音色のコントロールを難しくする理由
なぜ、高くから叩く奏法では音量や音色をコントロールしにくいのでしょうか。
鍵盤が下がり始める瞬間がポイントです。
高くから叩く場合は、手が鍵盤へ触れるまでの間にすでにスピードがついているので、鍵盤へ触れたときにはそのスピードを伴って鍵盤が下りていきます。したがって、鍵盤をどれくらいの加減で打鍵するかのコントロールがほとんどできません。
一方、鍵盤のすぐ近くから、あるいは、鍵盤に触れた状態から打鍵した場合は、鍵盤が下がり始めるポイントにおける上例のようなスピードはありません。したがって、鍵盤をどれくらいの加減で打鍵するかのコントロールが可能となり、音量や音色をコントロールできます。
‣ 4. 強打における意識と身体の関係性
強打をすべきところはあらゆる楽曲の中に出てきますが、その際には「意識が先で身体や手は後、もしくは、同時」と考えてください。
・「意識」というのは、出したい音色のイメージのこと
・また、耳障りのしない良質の音を出したいという気持ちのこと
これらは、一瞬で準備できます。
意識なしで身体や手が出しゃばると叩く結果になり、低音はガンガン、高音はカンカンになります。仮に偶然そこそこキレイな音が出たとしても、直前とはまったく関係のない音色が響くことになってしまうでしょう。
「音が間違っていないのに失敗」ということにならないよう、強打のときには意識を働かせてください。
‣ 5. ダンパーペダルの特性と音の共鳴
ダンパーペダルを踏み込むとすべてのダンパーが一斉に弦から離れるので、一種のトンネル状態になります。
試してみたことがあるかもしれませんが、この状態でピアノの中へ向かって騒ぐと、大騒ぎになって返ってきます。手をパチンと叩くと、共鳴してパァーンみたいな響きになります。
要するに、この状態では、純粋にピアノが出した音以外の様々な騒音・雑音も拾ってしまうということです。ピアノの内部で起こった音も外部で起こった音も共鳴することになり、七難隠してはくれません。
だからこそ、高くから叩く奏法は良くないとされているのです。
上記のように、叩くと、指が鍵盤にぶつかることによる騒音が立ち、鍵盤が鍵床へぶつかる騒音も大きくなります。また、叩く奏法では、鍵盤が下り始める瞬間に手の移動にかなりのスピードがついてしまっているため、そのスピードのまま鍵盤が下り始めてしまいます。したがって、スナップを効かせたようなハンマーの動かし方ができないまま弦をぶっ叩くことになるので、音色が散らばってしまいます。
こういったあらゆる騒音・雑音成分までピアノのトンネルが響かせてしまうことを再確認しておきましょう。
「ピアノ演奏のテクニック」 著:ヨーゼフ・ガート 訳:大宮真琴 / 音楽之友社
という書籍の中に、以下のような文章があります。
聴き手のなかにおこる音量の感じは、強弱の度合だけではなく、音量に比較して雑音を小さくする奏者の能力に依存しているのである。
(抜粋終わり)
「ぶっ叩いた音は近くで聴くと大きい音に聴こえるけれども、遠くまでは届かない」
ということはよく言われ、実際にそのように感じたことも多いことでしょう。
その理由には、上記のような「叩いたことによるあらゆる騒音・雑音」をすらダンパーが解放されたトンネル状態のピアノが共鳴させてしまうから、という決定的なものがあると言えます。
・ピアノ演奏のテクニック 著:ヨーゼフ・ガート 訳:大宮真琴 / 音楽之友社
► C. 音色改善の実践的アプローチ
‣ 6. 叩いている箇所を特定する実践的な方法
ざっくりとではありますが、叩いているところの検討をつける方法があります。
和音、それも手がラクラク届く強奏の和音を疑うようにしてみましょう。
大抵の場合、叩いてしまうのはラクにおさえられる和音だからです。
手をいっぱいに開いてようやく届くような和音では、上から叩こうとすると音を外すので、意識せずともしっかりとポジションを準備して鍵盤の近くから打鍵しています。叩くような結果にはなりにくいでしょう。
では、ラクにおさえられる和音を叩かないためにはどうすればいいのでしょうか。
答えはすでに書いてあります。しっかりとポジションを準備して、鍵盤の近くから打鍵してください。“叩けなかった” 和音のやり方と同じです。
跳躍などの関係で十分にポジション準備の時間がとれない場合は、事を難しくします。その場合は、練習の段階から跳躍の距離を意識してさらっておき、その際にも指先に眼がついているつもりで跳躍するようにしましょう。行き当たりばったりでエイとやると、大抵叩く結果になります。
‣ 7. 叩く奏法を改善するための具体的な対策
「叩いてしまう奏法」の対策をするためには、まず、自身が次のうちどちらに当てはまるのかを整理しましょう:
・自分では叩いていることに気づかず、他者に言われてようやく知った
・自分で叩いていることに気づいているけれど、手の移動など技術の問題で防げない
「自分では叩いていることに気づいていなかった」方は、一度、ピアノが壊れない程度で叩いてみて、音色の違いを知ることから始めてみましょう。
「自分で叩いていることに気づいているけれど、手の移動など技術の問題で防げない」方へは、叩いてしまう箇所はテンポをたっぷり弾くことが許されるところかどうか調べてみることをおすすめします。
例えば、セクションの切り替わりなどでは、楽曲によっては多少たっぷり弾いても音楽的に不自然にならないケースがあります。たっぷり弾くことができれば、手を移動させる難易度を下げることができます。
‣ 8. 和音の美しさを損なう隠れた要因
感じたことがあるかもしれませんが、叩いていないのに、弾いた後に押さえつけてもいないのに、強奏の和音が美しく聴こえないことはあります。
汚く聴こえてしまう別の理由は、「和音各音のバランス」にあります。
弱い指で弾く音が埋もれてしまったり強い指で弾く音が突出していると、全体で聴いた和音の印象は美しく聴こえません。その和音の中にメロディ音が含まれているのであれば、当然それを浮き立たせるべきですし、バス音まで含まれるのであれば、メロディと内声とバスとのバランスを考えなければいけません。
目の前の和音を見たときに、各音をどのようなバランスで弾くことが求められているのかをよく考えてみましょう。
和音が連続するときにはそれらがきちんとフレーズを作るように、横の流れを意識してください。
それがなくなると、「和音和音和音」「一つ一つ一つ」になっていまい、ただの音の連続になってしまいます。各和音そのものは美しく弾けていても、全体で把握したときには美しくありません。
► 終わりに
「叩く奏法」の改善において重要なのは、とにかく「意識」を持つことです。本記事で紹介した視点を日々の練習に少しずつ取り入れ、自分の演奏を客観的に聴き、改善を重ねてみましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
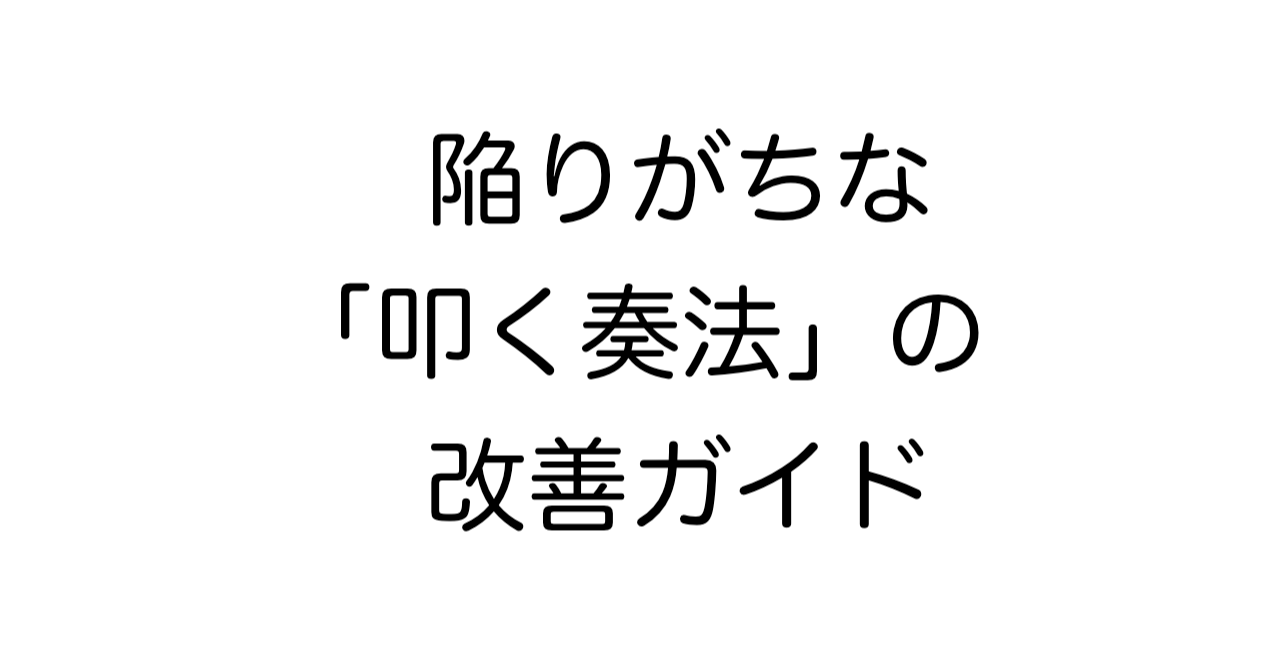

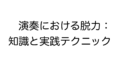
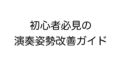
コメント