【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア全15曲 練習参考記事一覧と学習ガイド
► はじめに
J.S.バッハの「3声のシンフォニア」は、ピアノ学習者にとって必修ともいえる重要な作品集です。2声のインヴェンション全15曲が終わった後の発展学習として、それぞれ異なる技術的・音楽的課題を持っています。ただの練習曲ではなく、演奏会でも使える芸術的価値の高い楽曲でありながら、ピアノ演奏に必要な基礎技術を効率的に身につけることができる理想的な教材と言えるでしょう。
本記事では、シンフォニア全15曲の練習に役立つ記事をまとめました。これらの記事では、「全運指」公開やその他の練習のヒントまで、効率的かつ音楽的に学習を進められるよう構成しています。
2声のインヴェンションの学習が済んでいない方は、先に以下の記事を参考にしてください。
【ピアノ】J.S.バッハ インヴェンション全15曲 練習参考記事一覧と学習ガイド
► 練習参考記事一覧
‣ 2声のインヴェンションから3声のシンフォニアへの橋渡し記事
これから3声のインヴェンションへ入門する方は、まず以下の記事からお読みください。
【ピアノ】インヴェンションからシンフォニアへ:知っておくべき技術的変化点
この記事では、3声のシンフォニアへ進む際の技術的変化点を詳しく解説しています。声部の受け渡し、替え指技術、片手内多声表現、声部認識などを取り上げた、指導者と独学者必見のガイドです。具体的な譜例と指導や練習のポイントを紹介しています。
指導者向けに書いた記事ですが、独学でシンフォニアに取り組む方にとっても重要な内容です。「生徒が直面する課題」を「自分が直面する課題」として読み替え、「指導のポイント」を「練習時の注意点」として活用してください。
‣ シンフォニアの入門者向け詳細解説シリーズ
シンフォニアに初めて取り組む方は、まず以下の3曲から始めることをおすすめします。これらは、他の対位法的なシンフォニア作品と比較して、ホモフォニー(主旋律と伴奏)の要素が強く現れた作品であることから、比較的取り組みやすいものとなっています。
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第5番 BWV791 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第11番 BWV797 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第2番 BWV788 全運指付き楽譜と練習のコツ
第5番(作曲者自身による装飾音がない版)、第11番、第2番の順番で取り組むのがいいでしょう。2声のインヴェンションと比較したときの体感難易度をスムーズに橋渡しすることができます。
重要な注意点
上記の解説記事では、著作権に配慮し「原典版」の譜例を使用しています。これは楽曲自体はパブリックドメインですが、各出版社の解釈版には独自の表現記号等が含まれるためです。実際の学習では、下記で紹介する解釈版楽譜を用意してください。既に別の楽譜をお持ちの方は、それを使っていただいても構いません。
・園田高弘 校訂版 J.S.バッハ シンフォニア BWV787−801
‣ 中級者向け詳細解説シリーズ
入門3曲を終えた方、または最初からより難しい曲に挑戦したい方向けの12曲です。各曲の練習のコツ等を解説しています。
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第1番 BWV787 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第3番 BWV789 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第4番 BWV790 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第6番 BWV792 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第7番 BWV793 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第8番 BWV794 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第9番 BWV795 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第10番 BWV796 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第12番 BWV798 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第13番 BWV799 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第14番 BWV800 全運指付き楽譜と練習のコツ
・【ピアノ】J.S.バッハ シンフォニア 第15番 BWV801 全運指付き楽譜と練習のコツ
► 効果的な学習の進め方
シンフォニア初挑戦の方
まず「入門シリーズ」の3曲の中から選んで始めることをおすすめします。上記の橋渡し記事の中でも触れているように、3声のシンフォニアでは2声のインヴェンションとは異なる技術が求められます。焦らずに基本的な番号から取り組んでいきましょう。
中級者の方(ツェルニー40番中盤〜程度)
どの楽曲からでも挑戦可能ですが、3声の対位法作品に慣れていない場合は「入門シリーズ」から始めるのも有効です。
上級者の方(ツェルニー50番中盤〜程度)
どの楽曲からでも学習可能です。既にシンフォニアを解釈版で学習済みの方は、原典版での学び直しをおすすめします。より深い音楽的理解が得られるでしょう。原典版を基本とし、必要に応じて複数の解釈版を比較検討してください。
おすすめの解釈版楽譜
特に独学の方には「園田高弘 校訂版」が最適です。アーティキュレーションやその他の解釈の指針が詳しく記載されており、独学でも安心して学習できます。
► インヴェンションとシンフォニアの学習の意義
「インヴェンションとシンフォニア」がピアノ教育で重要視される理由は、基礎技術の習得と音楽性の向上を同時に実現できることにあります。
技術面での効果:
・複声部の独立した演奏技術
・様々な調性での練習
・さまざまなテンポやリズムパターンの習得
・カンタービレの表現、速いパッセージ
・左右両手の均等な技術発達
・精密な運指技術の確立
音楽面での効果:
・対位法の基本的理解
・バロック様式の表現技法
・歴史的演奏法への理解
・構造的な楽曲分析能力
・フレージングとアーティキュレーションのボキャブラリー増加
教材としての優位性:
・各声それぞれ全15曲ずつという適切な分量であり完走可能
・1曲2-3分程度のコンパクトな構成
・豊富な参考資料と録音の存在
・曲が魅力的で退屈しない
・練習曲でありながらレパートリーとしても成立
・他のJ.S.バッハ作品(平均律クラヴィーア曲集 等)への橋渡し
► よくある質問
Q:シンフォニアはどのくらいの期間で全曲マスターできますか?
A:個人差がありますが、週1曲のペースで進めると約4ヶ月程度が目安です。1曲1曲を徹底的に仕上げることを重視する場合は、1曲あたり3週間かけて細かく学んでいくといいでしょう。そうすると約1年間で終わります。
Q:原典版と解釈版、どちらを使うべきですか?
A:中級者までは解釈版から始め、必要に応じて原典版も併用することをおすすめします。最終的には両方を比較検討できるレベルを目指しましょう。
Q:J.S.バッハの作品に関して、「3声のシンフォニア」の後は何を学ぶべきですか?
A:「平均律クラヴィーア曲集」へと進むのが一般的な流れです。取り組みやすいフーガを持つ番号を選択することで、大きなハードルなく接続することができます。「平均律クラヴィーア曲集」まで到達した後は、「パルティータ」「イタリア協奏曲」「イギリス組曲」等、併用学習できる教材は多くあります。
► 終わりに
本記事で紹介した3声のシンフォニア全15曲の詳細解説記事を活用し、段階的に学習を進めることで、2声のインヴェンションからさらに一歩踏み込んだバロック音楽の世界を体感できるでしょう。焦らず一曲一曲を丁寧に学習することが、確実な上達への道筋となります。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
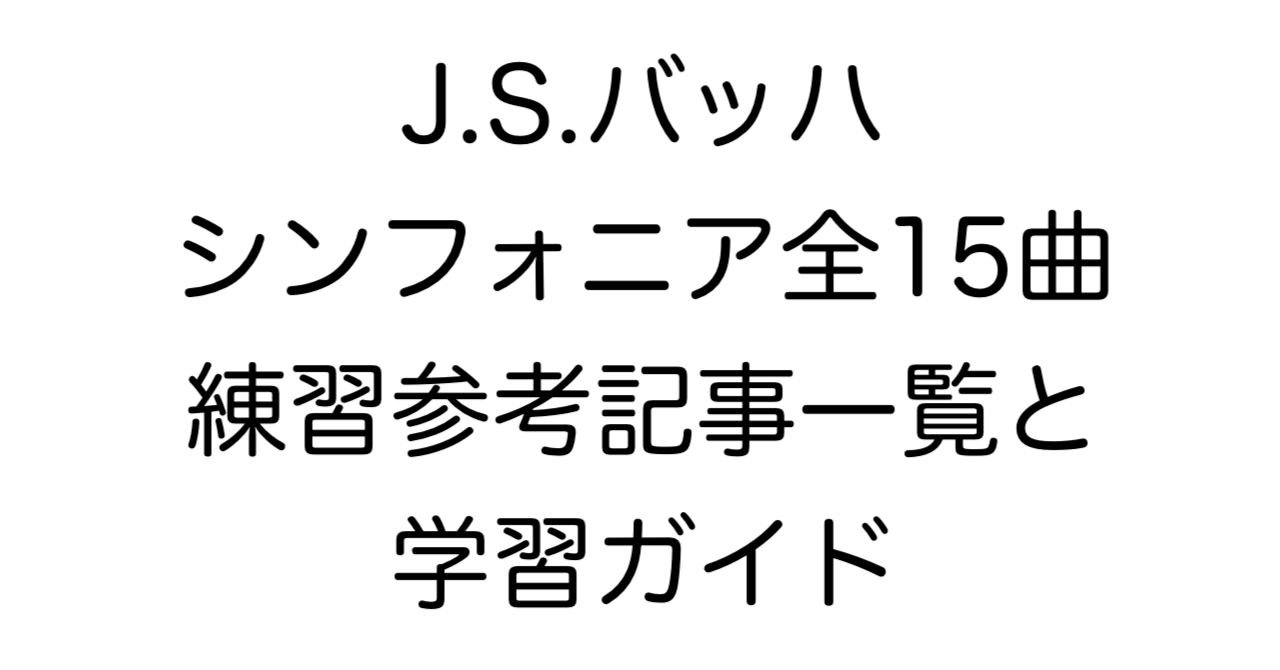

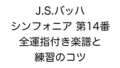
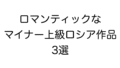
コメント