【ピアノ】最終音の後の休符小節に隠された音楽的意図とは
► はじめに
ピアノ曲を演奏していると、最終音を弾いた後にもなぜか丸々1小節分の休符が書かれている楽譜を目にすることがあるでしょう。実はここには作曲家の意図が隠されています。
本記事では、クラシック音楽でよく見られる「最終音の後の休符1小節」の意味と、演奏時の考え方について解説します。
► 音楽的意図と演奏のヒント
‣ 最終小節の休符が存在する音楽的意図
例えば、以下の譜例のように、最終音の後に丸々休符の1小節が存在する楽曲はよく見られます。
ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

なぜ、こういった休符の小節が存在するのかには、明確な意図があります。 特に古典派までの作品に多く見られますが、主な理由はフレーズの小節単位を一貫させるためです。
この譜例の場合、カギマークで示したように、4小節単位のフレーズで構成されてきていることに着目してください。最後の部分だけ3小節で終わらせるのではなく、休符の小節も加えて4小節単位を維持し、音楽的なバランスを保っているわけです。
ここまで4小節単位で進行してきたわけなので、聴き手は無意識のうちにそのリズム感を内在化しています。そのため、最後の部分でも自然と4小節目を期待する心理が働きます。つまり、この休符の小節は単に形式を整えるために必要なだけではなく、音楽の重要な一部なのです。
実際の楽曲の中には、「最終音の後ですぐに音楽を辞めないで欲しい」という意図などで、小節構造と関係なく休符の1小節を置いているものもあります。したがって、休符による最終小節を見つけた場合には、まずは小節構造を探ってみて、それに当てはまらない場合は別の意図を考えてみるといいでしょう。
‣ 演奏のヒント
休符の小節は「無音」ですが、決して「無意味」ではありません。むしろ、音楽の構造を支えている重要な要素です。多くの作曲家たちは、小節構造の美学や音楽の余韻を大切にしていました。
演奏する際は、こうした休符による最終小節もしっかりと意識して、その間も音楽が続いているという意識を持ちましょう。たとえ、指は鍵盤から離れていたとしてもです。
► 終わりに
4小節や8小節といった規則的なフレーズ構造は、西洋音楽の基盤となる美学の一つです。この構造を最後まで貫くことで、楽曲全体に統一感をもたらしているのです。また、休符の間に流れる静寂もまた、音楽の一部として大切な役割を果たしています。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
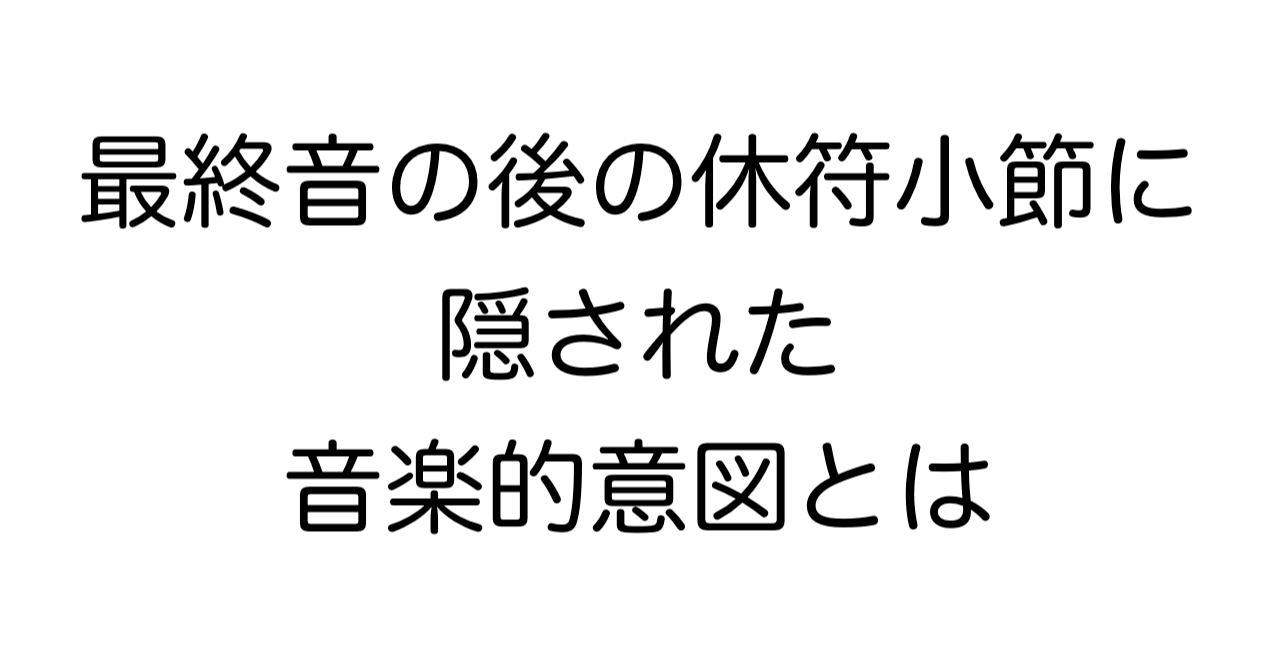
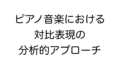
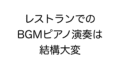
コメント