【ピアノ】通し練習と部分練習のコツと進め方
► はじめに
ピアノの練習では、ただ音符を弾くだけではなく、効率的な練習法を身につけることが上達への近道です。
本記事では、通し練習と部分練習の効果的な進め方を解説します。それぞれの練習法の特徴やコツを理解し、自身にとっての最適な方法を見つけていきましょう。
► A. 通し練習
‣ 1. 最適な通し練習の回数と方法
「ピアノの技法―楽しみつつマスターできる」 著 : チャールス・クック 訳 : 堀内敬三 / 音楽之友社
という書籍に、以下のような文章があります。
私が毎日実行している全曲の繰り返しの回数は大体五回である。
始めの二回はゆつくりと、次の一回は正しいテンポで、後の二回は又ゆつくり弾くのである。
(抜粋終わり)
「実際のテンポでの通し練習は1回にする」という視点は非常に重要です。
実際のテンポでの通し練習というのは、我々の想像以上に身体への負担がかかっており、集中力も使います。「1曲につき1回まで」というのは、故障せずに、なおかつ、集中して質の高い練習をするためのやり方として理に適っていると言えるでしょう。
では、「実際のテンポでの通し練習をどこへ入れるか」についてですが、上記抜粋のように「2回のゆっくり通し練習を入れたあと」でもいいのですが、筆者は、真っ先に行う実際のテンポでの通し練習をおすすめしています。
その演奏を録音しておき、聴き直して練習方針を立ててから、ゆっくり通し練習をしたり部分練習をはさんだりして進めていくといいでしょう。
様々なやり方を試した結果、筆者にとってはこのやり方が最適でした。チャールス・クックの方法はもちろん、何パターンかを試してみて、自身に一番合ったやり方を探ってください。練習方法が無数にある中で失敗を重ねながら自分にあったやり方を見つけていくのも、大切な過程の一つです。
・ピアノの技法―楽しみつつマスターできる 著 : チャールス・クック 訳 : 堀内敬三 / 音楽之友社
‣ 2. 朝の通し練習で実力を知る
筆者は学生の頃から、レッスンの直前や本番の直前は、朝起きてすぐのタイミングで一度通し練習をしてみることにしていました。
「朝起きてすぐ」というのは、寝起き30秒とかではなく、顔を洗ったり一通りのことを済ませた後で、寝起き30分以内程度のことです。
「朝起きてすぐのタイミングは一番その人の実力が現れる」と言われることもあるくらいで、普段うまくいっているところでも思いがけないアクシデントが起きたりするから不思議です。起きて何時間も経って気合いを入れて通すのとは全く異なる状況です。
当然、本番というのは寝起きすぐにやるものではありません。しかし、潜在的な危険なところを知っておくためにも、朝の通し練習を取り入れて、このような方面からの対策もしておくといいでしょう。
► B. 部分練習
‣ 3. 両手で概ね弾けるようになったら、片手練習を減らす
片手練習では:
・難しいところを部分練習する
・難しいところで片方の手のパートだけ先に暗譜してしまって、難易度を下げる
などといった取り入れ方があるので、新たに取り組み始めた楽曲を練習していく段階にとっては有益です。
一方、ピアノ音楽はやはり「両手で弾く音同士のバランスをとっていくこと」を前提として書かれています。したがって、両手で概ね弾けるようになってからも片手練習が多過ぎると、むしろマイナスになることもあると思ってください。両手によるバランスはそっちのけだからです。
ある特定の箇所がうまく弾けないのであれば:
・テンポを落として両手でさらったり
・1拍ずつ速く弾く練習(拍頭止め)をしたり 推奨記事:「1拍ずつ速く弾く練習法」
などと、別の視点でアプローチしてみてください。
片手練習は、取り入れるタイミングや意図を考えたうえで適度に付き合うようにしましょう。
‣ 4. 効果的な部分練習のコツ
つっかえてしまう難しいところで、メトロノームにあわせてミスしないまで弾き続ける、などといった目も当てられない練習方法が度々話題になります。
仮に、10回に1回、いや、5回に1回、ミスをせずに音色なども満足に弾けたとしましょう。それでもその練習はマイナスです。
理由は簡単で、上手くいっている回数よりもそうでない回数のほうが上回っているからです。誤りを繰り返して身に付けても意味ありません。
部分練習を設定するときには、せめて、誤りの回数のほうが少なくなるようなテンポや練習方法を試みましょう。誤りが多くなる練習というのは、頭か身体か、もしくはその両方が準備できていない状態で行われるものです。
まずは、誤りの少なさに加えて、音色をきちんとコントロールできるテンポからやり直すことが重要です。そのような頭も身体も準備できる状態であれば、文字通り準備して打鍵できるので、弾いたときに発生する叩いた騒音が少ないことにも気づくでしょう。
‣ 5. 練習の仕上げと弾きこぼしの修正
日頃の練習では、「ゆっくり練習(拡大練習)」に加えて:
・譜読み段階の曲で、テンポを上げるべく速く弾く練習
・仕上げ段階の曲での、通し練習
なども取り入れることでしょう。
有効な練習ではあるのですが、「弾きこぼしをつくりやすい」という問題点もあります。
弾きこぼしをつくったまま放置してしまうと、それが身体へ染み込んでしまいます。だからこそ、速く弾く練習ばかりしたり通し練習ばかりするのは、むしろマイナスになってしまうのです。
・速く弾いたら、その部分をゆっくりさらって弾きこぼしやその他の音楽面を整える
・それを繰り返していく
・一度通し練習をした場合も、必ず整える
この皿回しのような練習をすることで、良くないクセをつけることなく、あらゆる練習の恩恵を受けることができます。
そして、もう一つ重要なのは、こぼれたものをきちんと拾って、その日の練習を終わらせること。良くない染み込みを防ぐためと、練習後にその日1日モヤモヤを残さないためにです。
‣ 6. 自身にとっての適切な練習法を見つける
ピアノの力がグンと伸びる瞬間は、”自身にとっての” 適切な練習法を見つけて一定期間継続したときです。
「自身にとっての」というところがポイントです。
知人のピアニストで「譜読みさえ終われば、それ以降は通し練習しかせず、部分練習は一切しない」という方がいます。通し練習の中であらゆることを調整していくのだそうです。
試してみましたが、筆者にとってこの方法は真似できない内容だと感じました。しかし、そのピアニストにとってはベストな練習方法だったのです。
本Webメディアでは、あらゆる練習方法や音楽の捉え方などをお伝えしていますが、それらを実際に一定期間試してみて、自身に合ったものを引き出しへ入れてください。その繰り返しで、自分にとっての適切な練習法を見つけることができます。
► 終わりに
ピアノの練習において正解は一つではありません。本記事で紹介した通し練習と部分練習のヒントを参考に、自身に適した練習スタイルを見つけ、日々の練習に活かしてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
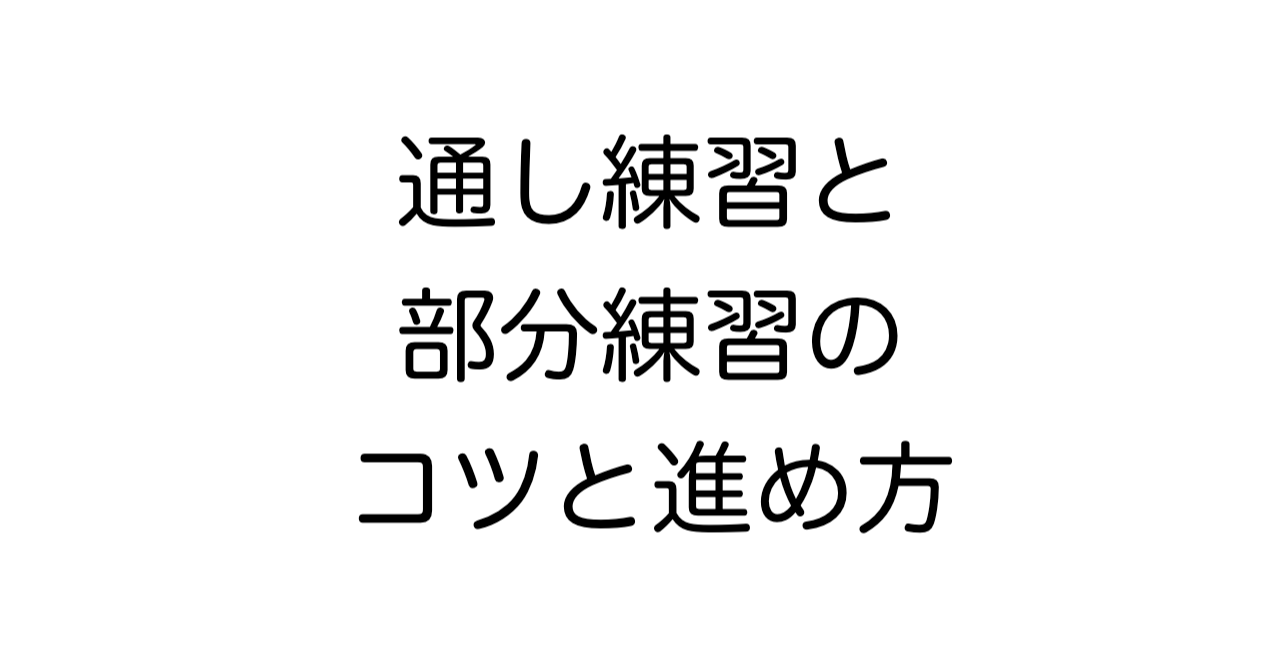

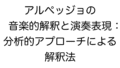
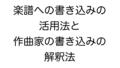
コメント