【ピアノ】映画「想い出を売る店」レビュー:リチャード・クレイダーマンのピアノが織りなす切なさと希望
► はじめに
1985年に公開された映画「想い出を売る店」は、サンリオが制作した実写映画作品です。北フランスのノルマンディー地方を舞台に、想い出を映し出す不思議な店と、そこに訪れる人々の切ない物語を描いています。本作の音楽面での特徴は、世界的に人気のピアニスト、リチャード・クレイダーマンの演奏を全編にわたって使用している点にあります。
・公開年:1985年(日本)
・監督:近藤明男
・ピアノ関連度:★☆☆☆☆(ピアノが物語の主題ではない)
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
‣ クレイダーマンが映画の語り部に:特徴的なオープニング演出
本作のオープニングは、1980年代の映画としては珍しい構成となっています。映画は「想い出を売る店(ピアノソロ Ver.)」の演奏で幕を開けますが、当初は通常のBGMかと思わせておきながら、途中から実際にピアノを弾くリチャード・クレイダーマン本人の姿が映し出されます。これはまさにミュージックビデオ的な演出で、音楽と映像の境界を曖昧にする試みと言えるでしょう。
さらに興味深いのは、演奏を終えたクレイダーマンが映画本編の前振りを語り、ナビゲーターの役割を担っている点です。通常、映画音楽のスタッフが画面に登場することは稀ですが、本作ではクレイダーマン自身が物語の案内人として機能しています。この演出は、状況外音楽(通常のBGM)と状況内音楽(劇中で実際に流れている音楽)の境界を意図的に曖昧にし、観客を物語世界へと誘う効果を生んでいます。
エンディングでも同様に、クレイダーマンが再び登場して本編についてコメントを述べ、映画全体を音楽的に包み込む額縁構造を作り上げています。この手法は、音楽が物語を語る主体の一つとなっていることを示しています。
‣ クレイダーマン楽曲の使用:全編を彩る9曲
本作で使用されるクレイダーマンの楽曲は以下の9曲です:
・想い出を売る店(ピアノソロ Ver. コンチェルト Ver. ピアノ+ストリングス Ver.)
・母への手紙
・ノルマンディーの詩
・悲しみのかなたに
・愛のコンチェルト
・アナスターシャの最後の日々
・椿姫
・おもかげ
・きっと、ずっと・・・(ピアノソロ Ver.)
注目すべきは、映画全体の音楽構成において、クレイダーマン以外の楽曲はわずか3曲のみという点です。マリーの誕生日パーティでのダンスミュージック、トムのヴェニス修行時代のゴンドラのシーンと河辺のバーのシーンで流れる歌が使用されているのみで、それ以外はすべてクレイダーマンのピアノ音楽が映画を彩っています。
この徹底したクレイダーマン楽曲の使用は、映画全体に統一された音楽的な世界観をもたらし、切なさと温かさが同居する独特の雰囲気を生み出しています。
‣ 音楽の使い方で示される物語構造の巧みさ
「想い出を売る店」には、大きく分けて3組の人物が訪れます:
・30年前に船の事故で亡くなった息子を待ち続ける女性
・戦死した男性を待ち続ける若い女性
・主人公のトムとマリー
前半の2組のエピソードでは、それぞれの想い出のシーンにクレイダーマンの楽曲が当てられ、簡潔に言うと「切なさを強調する使い方」がされています。
しかし、トムとマリーの物語が始まると、音楽の使い方が変化します。彼らのエピソードは映画の主軸であり、より長く複雑な展開を見せるため、単純に「想い出のシーンに音楽を当てる」という手法から離れ、様々なタイミングで多彩な楽曲が使用されるようになります。この音楽演出の変化によって、観客は早い段階から、前半の2組とは異なる物語的重要性を持つことを察知できるのです。
音楽の使い方そのものが、物語の構造を暗示する演出手法と言えます。
‣ 象徴的楽曲「愛のコンチェルト」:映像と音楽のコントラスト
本作で最も印象的な音楽演出は、ラストシーンにあります。マリーとトムがついに結ばれるハッピーエンドの場面で、切ない「愛のコンチェルト」が流れるのです。
それまでのシーンでは、切ない場面には切ない音楽といった、映像と音楽が直接的に対応する使い方がされていました。しかし、このラストシーンでは、映像はハッピーであるにもかかわらず、音楽は切なさを湛えています。
この対比的な演出は、音楽が単に状況説明のためのものではなく、映画全体のテーマを象徴する楽曲となっていることを意味しています。「愛のコンチェルト」は、トムが登場して以降のシーンで繰り返し使用されており、タイトル曲「想い出を売る店」に次いで重要度の高い楽曲です。この楽曲は、6年間の別離と待ち続けた苦しみ、そして再会の喜びが入り混じった複雑な感情を表現しているのでしょう。
‣ 1985年の先進性:状況外音楽としての歌の使用
本作でもう一つ注目すべき点は、トムのヴェニス修行時代のシーンで使用される歌の扱いです。ゴンドラに乗るシーンと河辺のバーのシーンで流れる歌は、いずれも状況外音楽、つまり通常のBGMとして使用されています。
一般的に、歌というのは登場人物が劇中で歌っていたり、ラジオから流れていたりと、状況内音楽として使われることが多いものです。しかし本作では、歌がインストゥルメンタルのBGMと同じように、登場人物には聴こえていない音楽として機能しています。
近年の映画音楽では、スキャットやボイスパーカッション的なフレーズを加えた楽曲が多く見られますが、1985年当時、このような歌の使い方は比較的珍しいものでした。
特にゴンドラのシーンで流れる楽曲は、「ゴンドラ」という歌詞が含まれており、水辺の情景にふさわしい詩的な言葉が乗せられています。この歌詞の内容と映像のシンクロニシティも、音楽演出の綿密さを物語っています。
► 使用されたクレイダーマン作品の楽譜と音源
本映画で使用されたクレイダーマン作品の一部は、実際に楽譜も手に入れることができます。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【ピアノ】クラシックピアニストのためのリチャード・クレイダーマン楽譜ガイド
DVDの特典映像には「リチャード・クレイダーマン 楽曲集」が収録されており、本映画で使用されたクレイダーマン楽曲を楽曲別に映像と共に楽しむことができます。
► 終わりに
「想い出を売る店」は、リチャード・クレイダーマンのピアノ音楽を全面的に使用することで、独特の詩情と切なさに満ちた作品世界を構築しています。オープニングでのミュージックビデオ的演出、音楽の使い方による物語構造の暗示、映像と音楽の対比的使用など、興味深い音楽演出が見られます。
クレイダーマンの繊細で抒情的なピアノの音色は、想い出というテーマを美しく彩り、観客の心に長く残る余韻をもたらしています。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
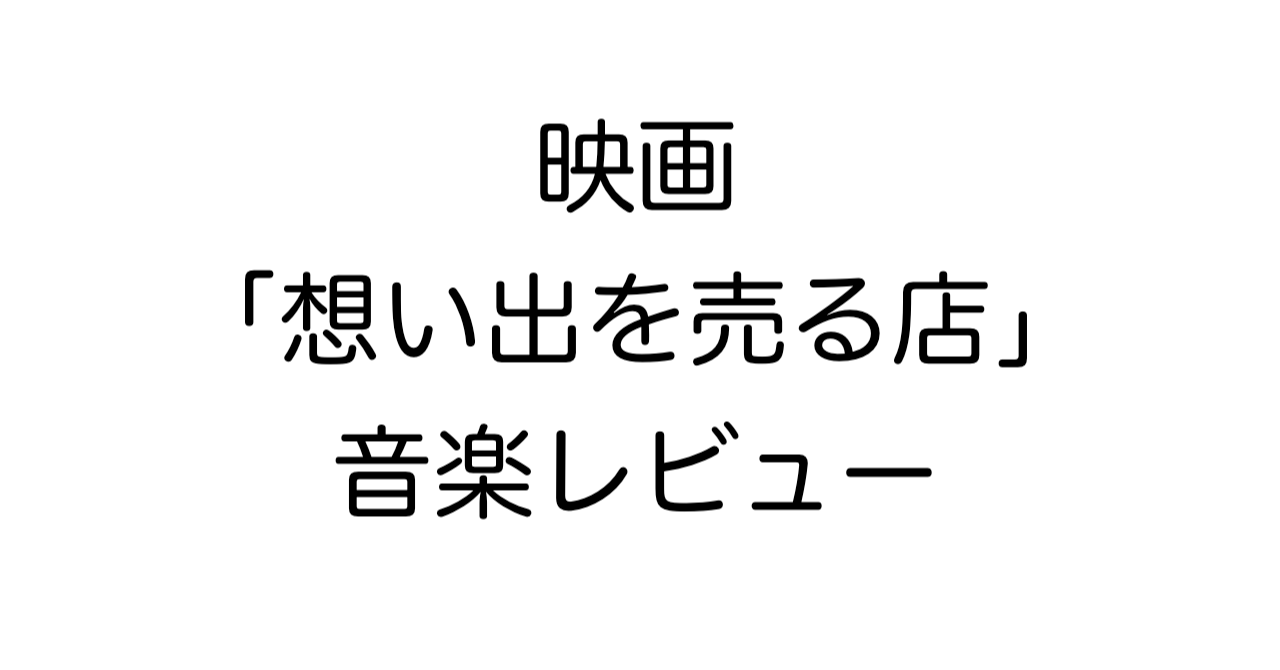
![想い出を売る店 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL160_.gif)
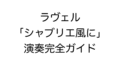
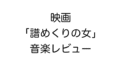
コメント