【ピアノ】エルヴィン・シュタイン「作品構造と演奏」レビュー
► はじめに
「作品構造と演奏」は、エルヴィン・シュタイン(1885-1958)による、音楽作品の構造を深く理解し、それに基づいた演奏アプローチを考えるための指南書です。著名な作曲家ベンジャミン・ブリテンによる序言が付されていることからも、本書の価値の高さがうかがえます。
「楽曲分析的視点が強い著作」であり、演奏テクニックの解説書ではなく、作品の内的構造を理解し、その理解に基づいた演奏解釈を導き出すための方法論が提示されています。
・訳 : 黒川武
・出版社:全音楽譜出版社
・邦訳初版:1972年
・ページ数:198ページ
・対象レベル:中級〜上級者
・作品構造と演奏 著:エルヴィン・シュタイン 訳:黒川武 / 全音楽譜出版社
► 著者について
エルヴィン・シュタインは1885年ウィーン生まれの多才な音楽家で、批評家、編集者、作曲家、指揮者といった幅広い分野で活躍しました。特筆すべきは、21歳から25歳までの青年期にシェーンベルクの下で作曲を学び、1921年からは彼の助手を務めたという経歴です。ダンツィッヒ、ダルムシュタット、シュトラスブルクなどの歌劇場の指揮者としても活動しました。
ユニヴァーサル社やブージー・ホークス社といった名門音楽出版社が彼を音楽顧問として迎えたことからも、彼の学識の高さと音楽への貢献度がうかがえます。特にベンジャミン・ブリテンとは親交が深く、彼の才能をいち早く見出しました。シュタインは1958年にイギリスで没しました。
► 内容について
‣ 目次構成
本書は以下の章立てで構成されています:
・ヘアウッド女史の覚え書き、序言(ベンジャミン・ブリテン)、はしがき、序
・第1章 楽音の要素
・第2章 音楽の形態,構造の要素
– 調的な展望
– 時間的要素
– ダイナミック
– 音質と音色
・第3章 構造
・第4章 運動の流れ
・第5章 フレージング
・索引、譜例索引、訳者あとがき
各章では譜例を多数用いながら、音楽の基本要素から複雑な構造に至るまでを解説しています。注目すべきは、C.P.E.バッハの有名著作の奏法内容の欠点を指摘している点や、休符の意味の詳細分析など、豊富な経験からくる鋭い視点を提供している部分です。
‣ 本書の価値
本書は、演奏テクニック習得の書ではなく、「作品構造を理解し、それを表現する」という音楽演奏の本質的な課題に取り組むための指針となっています。譜例はピアノ曲に限らず多様な楽器編成の作品も含まれていますが、ピアノ曲も多数取り上げられており、ピアノ学習者にとって有益な内容となっています。
特に以下の点において、本書の価値が高いと言えるでしょう:
・楽曲分析能力の向上:音楽作品の構造を分析する視点と方法論を学ぶことができる
・演奏解釈の深化:ただの「演奏テクニック」ではなく、作品構造に基づいた演奏解釈を導き出す方法を学べる
‣ 本書からの重要な引用
重要な引用として、例えば以下の部分が挙げられます:
構造と響きが演奏者の内部で1つのものとならなければならない。1つ1つのパッセージの正確な構造、クレッシェンドの1つ1つの度合い、すべてのフレーズの重点などを、はっきりそして生き生きと演奏者が内的に聞けるようになっていなくてはならない。
(抜粋終わり)
また、シュタインの音楽観を表す部分として、ベンジャミン・ブリテンは以下のように指摘しています:
彼(エルヴィン・シュタイン)は、作曲家の書いた実際の音の強調、およびその音の背後にあるものを詳しく述べようとしている(中略)彼は人生の中で最も重要な仕事の1つは偉大な音楽的真実のコミュニケーションだと確信しており、その音楽的真実を細心の注意と深い愛情をこめこの著作で啓示しているのである。
(抜粋終わり)
► おすすめの読者層
本書は、以下のような方々におすすめです:
・ピアノ演奏の中級・上級学習者
・音楽教育者・指導者
・作曲・編曲に取り組む方
・楽曲分析に関心のある方
► 終わりに
「作品構造と演奏」は、楽曲構造の理解から演奏へアプローチする一冊です。全198ページと内容も比較的コンパクトなので、取り掛かりのハードルも高くはないでしょう。
・作品構造と演奏 著:エルヴィン・シュタイン 訳:黒川武 / 全音楽譜出版社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
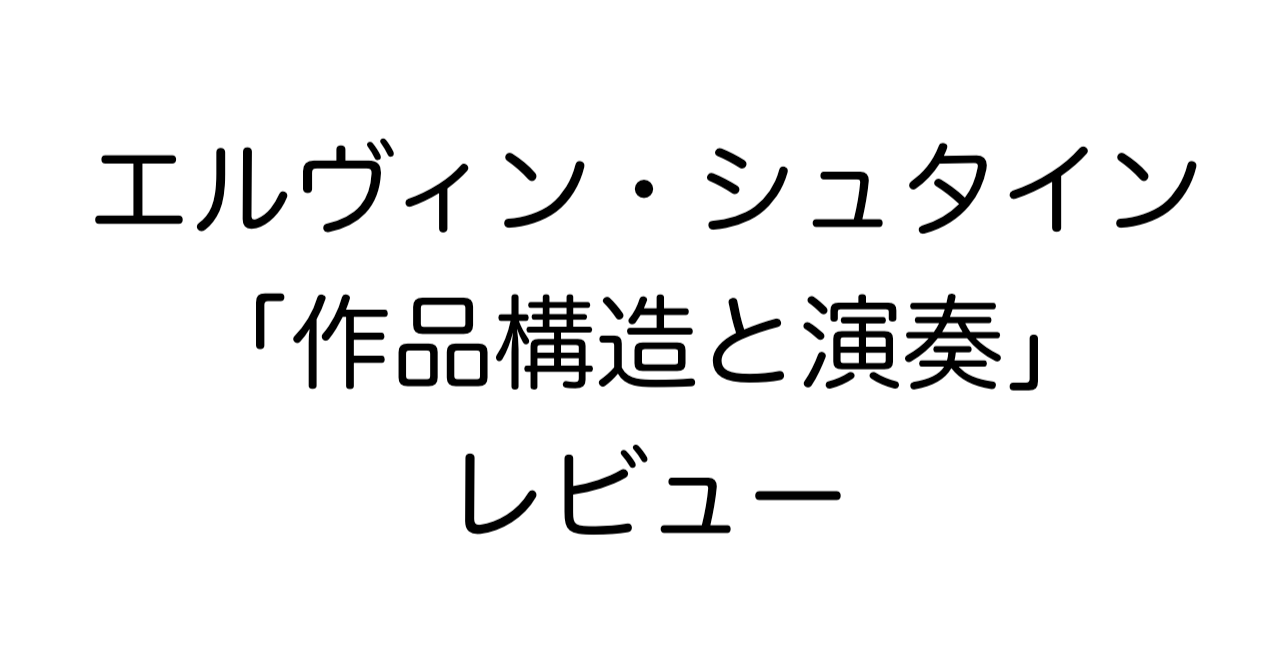


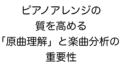
コメント