【ピアノ】原典版(Urtext)の活用ガイド:いつ・なぜ・どう使うべきか
► はじめに
ピアノを学ぶ過程で、「原典版を使ったほうがいいのか」「今の段階で原典版を買うべきか」といった疑問を持つ学習者は少なくありません。原典版は確かに価値がありますが、学習段階によってはかえって混乱を招くこともあります。
本記事では、原典版の価値と、ピアノ学習において最適な楽譜選びの基準を紹介します。
► 原典版とは何か
‣ 原典版(Urtext)とは
原典版(Urtext)とは、「作曲者の意図を、第三者の手を加えずにできる限り忠実に再現しようとした楽譜」です(実際には、原典版でも多少の編集者の判断が入る)。代表的な原典版としては:
・ヘンレ原典版(G. Henle Verlag)
・ウィーン原典版(Wiener Urtext Edition)
・ベーレンライター原典版(Bärenreiter Urtext)
・新モーツァルト全集
などが挙げられます。
‣ 批評版(Critical Edition)について
批評版(Critical Edition)は、「批判版」「批判校訂版」とも呼ばれ、大きく以下の二つの意味で使われます:
・原典版(Urtext)と同義
・原典版に校訂者が演奏のヒントを書き加え、作曲家自身の指示と区別できるように表記したもの
ただし、後者は実用版との区別が曖昧なため、前者の意味で使われることがほとんどです。
‣ 他の楽譜との違い
一方、以下の楽譜とは明確に区別する必要があります:
・解釈版(interpretive edition):コルトー版など、作曲家や演奏家によって解釈を伝達するために校訂されたもの
・実用版(practical edition):教育用の目的などで、本来書かれていない各種記号などを補ったもの
これらは学習サポートとして重要なものではありますが、原典版と比較すると、作曲者の意図を厳密に再現することには限界があります。
► 原典版のメリットとデメリット
‣ メリット
メリット①:作曲者の意図に忠実
原典版の最大の魅力は、作曲者が書いた音楽をできるだけ忠実に伝えようとしていることです。余計な編集や解釈が加えられていないため、演奏者が自分自身の解釈を構築するための純粋な土台となります。
メリット②:学術的な信頼性
原典版は一般的に、複数の資料(自筆譜、初版譜、作曲家の書簡など)を比較検討し、厳密な校訂過程を経て出版されます。巻末には校訂報告が含まれることもほとんどであり、音楽学的知識を深めるのにも役立つでしょう。
メリット③:演奏の自由度
書かれている情報が限定的であることは不便に思えるかもしれませんが、これは演奏者に自由な解釈の余地を与えるものでもあります。自分自身で音楽を考え、表現方法を探る機会となります。
‣ デメリット
デメリット①:とにかく expensive!
原典版はとにかく高価です。例えば、シューマンの「謝肉祭 Op.9」の単曲楽譜の場合:
・ヘンレ原典版:約2,700円
・一般的な実用版:約1,300円
(2025年4月現在)
他の原典版や他の作品も調べてみましたが、平均して1.5倍〜3倍程度の価格はしています。それも輸入楽譜というのはいきなり値段が跳ね上がる可能性すらあることを踏まえておく必要があるでしょう。
デメリット②:初心者には情報不足
原典版は指使いやペダリングなどの情報が限られており、初心者が独学で進めるには適していません。特に日本語の解説がない外国版は、理解するのに追加の労力が必要です。
► 原典版を買うべき作品の見分け方
‣ 購入を検討すべきケース
先ほども触れたように、原典版は高価であるうえに、初心者には情報不足です。したがって、弾いてみる作品全てで原典版を手にするのは現実的ではありません。そこで、どのような作品であれば原典版を買うべきなのかについて、一つの指標を示しておきましょう。
まず、今現在はインターネットがあるので、「手に入りにくさ」はもうさほど気にしなくていいでしょう。余程マニアックな作品でなければ、大手通販サイトにも普通に置いてあります。
中級以上の学習者が演奏発表会やコンクールで演奏する作品:
公の場で演奏する作品は、一生のレパートリーになる可能性があるため、原典版を基に練習することが望ましい
特に深く学びたい好きな作品:
お気に入りの作品や、音楽的に深く掘り下げたい作品については、原典版で学ぶ価値がある
中級以上の段階で学び直す作品:
初心者時代に実用版で学んだ作品(J.S.バッハの小品 等)を原典版を使って学び直すと、新たな発見がある
楽曲分析や音楽理論の学習の教材作品:
分析や理論の学習をおこなう教材にする作品では、余計な編集が加えられていない原典版が適している
‣ 原典版が必ずしも必要でないケース
初級〜中級前半の学習者:
この段階では、日本語の解説や豊富な追加情報のある実用版や解釈版の方が学習効率が高い
試しに弾いてみる程度の作品:
本格的に取り組む予定のない作品に対して、その都度高価な原典版を購入する必要はない
指練習的な要素が濃厚な教則本や練習曲集:
このような教材は一生のレパートリーになり得ないので、原典版にこだわる必要性は低い
初級者は、「何となく原典版がいいらしいよ」という周囲の声に惑わされずに、解説が日本語で書かれていて編集者によるサポート事項も多い実用版や解釈版を使ってください。情報が限定的である原典版を本格的に取り入れるのは、中級以上の段階を迎えてからがおすすめです。
► 原典版を最大限に活用するコツ
1. 中級者以上は、複数の資料を併用する
原典版だけでなく、解釈版や実用版、録音資料なども参考にすることで、より深い学習が可能になります。例えば:
・原典版で基本的な音楽テキストを確認
・著名な演奏家による解釈版でヒントを得る
・複数の録音を聴いて様々なアプローチを学ぶ
2. 自分だけの楽譜を作る
原典版をベースに、自分自身の指使いやペダリング、表現のヒントなどを書き込んでいきましょう。例えば、ベートーヴェン「エリーゼのために」の原典版を見てみると、驚くほど簡素。現代に多く出回っている教育用の解釈が書き込まれた楽譜とは大きな違いがあります。中級以上になってから学び直す時に、書き込む余地がしっかりと残されています。
3. 歴史的背景を学ぶ
原典版に付属している序文や校訂報告を読むことで、作品についての理解が深まります。これらは多くの場合、英語やドイツ語で書かれていますが、翻訳ツールを活用すれば理解できるでしょう。
► おすすめの原典版入門時期
おすすめの原典版入門時期は、やはり「ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのソナタ」からでしょう。実用版の「ソナチネアルバム1」を使用している場合は、入門に適した彼らのソナタが数曲収載されているので、それらの作品は実用版のまま学習して構いません。追加で彼らのソナタに取り組みたい時に、原典版へ移行してください。
J.S.バッハ「インヴェンションとシンフォニア」は実用版や解釈版で学習し、学び直しの時に原典版を使うといいでしょう。J.S.バッハに関しては、3声のシンフォニアの次に取り組む教材から原典版へ移行するのがおすすめです。
この時期であれば、原典版を読み解く最低限の力はついているはずなので、必要に応じて実用版や解釈版を併用していけば学習を進めていくことができます。
► 終わりに
原典版はそれ自体が目的ではなく、より良い音楽表現のための手段の一つです。学習段階や目的に応じて、適切な楽譜を選択することが重要です。
初心者は実用版で基礎を固め、徐々に原典版も取り入れていくというアプローチが、多くの学習者にとって効果的でしょう。音楽的に成長するにつれて、原典版を読み解く力も自然と身についていきます。
関連内容として、以下の記事も参考にしてください。
【ピアノ】原典版で既習曲を学び直す方法:学習の利点と取り組みのポイント
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
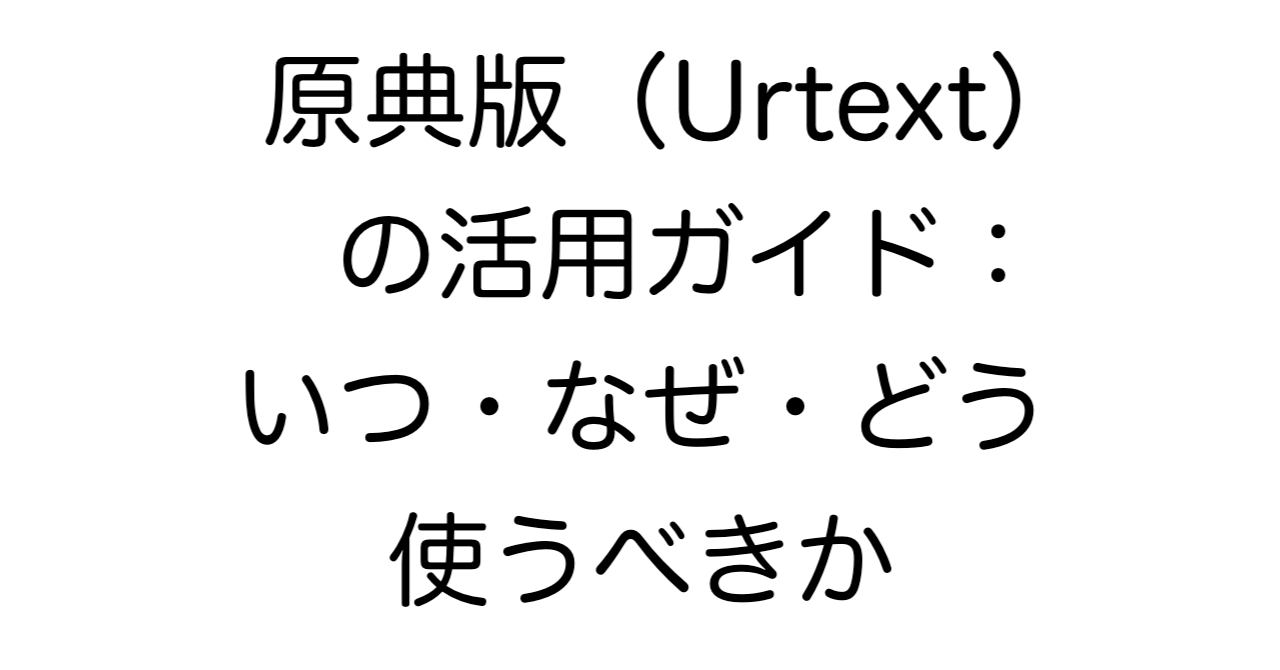
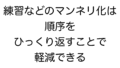
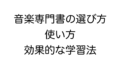
コメント