【ピアノ】「ピアノ演奏法」(笈田光吉 著)レビュー
► はじめに
1951年に音楽之友社から出版された笈田光吉氏の「ピアノ演奏法」を紹介します。この本は、著者の「ピアノペダルの使い方」と対をなす重要な指南書です。
・出版社:音楽之友社
・初版:1951年
・ページ数:89ページ
・対象レベル:中級~上級者
・ピアノ演奏法 著:笈田光吉 / 音楽之友社
► 本書の特徴
本書の特徴は、ピアノ演奏を「身体(奏者)」と「楽器」という二つの観点から、体系的に解説している点です。序文で著者が述べているように、これらは「車の両輪」のように不可分な関係にあります。
全10章、89ページという比較的コンパクトな本ではありますが、その内容は密度が高く、特に以下の点が特徴です:
ピアノ演奏の技術を理解する3つの視点
本書では、ピアノ演奏の技術を以下の3つの重要な側面から解説しています:
心の側面:
演奏時の心の状態や精神的なアプローチに関する部分です。例えば、演奏への集中力、曲の理解、表現意図、そして演奏時の不安やプレッシャーへの対処などが含まれます。
効率的な身体の使い方:
ムダのない、理想的な演奏フォームについての部分です。必要以上に力を入れ過ぎない、疲れにくい弾き方、そして長時間の練習や演奏に耐えられる合理的な身体の使い方などが解説されています。
身体の仕組みと動き:
腕、手首、指などの身体の構造と、その動きの仕組みについての部分です。例えば「手首をかたくするという事は、手首の運動を司さどる筋肉を緊張させる事である」という記述にあるように、身体の仕組みに基づいた演奏技術の解説がなされています。
つまり、本書は「指を動かす」という単純な技術論に留まらず、「心」「身体の使い方」「身体の仕組み」という3つの観点から、総合的にピアノ演奏技術を解説しているのです。この多角的なアプローチこそが、本書の大きな特徴と言えます。
実践的な運指の解説
第三章「指使い」も重要セクションです。特に注目すべきは:
・各指の特性についての詳細な解説
・「小指は薬指と違って遠慮なく鍛える事のできる指である」という、実践に基づいた指摘
・フレーズと運指の関係性についての考察
► 留意点、活用のヒント
読解について:
・文体に古さを感じ、特に前半部分は読みにくい箇所がある
・同著者の「ピアノペダルの使い方」と併読することで、より深い理解が得られる
学習アプローチ:
・一度にすべてを理解しようとせず、関心のある章から読み進める
・特に第三章「指使い」と第六章「ペダルの技術」は、現代のピアノ学習者にとっても直接的に役立つ内容
► 対象読者
本書は中級~上級者向けの専門書です。特に以下の方々におすすめです:
・ピアノ演奏の技術的な裏付けを求める方
・運指やペダリングの理論的な理解を深めたい方
・ピアノ教師として、より体系的な指導法を探求している方
► 終わりに
1951年初版の出版物でありながら、その本質的な価値は現代でも色褪せていません。特に、身体の使い方や楽器との関係性についての考察は、現代のピアノ教育にも大きなヒントを与えてくれます。文体の古さはありますが、内容の本質を理解すれば、演奏技術の向上に役立つはずです。
・ピアノ演奏法 著:笈田光吉 / 音楽之友社
姉妹書として同著者の「ピアノペダルの使い方」も併読することをおすすめします。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
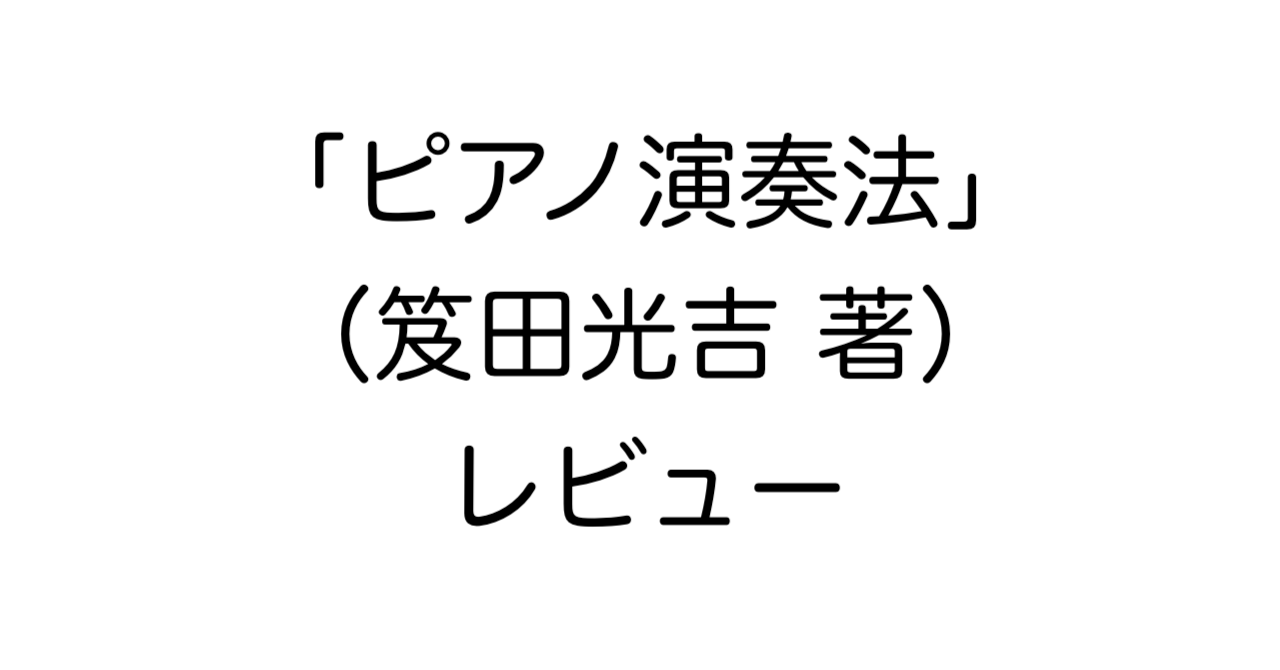

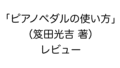
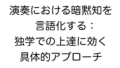
コメント