【ピアノ】編曲作品を学習に取り入れるメリットと曲目コレクション
► はじめに
ピアノ学習において、オリジナル作品だけでなく「編曲もの」に取り組むことは、演奏技術の向上だけでなく、音楽的理解を深める重要な学習です。本記事では、なぜ編曲作品を学習に取り入れることが有益なのか、そして、ソロ用編曲にはどのような作品があるのかを具体的に解説します。
► 編曲作品を学習に取り入れるべき3つの理由
1. 演奏解釈の深化
多くの編曲作品では、原曲の魅力を保ちながら編曲者の個性や解釈が反映されています。原曲と編曲版を比較することで、同じメロディに対する異なるアプローチを学ぶことができます。
例えば、J.S.バッハの有名なヴァイオリン曲「シャコンヌ ニ短調 BWV1004」をブラームスのピアノ編曲版で学習する場合、ヴァイオリンの音遣いをピアノでどう表現しているかなどの編曲者の工夫を理解することで、比較的視点も養えるうえ、より深い音楽的視点を得られます。
2. 実践的な編曲技法の習得
編曲作品を演奏することは、そのまま編曲技法の学習にもつながります。原曲と比較しながら実際に音を出すことで、以下のような編曲テクニックを身体で理解することができます:
・原曲の音楽性をピアノ一台でどのように表現するか、または、どのように全く異なる世界観を表現するか
・「他楽器→ピアノ」において、楽器の特性の違いをどう表現するか
・原曲の音遣いをどう簡略化または拡張するか
3. レパートリーの拡充と発掘
編曲作品には、通常のピアノレパートリーでは出会えない魅力的な楽曲が数多くあります。
オペラのアリア、バレエ音楽、交響曲の楽章など、原曲がピアノ作品ではない名曲をピアノで演奏できるのは編曲作品ならではの醍醐味です。また、片手のみで演奏するピアノ曲など、良質なオリジナルピアノ曲の数に限りがある分野を知るきっかけにもなります。
► クラシックピアノ編曲作品の選択的コレクション
以下で紹介する楽曲は、網羅的なリストではなく、選択的なコレクションです。
‣ J.S.バッハ作品の編曲
ブゾーニ編曲:
・シャコンヌ ニ短調 BWV1004
・プレリュードとフーガ ニ長調 BWV532
・トッカータとフーガ ハ長調 BWV564
・トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
・コラール前奏曲集 第1巻・第2巻
リスト編曲:
・幻想曲とフーガ ト短調 BWV542
・前奏曲とフーガ イ短調 BWV543
ブラームス、ジチー、フォリップ、ヴィットゲンシュタイン 他 編曲
・シャコンヌ ニ短調 BWV1004(左手のための)
その他の編曲者:
・コルトー編曲:「BWV1056」より「アリオーソ」、「トッカータとフーガ ニ短調 BWV565」
・ケンプ編曲:ピアノのための10の編曲
・グリャズノフ編曲:幻想曲とフーガ BWV572
・ファジル・サイ編曲:幻想曲とフーガ ト短調 BWV542、パッサカリア ハ短調 BWV582
・ダルベール編曲:パッサカリア ハ短調 BWV582
・サンサーンス編曲:「カンタータ 29番」より「序曲」
・アレクサンドル・タロー編曲:バッハ ピアノ編曲集
・ラフマニノフ編曲:「BWV 1006」より「前奏曲、ガヴォット、ジーク」
‣ ワーグナー作品の編曲
リスト編曲:
・「トリスタンとイゾルデ」より「イゾルデの愛の死」
・「さまよえるオランダ人」より「紡ぎ歌」
グールド編曲:
・ジークフリート牧歌
・楽劇「神々の黄昏」より「夜明けとジークフリートのラインの旅」
・楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲
その他
・コチシュ編曲:「トリスタンとイゾルデ」前奏曲
‣ チャイコフスキー作品の編曲
グリャズノフ編曲
・幻想序曲「ロミオとジュリエット」
プレトニョフ編曲
・演奏会用組曲「眠れる森の美女&くるみ割り人形」
その他:
・エシポフ編曲:序曲「1812年」
・グレインジャー編曲:「花のワルツ」によるパラフレーズ
‣ シューマン作品の編曲
リスト編曲:
・献呈
・春の夜
クララ・シューマン編曲
・ロベルト・シューマンの30のリートと歌
シューマンの編曲と言えば、妻のクララ・シューマンが編曲した「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」は外せません。
推奨記事:【ピアノ】クララ・シューマン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド
‣ ラフマニノフ作品の編曲
自身による編曲
・リムスキー=コルサコフ「熊蜂の飛行」、クライスラー「愛の悲しみ」など
コチシュ、ワイルド、シュルツ 他 編曲
・ヴォカリーズ Op.34 No.14
‣ その他の注目すべきピアノ編曲
・アゴスティ編曲:ストラヴィンスキー「火の鳥 より」
・ヴィットゲンシュタイン編曲:左手のための教則本 より 編曲集(あらゆる作曲家の作品の編曲作品集)
・カツァリス編曲:ロドリゲス「ラ・クンパルシータ」
・ギーゼキング編曲:R.シュトラウス「セレナーデ Op.17-2」
・グリャズノフ編曲:ピアノ編曲集(グリンカ、チャイコ、ボロディン、マーラー、ラフマ、ドビュッシー)
・グリューンフェルト編曲:「ウィーンの夜会」ヨハン・シュトラウスのワルツ主題による演奏会用パラフレーズ Op.56
・ケンプ編曲:ヘンデル「チェンバロ組曲 第9番」より「メヌエット」、グルック「精霊の踊り」
・ゴドフスキー編曲:アルベニス「タンゴ Op.165-2」
・コルトー編曲:ブラームス「子守歌 Op.49-4」、フランク「ヴァイオリンソナタ」
・サマズイユ編曲:R.シュトラウス「メタモルフォーゼン」
・サンサーンス編曲:グルック「オルフェオ」より「メヌエット」
・シフラ編曲:2つの演奏会用エチュード(熊蜂の飛行、トリッチ・トラッチ・ポルカ)
・シュルツ=エブラー編曲:ヨハン・シュトラウスの「美しく青きドナウ」によるアラベスク
・ジル・マルシェクス編曲:ラヴェル歌劇「子供と魔法」より「5時 フォックストロット」
・ストラヴィンスキー自編:ペトルーシュカからの3章
・スガンバティ編曲:グルック「オルフェオ」より「メロディ」
・ドホナーニ編曲:ドリーブ「2つのワルツ」
・ナオモフ編曲:ドリーブの歌劇「ラクメ」より「花の二重唱」
・ファジル・サイ編曲:モーツァルト「トルコ行進曲」
・フロリアン・ノアク編曲:ショスタコーヴィチ「ワルツ 第2番」
・ホロヴィッツ編曲:ビゼーのカルメンの主題による変奏曲、スーザ「星条旗よ永遠なれ」
・リスト編曲:ベートーヴェン「交響曲 全曲」、サンサーンス「死の舞踏」、ヴェルディ「リゴレットパラフレーズ」
► ポピュラーピアノにおける編曲作品の選び方
ポピュラー音楽の分野では編曲版楽譜が数多く出版されていますが、品質にばらつきがあるのが実情です。以下の基準で選ぶことをおすすめします。
最優先:作曲者監修楽譜
数は限られますが、作曲者自身が編曲または監修している楽譜は、その楽曲の本質を最も正確に伝えているため、迷わず選択して構いません。もちろん、第三者の解釈が入ったアレンジの面白さもありますが、アレンジものが多く出回るポピュラーピアノの分野においては、作曲者自身が編曲、もしくは監修している楽譜の価値は圧倒的です。
推奨:音源準拠楽譜
「音源マッチング楽譜集」や「完全コピー楽譜」は、実際の録音(場合によっては、レコーディング時に使用したスコア)を元に作られているため、クオリティが高い可能性が高く、比較的安心して使用できます。商品名に「マッチング」「準拠」「完全コピー」などの表記があるものを選びましょう。
推奨記事:【ピアノ】ポピュラーピアノにおける楽譜選びのポイント 6選
► 編曲作品学習のポイント
・原曲との比較:可能な限り原曲も聴いて、編曲者がどのような工夫をしているかを理解する
・多少の疑いの目も必要:絶対に弾けない編曲も混在しているので、粘っても弾けなければ一旦切り捨てる勇気を持つ
・編曲意図の考察:なぜこのように編曲されたのか、その理由を考えながら学習する
► 終わりに
編曲作品への取り組みは、レパートリー拡充の手段であると共に、原曲との比較を通じて音楽的理解を深め、実践的な編曲技法を学び、新たな音楽の世界を発見する貴重な学習方法です。本記事の内容を参考に、学習プランに編曲作品を取り入れてみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
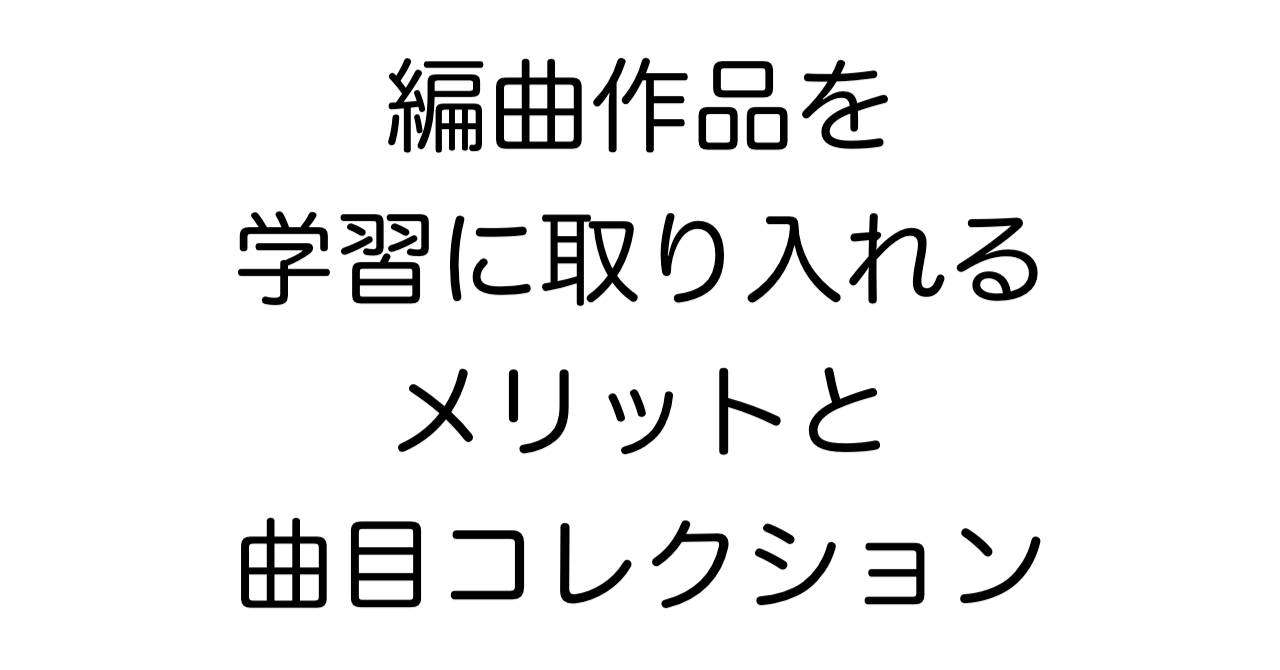
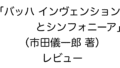
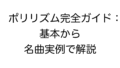
コメント