【ピアノ】「ピアニストの歴史」(パウル・ローレンツ 著)レビュー
► はじめに
本書は、チェンバロからピアノへの楽器の変遷とともに、約300年にわたるピアニストの歴史を辿った専門書です。一般的なピアノ音楽史の書籍とは異なり、演奏の側面に特化して書かれており、ピアノという楽器と演奏家の発展を詳細に描いています。
・出版社:株式会社芸術現代社
・初版:1990年
・ページ数:186ページ
・対象レベル:初級~上級者
・ピアニストの歴史 ピアノ奏法、三世紀の変遷と巨匠たち 著:パウル・ローレンツ 訳:田畑智世枝 / 株式会社芸術現代社
► 内容について
‣ 本書の特徴
演奏面に特化した視点
本書の特徴は、演奏の方面にフォーカスしたピアノ音楽史書であることです。例えば、ピアノ教師三大「C」と呼ばれるクレメンティ、クラーマー、ツェルニーについて深く取り上げているのも、このような視点があってこそです。また、ドゥシェックやカルクブレンナーの座り方についても言及されており、ただの人物史に留まらない興味深い内容となっています。
興味深い歴史的事実
本書には、現代では想像しにくい興味深い歴史的事実が数多く記されています。モーツァルトの時代には3〜4時間それ以上に及ぶコンサートがしばしば開催されていたことや、19世紀前半においてオーケストラの演奏は大音楽都市でのみ行われ、小都市では滅多になかったため、交響曲をピアノ演奏で知ることが決して異例ではなかったという事実などです。
音源が溢れている現代では気づきにくいこうした事実は、ピアノという楽器が中流階級に広く普及した理由の一つでもあります。「交響曲、室内楽、オペラ、オラトリオなどをピアノ編曲版やスコアから弾き、最新の音楽を知る手段となったこと」が、ピアノ普及の重要な要因だったのです。
リサイタルの発展
フランツ・リストによるリサイタルの始まりについても、よくある記述に留まらず、さらに掘り下げて論じています。3〜4時間という巨大プログラムに満足することが普通だった聴衆の関心を、他の芸術家の共演なしに満たすには、優れたピアニストにしかできなかったという、リサイタル黎明期の問題点についても解説されています。
‣ 構成の変遷
本書前半では、ピアニストと作曲家が兼業だった時代を扱っているため、演奏の話を絡めた作曲家の歴史を読んでいるような内容となっています。しかし、レシェティツキーの章あたりから内容的な転換点を迎え、純粋にピアニストとしての活動に焦点を当てた内容が多くなります。
後半では「女流ピアニストのスターたち」「派(エコール)」「ベートーヴェン・スペシャリスト」「ショパン・スペシャリスト」など、より専門的で現代的な観点からピアニストの世界を描いています。
► 筆者の経験談
筆者自身、この書籍は一度読んだきりで読み返してはいませんが、従来の音楽史の書籍に比べると随分とコンパクト(186ページ)かつ、1ページの文字数がそれほど多くないので、気軽に読める本だと感じた記憶があります。
ピアノ音楽史では、作品、楽器の進化、奏法の進展、様式の変化、ピアニストの活動などの様々な観点を扱いますが、本書を読むことで、主にピアニストの歴史について知識を時系列に並べることができました。専門的な内容でありながら、読みやすさを保っているのは本書の大きな魅力だと思います。
► 終わりに
本書は、ピアノという楽器と演奏家の歴史を体系的に学びたい方にとって、価値のある一冊です。演奏面に特化した視点から書かれているため、ただの人物史や楽器史に留まらない知識を得ることができます。
ピアノ音楽の人物史についてさらに深く学びたい場合は、以下の書籍を併読するといいでしょう。
【ピアノ】「20世紀のピアニストたち 上・下」(千蔵八郎 著)レビュー
・ピアニストの歴史 ピアノ奏法、三世紀の変遷と巨匠たち 著:パウル・ローレンツ 訳:田畑智世枝 / 株式会社芸術現代社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
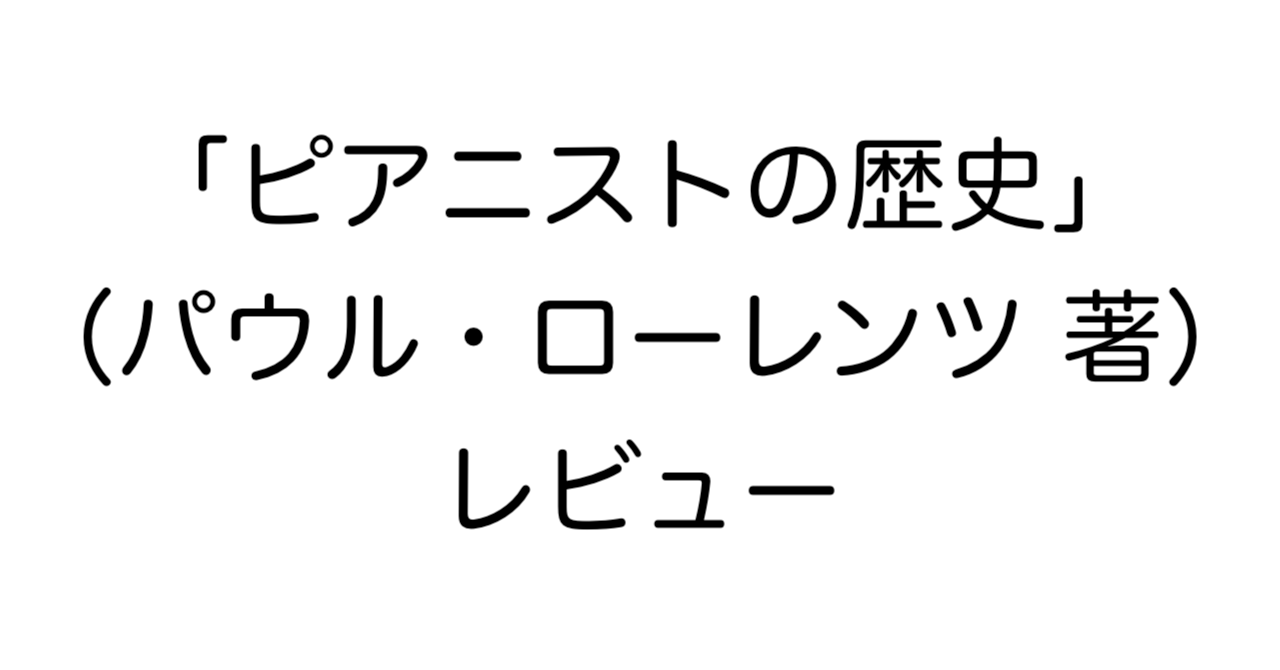


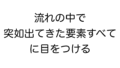
コメント