【ピアノ】物事をたった一面で判断しない:先入観を超える多角的視点
► はじめに
我々は無意識のうちに限られた情報や経験から物事を判断してしまいがちですが、音楽は狭い視点では決して理解できない側面も持っています。
本記事では、音楽にまつわる3つの具体例を通じて、物事を多角的に見ることの大切さを解説します。
► 3つの具体例
‣ フランツ・リストの老年期
「フランツ・リスト」と耳にするだけで:
・技巧的な演奏をするピアニスト
・技巧的な作品ばかりを作る作曲家
と思っている方は多いようです。しかし、実際にはその一面のみではリストのことは理解できません。有名な演奏エピソードや作品にそういったものが多く、それを面白おかしく誇大した文献や広告に毒されているだけでしょう。
実際にリストの作品を多く調べてみて欲しいところですが、ここでは彼の演奏家としての姿勢や芸術思想について書かれている短い文章を抜粋しておきます。
ショパンとデッペに学ぶシンプルなピアノ演奏法 著:エルギン・ロート 訳:コサキ共子 / CLAP
という書籍に、以下のような文章があります。
1880年代にワイマールに住んだ「老年」のリストの芸術思想は、すっかり中庸で簡素な方向に変わり、技巧を見せびらかすようなテンポで弾くこともありませんでした。彼はワイマールのレッスンでは「充分に時間を取りなさい。楽に自然に」と語ったのです。
(抜粋終わり)
‣ 減衰楽器としてのピアノの特性
ピアノは減衰楽器なので、たとえダンパーペダルを使っていても発音後の音は減衰していってしまいます。そのため、「楽器としても演奏者としても長いフレーズを演奏するのが苦手」とまとめられることが多いようです。
実際にその傾向はありますが、よく考えてみると、長いフレーズを本当の意味で「切れ目無し」に連結できるのは、弦楽器や管楽器にはない魅力と言えるでしょう。というのも:
・弦楽器では一弓での演奏時間が限られていて、素早く弓を返しても、一瞬の切れ目ができてしまう
・管楽器では一息での演奏時間が限られていて、素早くブレスをしても、一瞬の切れ目ができてしまう
この例も、思い込みにとらわれて物事をたった一面で判断すべきでないことが分かるものです。
‣ 電子ピアノの進化
最後に、筆者自身の経験談を一つ紹介します。
普段、グランドピアノ、アップライトピアノ、電子ピアノのそれぞれを使い分けて作曲や編曲をしているのですが、この中で一番買い替えがきくのが電子ピアノというだけあって、今までに数十台の様々な機種を試してきました。
ここで驚いているのが、電子ピアノの進化についてです。20年前には30万円程出さないと手に入らなかったような性能が、3万円程の機種にも備わってきました。それに、もっと上位機種のレヴェルももちろん上がっています。
自分の中で、「この価格帯であればこれくらいか」という思い込みがありながらも、実際に触ってみると様々な企業努力でそれを裏切ってきます。いつの間にか急速に進化しています。
改めて「物事をたった一面で判断しないでおこう」と思うきっかけになりました。
► 終わりに
筆者自身の経験からも言えることは、物事を一面的に捉えることは、時として思い込みを生み、それが真実を見えづらくしてしまうということです。常に情報をアップデートし、どんな対象でも新たな視点から理解することを大切にしてみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
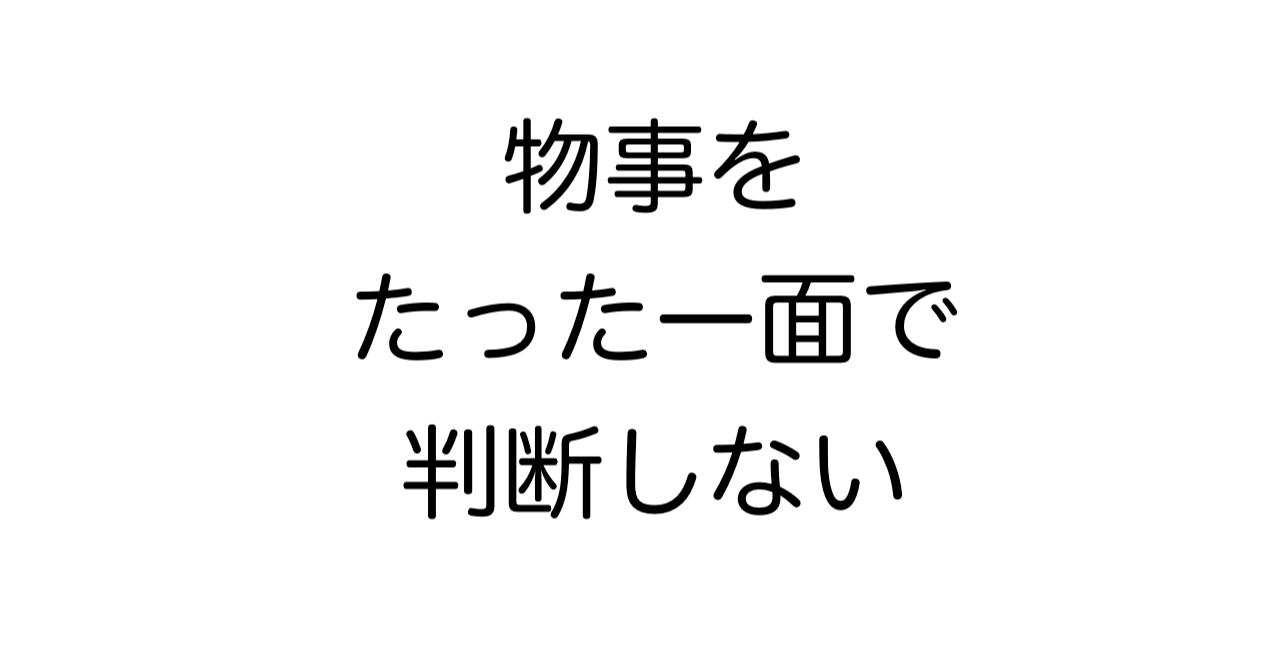

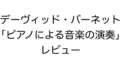
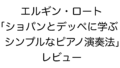
コメント