【ピアノ】マルグリット・ロン「回想のフォーレ―ピアノ曲をめぐって」レビュー
► はじめに
フォーレの音楽に興味のあるすべての方にとって、この書籍は特別な意味を持ちます。20世紀を代表するピアニスト、マルグリット・ロン(1874-1966)が、作曲家フォーレ本人から直接指導を受けたり交流した体験をもとに綴った貴重な証言集だからです。ロン=ティボー国際コンクールの設立者として知られるロンの言葉には、生きた音楽の記録としての重みがあります。
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:2002年
・ページ数:188ページ
・対象レベル:中級~上級者
・回想のフォーレ―ピアノ曲をめぐって 著:マルグリット・ロン 訳:遠山菜穂美 / 音楽之友社
► 内容について
‣ 構成と内容
本書は全11章で構成されており、大きく3つの部分に分けることができます:
第1部(第1章~第7章):人物像と交流の記録
フォーレとの出会いから関係の深まり、そして彼を取り巻く音楽界の人々との関係まで、まさに「回想」の名にふさわしい体験が語られます。
第2部(第8章):演奏家としての視座
ここでロンは、フォーレから離れて自身のピアニストとしての意見を展開します。練習方法、メトロノームについての考え、演奏時の心理状態など、興味深い内容が含まれています。
第3部(第9章~第11章):作品論や音楽観、まとめ
フォーレの具体的な作品について、舟歌、夜想曲、ヴァルス・カプリス、即興曲、バラード、ドリー、主題と変奏、前奏曲集、そして室内楽曲まで、ロンの深い洞察が語られます。作品によっては演奏上の助言も含まれており、実用的な価値も高いものです。
‣ 本書の魅力
生きた証言の価値
フォーレが日常的に口にしていた「ニュアンスをこめて。でも動きは変えないで。」という言葉や、「僕たちにとって、バス声部は重要だ。」という発言は、楽譜からは読み取れない作曲家の真意を伝えてくれます。
フォーレの具体的な音楽観
「フォーレは短くて息をのむような『クレッシェンド』や『ディミヌエンド』を好んでいました。」などといった具体的な音楽観についての様々な記述は、フォーレの音楽を理解するうえで有用です。
人間としてのフォーレ
「フォーレの逆説的な性格に、私はよくひっかかりました。彼は極端に伝統を尊重するかと思えば、自分自身の作曲に関しては、頑固ではないといった態度を示すのです。」という記述は、創作者としてのフォーレの複雑な内面を垣間見せてくれます。このような「人間としてのフォーレ」が感じられる記述も散りばめられています。
► 留意点
本書は回想録という性格上、客観的な音楽分析書ではありません。ロンの主観的な視点に基づいた記述が中心となっているため、学術的な研究書として用いる際には注意が必要です。
► 関連書籍
同じマルグリット・ロンによる「ドビュッシーとピアノ曲」や「ラヴェル―回想のピアノ」もあわせて読むことで、20世紀フランス音楽の理解がより深まるでしょう。この3つの書籍を通読することで、ロンの音楽観の全体像を把握することができます。
► 終わりに
「回想のフォーレ―ピアノ曲をめぐって」は、音楽史的資料としての価値と、実践的な演奏指南書としての価値を兼ね備えた書籍です。フォーレの音楽を愛するすべての学習者にとって、この本は必読書と言えるでしょう。
ロンの個人的な体験を通して、19世紀末から20世紀初頭のパリ音楽界の空気を肌で感じることができ、また、作曲家と演奏家の理想的な関係性についても多くのヒントが得られます。
・回想のフォーレ―ピアノ曲をめぐって 著:マルグリット・ロン 訳:遠山菜穂美 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
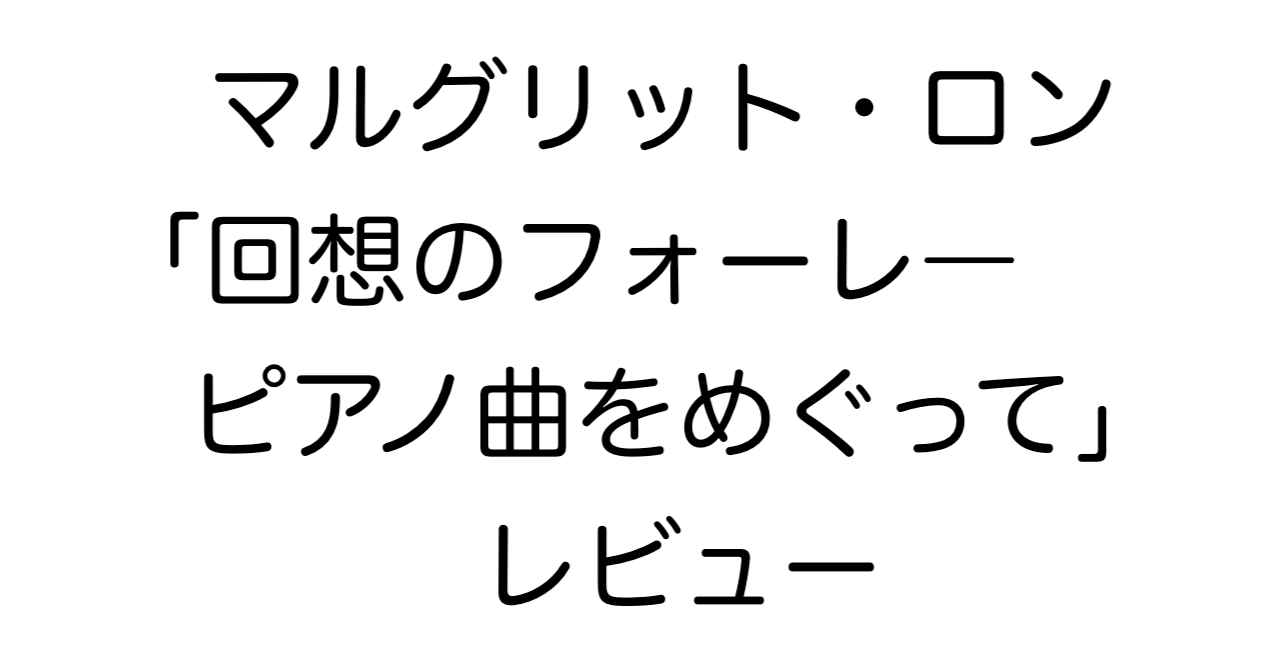

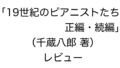
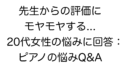
コメント