【ピアノ】演奏における脱力:知識と実践テクニック
► はじめに
ピアノ演奏において、「脱力」は多くの音楽家が追求する重要な技術です。しかし、その概念は曖昧で、実践が難しいと感じている演奏者も少なくありません。
本記事では、脱力の必要性や具体的な実践方法について、詳しく解説します。
► A. 脱力の基本概念
‣ 1. なぜ、脱力が必要なのか
なぜ、脱力が必要なのでしょうか?
大きくは以下の点に集約されます:
・脱力ができていないと、うまく動けない
・脱力ができていないと、姿勢などの見た目にも影響がある
・脱力ができていないと、手などの故障につながる可能性がある
・脱力ができていたほうが、ピアノが良く鳴る
脱力というのは、「いかにピアノの能力を引き出すのか」ということです。
指は下げるのは楽ですが、上げる動きは苦手です。逆に「ピアノの鍵盤」は、上がるときは自然に上がってきますが、下げるときには人間の力が必要です。
ここをどうやって人間の身体とリンクさせていくかを学んでいきましょう。
また、脱力により、指先のセンサーを働かせやすくなる点は大きいと言えます。
演奏(特に弱奏)するときに必要なことの一つとして、鍵盤からの情報を覚えることがあります。鍵盤を触っているという感覚を持ち、感触を覚えることで:
・鍵盤が勝手に上がってくる力がどれくらい存在するのか
・鍵盤がどれくらい下がっているのか
・そのピアノのキータッチの重さ
などといった情報を感じとることができます。その結果、打鍵の際の細かなニュアンスを表現することができるだけでなく、はじめて触る本番会場のピアノにも適応しやすくなります。
力が抜けているときのほうが、鍵盤の情報を得やすくなることを覚えておきましょう。
‣ 2. 無駄な動きを減らす脱力の基本
脱力の基本は「無駄な動きを減らすこと」と言えます。
知らず知らずのうちに、クセで無駄な動きをつけてしまっていませんか。例えば:
・無意識に身体を大きく振る
・手首を必要以上に回す
・弾き始める前に手でカウントをとっている
・フォルテで打鍵した後に上半身を跳ね上げている
これらは、脱力とは反対方向へ向かっているクセとなってしまっているのです。
脱力というのは本来、自然なフォームから生まれます。最終的に身体の動きが入ることのすべてが悪いわけではありません。しかし、演奏のために本当に必要な動きとそうでない動きを一度区別してみる必要があります。そうすることで、脱力に関するさまざまな考え方に取り組んでいくうえでより効率よく実践していけるでしょう。
脱力に限らず、無駄な動きは音楽自体からも遠ざかります。自分の音をよく聴けなくなる可能性があるからです。
中々動作を減らせないのであれば、まずは、無駄に動作を誇張しないことだけを意識してみてください。素直に鍵盤と向かい合って、素直に音を出してみる。まずはここからスタートしましょう。
人は動くものを見るので、無駄に「手首」や「頭」や「その他の身体」を揺すぶったりする動きは、演奏そのものに集中してもらえなくなる原因も招きます。良い面でも良くない面でも、人は視覚的にも音楽を聴くのです。
‣ 3. なぜ、脱力だけでは何もできないのか
完全に弛緩しきっていても何もできないのは言うまでもなく、必要なときには力を使わなければいけません。この部分について、分かりやすい具体例で解説されている文章があります。
「心で弾くピアノ―音楽による自己発見」著 : セイモア・バーンスタイン 訳 : 佐藤 覚、大津 陽子 / 音楽之友社
という書籍に、以下のような文章があります。
ピアノを離れ、部屋をゆっくり横切って歩いていく。その時の身体の感覚に注目する。
さらに速く歩いてみる。再び身体の状態を観察する。
さまざまな筋肉が自動的に引き締まるのに気づくだろう。
しかし、それは身体を安定させるために必要なほどにすぎない。
ピアノで大きな音の速いパッセージを弾くには、これと似たエネルギーの使い方が要求される。
すなわち筋肉を正しく引き締めることによって、はじめて体が〈自由に〉なる。
(抜粋終わり)
脱力だけでは何もできない理由については、ここにヒントがあることが分かります。特に、最後の一文に注目してみましょう。
では、脱力をどう考えればいいのかというと、できる限り、力が停滞している時間を作らなければいいのです。この部分さえクリアできていれば、力を使っても構いません。
これについては、次の項目で詳しく解説します。
・心で弾くピアノ―音楽による自己発見 著 : セイモア・バーンスタイン 訳 : 佐藤 覚、大津 陽子 / 音楽之友社
‣ 4. 脱力の肝は、力が停滞している時間を作らないこと
前項目で書いたように、完全に弛緩しきっていても何もできないのは言うまでもなく、必要なときには力を使わなければいけません。
このように考えると脱力で重要なことはシンプルだと気づくはずです。つまり、「できる限り、力が停滞している時間を作らない」ことです。
「打鍵したらすぐに力を抜いて」という指導がありますが、これは簡潔に言うと、入れた力をそのまま停滞させないためにやっているのです。「肩を下げて」というのも、力が入りっぱなしになって停滞してしまうのを避けるためだと思ってください。
力を使うから手を痛めるのではなく、使った力が停滞するから痛めるのです。
力を入れること自体はいいのですが、その力が常に動いて流れていくようにする必要があり、それを実現するのが、各種の脱力テクニックです。
はじめのうちは難しいかもしれませんが、「力が停滞状態になっていないか」を常に意識しておくと、脱力の目指すべき方向性がはっきりするでしょう。
► B. 身体的アプローチ
‣ 5. 身体の軸を安定させる:脱力の土台づくり
脱力するには、ただ力を抜こうとするだけではなく、呼吸をしっかりとおろす、つまり、身体の軸を安定させることが重要です。
ピアノを演奏するとき以外にも言えることで、変わった姿勢をしているときには身体に余計な力が入ってしまっています。
まずは弾き始めるときだけでも意識してみましょう。やり方としては、座ったらすぐに弾き始めるクセを修正するのがおすすめです。
例えば本番であれば、椅子の位置をチェックしたり軽く深呼吸したりと、最高のパフォーマンスをするために椅子に座ってから少しの時間を設けるはずです。一方、自宅での日頃の練習ではどうでしょうか。座った瞬間から手先で弾き始めてしまっていませんか。
練習のときから、このようなことまで本番同様に意識して練習するようにしましょう。
‣ 6. なぜ、肩を下ろすべきなのか
肩が上がっているときは、余計な力が入ってしまって身体が硬直していることはもちろんですが、もう一つ肩を下ろすべき理由があります。
「肩を下ろした状態で腹式呼吸ができるようになると、すべての力が腕にくるようになる」のです。筆者はこれを指揮者の先生から学びました。
肩が上がってしまっているときは、身体が緊張している状態です。このまま演奏すると出てくる音質が非常に硬い音になってしまううえ、身体への負担も大きいので、改善を要します。
自宅練習における対策としては、弾き始める前に一度わざと両肩を上げてから、力を抜いてストンと落とすという動作をやってから弾き始める習慣をつけるといいでしょう。
弾いている最中にまた肩が上がってきてしまうはずなので、「楽譜の数カ所に目立つカラーの付箋を貼るなどして、その箇所にきたら肩が上がっていないか確認する」方法で抜き打ちチェックするのがおすすめです。付箋でもタイマーでも何でもいいのですが、とにかく定期的に肩の位置のことを思い出すことが重要です。
‣ 7. どこが疲れてしまうのかを把握する
「どこが疲れてしまうかを把握する」ということは脱力にとって有益です。例えば:
・前腕
・上腕
・首や顔
・手のひら
・親指の付け根
意外に多いのが「首や顔」に力が入ってしまっているケースです。
気持ちを入れようとした結果、ものすごい形相で顔を突き出して演奏してしまっていることがあります。「顔を脱力する」などというと笑い話のようですが、本当に顔をラクにしてください。
「前腕」「上腕」「手のひら」などが疲れる原因は学習者によりきりですが、「親指の付け根」が疲れる原因のほとんどは、練習不足です。
「トレモロ」を練習すると、親指の付け根が熱くなってきませんか。これは、たとえ脱力を意識して練習していても、一定時間行っていると熱くなってきます。つまり、普段あまり開発されていない筋肉なのです。繰り返し練習することで、少しづつ疲れにくくなってくるのが実感できることでしょう。
このように、「必ずしも脱力が原因ではなくても疲れてくる部位はある」ということも、あわせて理解しておきましょう。
‣ 8. 楽な状態を知っておく
弾き始める前に1回グーパーをし、パーにした瞬間に力を捨て切るというのを取り入れてみましょう:
・弾き始める前に1回グーパーをする
・必ず、パーにした瞬間に力を捨て切る
これをすることで、手だけでなく前腕の筋肉もほぐれます。パーにして力を捨て切ったときの手の形は自然な状態であることに気づけるかどうかが重要です。
実際の本番ではステージ上ではなくステージに出る直前に行ってください。
拍子抜けするくらい簡単なことですが、まずはこういったことを通して「楽な状態を知っておく」ということが、脱力の一歩となります。
► C. 具体的な脱力テクニック
‣ 9. 鍵盤で指立て伏せをしない
「脱力」といっても、実はピアノ演奏において脱力するだけでは何もできません。力を使う瞬間はあってもいいのです。改善すべき問題となるのは、その力をずっと入れっぱなしにしてしまうことです。
長い音価の音では、打鍵した直後に力を開放してあげることを意識してみましょう。
ピアノの演奏では、そのアクションの構造上、ハンマーが弦を打つスピードを決めるための動作を打鍵が担います。
ピアノの内部には「バックチェック」という、弦を打った後に戻ってきたハンマーをキャッチしてリバウンドを防止する部品があり、打鍵直後には、バックチェックにハンマーがとらえられています。つまり、打鍵して鍵床についている段階(厳密には、もう少し前の段階)でその音を変えるために我々にできることはなく、もうペダリングなど別の内容に頼るしかありません。
ここで一番問題となるのは、鍵盤の上で指立て伏せをしてしまうことです。
鍵床についている状態からさらに力いっぱい押し込んでも、音は変わりません。むしろ、次への動作へスムーズに移れなくなったり手に負担をかけたりと、マイナス面はたくさんあります。この状態で鍵盤をこすったり、ねんりきを込めるのも、音へは影響を与えません。
感覚的には分かっていてもやってしまいがちなので、注意してみましょう。
必ず鍵盤から指を離さなくてはいけないわけではなく、打鍵後に鍵盤を下げたままにしておいたほうが次に弾く音に対する手のポジションをとりやすい場合など、打鍵状態を維持することは必要に応じて取り入れていいのです。しかしその場合も、必要でない力は捨てておきましょう。
余談ですが、1996年に「ポケットモンスター 赤・緑」というゲームソフトが発売された当時、ゲームボーイを使って遊んでいました。ポケモンを捕まえるために、ボールを投げた直後にAボタンを強く押し込むと捕まえやすくなるとか、AボタンとBボタンを交互に連打すると捕まえやすくなるとか、様々な噂がはびこりました。
これも、打鍵後の押し込みやねんりきと似ていて、効果がないことは分かっていても気持ちの問題でやってしまうのです。それとも、本当に捕まえやすくなるようにプログラムされていたのでしょうか。
‣ 10. 簡単にチェックできる中指の脱力
チェックの仕方は簡単です。
右手の「人差し指」と「薬指」で白鍵上の3度音程を押さえてみましょう。「Doナチュラル、Miナチュラル」など、「長短3度音程」であればどこでも構いません。
このときに、手を見てみてください。
中指が突っ張ってしまっていませんか。または、突っ張るまではいかなくても必要以上に上がってしまっていませんか。
該当する場合は、中指の力をゆるめてみてください。「左手」も同様にチェックしてみましょう。
この「突っ張るクセ」は特に「中指」で起きやすく、他指のコントロールのしやすさに影響を与えてしまったり、積み重なることで手への負担にもつながります。さらに、見栄えもあまり良くありません。
‣ 11. 修正すべき、親指のフォームの例
(写真)

親指の写真ですが、演奏中にこのように関節から先の指先を反ってしまうのは、改善すべき例です。
このように親指を反ったままで手首を振ってみてください。思うように振れないことに気づくでしょう。一方、反りを開放してから手首を振ってみてください。とても柔軟に手首が振れるはずです。
つまり、親指を反るとそれだけで手首を固定してしまっているということです。クセになってしまっている方は意識的に修正してみましょう。
一方、親指の場合は指の横側で打鍵することが多いため、反ることで鍵盤に触れる面積が大きくなります。したがって、細い黒鍵を強く打鍵するときなどにミスタッチを避ける目的でわずかに取り入れるのは構いません。
‣ 12. 通し練習の最中に腕がパンパンになってしまう場合の対処法
2-3分の楽曲であれば何とかなっても、7-8分程度の長さになってくると、楽曲の後半で腕がアツアツ・ガクブルになってしまい通して弾けない、という方の声をよく耳にします。
ここまでに書いてきた脱力のことを意識して欲しいのですが、もう一つの対処法があります。
弾き始める「前」に楽曲全体の力配分を見通しておくクセをつけることです。
どうしてこんなに基本的なことをあえて書くのかというと、どんな楽曲でも曲頭からずっとマックスで弾いてしまう学習者が意外にも多いからです。
楽曲というのは、余程の例外曲でない限り、1曲の中での盛り上がりとそうでない部分との差がハッキリとつけられて作曲されていると考えていいでしょう。つまり、一曲の中で力配分としてラクをできる場所はあるのです。
これを意識したうえで演奏するのと意識せずに演奏するのとでは、力配分に大きな差が出てきます。
► D. 演奏の心理的アプローチ
‣ 13. 感情を音楽に変換する:想いを空回りさせない
改善すべきだと考える、初級者から上級者まで幅広くみられる特徴があります。
それは、「想いが空回りしてしまっていて、見た目だけにそれが表れている」ということです。
作品に対してたくさんの想いがあり、それを表現したくて仕方がないのはとても良いことです。そういった気持ちが無いよりは、あるほうがいいでしょう。しかし、ただ顔ばかりに力を入れてそちらに意識がいってしまい、むしろ音に良くない影響が見られることもあります。
「ねんりきを込めすぎずに、素直に音をつくる」ことを意識しましょう。
つまり、適切な「脱力」ができたうえで演奏できれば、表現したいことは音に反映されるのです。ねんりきを込め過ぎて想いが空回りしているときというのは、大抵、身体もかたくなっています。
‣ 14. 不必要な力みは思考停止を招く
筆者自身、変な力みが入っているときには、どうも自分の音をよく聴けていないと感じていました。弾いていてそう感じたこともありましたし、力みを感じていた演奏では、録音をしてみたときの想像と現実のギャップがすごかったので、後になって実感したこともあります。
この部分について昔からずっと疑問を感じていたのですが、常にこの疑問を持ち続けていたところ、面白い実験の記事を見つけることができました。
「ピアノ演奏技法」 著:ジョージ・コチェヴィッキー 訳:黒川武 / サミーミュージック
という書籍の中に、以下のような文章があります。
筋肉の過度の緊張は精神活動全体を妨害するものである。
モスコー芸術座の創立者でディレクターであったスタニスラフスキーは実験でこのことを示している。
ある生徒にグランドピアノの片端を持ち上げさせ、力んで持ち上げている間に都市の名や九九を言わせた。
この生徒はグランドピアノを降ろさないと、このような簡単な問いに答えることができなかった。
(抜粋終わり)
この書籍には、指を動かすことにおいて筋肉以外の要素がどのように重要であるのかについて詳しく書かれています。普段の学習とは異なった視点が得られて面白いので、参考にしてみてください。
・ピアノ演奏技法 著:ジョージ・コチェヴィッキー 訳:黒川武 / サミーミュージック
► 終わりに
本記事で解説した内容は、すぐに完璧にできるものではありません。むしろ、長期的な意識と練習を通じて少しずつ身についていくものです。
これからのピアノ練習で、この脱力の知識が少しでも助けとなれば幸いです。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
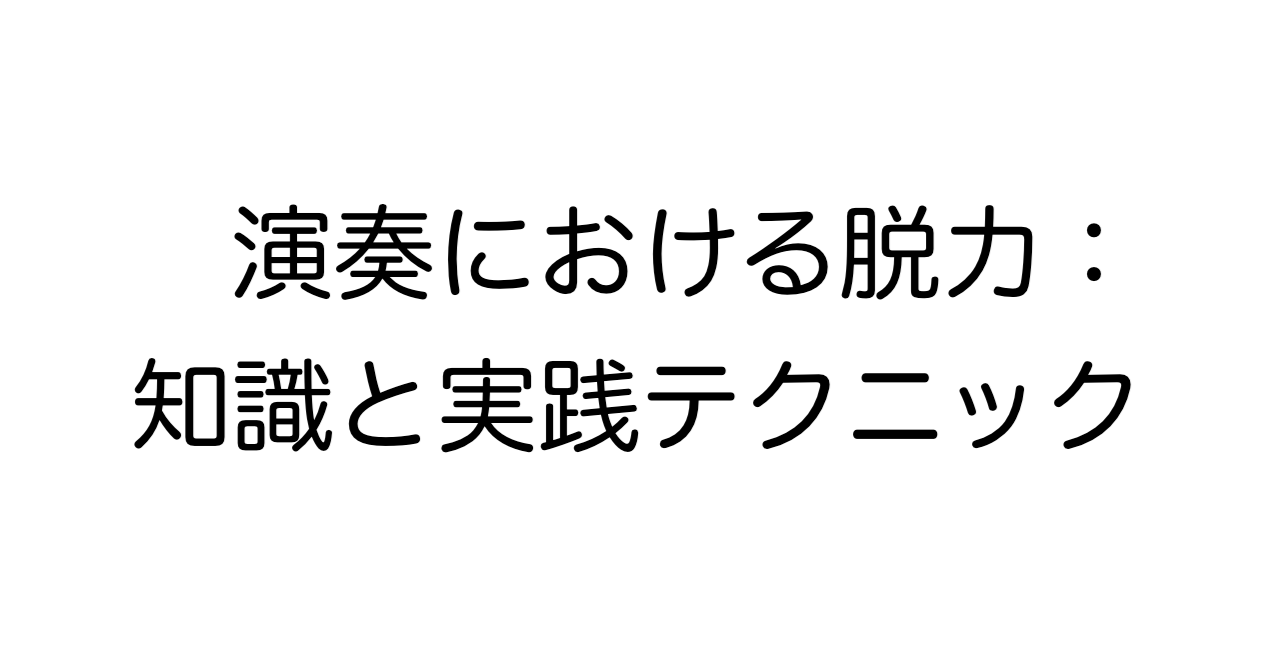


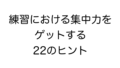
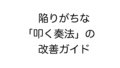
コメント