【ピアノ】ヨーゼフ・ホフマン「ピアノ演奏・Q&A」レビュー
► はじめに
ヨーゼフ・ホフマン著「ピアノ演奏・Q&A」は、20世紀初頭を代表するピアニストによる貴重な教育的文献です。
2部構成となっており、第1部ではピアノ演奏の本質的な考え方や技術について体系的に論じ、第2部では具体的な質問に答える形式で、初歩的な内容から高度な内容まで幅広くカバーしています。
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:1989年
・ページ数:189ページ
・対象レベル:初中級~上級者
ピアノ演奏・Q&A ムジカノーヴァ叢書 15 著:ヨーゼフ・ホフマン 訳:大場哉子 / 音楽之友社
► 著者について
ヨゼフ・カシミール・ホフマン(1876-1957)は、ポーランド出身のピアニスト・作曲家です。10歳で神童として欧米で演奏活動を行い、後にアントン・ルービンスタインの個人指導を受けています。カーティス音楽学校の校長を務め、シューラ・チェルカスキーやゲイリー・グラフマンといった名ピアニストを育成しました。
► 内容について
‣ 本書の構成
本書は2部構成となっています。注目すべき項目をピックアップすると:
第1部:ピアノ演奏法
・一般的な心構え
・正しいタッチと技術
・ペダルの用い方
・作品の性質に即した演奏
・アントン・ルービンスタインの教育法
・ピアニストとして成功するための要素
第2部:ピアノに関する質問と解答
・技術的な詳細(手の位置、運指、ペダリング、オクターヴなど)
・特定の作曲家と作品について
・練習方法、暗譜、初見
・教育に関する質問
これらの他、数多くのピアノ学習に有益な項目が取り上げられています。
‣ 注目すべき内容のピックアップ
ピアノという楽器の本質的理解
第1部の「ピアノとオーケストラ」の項目は必読です。ピアノが他の楽器と根本的に異なる点、楽器としての限界が明確に述べられており、演奏解釈はもちろん、ピアノ音楽の作編曲をするうえで極めて重要な視点が示されています。
作品中心主義のアプローチ
「作曲家を正当に評価するということは、彼のすべての作品、特にあらゆる作品を正当に評価する、ということなのです」という言葉に象徴されるように、ホフマンは「ショパンだからこう弾くべき」といった表面的な判断を避け、作曲者ではなく作品そのものに集中することの重要性を説いています。
J.S.バッハ作品の演奏へのヒント
J.S.バッハ作品の演奏に関する「多くの人々が自分の弾く作品がクラヴィコードのために書かれたのか、オルガンのために書かれたのか知らない」という指摘は、解釈の議論が絶えないバッハ作品に取り組む際の本質的な問題を突いています。
ルバートの具体的説明
ショパン作品の解釈で特に議論の多い「旋律を弾く手は全く自由に動き、伴奏を弾く手は厳格な拍子で弾く」というルバート手法の一つについて、具体的な説明がなされています。
‣ 辛口な批判も
ホフマンは当時の音楽教育や演奏習慣について、辛口な批判を展開しています。例えば:
・質の悪い音楽会を後援してはならない
・音楽学生が「世間を上手にうならせる」ことだけを目的とすることへの警告
・「自分自身の楽しみを考える人には先生は要りません。服従することを学びなさい!」
・体をゆすったり、誇張した動作をするのは「演奏で聴き手を満足させられない証拠」
これらの指摘は、現代の音楽教育にも通じる普遍的な問題を浮き彫りにしています。
‣ 心に残る格言の例
・「選ぶべき良いものがない場合は、常に悪いものを避ける」
・「学習とは習慣を身につけること」
・「量の問題は、質と両立したときだけ重要」
► 注意点
第2部のQ&Aセクションは、入門段階の内容と上級者向けの高度な内容が混在しています。特に学習段階が浅い方は、自分のレベルに合った項目を選んで読む必要があります。
► 終わりに
本書は、20世紀初頭の偉大なピアニストによる、技術論に留まらない深い音楽的洞察に満ちた一冊です。表面的なテクニックの習得だけでなく、音楽の本質、作品への誠実な姿勢、楽器の特性理解など、ピアノ弾きとして成熟するために必要な要素が網羅されています。
初中級者から上級者まで、それぞれのレベルで新たな発見がある内容であり、何度も読み返すことで、その都度異なる気づきが得られる価値ある書籍と言えるでしょう。
ピアノ演奏・Q&A ムジカノーヴァ叢書 15 著:ヨーゼフ・ホフマン 訳:大場哉子 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
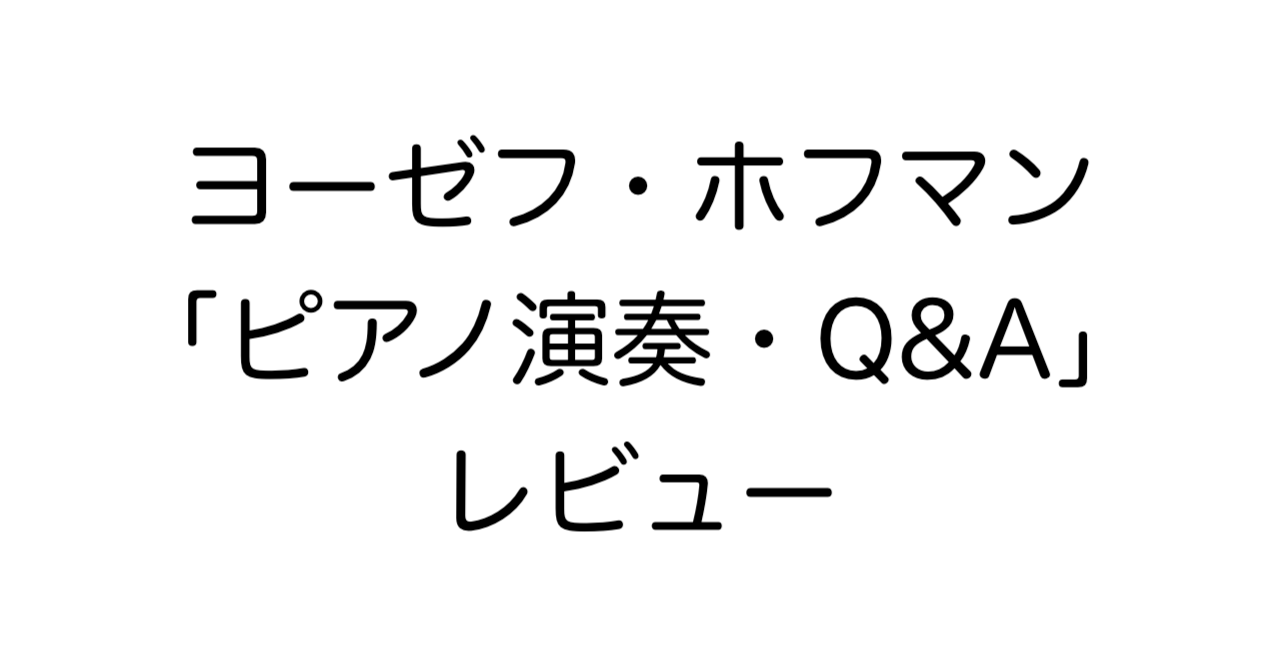
![ピアノ演奏・Q&A[ムジカ] (ムジカノーヴァ叢書 15)](https://m.media-amazon.com/images/I/51b55tJFbSL._SL160_.jpg)
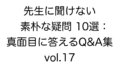
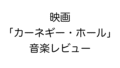
コメント