- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.10
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. 練習では「質」と「量」のどちらが大事?
- ‣ Q2. 継続がしんどい時期、どうモチベーションを維持する?
- ‣ Q3. SNSで上手な演奏を見過ぎてやる気を失った…どうしていくのがいい?
- ‣ Q4. 自分の演奏を客観的に評価できるようになるためにはどうすればいい?
- ‣ Q5. 趣味の仲間と「教え合い」をする学習はどうか?
- ‣ Q6. 演奏会を聴きに行ったほうがいい、と言われるが、どんな視点で聴くべき?
- ‣ Q7. ピアノ学習を「生涯の趣味」として続けるために重要な心構えは?
- ‣ Q8. 楽譜への記号の書き込みについて注意点はある?
- ‣ Q9. 手書きの楽譜が読みづらくて困っている
- ‣ Q10. 東京近郊の音楽学校で勉強したい気持ちが大人になっても消えないが、経済的に難しい
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.10
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. 練習では「質」と「量」のどちらが大事?
結論:質と量は対立しない。両方を意識的に追求する
練習について最もよく議論されるのが「量か質か」という問題です。
よくある考え方:
・「たくさん練習すれば上手くなる」vs「短時間でも集中すれば十分」
・「量をこなすと雑になる」vs「質ばかり考えると進まない」
しかし、実際にピアノが上達している人を観察すると、質の高い練習を継続的に行っていることが分かります。つまり、量と質は対立するものではなく、両方を追求することで相乗効果が生まれるのです。
具体的な実践方法
パターンA:質重視からスタート
・まず集中できる範囲で質の高い練習を確立
・その質を保ちながら、徐々に練習時間を延長
・疲労で質が落ちる手前で終了し、翌日また挑戦
パターンB:量確保からスタート
・確保できる練習時間を最大限活用
・その中で「意識的に質を上げる瞬間」を設ける
・毎回1箇所でも「今日は特に丁寧にやった部分」を作る
どちらが合うかは人によって異なりますが、重要なのは「無意識に量だけこなす」「質だけにこだわって量が足りない」を避けることです。
‣ Q2. 継続がしんどい時期、どうモチベーションを維持する?
結論:学習方法・環境・目標を多角的に見直す
モチベーション低下の原因は人それぞれです。以下の記事で筆者の実体験を交えた具体的な方法を紹介しています:
【ピアノ】実体験:大人のピアノ練習嫌いを直すために効果があった方法
記事で紹介している主な内容
練習嫌いを直すための3つの取り組み:
・ピアノ学習のすべてを一つの明確な目標に結びつける
・練習開始までのハードルを徹底的に下げる
・目先の本番(発表会・録音 など)を設定する
すぐに実践できる工夫:
・自分の「続けられた瞬間」を分析する
・今日から始められる小さな工夫 5選
最終手段も含めた選択肢:
・タイプの先生のところへ習いに行く
・一時的に休む選択肢も検討する
詳しくは上記の記事をご覧ください。
‣ Q3. SNSで上手な演奏を見過ぎてやる気を失った…どうしていくのがいい?
結論:見る内容を選別し、自分より年齢が上の演奏者のだけ見るようにする
SNSで自分より上手な演奏を見て落ち込むのは、誰もが経験することです。特に年齢がずっと若い学習者の演奏を見ると、余計に辛くなるでしょう。
具体的な対処法
情報摂取をコントロールする:
・自分より年齢が上の演奏者の動画を中心に見る
・完成度の高い演奏だけでなく、練習過程を公開している動画も見る
視点を変える:
・「なぜこの人の演奏は魅力的なのか」を分析する姿勢
・落ち込んだ演奏者が知り合いなら、思い切って教えを請うのも手
自分の成長ペースは自分だけのものです。他者との比較ではなく、過去の自分と比べることを意識しましょう。
‣ Q4. 自分の演奏を客観的に評価できるようになるためにはどうすればいい?
結論:録音と振り返りを習慣化し、理想と現実のギャップを埋める
録音チェックの重要性
通し練習を録音して聴いてみると、次のような発見があります:
・思っていたよりもテンポが遅い/速い
・演奏中は気づかなかったミスやリズムの乱れ
・意図しない箇所での不自然な間
これらは「想像している音」と「実際に出ている音」のギャップです。つまり、演奏中に自分の音をしっかり聴けていないということです。
ギャップを埋める練習法
・録音する:通し練習や部分練習を録音
・分析する:理想と現実の違いを具体的に把握
・部分練習:ギャップがあった箇所を重点的に練習
・再録音:改善されたか確認
これを繰り返すことで、段々と理想と現実のギャップが縮まり、頭の中で鳴っている音楽を実際に演奏できるようになります。
「内なる耳」を育てる
作曲家シェーンベルクは、著書「作曲の基礎技法」の中で、こう述べています:
およそ、良い音楽家になりたいと思うのならば、「内面の耳」、すなわち、耳によるイメージ、つまり、想像で音楽を聞く能力をそなえていなければならない。
(抜粋終わり)
これは作曲家向けの言葉ですが、演奏にもそのまま当てはまります。「こういう音を出したい」という明確なイメージがなければ、そもそもその音を出すことはできません。録音練習は、この「内なる耳」を育てる最も効果的な方法の一つです。
・作曲の基礎技法 著:シェーンベルク / 音楽之友社 ※楽曲分析書として、演奏者にも有益
‣ Q5. 趣味の仲間と「教え合い」をする学習はどうか?
結論:効果的だが、ルールを明確にしないとトラブルの原因になる
教え合い学習のメリット:
音楽仲間と学び合うことで、以下のような効果が期待できます:
・自分では気づかなかった視点を得られる
・疑問点を相互に解決できる
・説明することで自分の理解が深まる
・モチベーションを共有し合える
成功させるための注意点
対等な関係を保つ:
・力が同程度の仲間と行う
・レベル差が大きいと、無意識に一方が他方の意見を軽視しがち
明確にルールを設ける:
・「今から意見を出し合いましょう」と明確に時間を設けてから始める
・その中でだけ評価をするようにし、普段の練習中に突然アドバイスするのは避ける
・マウンティングと受け取られるリスクを排除
ゼミ形式の学習
筆者が音楽学校で実践している方法として、数人でピアノや机を囲んで一つの作品について分析し、意見を出し合う「ゼミ形式」があります。
この方法の利点:
・疑問に思わなかったところでも、他者の話から新たな気づきが得られる
・自分の疑問が他者の意見で解決される
・ディスカッションによって理解が深まる
・「みんなで」やることで楽しく続けられる
‣ Q6. 演奏会を聴きに行ったほうがいい、と言われるが、どんな視点で聴くべき?
結論:予習したうえで、まずは純粋に楽しむ。学びは副産物として
演奏会を楽しむための準備
リサイタルでは事前にプログラムが発表されます。クラシック作品の場合は簡単な予習をすることで、より深く楽しめます:
・曲を一度聴いておく
・作曲家や作品の背景を軽く調べる
・楽譜を持っている曲であれば、目を通しておく
予習することで「知っている曲」として納得しながら聴けるため、当日の満足度が大きく変わります。
演奏会当日の心構え
無理に解釈を学び取ろうとせず、録音では味わえない空気感や臨場感を楽しむことを優先しましょう。「印象に残った部分があれば、後日自分の演奏に活かしてみる」程度の軽い気持ちで十分です。
‣ Q7. ピアノ学習を「生涯の趣味」として続けるために重要な心構えは?
結論:面白がることを一番の目標とする。一人でやろうとしない
音楽を純粋に楽しむ
結局のところ、面白がることを最優先にするのが、最も有意義で長続きする方法です。
・見栄や比較やミーハーな気持ちで音楽を雑に扱わない
・純粋に音楽そのものを楽しんで、「また一歩深く入っていけた」という喜びを大切にする
すべてを一人でやろうとしない
ピアノは一人で完結する楽器ですが、だからこそ意識的に仲間を作ることが重要です:
・音楽仲間と学習の困難や喜びを共有する
・定期的に集まって一緒に学習する
・オンラインコミュニティも活用する
孤独な練習の時間と、仲間と共有する時間の両方があることで、学習は持続可能になります。
‣ Q8. 楽譜への記号の書き込みについて注意点はある?
結論:自分が理解しやすい記号を創造的に使う。直線より曲線がおすすめ
一般的な音楽記号
楽譜には決まった記号があります。例えば:
・クレッシェンド / デクレッシェンドの松葉(< >)
・スラーやフレーズの曲線
・トリルの波線
オリジナル記号の活用
自分の学習用であれば独自の記号を作っても構いません。むしろ、ひと目で音楽が捉えやすくなるのであれば推奨すべきことです。
例:後ろ寄りのクレッシェンド(Sibeliusで作成)
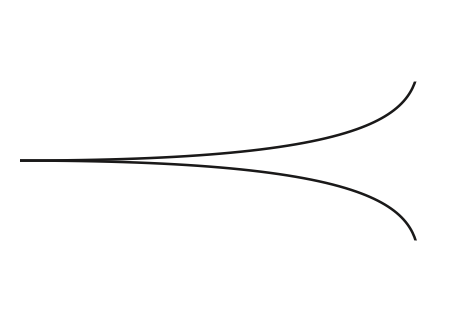
自分で作ったというよりも、現代音楽の世界では時々目にするものですが…。通常の松葉記号(< )を変形させて、このような形にすることで後ろ寄りの変化が視覚的に理解しやすくなります。直線ではなく曲線や変形を使うことで、より音楽的なニュアンスを視覚化できます。
そこに書かれているクレッシェンドへ上書きするように書き込んでみましょう。
‣ Q9. 手書きの楽譜が読みづらくて困っている
結論:書き込みで対応。どうしても困る場合は浄書も選択肢
基本的な対処法
手書き楽譜は、特に近現代以降の作品やアンサンブルのパート譜などで遭遇することがあります。
・読みにくい音符や記号を書き直す
・必要に応じて色ペンで強調する
・分からない箇所は作曲者や編曲者に確認する
浄書という選択肢
どうしても読みにくい場合は、楽譜浄書ソフト(Sibelius、Dorico、MuseScore など)を使って自分で浄書する方法もあります。
浄書ソフトのメリット:
・基本操作は数時間で習得可能
・自作のアレンジ譜や教材作成にも応用できる
・デジタルデータで保存・共有が容易
導入を検討する方は、以下の記事を参考にしてください:
・【ピアノ】演奏者のための楽譜浄書ソフト入門ガイド
・【ピアノ】ピアノ学習者におすすめ:楽譜浄書ソフト用シンプルMIDIキーボード比較
‣ Q10. 東京近郊の音楽学校で勉強したい気持ちが大人になっても消えないが、経済的に難しい
結論:代替的な学習環境を選ぶ or 実際に入学して1年間限定で学習する
音楽学校での学習に憧れがあっても経済的に難しい場合は、以下のような選択肢も検討できます。
代替的な学習環境:
・夏期講習や短期講座に参加
・聴講生として特定の公開授業のみ受講
・東京近郊在住の音楽家によるプライベートレッスン
・マスタークラスに参加(参考:【ピアノ】ピアノ上達の新しいアプローチ:多様な学びの可能性)
慎重に検討すべき選択肢:1年だけ在籍して退学する
慎重な検討が必要な選択肢ではありますが、経済的な問題を軽くすることさえできれば東京近郊住みでの学習も視野に入れることができるのであれば、以下のような案があります:
・学校専用寮があり、かつ特待生奨学金をくれる東京近郊の音楽学校に入学し、1年間限定で本気で勉強する
・1年次が終わったときに退学し、学習方法を切り替える
ただし、以下のリスクを十分に理解する必要があります:
・退学歴が履歴に残る
・対面での友人関係が途中で途切れる
・学習の連続性が途切れる
・入学前に学校に対して十分な説明をし、それでも受け入れてもらえるかの確認必須
このような方法を検討する場合は、必ず事前に学校に相談し、自分の状況を正直に伝えることが重要です。音楽学校には様々な事情を持つ学生が学んでいますので、あなたに合った学び方を一緒に探してくれるはずです。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
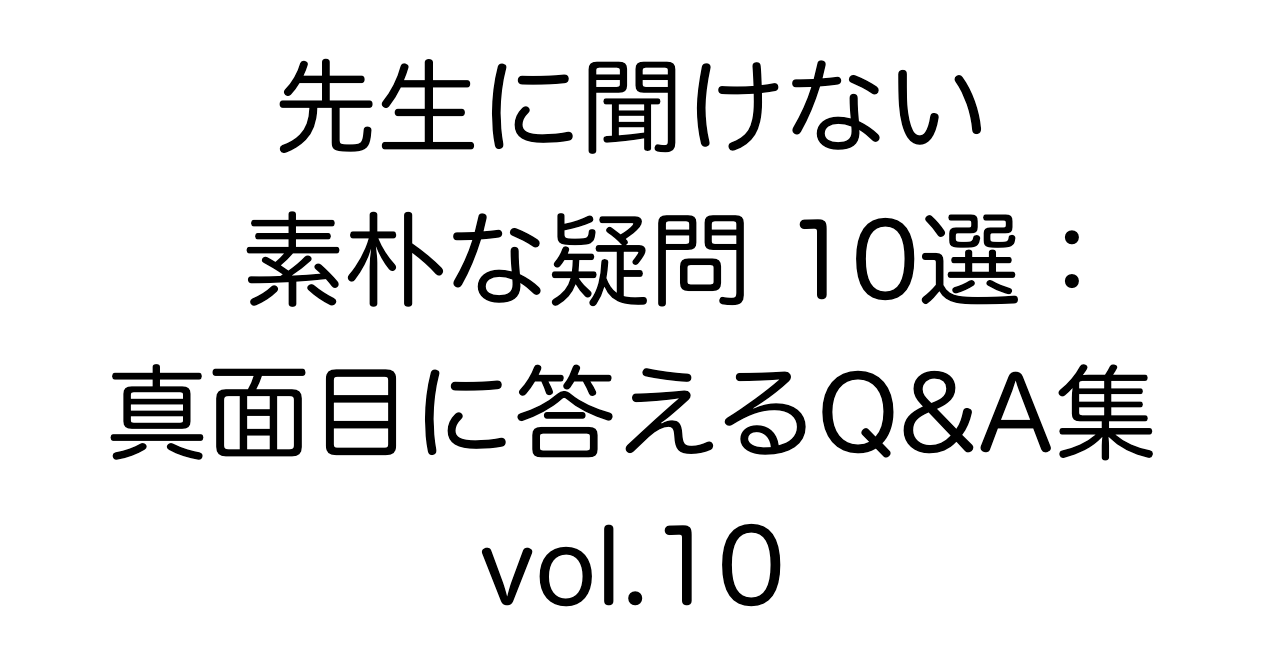

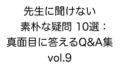
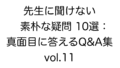
コメント