【ピアノ】バロック期における装飾音は創作的視点で取り入れる
► はじめに
バロック時代の作品を演奏する際に直面する課題の一つが「装飾音」の扱いです。現代の楽譜では多くの場合、演奏すべき音符が詳細に記されていますが、バロック時代の音楽では演奏家の創造性と即興性が重要な役割を果たしていました。
本記事では、バロック期における装飾音の考え方と、その創作的側面について掘り下げていきます。
► 前提知識
‣ バロック時代の装飾音の自由度
バロック時代の装飾音には大きな特徴があります。それは、装飾音の扱いにおいて演奏者に与えられた自由度の高さです。バロック音楽では:
・楽譜に書かれた装飾音を省略することも可能
・楽譜に指定のない箇所に装飾音を追加することも可能
つまり、演奏家の裁量と音楽的判断が尊重されていたのです。このことについては、バロック音楽の専門書などで解説されています。
‣ C.P.E.バッハの装飾音に対する考え方
J.S.バッハの次男であるC.P.E.バッハの著書「正しいクラヴィーア奏法」では、装飾音について重要な指針が示されています。彼の教えによれば:
多様性の重視:
同じフレーズを繰り返す際に、異なる装飾音を用いることで変化を持たせると良い
装飾音の省略という選択肢:
時には装飾を全く加えずに演奏することも効果的な表現手段となる
楽曲の内容との調和:
装飾音は主音符の長さやテンポに比例すべきであり、短い音符や速いパッセージには複雑な装飾は不適切
これらの指針は、装飾音がただの技巧的な飾りではなく、音楽の重要な要素であることを示しています。
► 創作過程としての装飾音
バロック期の装飾音の魅力は、その「創作的過程」にあり、演奏家は以下の観点から装飾音を選択する必要があります:
・曲の雰囲気に合っているか
・テンポや音価との関係は適切か
・前後の音楽的文脈との調和はとれているか
・音楽的なバランスや起伏を生み出せているか
これは、「弾きにくいから省略する」とか「何となく付け加える」という安易な判断とは全く異なります。むしろ、作曲家と演奏家の共同創作のような性格を持っていると言えるでしょう。「どこに取り入れるか」「どのように取り入れるか」ということを判断していくあたりが、非常に創作的な過程と言えます。
► インヴェンションとシンフォニアの例
J.S.バッハ自身が、インヴェンションとシンフォニアについて「作曲への強い興味を起こすことへの指針」と述べていることにも着目しましょう。この作品に限ったことではありませんが、対位法の学習としてだけでなく、装飾音の扱い方という創作的側面も教える教材として機能していたと考えられます。「シンフォニア 第5番 BWV791 変ホ長調」に関しては、「装飾音がない楽譜」と「装飾音を付け加えた楽譜」の2種類を残してくれました。
J.S.バッハの時代、演奏家は同時に作曲家でもあるという前提があり、装飾音の扱いは即興的な演奏技術としてはもちろん、創作能力の一部として認識されていたのです。
► 終わりに
バロック音楽を学ぶ現代のピアノ学習者にとって、装飾音の扱いは技術的な課題であると同時に、創造性を発揮できる機会でもあります。以下のアプローチを参考にしてください:
歴史的背景の理解:
バロック時代の演奏習慣や装飾音について歴史的背景から学ぶ
様々な解釈の比較:
同じ楽曲の異なる演奏者による装飾音の扱いを聴き比べる
実験と試行錯誤:
様々な装飾音を試して、効果的なものを選び出す
装飾音関連の基本と応用については以下の記事にまとめています:
・【ピアノ】装飾音符の基礎知識:歴史的変遷と実践的アプローチ
・【ピアノ】装飾音の応用:バロックから現代までの技法と解釈
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
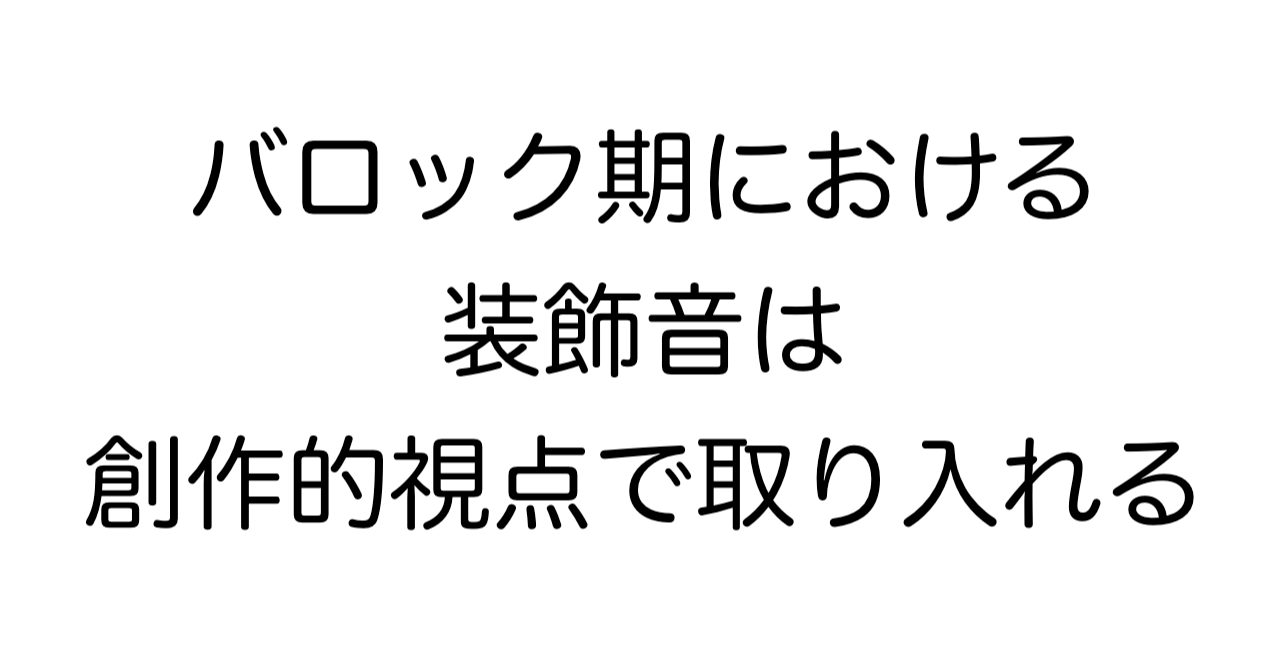
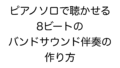
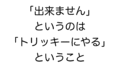
コメント