【ピアノ】「最新ピアノ講座」演奏解釈シリーズのレビュー
► はじめに
本記事では、「最新ピアノ講座」シリーズの2冊を紹介します。これらの書籍は、演奏解釈本に留まらず、コンパクトにまとめられたピアノ音楽史の解説を含む、学習者にとって貴重な一冊です。
・出版社:音楽之友社
・初版:最新ピアノ講座(7) 1981年、最新ピアノ講座(8) 1982年
・ページ数:(7) 215ページ、(8) 243ページ
・対象レベル:初中級~上級者
・最新ピアノ講座(7) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ / 音楽之友社
・最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ / 音楽之友社
► 内容について
‣ 本書の特徴
定番かつ典型的な解釈本
基本的な解釈の考え方が学べる
実用的な内容
運指やペダリングなど譜読みに直結する情報が満載(楽曲分析的な内容は限定的)
幅広い専門家の見解
各楽曲を異なるピアニストが解説、多角的な音楽観を得られる
コンパクトな音楽史
千蔵八郎氏による各時代のピアノ音楽史が簡潔にまとめられている(合計43ページ)
バロックから現代まで網羅
全時代の主要作品と作曲家を系統的に学べる
‣ 本書の価値
1. 効率的な音楽史学習
全てのピアノ音楽史部分を合わせても約43ページと非常にコンパクト。それでいて、各時代の本質的な特徴と重要作曲家を押さえた内容になっています。
2. 演奏と歴史の融合
音楽史を学んだ後、すぐに関連する楽曲の演奏解釈へと進めるため、知識と実践を直結させやすい構成です。理論だけで終わらない点が独学者には特に有益です。
3. 実践的なアドバイス
各曲解説の部分では、運指やペダリングなどの譜読みにも役立つ内容と具体的な演奏解釈が収載されています。
‣ 時代別・作曲家別の代表的収録曲
時代別・作曲家別の代表的収録曲を挙げておきましょう。もちろん、これら以外にも多くの作品が取り上げられています。
バロック期
J.S.バッハ:
・インヴェンションとシンフォニア BWV 772-801
・平均律クラヴィーア曲集 第1部,第2部 BWV 846-869,870-893
・イタリア協奏曲 BWV 971
スカルラッティ:
ソナタ ニ短調 K.9/L.413
ソナタ ホ長調 K.380/L.23
ソナタ ハ長調 K.159/L.104
古典派
ハイドン:
・ソナタ ハ長調 Hob.XVI-35
・ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-49
・アンダンテと変奏曲 ヘ短調 Hob.XVII-6
モーツァルト:
・ソナタ ハ長調 K.545
・ソナタ イ短調 K.310
・幻想曲 ハ短調 K.475
ベートーヴェン:
・ソナタ 第3番 op.2-3
・ソナタ 第7番 op.10-3
・その他、有名なソナタ(悲愴、月光、田園、テンペスト、ワルトシュタイン、熱情 等)
ロマン派前期
シューベルト:
・ソナタ op.120/D. 664
・即興曲 op.142-3/D. 935-3
・楽興の時 op.94/D.780
メンデルスゾーン以降、「最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ」に収載
メンデルスゾーン:
・無言歌(狩の歌、ヴェネツィアの舟歌 op.30-6、デュエット、春の歌、紡ぎ歌 等)
・ロンド・カプリッチョーソ op.14
・厳格な変奏曲 op.54
ロマン派後期
ショパン:
・前奏曲集 op.28
・練習曲 op.10、op.25、遺作
・ノクターン(op.27-2、op.48-1、op.48-2)
シューマン:
・子供の情景 op.15
・幻想小曲集 op.12
・謝肉祭 op.9
リスト:
・愛の夢 第3番
・ラ・カンパネラ
・3つの演奏会用練習曲 第3番〈ため息〉
ブラームス:
・3つの間奏曲 op.117
・ワルツ op.39
・2つの狂詩曲 op.79
近現代
ドビュッシー:
・子供の領分
・ベルガマスク組曲
・ピアノのために
ラヴェル:
・水の戯れ
・ソナチネ
バルトーク:
・ミクロコスモス より
日本の作曲家:
・中田喜直「変奏的練習曲 イ短調」
・矢代秋雄「ソナタ」
・三善晃「ソナタ」
► 終わりに
「最新ピアノ講座 ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ・Ⅱ」は、演奏技術と音楽的知識の両方を効率よく学べる点で、価値のある一冊です。
本書籍を使用した音楽史学習については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
・最新ピアノ講座(7) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ / 音楽之友社
・最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
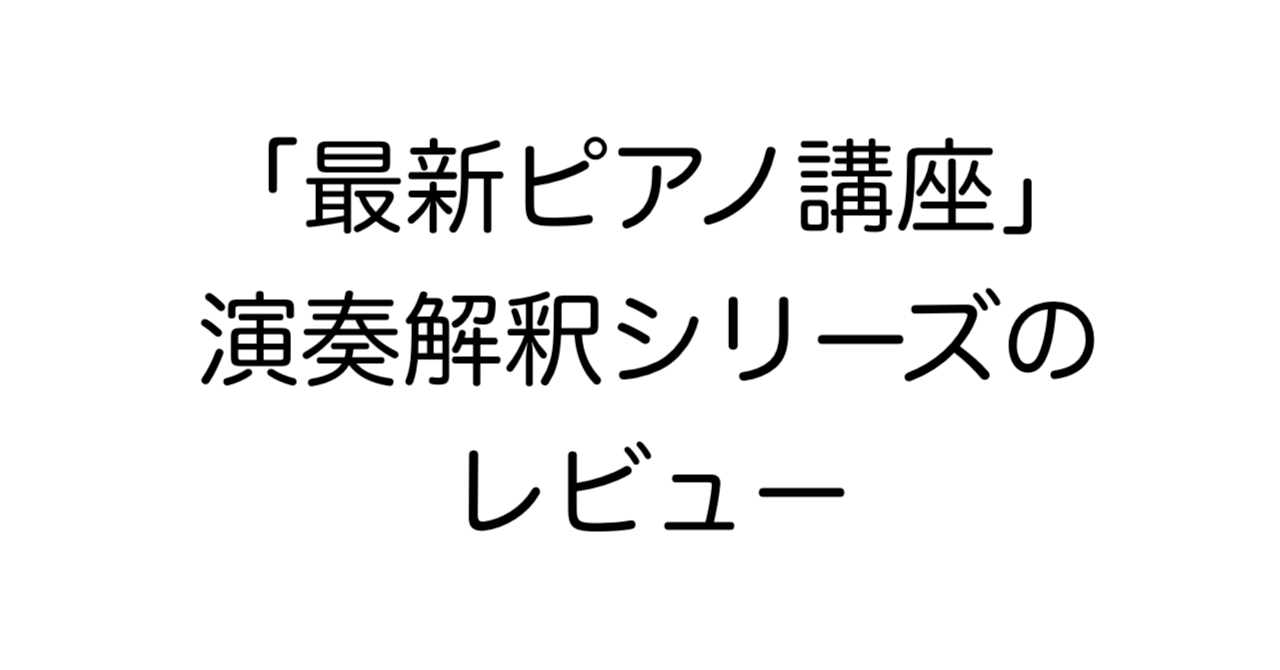


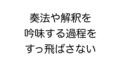
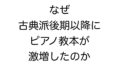
コメント