【ピアノ】先生の選び方・正しい門のくぐり方・その後の付き合い方
► はじめに
本Webメディアでは「独学」を前提とした記事を提供していますが、ピアノ学習において指導者の存在は時に大きな助けとなるものです。スポット(単発)レッスンを受けたり、一定期間のみ習いに行ったりすることで、独学では気づきにくい点を補完できるでしょう。
本記事では、大人の学習者が先生との関係を上手に構築し、必要に応じて適切な選択をするためのヒントを紹介します。独学と教室での学びを最適に組み合わせ、より充実した音楽学習をするための参考になれば幸いです。
► 6つのヒント
‣ 1. 教室退会申し出の心理的負担を軽くする方法
生徒自身が辞めたいのに辞められない状態で尻込みしてしまうのは、何だか違うのでないかと思います。
先生に辞めると言い出すことが怖くてダラダラと年月ばかりが経ってしまったり、逆に、思い切って「辞めたい」と伝えても「休会するだけだよね?」などと話を変えられてしまって遠回しに止められた、なんて話も耳にします。
必ずしも全員ができるわけではありませんが、「大人」の学習者にとって教室退会申し出の心理的負担をグンと軽くする方法があります。
それは、「あらかじめ、辞める可能性があるということを伝えたうえで入会する」という方法。
これから教室を決める方にしかできない方法ですが、すでに通いに行っている方であっても、もし今後教室を変更することがあれば次回からは実行出来ますね。
例えば、次のように伝えてみるのはどうでしょうか。
このように、あらかじめ辞める可能性を伝えておくだけで、いざ退会意思を伝える時期となった時に気持ちが全然ラクなのです。もし引き止められても、入会した時に約束した条件だと生徒側から主張もできるわけです。
入会時にこのように伝えた際、あいまいな返事をされたら要注意です。
なんて話をそらされたら、
などと、返しましょう。
「はい、分かりました。」というきちんとした返事をもらうまで、絶対に入会してはいけません。
ここまで文章で読んでいると、「そんなにグイグイ言える勇気ない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、大丈夫です。入会する “前” であれば、意外と心理的負担少なくあらゆるお伺いを立てることができるもの。原則、お互いに納得できたらはじめて入会が成立するわけなので。それでムリだと言われれば、体験後の初回レッスンに行かなければいいだけです。
ワンレッスン制でやっている先生であっても、「レッスン終わりに、その場で次の予約を取らなければいけない教室」の場合は、拘束的な意味で言えば月極めのレッスンとほぼ同じことです。
どんなレッスン形態であっても、今回紹介した内容で期限を宣言しておくことは心得ておきましょう。何でも最初が肝心。いざ期限がきてどうするかについては、改めて考えればいいのです。
‣ 2. 教室に何の目的で通うのかを考える
前提として、筆者自身は子供の頃からピアノ教室へ通っていましたし、通うメリットは分かっています。しかし、ピアノ教室というのは関わり方によっては「学びを深める場」にもなれば「ただ単に時間とお金を使うだけの場」にもなりかねません。
まず、ピアノ教室へ通うメリットを考えてみましょう:
・一人では何から始めていいか分からない、という状況をクリアできる
・レッスン日という一種の締め切りにより、練習する習慣がつく(可能性がある)
・練習の疑問点や悩みを相談できる
・客観的な視点での適切なアドヴァイスをもらえる(可能性がある)
・自宅にないタイプのピアノに慣れる機会となる
・先生との交流が生まれる
・同じ門下生との交流が生まれる(可能性がある)
・発表会に申し込むだけで本番の機会を得られる
など。細かいことを挙げていけばまだまだあります。
本項目のタイトルは、「ピアノ教室に何の目的で通うのかを考えよう」ということでした。なぜメリットを挙げたうえでこういったテーマを投げかけるのかというと、「中級者以上の学習者ほど、何となくで通ってしまっている可能性が高いから」です。
入門者や初心者の頃というのは、「一人では何から始めていいか分からない、という状況をクリアできる」メリットが大き過ぎるため、通う目的もはっきりしていることでしょう。
しかし、問題になりやすいのは中級者以上。ある程度弾けるようになってくると、基本的な問題点は自分自身で解決できるようになります。先生側も能力の高い先生でない限りは「とりあえず少し気になったことだけを言って、あとはマルをしていく」などといった指導になりがち。そして、「ツェルニー40番を終わらせる」などといった、「教則本を進める」ということのみを目的に通っていたりするケースは多いのです。
決していけないことではありませんが、高いレッスン代と時間を使ってそれでいいのでしょうか?
筆者は、ある程度弾けるようになってきた学習者こそ、「ピアノ教室に通う目的がはっきりしていないのであれば、独学の方がいい」と思っています。
「何をやっていいか分からないから、とりあえず通う」というのは初中級までにしましょう。もちろん、ピアノ教室に通うメリットや目的を十分に考えているのであれば、教室で学ぶのも大いにアリです。問題は、それを考えてみるという行動をしているかどうか。
ピアノ教室が「ただ単に時間とお金を使うだけの場」ではなく「学びを深める場」になるかどうかは、90%以上の部分が自分次第。残り10%は先生の能力と指導方針でしょう。
‣ 3. 先生との関係が辛いのであれば、独学にする
ピアノの教室に通っている方から悩みを伺うことが多くあります。そんな時に多い悩みが、「先生との相性」についてです。
生徒側にも先生側にも様々な事情があります。「こうして欲しい」という要求のすれ違いや、元々の性格の不一致など、様々な理由でいつの間にか距離が開いていってしまうこともあるでしょう。
昔の筆者もそうでした。4ヶ月弱習っただけで当時の先生から離れた、という経験をしています。
もしピアノの先生と相性があわないのであれば、無理せずに一度独学をしてみた方が結果的に伸びる可能性はあると思っておいてください。今の時代はスポット(単発)でレッスンしてくれる専門家も増えたので、ヌケを補っていく方法はいくらでもあります。その後、本当に必要だと思えばまた教室へ行けばいい。
特にある程度弾けるようになってきた方には、こういったことを考えてみて欲しいと思います。
ピアノの先生はいくらでもいます。今の時代は独学でピアノを学べる環境もいくらでもあります。それなのに、相性のあわない先生のところでいつまで我慢しているのでしょうか。学び方は自分で決めてください。それができるのが、大人の学習者です。
‣ 4. 自分の音楽を否定せずに反省する方法
自分の音楽をより良くしていくためには、PDCAサイクルで説明されるように反省の機会も必要になります。しかし、反省する時に、自分の音楽を否定までしてしまう学習者は多いのではないでしょうか。
なぜそんなことが分かるのかというと、昔の筆者がそうだったからです。
解決策としては、とにかく、支配的なもの言いの人物から距離を置くということ。
このWebメディアの記事では割とはっきりと言い切ることは多いですが、それはブログだからであって、音楽学校の個人レッスンなどではここまで直接的な言い方はしていません。
特に気をつけるべきなのは、対面で人と接する時に言い方が強過ぎる人物です。
ある程度はっきり言ってくれる先人の助言はいいのですが、音楽家は良い意味でもそうでない意味でも自分が強い方が多いので、中には:
・「唯一の正解はこうだ」
・「それはぜったいにダメ」
などといった、支配的な主張をしてくる方もいます。その人物に運悪く立派な肩書きなんかがついていたりすると、余計に信じないといけないかなと思ってしまう。
言い方が強い人にされた指摘は、仮にそれが適切な内容だったとしても反省するだけでなく自分を否定しまう原因になります。したがって、いったんそういった方とは距離をとってください。学べる機会は他にもありますので。
‣ 5. 2人目の先生のところへ行く前に考える
2人目の先生のところへ行くのは、以下の2パターンのどちらかに当てはまる場合のみにすべきでしょう:
・今の先生から行くように提案された場合
・自分の意思で行く場合は、今の先生に納得してもらえた場合
2人目の先生のところへ行こうと思うきっかけは様々だと思いますが、少しストレートな言い方をすれば、多くの場合は「焦り」や「勘違い」から来ています。
「解釈をもらいたくてセカンドオピニオンへ行ったのに、根本的な奏法の基礎ばかりを言われて曲が仕上がらなかった」などという例はよく耳にしますが、それはまだセカンドオピニオンへ行く段階ではないことを意味します。この段階ではまだ判断能力もそれほど高くないはずなので、1人の先生に絞って整合性のとれた学習をするほうが得策。
実際には、基礎奏法には「流派」や「各自の特徴」があるので、かなり弾ける方がセカンドオピニオンへ行っても新たな奏法を習得するように言われることはあるでしょう。それに:
・奏法の事ばかりを言う先生
・解釈のことばかりを言う先生
・解釈のことしか言えない先生
など、指導者自体にも偏りがあります。それは確かなのですが、まずは:
・自身がなぜ、セカンドオピニオンを必要だと思うのか
・自身がセカンドオピニオンを必要とする段階に達しているのか
これらの点を自分なりに考え直してみることが必要で、それをしないことには、どこへ行っても身になる学習はできません。
だからこそ、上記2パターンのどちらかに当てはまる場合のみにすべきなのです。それが嫌なら、まずは今の先生のところから完全に離れて、その後に新しい先生を探すべきです。
‣ 6. 先生を変えようか悩んでいる場合のチェックポイント 3選
· チェックポイント①
先生が最近「具体的なこと」を言ってくれなくなって、手抜きをしているのではないかと感じている場合
これについては、多くの場合は先生が悪いわけではないでしょう。レッスンで「抽象的なこと」ばかり言われるようになってきたら、それは、自身がレベルアップしたサインかもしれません。
生徒の基礎ができていない段階というのは、先生はどうしても「テクニック寄りの内容」を教えることになります。例えば:
・「ここでこれだけダンパーペダルを踏んで」
・「ここの指遣いはこのようにして」
などといったように、すぐに演奏に反映される内容を教えてもらえることでしょう。
一方、生徒の基礎ができてくると、こういったことは生徒が自身で解決した状態でレッスンに向かうことになります。そこで、指導はどうしても「音楽論」と言いますか「抽象的な内容」が多くなってきます。この傾向が見えたら、自身がレベルアップしたということでしょう。
先生がサボっていると思って新しい先生を探す前に、現状をよく眺めてみることが重要です。
しかし、ピアノの先生というのは「資格」がなくてもできるため、正直なところ、あまり勉強を積んでいない方もゼロではありません。そこで、もし先生との能力差が限りなく縮まってしまい、その結果、先生の言うことが具体的でなくなったのだとしたら、変え時かもしれません。
判別するポイントは、「とにかく、先生と音楽の話をたくさんしてみること」に尽きます。
音楽における、先生との「距離」は、たくさん話してみればなぜかよく分かるものです。「学びのある会話を先生が返してくれるかどうか」が一つの基準でしょう。
· チェックポイント②
好きな曲を一切やらせてもらえない場合
「課題をたくさん与えられたから」という理由で、先生に「やりたい曲がある」と相談してみることすらせずにこのように言っている方が意外に多いようです。まずは、やりたい曲があるということをしっかりと先生に伝えましょう。
そのうえで「ダメ」と言われてしまったら、理由をしっかりとききだすことです。もしその理由に納得できるのであれば、そのままその先生のもとで学びましょう。特に理由を言ってもらえなかったり、門下生の中でみんなに同じ曲を与えて指導準備の楽をしているような先生だったとしたら、変更を検討すべきかもしれません。
加えて、大きな考慮のポイントは、「自分がどこを目指すか」です。例えば、趣味で続けていきたいのに一方的に毎週4冊も課題を与えられては大変ですね。
必要に応じて、先生とレッスン方針を再度話し合ってみる必要があるでしょう。このプロセスは、音楽を続けていくうえで重要なものです。
· チェックポイント③
「音大受験」を決心したけれど、先生が「受験対策指導」をしていない場合
迷わず変更してください。
音大受験は大きなイヴェントです。「ただ弾く」ということだけでなく、「選曲」や「受験校の傾向に対しての対策」、また「精神的なサポート」まで含めて、音大受験を扱っている先生にすぐに変えないと、結果に結びつけるのは難しいと言わざるを得ないでしょう。
最近は、音大を出ていない方がネットかどこかで拾った情報で「少子化だから…」などとレベルの低下を口にしたりしてしますが、中堅以上の音大であれば、不勉強であれば落ちます。
一般的な筆記の試験と違って、音大受験での実技試験は「たった数十分」で判断されてしまいます。一種の「賭け」のような感じさえしますね。そういった意味でも、餅は餅屋に任せて徹底的な準備をすべきです。現時点での実力にもよりますが、中堅以上の音大を目指す場合、最低でも「1年半」の準備期間を専門の先生と過ごすことが望ましいでしょう。
一番良いのは、現在習っている先生に受験のことを相談して、その先生から新しい専門の先生を紹介してもらうケース。
現時点で習っている先生がそのような専門の先生と面識がないようであれば、マスタークラスに出かけてコネクションを作るのも手ですし、場合によっては第三者のサービスを利用するのもアリです。最近は音大受験のための先生を紹介してくれるアドバイザーのような方も複数いますし、そういった機関の利用を検討みるのもアリかもしれません。
いずれにしても、大事な受験対策の先生を独断で選ぶのだけはやめるべきです。
► 終わりに
独学と教室での学びを上手に組み合わせることで、ピアノ学習はより充実したものになるでしょう。ピアノの先生は多くの知識と経験を持つ貴重な存在ですが、最終的に演奏するのは自分自身です。
特に大人の学習者の場合、自分の目標や学び方について自覚的になることで、より効率的に、そして何より楽しく上達することができます。時には先生との関係を見直し、必要であれば独学の期間を設けたり、新しい先生を探したりする勇気も大切です。
関連内容として、以下の記事も参考にしてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
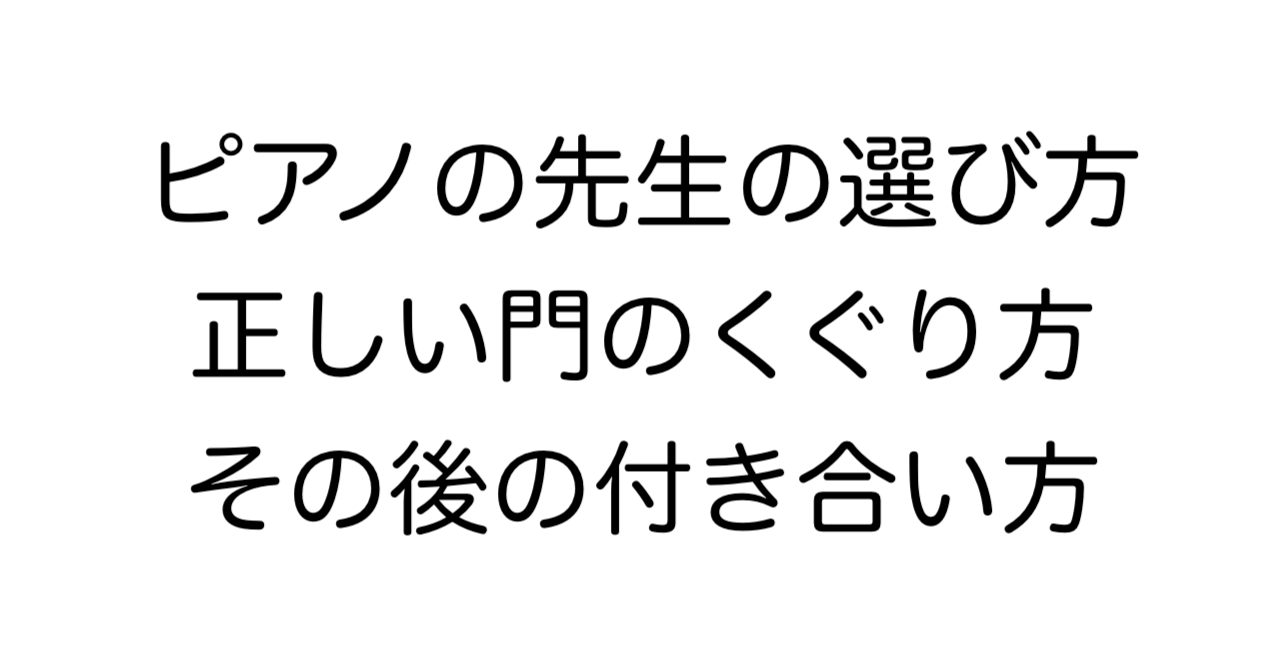
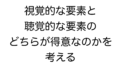
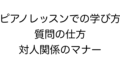
コメント