【ピアノ】モーツァルト ピアノソナタ 中級者向け発表会おすすめ楽章ガイド
► はじめに
演奏発表会でモーツァルトのピアノソナタを演奏したいと考える方は多いでしょう。しかし、「どの作品を選べばいいのか」「限られた演奏時間でどの楽章を選ぶべきか」といった疑問を抱えている方も少なくないはずです。
本記事では、中級以降の学習者が本番で演奏するのに最適なモーツァルトのピアノソナタを、具体的な選曲理由とともに紹介します。
► 発表会でのモーツァルト選曲のポイント
‣ カデンツァ付きの終楽章がおすすめ
モーツァルトのピアノソナタの中でも、カデンツァ付きの終楽章は演奏発表会に特におすすめです。その理由は以下の通りです:
楽曲としての充実度:カデンツァが含まれる楽章は、それに見合う規模と内容を持っている
視覚的・聴覚的効果:ピアノ協奏曲を聴いているような印象を与え、ソリストとしての存在感を演出
聴衆への訴求力:カデンツァの魅力が聴衆の注意を引きつける
‣ おすすめ作品の詳細比較
推奨作品
| 作品 | 調性 | 楽章 | 演奏時間 | 難易度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| K.311 | ニ長調 | 第3楽章 | 約6分 | ツェルニー40番中盤程度 | オーケストラ的なピアノ独奏曲 |
| K.333 | 変ロ長調 | 第3楽章 | 約6分30秒 | ツェルニー40番中盤程度 | モーツァルトのソナタの中では大規模 |
ピアノソナタ ニ長調 K.311 第3楽章 作曲年:1777年
譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)
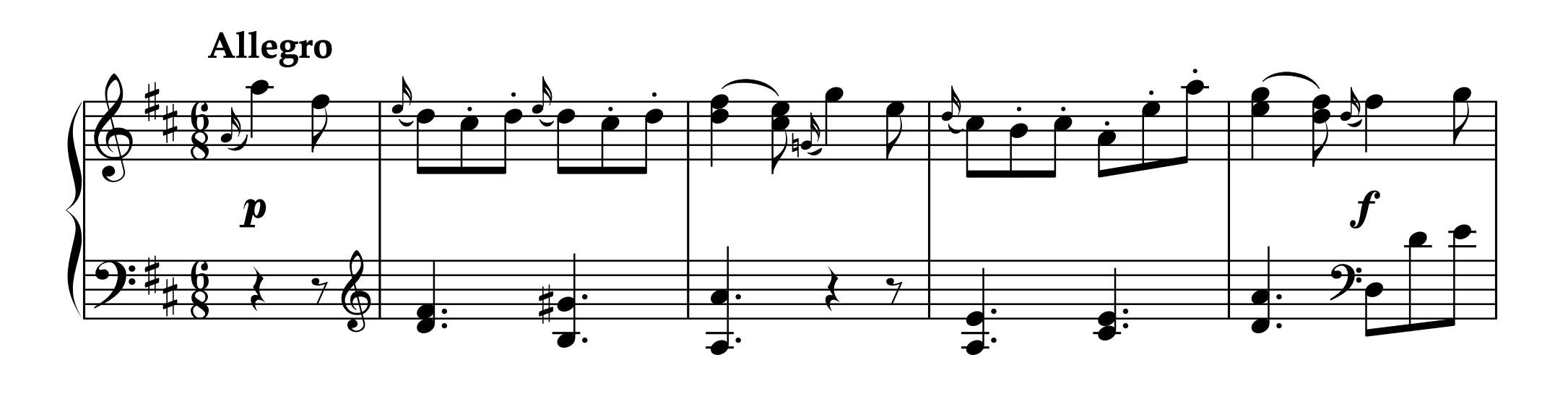
ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第3楽章 作曲年:1783年
譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

‣ 演奏パターンの提案
| 演奏パターン | 総演奏時間 | 適用場面 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| K.311 第3楽章のみ | 約6分 | 短時間の本番 | 「K.333 第3楽章」よりもやや派手なステージになる |
| K.311 第2楽章+第3楽章 | 約10分 | 中規模演奏可能な本番 | 美しいロマンスとメインのフィナーレへ |
| K.333 第3楽章のみ | 約6分30秒 | 短時間の本番 | 単一楽章演奏でも充実した演奏時間 |
‣ 作品別詳細解説
· ピアノソナタ ニ長調 K.311 第3楽章
技術的特徴:
・「K.333 第3楽章」と同程度の技術レベル
・ロンド形式による繰り返しが多いため、音楽的まとめ方が重要
音楽的魅力:
・カデンツァ部分の技巧的・音楽的な美しさ
・第2楽章の美しいロマンスとの対比効果
練習のポイント:
・繰り返し部分での表現の変化を工夫する
・セクションごとのキャラクター変化が明確なので、場面転換を明瞭に
· ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第3楽章
技術的特徴:
・「K.311 第3楽章」と同程度の技術レベル
・やはりロンド形式による繰り返しが多いため、音楽的まとめ方が重要
音楽的魅力:
・第1楽章ほど有名ではないため、新鮮な印象を与える
・繰り返し部分のさりげない変奏加減が絶妙
練習のポイント:
・長めの楽章のため、全体の起伏を計画的に設計する
・技巧的になり過ぎず、楽曲の軽快さや可愛らしさを意識する
► おすすめの楽譜
楽譜は、原典版であるヘンレ版が定番かつ、専門家の信頼度も得ているのでおすすめです。これらの作品に取り組む学習段階まで来たら、原典版を使って学習しましょう。
K.311は第1巻、K.333は第2巻に収載されています。
モーツァルト ピアノソナタ集 第1巻 ヘンレ社
モーツァルト ピアノソナタ集 第2巻 ヘンレ社
► カデンツァの演奏ポイント
あらゆる作品のカデンツァに応用できる演奏ポイントを紹介します。
ピアノソナタ ニ長調 K.311 第3楽章
譜例(PD作品、Finaleで作成、カデンツァ部分)
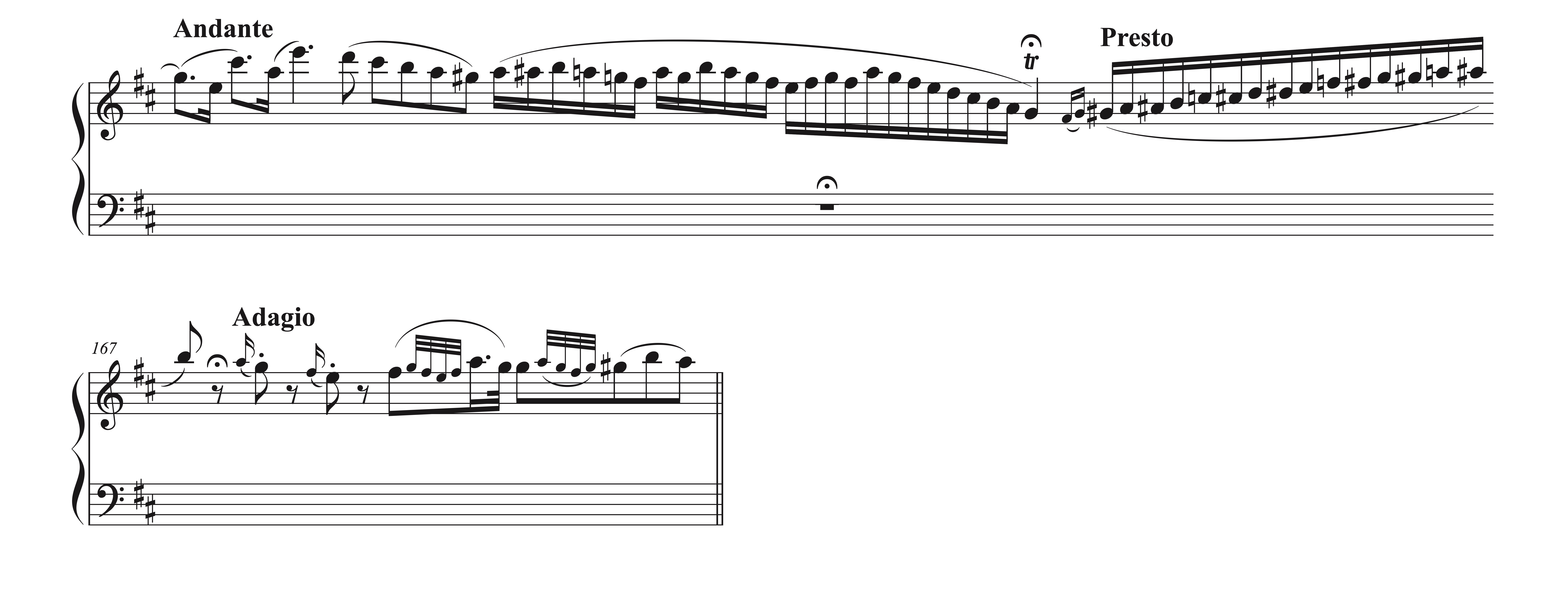
カデンツァの演奏では、「比較的自由ではあるけれども完全に自由にしないこと」を考慮すべきです。
上記の作品のカデンツァでは、モーツァルト自身が:
・4分音符
・付点4分音符
・8分音符
・付点8分音符
・16分音符
・32分音符
・装飾音符
といった様々な音価を書き残すことで、カデンツァでありながらも大づかみのリズムは伝えています。したがって、自由さはありつつも「拍の大づかみの感覚」は持って演奏してください。そうでないと音楽の骨格が歪められてしまいます。
最終的に自由に弾くのは構いませんが、まずは基本の骨格を把握しておきましょう。
作品よっては、音価が明確に書かれていなかったりとカデンツァの大まかなリズムが分からないものもあります。その場合でも、「どこまでが区切りなのか」というのを自身の判断で決めておきましょう。そうすることで、一応の骨格ができるということと、万が一途中で暗譜が飛んでしまっても復帰できるポイントを作ることができます。
► 終わりに
モーツァルトのピアノソナタから発表会向けの楽章を選ぶ際は、カデンツァ付きの終楽章が特におすすめです。K.311とK.333の第3楽章は、いずれも中級者が取り組みやすく、かつ聴衆に強い印象を与える優れた選択肢です。正直、派手さで言えばもっと他の作品も候補に挙がりますが、トータルで見たときにはカデンツァ付きの楽章の充実度は群を抜いています。
適切な楽譜選択と計画的な練習により、これらの作品は素晴らしいレパートリーとなるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
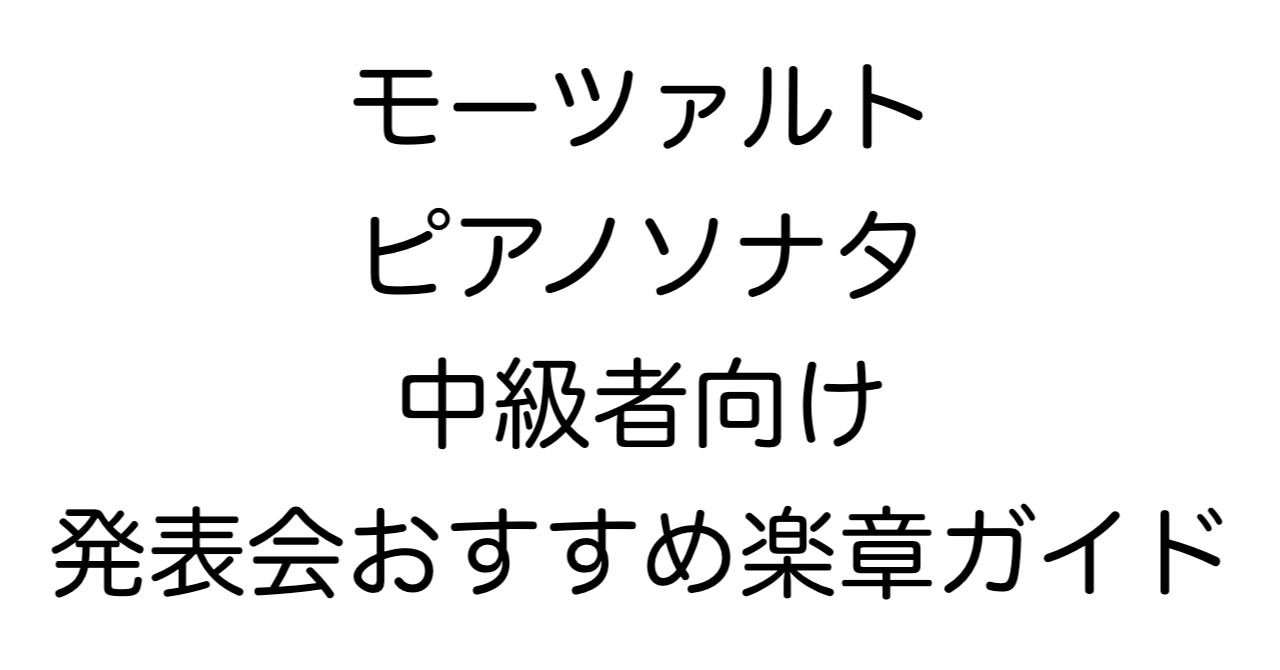


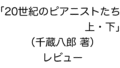
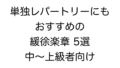
コメント