【ピアノ】耳コピで楽譜を作るためのヒントとステップ
► はじめに
ピアノ学習者にとって耳コピは非常に役立つスキルであり、必要になる場面は多岐にわたります。例えば:
・カデンツァをコピーする
・楽譜が出版されていないけれど弾きたい作品をコピーする
・アレンジなどの学習のために気になる部分をコピーする
・演奏に役立てる情報を手に入れる
本記事の内容の対象者は:
・耳コピを始めたい初心者
・初中級程度の楽譜を読める方
これから紹介するヒントや手順を参考にしながら耳コピを進めていけば、上記のような必要性にも対応できるようになります。
耳コピは決して「完璧にコピーすること」だけが目的ではなく、「自分にとって必要な情報を効率よく取り入れること」が大切です。
► 耳コピに挑戦する際の3つの重要なポイント
‣ 1. 耳コピの基本的なアプローチと心構え
「今回はどの要素をどれだけコピーするべきなのか」を考えると、効率よく必要な部分を取り入れることができます。
演奏のために音源に近い形でコピーしたい場合は別ですが、それ以外のケースでは、原則として完璧主義を捨てたほうがいいでしょう。
例えば、編曲の学習として気になる部分を分析するための耳コピであれば、まるまる全部をコピーする必要はありません。必要な部分のみを抽出し、それも自分にだけ分かるようにまとめる方法で十分です。前後関係を確認したければ、そのときに改めて取り込めばいいのです。
要するに、コピーを始める前に「なぜ採譜をするのか」を明確にすることが重要です。
作曲の勉強などですべての音を正確に採ろうとする方もいますが、基本的には「自分がピアノで弾くため」であることを意識しましょう。そう考えると、メロディ、バス、大体のハーモニーさえ採れれば、すべての音が完璧に採れなくても問題はないことが分かります。
やる前から「完璧に採れない」と悩んでいる方も多いですが、趣味の耳コピには完璧主義を持ち込む必要はないことをお伝えしたいと思います。
‣ 2. 耳コピを行う際の実践ガイド
本来、音楽理論の知識があれば、耳コピはより効率的に、確実に行えますが、その力はすぐには身につきません。したがって、今回はよりテクニック的な観点から、耳コピ初心者に向けてピアノ曲の採譜のポイントをまとめます。
採る順序:
・はじめにメロディを採る
・バスラインが明確な楽曲であれば、次にバスを採る
区切って採る:
・8小節など、短いひとカタマリを見つける
・難しければ、1小節か2小節などもっと短く区切る
繰り返し聴ける環境とスローテンポで聴ける環境の用意:
・音楽プレーヤーのスピード調整機能の活用
・スロー再生アプリの活用
補助ツールの活用:
・有名曲であればシンプルなメロディ譜などが出ているので、大枠を参考にする
・採譜サービスで、本当に分からない部分のみピンポイントで依頼する
この中で最も重要なのは、まずメロディを採ることです。
例えば、4声の和声書き取り聴音で「まずソプラノとバスのみを採る」といった指導があるのには理由があります:
・一番聴こえやすい部分から取り組むと、取りかかりやすい
・両脇(メロディとバス)が採れていると、他の声部が聴き取れなくても和声が推測しやすくなる
ピアノ曲でも同じことが言えます。
ピアノ曲の場合は必ずしも4声ではないですし、バスの所在が分かりにくいところも多々出てくるため、とりあえずメロディのみをはじめに採ってしまうといいでしょう。そうすることで、他の部分へ取り掛かるハードルが下がります。
‣ 3. 耳コピを演奏力アップに活かす実践法
耳コピをピアノ練習に応用する場合は、「歌の抑揚をコピーする」という観点を活用しましょう。
ポピュラー音楽の楽譜を使い、原曲の抑揚を細かく真似して弾いてみてください。楽曲は何でも良いわけではなく、ビートルズなど、表現力やクオリティに定評のあるアーティストの作品を選ぶと効果的です。
また、できる限り原曲の雰囲気に近いアレンジ譜を使用してください。判断が難しければ、ひとまず「メロディが変更されていないもの」という基準で選べば良いでしょう。
以前、レコーディングエンジニアの方が次のように話していました:
これは、おそらくピアノが持つ「減衰楽器」という特性が大きく影響していると思われます。管楽器や弦楽器のように発音後に音を膨らませたりすることが難しいため、表現を極端にしないと音楽が伝わりにくいのです。
このような背景を踏まえ、今回紹介したような練習方法で抑揚を表現することを身体に覚えさせておくと、表現力を高めるために非常に有益です。
► 終わりに
耳コピは最初は難しいかもしれませんが、続けることで確実に成果を実感できる方法です。完璧を目指すあまり負担にならないように、自分のペースで進めていきましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
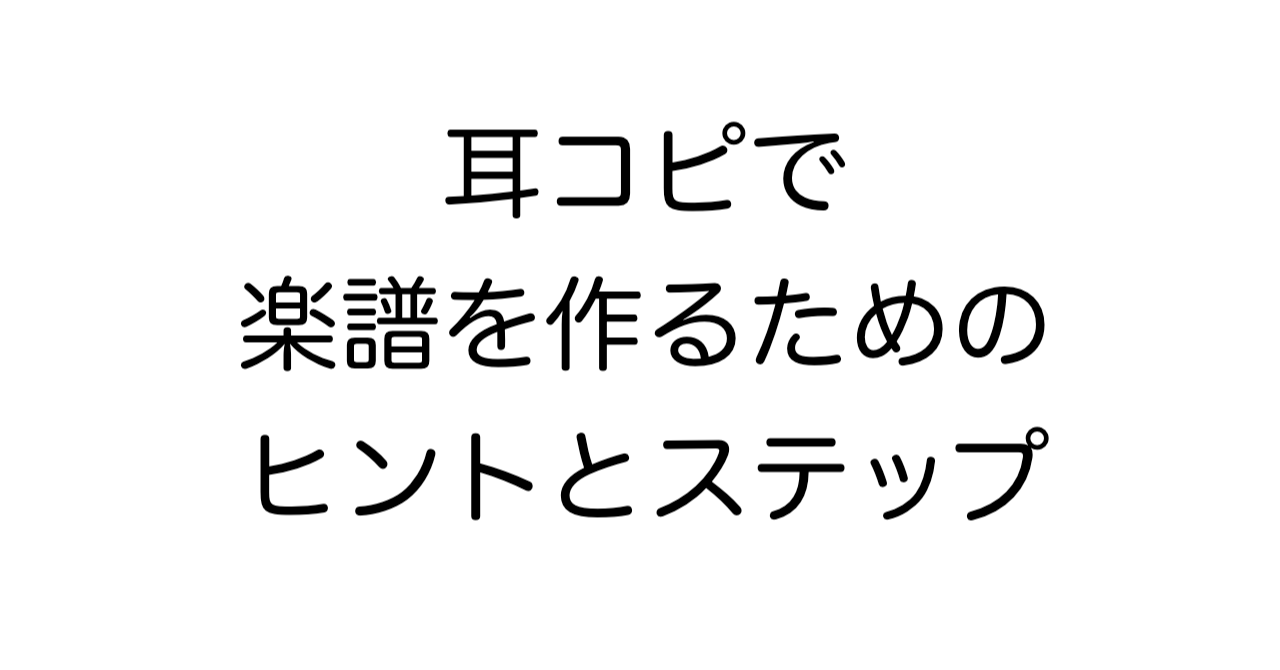
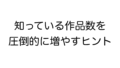
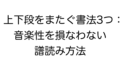
コメント