【ピアノ】ゲルハルト・プッヘルト「ソナチネのすべて」レビュー
► はじめに
ピアノ学習者にお馴染みの「ソナチネアルバム」ですが、なぜこの曲集にはソナチネだけでなくソナタやその他の小品まで収録されているのでしょうか。このような素朴な疑問から始まり、本書はソナチネという分野の奥深い世界を知ることができます。
著者のゲルハルト・プッヘルト(1913-1987)は、ドイツの名ピアニストとして活躍しました。その深い音楽的経験に裏打ちされた本書は、わずか63ページながら、ソナチネに関する包括的な知識を提供してくれます。
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:1988年
・ページ数:63ページ
・対象レベル:初中級~上級者
・書籍副題:愛らしい音楽形式の成立、その歴史と意義
・ソナチネのすべて ムジカノーヴァ叢書 11 著:ゲルハルト・プッヘルト 訳:寺本まり子 / 音楽之友社
► 内容について
‣ 目次
・はしがき
・I. ソナタ形式、ソナチネ、やさしいソナタの発展について
・II. 古典派のソナチネ 形式の楽しい練習 クレメンティ、ドゥシェク、ベートーヴェン
・III. 社会教育の手段としてのピアノ 楽しみの曲目とサロン音楽
・IV. 古典派のソナチネ その全盛期と衰退期 ディアベリ、クーラウ
・V. ロマン派への様式転換の影響 マルシュナー、タウベルト、シューマン
・VI. ロマン派様式の練習としてのソナチネ ライネッケ、キルヒナー、同時代の他の諸作曲家
・VII. 19世紀末以後の新しい飛躍 レーガー、ユオン、ニーマン
・VIII. 演奏会用の曲としてのソナチネ ラヴェル、プロコフィエフ、ブゾーニ
・IX. 20世紀における新しい刺激 民族音楽、新古典主義的演奏音楽、ジャズ、展望
・補遺 ソナチネ集 概観
・訳者あとがき
‣ 歴史的視点から紐解くソナチネ
本書の特徴は、ソナチネを音楽史の流れの中に位置づけて論じている点です。
クレメンティやモーツァルトなどの古典派時代から、ラヴェルやバルトークなどの近現代作品まで、各作曲家がどのようにソナチネという分野を捉えて作曲しているかを時代を追って解説しています。また、「ソナチネ」という言葉が時として低く評価されがちな現状についても、評価の移り変わりを歴史的な流れから解説しています。
‣ 実用的な知識も豊富
本書には楽曲分析などは掲載されていませんが、実際のピアノ指導や学習に役立つ情報も多数含まれています。
なぜソナチネアルバムの楽曲配置にあのような工夫がされているのか、一つの楽章だけを取り出して学習することの問題点など、指導者や学習者にとって有益な視点が随所に散りばめられています。また、「ソナチネ」と「小さいソナタ」という呼称の区別については、少し拍子抜けするような解説がされています。
‣ コンパクトながら充実の内容
63ページという手頃なボリュームも本書の魅力の一つです。忙しい指導者や学習者でも、短時間で読み通すことができます。しかしその内容は薄くなく、むしろ、無駄を削ぎ落とした簡潔な文章により、エッセンスがより鮮明に浮かび上がってきます。
目次を見るだけでも、ソナチネの発展史から20世紀の新しい動向まで、体系的に整理されていることが分かります。
► 終わりに
本書は楽曲分析書でも演奏技法の手引書でもありません。しかしそれゆえに、ソナチネという音楽形式の知識を多角的に理解することができます。また、ソナチネアルバムに収載されている定番作品に限らず、ソナチネ関連の様々な作品を知ることができます。
ピアノを学ぶ方、教える方にとって、既に理解していると思っていた分野に新たな発見をもたらしてくれる一冊になるでしょう。
・ソナチネのすべて ムジカノーヴァ叢書 11 著:ゲルハルト・プッヘルト 訳:寺本まり子 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
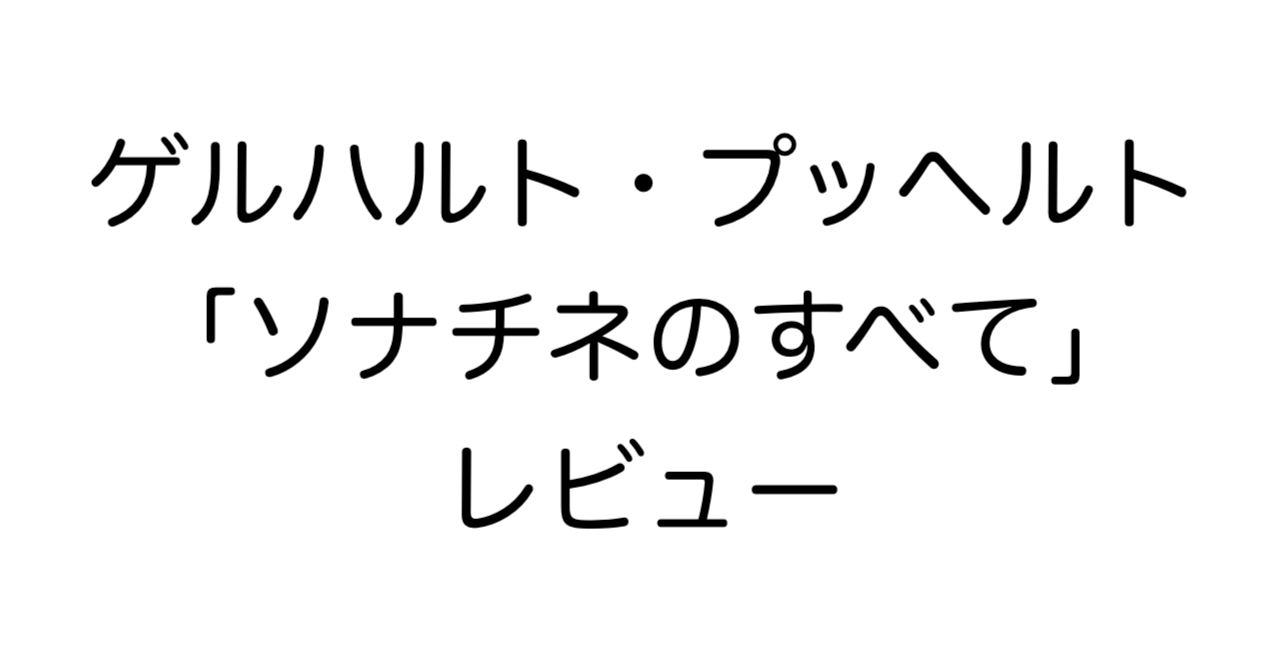
![ソナチネのすべて[ムジカ]](https://m.media-amazon.com/images/I/311-UA3hNjL._SL160_.jpg)
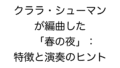
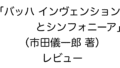
コメント