【ピアノ】演奏における暗黙知を言語化する:独学での上達に効く具体的アプローチ
► はじめに
「暗黙知」、それは言葉では表現しづらい体験的な知識であり、多くの場合「感覚」として語られます。しかし、この暗黙知を可能な限り言語化し、理解を深めることで、独学でのピアノ学習をより効果的に進めることができます。
簡潔に言うと、「感覚だけに頼ってやってきたものを少し言語化して理解してみよう」ということです。
► 暗黙知とは何か
ピアノ演奏における暗黙知とは、例えば:
・指先で感じる鍵盤のタッチ感覚
・音の粒立ちや響きのコントロール
・フレーズの自然な流れを作り出すタイミング
・曲想に合わせた適切なペダリング
これらは通常「感覚で掴む」と言われる要素ですが、実は細かく分解して考察することが可能です。
► 暗黙知の言語化
‣ なぜ今、暗黙知の言語化が必要なのか
独学でピアノを学ぶ多くの方が、このような経験をしているのではないでしょうか:
・楽譜通りに弾いているはずなのに、なぜか音楽的に物足りない
・先生から「もっと表情豊かに」と言われても、具体的に何をすればいいのかわからない
・YouTubeで上手な演奏を聴いて真似しようとするものの、どこが違うのかが掴めない
・練習を重ねても、なかなか上達を実感できない
これらの悩みの多くは、「暗黙知」と呼ばれる、言葉になっていない演奏技術が関係しています。
プロや経験豊富な教師は、長年の経験から自然とこれらの技術を身につけていますが、独学者にとっては「感覚」だけでは掴みにくい領域です。
‣ 暗黙知を言語化する試み
1. タッチの解剖学
ピアノの鍵盤は「ON/OFF」のスイッチではなく、また、ピアノのタッチは単なる「強い/弱い」ではありません。以下の要素に分解できます:
・指先の接触面積と圧力配分
・手首の角度と柔軟性
・腕の重みの使い方
・打鍵速度、打鍵角度
これらを意識的に変化させることで、様々なニュアンスが生まれます。
2. フレージングの構造化
自然なフレージングには、以下のような要素が含まれています:
・音楽的な重心の位置(「楽式論 石桁真礼生 著(音楽之友社)」で学べる)
・各音符間の微妙な時間的間隔
・音量の段階的な変化
・和声進行に応じた強調点
3. 感情表現の要素分解
「感情豊かな演奏」の背後には、様々な要素があります:
・アゴーギク(テンポの微細な揺れ)
・音の立ち上がりの速度
・フレーズ終わりのニュアンスの作り方(言語表現と共通)
・音色の扱い
‣ 例えばどのように活用できるか
暗黙知の言語化の具体例として、「フレーズの終わり方」について考えてみましょう。
多くの場合は「フレーズ終わりの音は大きくならないようにおさめる」と指導します。これは単なる規則ではなく、音楽表現の本質に関わる重要な要素。その理由を言語化して考えてみましょう。
まず、フレーズとは何かを明確にします。フレーズは、楽譜上では「フレーズのスラー」や「休符」によって示され、また、スタッカートが続く場合は、動機のまとまりやその区切りを観察することでフレーズを見分けることができます。
これを言語表現に置き換えて考えると理解しやすくなります。音楽のフレーズ終わりは、文章における句読点のような役割を果たします。例えば:
不自然ですね。句読点の直前を強調してしまうと、このように尻もちをついたような、または、怒っているような印象になってしまいます。
一方、
というように強調する場所によっては、その話し方で何を強調したいのかを印象付けることができます。その強調しても問題ないところが句読点の直前ではないということ。
このように、文章でも音楽でも、終わりの部分の扱い方が全体の印象を大きく左右します。特に感情表現において、終わり方は始まりや途中と同等、またはそれ以上に大きな影響力を持ちます。
この理解があれば、「もっと感情豊かに」という指示を受けたとき、単に「気持ちを込める」という漠然とした対応ではなく、フレーズの終わり方を意識的にコントロールするという具体的なアプローチが可能になります。「フレーズの終わり方」以外にも、感情豊かに演奏するための暗黙知の部分が多様に言語化されていることによって、具体的なヒントをたくさん知っていることになります。
このように、言語化することで、感覚的な理解だけでなく、技術的な視点からも演奏表現を改善することができます。
► 終わりに
暗黙知の言語化は、それ自体が目的ではありません。言語化することで:
・自己の演奏をより客観的に分析できる
・問題点を特定しやすくなる
・練習の方向性が明確になる
・新しい気づきを得やすくなる
・他人を指導することができるようになる
という効果が期待できます。
楽曲分析の学習などでも同様に、暗黙知の言語化を試みてみましょう。
完璧な言語化は不可能ですが、できる限り試みることで、独学での上達がより効率的になるはずです。これは単なる「感覚」に頼る方法と、言語化による意識的な学習を組み合わせた、バランスの取れたアプローチと言えるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこち
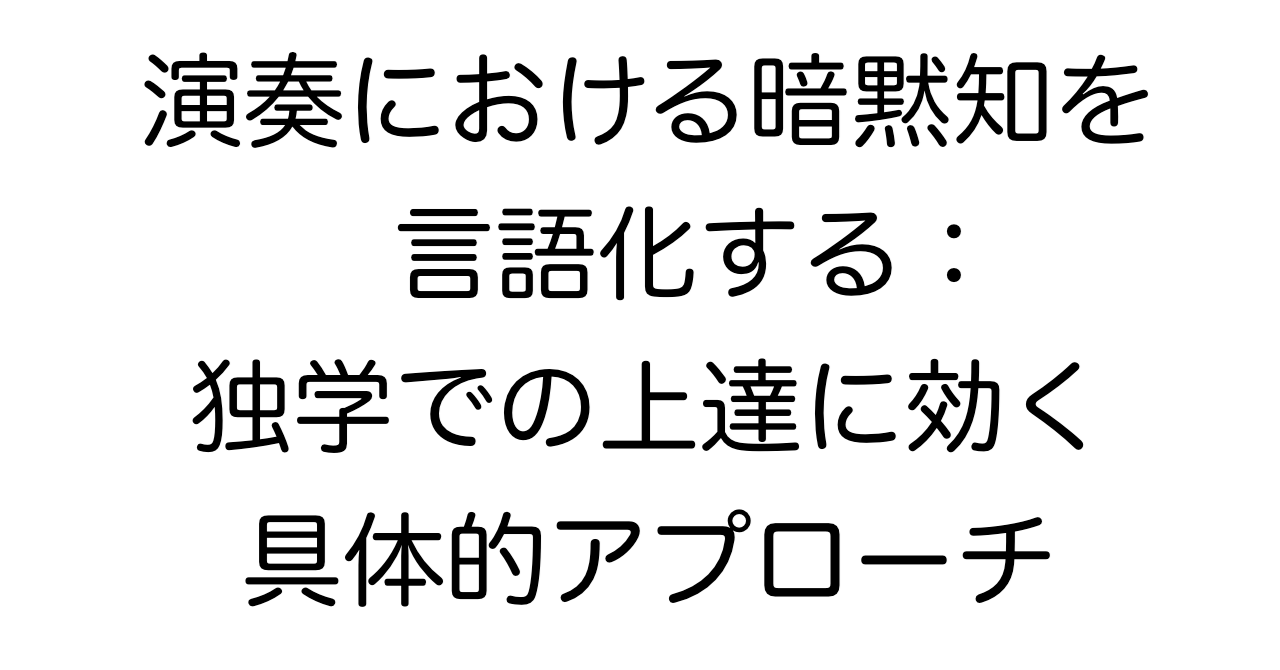
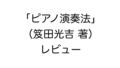
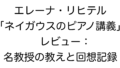
コメント