【ピアノ】「楽譜の話あれこれ」(伊藤義雄 著)レビュー
► はじめに
「楽譜の話あれこれ」は、ユニークな切り口のピアノ音楽史の参考書です。本書は「楽譜」という視点から音楽史、特にピアノ音楽史をたどるというアプローチを取っています。この具体的な視点を通して学習することで、音楽史をより親しみやすく感じられるでしょう。
・出版社:音楽之友社
・初版:1982年
・ページ数:188ページ
・対象レベル:初級~上級者
・著者:伊藤義雄(武蔵野音楽大学 名誉教授)
・楽譜の話あれこれ ムジカノーヴァ叢書 3 著:伊藤義雄
► 内容について
‣ 独自の視点で語られる楽譜の歴史
著者は、各時代の代表的作曲家たちの楽譜に関する興味深いエピソードや特徴を丁寧に解説しています。バロック時代のクープラン、ヘンデル、J.S.バッハから、古典派のハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、そしてロマン派の作曲家たちに至るまで、時代を追って楽譜の変遷を眺めることができます。
‣ 本書の特徴
1. 豊富な楽譜に関する話題
本書の最大の魅力は、やはり「楽譜」に焦点を当てた話題の豊富さでしょう。例えば:
・シューベルトの作品の中で最初に印刷された楽譜は何か
・特定の作品が作曲家の生前に出版されなかった理由
・作曲家の友人による自費出版のエピソード
・自筆譜から見える作曲家の特徴や創作過程
・ショパンの作品のファクシミリが多く残されている背景
これらの話題は、作品の解釈や理解を深めるうえで非常に重要な視点を提供してくれます。
2. 特に、後期古典派までの時代の豊富な情報量
本書の構成を見ると、バロック時代から古典派、そしてロマン派まで、各時代が扱われていることが分かります。特にJ.S.バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンについては、それぞれの創作期を分けて詳細に論じられています。
3. マイナー作曲家への言及
「初期ロマン派」の章は、クレメンティ、クラーマー、プレイエル、トマシック、フィールドといった、比較的マイナーな作曲家達についても触れられている点で注目に値します。こういった作曲家達は、陰ながらピアノ音楽の発展において重要な役割を果たした人物と言えるでしょう。
‣ 各章の内容と特徴
I〜III:初期の楽譜からヘンデルまで
初期の楽譜の歴史から始まり、クープランやヘンデルの楽譜に関する特徴が解説されています。バロック時代の楽譜や作曲家毎の特徴が理解できるでしょう。
IV:J.S.バッハ
J.S.バッハの章は「前半期」と「後半期」に分けられ、かなりの紙幅を割いて詳細に論じられています。具体的な重要作品も数多く取り上げられています。
V〜VI:スカルラッティとC.P.E.バッハ
鍵盤音楽の発展において重要な位置を占めるこの二人の作曲家についても解説されています。古典派への橋渡しとなる特徴を持っているマストで押さえておくべき人物について学べます。
VII〜IX:古典派三大作曲家
ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンという古典派の三大作曲家についての記述は、本書の中核をなしています。特にモーツァルトとベートーヴェンについては「習練期と活動期」「青年期と大成期」というように時期を分けて詳細に論じられており、作曲家の人生の変遷を順に追うことができます。
X:ロマン派
初期ロマン派の章は、上記のように、比較的マイナーな作曲家達についても触れられている点で注目に値します。一方、シューベルトの情報は豊富ですが、ショパンやリストについては比較的少なめの記述に留まっています。これは本書が主に「初期の楽譜」から「後期古典派」までに焦点を当てているためでしょう。
► 終わりに:「楽譜」という視点から見える音楽史
「楽譜の話あれこれ」は、「楽譜に関する話題が豊富な、作曲家人物音楽史」だと思ってください。バロック期からロマン派までの時代を「楽譜」という視点を重視して眺めることで、作曲家や作品の理解に新たな光を当ててくれます。
・楽譜の話あれこれ ムジカノーヴァ叢書 3 著:伊藤義雄
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
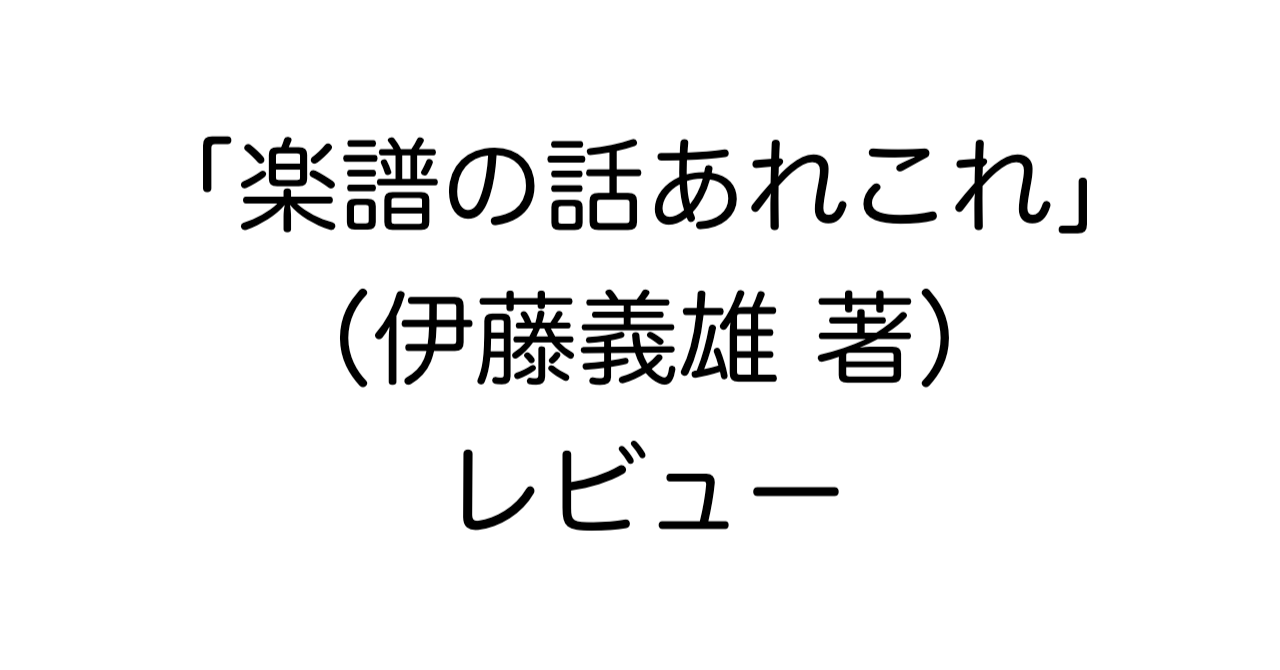

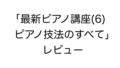
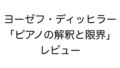
コメント