【ピアノ】「再現芸術」の誕生と作曲家・演奏家の分業
► はじめに
本記事では、クラシック文脈のピアノ音楽における「再現芸術」と、作曲家と演奏家の分業の関係について探ってみたいと思います。
「再現芸術」というのは、広義で捉えれば遥か昔からあったわけなので、「誕生」というよりは、「その明確化」といったほうがいいかもしれません。「ピアニスト=作曲家」という図式が崩れ始めた時、明確化されてきました。
※本記事は、一部「ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎」(春秋社)の内容を参考に、大幅な補足を加えたうえで作成しています。
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
►「再現芸術」とは何か?
「再現芸術」とは、作曲家が創作した作品を演奏家が解釈し再現する芸術形態を指します。現代のピアニストの多くは、この「再現芸術家」として活動していますが、これは特に、19世紀後半から20世紀初頭にかけての変化が関係しています。
►「ピアニスト=作曲家」の図式が崩れた理由
バロック時代から、音楽家は主に宮廷や教会に仕える立場にあり、J.S.バッハやハイドンのように特定のパトロン(後援者)に雇われていました。彼らは、一部を除き、自分の作品を自ら演奏するのが基本でした(ピアノに限らず)。
しかし、18世紀末から19世紀初頭にかけて、音楽家の社会的地位に大きな変化が起こります。フランス革命以降の社会変革により、音楽家は王侯貴族への従属から徐々に解放され、一人の独立した芸術家として活動する自由を得ました。一方、この自由は同時に、安定した収入源を失うことも意味していました。音楽会もまた、音楽を聴くために集まる聴衆によって維持されることになりました。そこで、音楽家たちは新たな収入源として、演奏活動を重視するようになったのです。この時期に「作曲家」と「演奏家」という職業的分化が進み始めました。それが、時間をかけて19世紀後半あたりになると、相当分業が進んだ状態になってきます。
►「ピアニスト=作曲家」の時代から「再現芸術家」の時代へ
‣ 作曲と演奏の一体時代
19世紀前半までは、「ピアニスト=作曲家」という図式が一般的でした。例えば、モーツァルト、リスト、ショパンといった音楽家達は、主に自らの作品を演奏することで名声を博しました。彼らは:
・自作の曲を演奏会で披露
・聴衆の反応に応じて即興的に曲を発展させる
リストがベートーヴェンやショパンの作品を弾いたりすることはありましたし、ショパンが演奏活動をあまりせずに作品を書いていた時期もあります。これらのような例外はいくつかありますが、主なスタイルとしては創作と演奏が密接に結びついていて、それが中心になっていました。
‣ 特に大きな転換期:ドビュッシーの時代
上記のように、フランス革命以降の社会変革を経て、「作曲家」と「演奏家」という職業的分化が進み始めていました。そして、19世紀末から20世紀初頭、ドビュッシー(1862-1918)の活躍した時代あたりから、特に大きな変化が生じ始めました。この時期に注目すべき変化として:
演奏家の専門化:
作曲はせず、演奏のみに特化するピアニストが特に増加
演奏技術の向上:
ピアニストの演奏力が格段に高まった
作曲家の意識変化:
作曲家が自作の初演を他のピアニストに任せるケースが特に増えた
特にドビュッシーは、「前奏曲」のうちの数曲など一部の作品を除き、他のピアニストに初演を任せる姿勢を持っていました。同時代のラヴェル(1875-1937)も、自身がピアノの腕前を持ちながらも、自作の初演は他のピアニストに任せる考え方を持っていたとされています。
► 再現芸術家としてのピアニスト
‣ 再現芸術家としてのピアニストの誕生
作曲者と演奏者の分業は、音楽表現に新たな可能性をもたらしたのは事実です。作曲家が演奏家に作品の解釈を全面的に任せることで:
・作曲者本人とは異なる新鮮な解釈が生まれる
・専門的な演奏技術による高度な表現が可能になる
・時に作曲者自身よりも優れた解釈が生まれることもある
こうして20世紀に入ると、ピアニストは「再現芸術家」としての地位を確立していきました。中には、「再現芸術家」というよりも、新曲初演を演奏活動の中心としているピアニストもいます。
‣ 過渡期の名ピアニストたち
この分業が進んだ過渡期に活躍した名ピアニストには、例えば次のような人々がいます:
1870年代生まれ:
・マルグリット・ロン(1874-1966) ※ラヴェル作品の初演を多く担当
・ワンダ・ランドフスカ(1879-1959)
・アルフレッド・コルトー(1877-1962)
1880年代生まれ:
・アルトゥール・シュナーベル(1882-1951)
・ヴィルヘルム・バックハウス(1884-1969)
・アルトゥール・ルービンシュタイン(1887-1982)
1890年代生まれ:
・マイラ・ヘス(1890-1965)
・ベンノ・モイセイヴィチ(1890-1963)
・ヴァルター・ギーゼキング(1895-1956)
また、テオドール・レシェティツキ(1830-1915)は、この時代を代表する名教師として、20世紀前半に活躍する著名なピアニストを多く育てました。
► 例外:創作と演奏を続けた20世紀の作曲家たち
20世紀前半には、まだ「ピアニスト=作曲家」の伝統を引き継ぐ音楽家も存在していました。例えば:
スクリャービン(1872-1915):
19世紀的な「ピアニスト=作曲家」の典型で、作品の大部分がピアノ曲
ラフマニノフ:
作曲家としてだけでなく、超絶技巧を持つピアニストとしても活躍
バルトーク、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ:
自作を演奏する機会も多かった
モシュコフスキー(1854-1925):
19世紀的な「ピアニスト=作曲家」として活動
グラナドス(1867-1916)・アルベニス(1860-1909):
共に優れたピアニストで自作品を演奏
►「再現芸術」への転換がもたらした変化
ピアニストが「再現芸術家」になることで、良い面と課題の両方が生まれました:
メリット:
・演奏技術の専門性が高まり、より高度な表現が可能に
・様々な演奏解釈により、同じ作品でも多様な表現が生まれる
・過去の名曲が保存され、広く伝えられるようになった
課題:
・「現場的感覚」にあふれる新作品が減少
・過去の名曲の再現に意識が集中し、同時代の新作品への関心が薄れる傾向
・作曲家の意図を代弁する役割にとどまることも
► まとめ
19世紀末から20世紀初頭にかけて生じた「作曲家と演奏家の分業」は、現代の「再現芸術家」としてのピアニストのあり方を形作りました。この歴史を知ることで、ただ単に楽譜を正確に演奏するだけでなく、再現芸術の担い手としての意識を高めることができるでしょう。また、作品のコンセプトを理解する大きなヒントを手にすることができます。
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
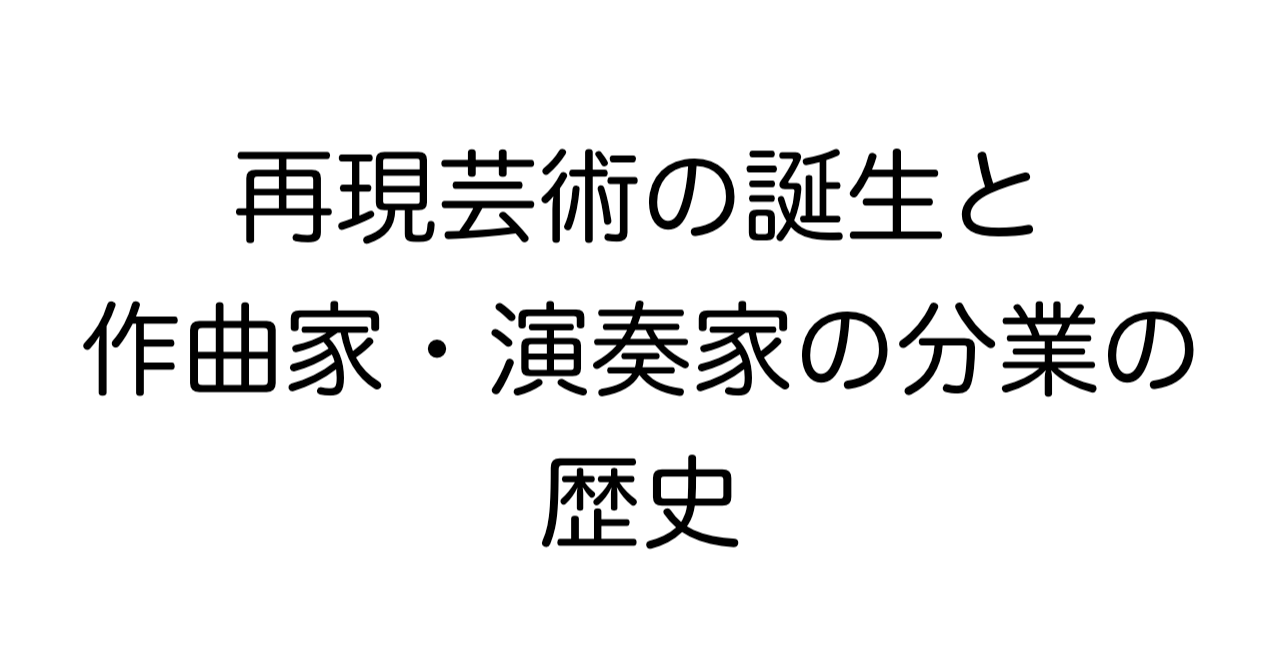

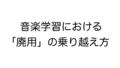
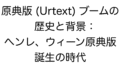
コメント