【ピアノ】1つ減らすことで、気持ちは3つくらい軽くなる
► はじめに
「今は大丈夫でも、いずれ問題になるかもしれないものを、自分の内側に残しておかないこと」
ピアノを学ぶ多くの方が、知らず知らずのうちに心の中に抱え込んでいる「重荷」があります。それは表面的には「向上心」や「努力」として現れますが、実は長期的に音楽との関係を損なう可能性を秘めているものです。
► いずれ問題になるかもしれないものを、自分の内側に残しておかない
本記事の内容は、筆者自身が「手の大きさ」のコンプレックスと向き合ってきた経験をもとにしています。
筆者は男性の中でかなり手が小さいほうで、音大生のときに友人がスクリャービンやラフマニノフなどのロシアものの作品をバリバリ弾いているのを、羨ましく思って聴いていました。
当然、一曲の中で数回くらい無理な箇所があっても、分割和音にしたり、アルペッジョにしたり、場合によっては音を省略したりすれば弾けてしまいます。しかし、そういった技巧的な箇所が頻繁に出てくる曲は、根本的に弾けるわけがありませんでした。
‣ 一見「挑戦心」だが、内在する危うさ
手の大きくない演奏者が、広い音域の同時打鍵を要求される楽曲ばかりに挑もうとすることは、一見「向上心」や「チャレンジ精神」に見えます。しかし、それが実は以下のような問題を内包している場合があります:
・自分の身体的限界を無視した自己否定
・現実の受け入れの回避
・「無理をしなければ価値がない」という思い込み
はじめに「今は大丈夫でも、いずれ問題になるかもしれないものを、自分の内側に残しておかないこと」と書きましたが、「自分の中に残しておきたくないもの」とは、具体的には次のような心理的な歪みや違和感です:
・自分の身体的な特性を受け入れられない気持ち
・無理をすることでしか価値を感じられない考え方
・本当は苦しいのに「これが上達だ」と自分をだます感覚
‣ 短期的には大丈夫でも、いずれ身体や心が壊れる
今は「音を省略しながらも何とか弾いている」かもしれません。しかし、以下のような長期的なダメージが潜んでいます。
精神面のリスク:
・常にコンプレックスを刺激されるレパートリーに心が疲弊する
・「物理的に絶対弾けない状況」「弾けない自分」への自己否定感の増大
・本来の自分に合った音楽表現の喜びを見失う
「今は問題になっていないように見えるけれど、心や身体の中に積もっている “無理” は、いずれ必ず姿を変えて現れてくる」
これが、冒頭で述べた「いずれ問題になるかもしれないもの」の正体です。
‣「受け入れ」は諦めではなく、可能性の開放と信じる
一方で、自分の体格や手のサイズに合った曲や編曲を探し、身体の自然な動きに寄り添う選択をしていくことは、「無理矢理制限を受け入れること」ではありません。むしろ、以下のような心理的な自由を広げていく道です。
心理的な解放:
・自分の身体的特徴を尊重した音楽作品への集中
・技術的な無理から解放された、純粋な音楽的喜び
・長期的に何十年後も音楽と付き合える安心感
・「無理はしていない」と大事な人に嘘をつく罪悪感からの解放
「1つ減らす」というのは、こうした無理や重荷を手放すことです。そうすることで気持ちが3つくらい軽くなり、解放感を得られるのです。
► 手の大きさに悩んでいる場合の2つの対応策
‣「選曲の自由」があるということを心の底から腑に落とす
ピアノ曲の圧倒的な数の多さを改めて実感し、選曲の自由があるということを心の底から腑に落としましょう。
特定の楽曲への「憧れ」を全否定する必要はありません。ただし、明らかに体格的にマッチしない作品については「憧れ」から「諦め(潔い見送り)」へと気持ちを切り替えましょう。そして、自分の手に馴染む膨大な楽曲群の中から、最高の作品を見つけ出して最高の演奏をすればいいのです。
自分が生まれ持っているものの中でやっていくのが一番自然ですし、楽しいし、上手くもいきます。こういったやり方は、妥協や縮小ではありません。
この方向性で最大限の挑戦をすれば、一生かかっても終わらないくらい多くの経験ができます。
‣ ピアノ編曲技術を習得して自分に対してオーダーメイドの作品を作る
自分の体格に合わせて音を編むことができるため、編曲スキルは、ピアノ学習者にとって大きなプラスになります。
ピアノを弾く方にとって、手の大きさという見た目そのものがコンプレックスなのではなく、弾ける作品が限られることがモヤモヤの原因のはずです。編曲技術を習得すれば、演奏したい楽曲を自分仕様にカスタマイズでき、この制約から完全に解放されます。
原曲がピアノ曲のクラシック作品は、楽譜を変更せずに「選曲の自由」で対応するのが原則ですが、原曲がピアノ曲ではないクラシック作品やノンクラシック分野の作品は、自分の体格に合った編曲で対応するという考え方を取り入れてみましょう。
編曲と言っても、難しいことばかりをする必要はありません。 「作曲・編曲テクニック」カテゴリーの記事を編曲学習の参考にしてください。
自分のレパートリー選びが自由自在になる未来を想像して、ワクワクしながら学習して欲しいと思います。
► 終わりに
「今は弾けるから」といって、無理をしている自分をごまかし続けることは、いずれ身体的にも、精神的にも、音楽の核心から自分を遠ざけてしまうかもしれません。だからこそ、心や身体の中にある違和感に早めに気づき、それを放置せずに丁寧に扱うことが、長く楽しく音楽と向き合う第一歩になります。
音楽的成長とは、自分という楽器を理解し、それを最大限に活かす方法を見つけることなのかもしれません。
・1つ減らすことで、気持ちは3つくらい軽くなる
・今は大丈夫でも、いずれ問題になるかもしれないものを、自分の内側に残しておかない
この2つを忘れずに音楽を続けていきましょう。本記事では「手の大きさ」をテーマにしましたが、どんなモヤモヤに対しても同様です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
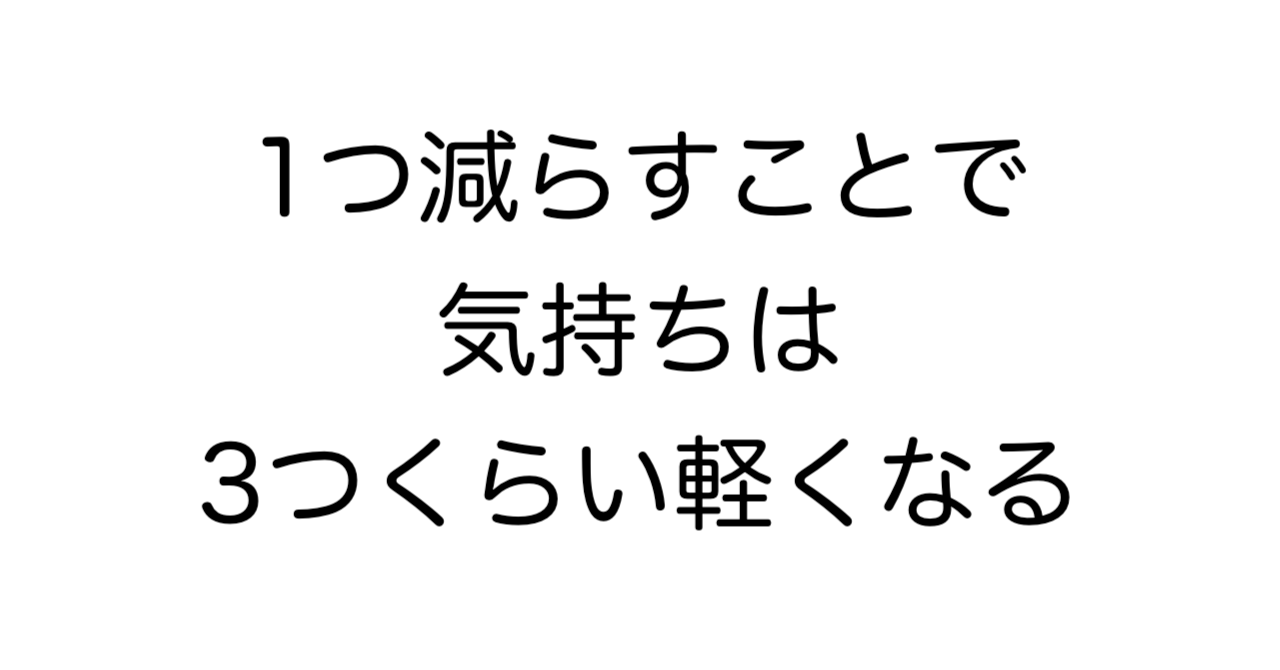
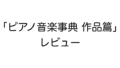
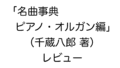
コメント