- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.16
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. 先生がレッスンで指導した内容を、家に帰ってすぐ忘れてしまう。どうすべき?
- ‣ Q2. 譜読み速度を上げるため、楽典の知識以外にできることは?
- ‣ Q3. 楽典の勉強を始めたが、レッスンで先生に相談してもいい?
- ‣ Q4. 音楽用語(例:Allegro など)の意味を、逐一先生に聞いてもいい?
- ‣ Q5. 過去のレッスンで挫折した曲に、再挑戦したいと伝えてもいい?
- ‣ Q6. 先生から「原典版(Urtext)」を勧められたが、どこまでこだわるべき?
- ‣ Q7. 先生の自宅(レッスン室)にある私物を、つい見てしまうのは失礼?
- ‣ Q8. 先生との会話で、つい自分の仕事や家庭の重い話をしてしまうのは迷惑?
- ‣ Q9. 先生からのメッセージに対し、返信が遅れるのはどこまで許容される?
- ‣ Q10. 発表会が終わった後、すぐに先生にお礼の連絡を入れるべき?
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.16
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. 先生がレッスンで指導した内容を、家に帰ってすぐ忘れてしまう。どうすべき?
結論:その場でメモを取り、帰宅前に補足する
レッスン中にメモを取ることは、決して失礼なことではありません。むしろ、学びの姿勢として好意的に受け取る指導者のほうが多いことでしょう。メモの取り方によってはレッスンを少し滞らせることになるので、事前に「メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか」と一言断りを入れておくとより丁寧です。
それでも会話の中でふいに出たアドバイスなど、書き留められなかった内容については、教室を後にしたらすぐに立ち止まって文字化しましょう。筆者はこれをずっと実践していました。
なお、録音が必要な場合は、必ず事前に許可を取ってから行いましょう。
一番良くないのは、話だけ何となく聞いていて全く書き留めず、次回以降にそれに関する話題が出たときに何も答えられないことです。「どうして大事なことなのに残そうとしないのだろう」と思うことがよくあります。
‣ Q2. 譜読み速度を上げるため、楽典の知識以外にできることは?
結論:楽式の学習が最もおすすめ
ソルフェージュや楽曲分析の学習など、様々なアプローチがありますが、中でも分析学習の一環としての楽式の学習は、効果や取り組みやすさの点から強くおすすめできます。
「楽式論 石桁真礼生 著(音楽之友社)」 では、以下の3部構成で楽曲の成り立ちについて体系的に学べます:
・第1編:楽節 – 音楽の諸形式を生み出すもととなるもの
・第2編:基礎楽式 – 音楽の骨格を学ぶ
・第3編:応用楽式 – 様々な楽曲形式を知る
構成を見抜けるようになることは、譜読みの速度アップに有効なだけでなく、読譜の正確性や音楽理解の深さまで向上させてくれます。
推奨記事:【ピアノ】名著「楽式論」がピアノ学習者に必須な理由:70年を超える影響力
‣ Q3. 楽典の勉強を始めたが、レッスンで先生に相談してもいい?
結論:内容と量による
楽典の勉強はピアノ学習に直結する内容が多いため、簡単な質問であればレッスンの中で答えてもらえることでしょう。しかし、以下のような場合は別枠での対応を検討すべきです:
・「楽典―理論と実習 / 音楽之友社」で扱われる純正律や調判定など、やや離れる内容
・大量の質問がある場合
・体系的に教わりたい場合
推奨される対応:
・楽典も別枠で教えている先生であれば、別料金で一コマ予約する
・教えていなければ、ピアノのレッスン枠を一枠使う(事前相談必須)
「ついでにお願いします」という姿勢は、レッスンの本来の目的を損なうだけでなく、先生への配慮に欠けると受け取られる可能性があります。
‣ Q4. 音楽用語(例:Allegro など)の意味を、逐一先生に聞いてもいい?
結論:基本的な用語は自分で調べてからレッスンへ
初めの数回は親切に教えてもらえるかもしれませんが、調べれば分かる基本的な用語を毎回質問していると、学習姿勢そのものに疑問を持たれてしまいます。
音楽に限らず、明らかに調べれば分かることを調べずに人に聞くのは避けるべきです。むしろ、「○○という意味だと理解していますが、この曲の文脈ではどう解釈すべきでしょうか」といった一歩踏み込んだ質問のほうが、学習意欲に受け取られますし、実際に身にもなります。
ただし、以下は質問してOK:
・楽語の具体的な解釈の仕方(どの程度のテンポが適切か、など)
・時代や作曲家による表現の違い
・複数の解釈がある場合の判断基準
‣ Q5. 過去のレッスンで挫折した曲に、再挑戦したいと伝えてもいい?
結論:構わないが、ある程度準備してから相談すべき
以前挫折した原因は様々でしょうが、レベルアップした今では、独学で学べる範囲も増えているはずです。まずは自分でコツコツと練習を進めておき、ある程度先生を説得できる状態にしておきましょう。
筆者は、初めてショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58」をやりたいと当時の先生へ伝えたとき、「こういう曲は、しばらく内緒で練習してから持ってきなさい」と笑いながら言われた記憶があります。
再挑戦の場合も同様で、「自分一人でもここまでできる」というのを示せるくらいに準備を進めてから相談しましょう。目安としては、最低でも以下の段階まで:
・全曲を一通り弾き通せる
・指導を受けないと克服できそうにない技術的な難所をきちんと把握している
・前回との違いや成長点を説明できる
‣ Q6. 先生から「原典版(Urtext)」を勧められたが、どこまでこだわるべき?
結論:勧められた作品であれば、導入して損はない
基本的な考え方として、原典版での学習に損はありません。ただし、原典版は運指やペダリングなどの情報が限られており、初心者が独学で進めるには適していません。特に日本語の解説がない外国版は、理解するのに追加の労力が必要です。
先生が勧めてきた段階であれば、多少値は張りますが、取り入れてみて構いません。一般的には、原典版が必要でないケースは以下のように考えましょう:
初級〜中級前半の学習者
この段階では、日本語の解説や豊富な追加情報のある実用版や解釈版のほうが学習効率が高い
試しに弾いてみる程度の作品
本格的に取り組む予定のない作品に対して、その都度高価な原典版を購入する必要はない
指練習的な要素が濃厚な教則本や練習曲集
このような教材は一生のレパートリーになりにくいため、原典版にこだわる必要性は低い
推奨記事:【ピアノ】原典版(Urtext)の活用ガイド:いつ・なぜ・どう使うべきか
‣ Q7. 先生の自宅(レッスン室)にある私物を、つい見てしまうのは失礼?
結論:見るのは失礼には当たらないが、話題にするのは控えめに
レッスンを受けるにあたって通る場所——玄関やレッスン室、その移動通路などに置かれているものは、見られている前提で置かれているため、見ること自体は失礼には当たりません。ただし、それらは「景色として目に入る」程度に留めておき、あまり細かく言及しないほうが賢明です。先生の私物や生活空間に関する話題は、親しい関係であっても踏み込み過ぎない配慮が必要です。
もちろん、掃除が行き届いていない場合や、廊下に一時的に置かれているものなどについては、見ていないふりをする配慮も大切です。
適度な距離感の例:
・目に入った楽譜や本について、さりげなく「○○をお持ちなんですね」程度
・インテリアや飾られているものなどには、基本的に触れない
・特に、よりプライベートに関わるものについては、深い関係性ができるまでは言及しない
‣ Q8. 先生との会話で、つい自分の仕事や家庭の重い話をしてしまうのは迷惑?
結論:関係性と話し方による
レッスン前後の適度な雑談は、良い関係を築くうえで大切な時間です。ただし、以下の点に注意しましょう:
確認すべき2つのポイント:
・レッスンという双方向のコミュニケーションの場で、自分だけが一方的に話していないか
・話の内容が、一方的な愚痴や重過ぎる相談になっていないか
自分の話ばかりしてしまうのは問題がありますし、会話の内容が一方的な愚痴ばかりだと、「この方は他所でも私の教室のことをこのように話すのでは」と疑念を持たれても無理はありません。
また、先生とどれくらいの関係性ができているかも重要な視点です。筆者の経験として、まだあまり関係性ができていない時期(出会って数ヶ月)に重い話を相談したところ、それ以降すごく気を遣われてしまい、かえってやりにくくなった経験があります。
バランスの良い会話:
・相手の話も聞く双方向のやりとり
・深刻過ぎない、日常的な話題が中心
・時間を見て適度に切り上げる配慮
‣ Q9. 先生からのメッセージに対し、返信が遅れるのはどこまで許容される?
結論:「どこまで許容されるか」ではなく、返せるときにすぐ返すべき
一般的なビジネスマナーでは24時間以内の返信が推奨されています。実際、24時間を超えてしまうと「相手を重視していない」という印象を与えかねません。
基本的な対応:
・返信できる時点ですぐに返す
・すぐに答えが出せない場合でも、「メール拝受しました。後ほど改めて返信いたします」と一報を入れる
・日程調整などの連絡は特に迅速に(相手の予定調整に影響するため)
避けるべき考え方
「向こうの返事が遅かったから、同じくらい間隔を空けて返信しよう」といった駆け引きは不要です。「相手がどうであれ、自分は見たら返す」というシンプルなルールで十分です。
基本的にレッスン間でのやりとりは限定的なはずですから、要件を早めに済ませることを心がけましょう。
‣ Q10. 発表会が終わった後、すぐに先生にお礼の連絡を入れるべき?
結論:できるだけ早く連絡すべき
発表会のためにレッスン時間を特別に取ってもらっていなくても、お礼の連絡は重要です。先生が発表会のために費やしている労力は、生徒が想像する以上に多岐にわたるからです。
お礼を伝える2つの大きな意図:
1. 本番という「場」を準備していただいたことへの感謝
先生は「主催者」として、多くの準備をされています。基本的な内容だけでも、以下の通りです:
・会場の手配、時間帯の確保
・プログラム作成、出演者情報の確認
・当日の運営・進行管理
・関係者(調律師、照明、音響スタッフなど)との調整
2. 本番までの指導と当日のサポートへの感謝
発表会前のレッスンでは、時間の長さは変わらなくても、通常とは違った集中が必要です:
・生徒のレベルに合った曲の提案と、発表会で成功するための具体的なアドバイス
・本番に向けた仕上げの指導
・本番前の声かけ、緊張のケアなど、生徒が力を発揮できるような当日サポート
連絡のタイミング:
・理想:発表会当日の夜
・遅くとも翌日
本番が終わっても後処理が多く残っていたり、他の生徒の連絡にも対応しています。連絡が返ってこなくてもそこに無駄な気を持って行かれないようにしましょう。また、メールで演奏に対する感想を求めるのは避け、内容の反省などは次回のレッスンで行いましょう。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
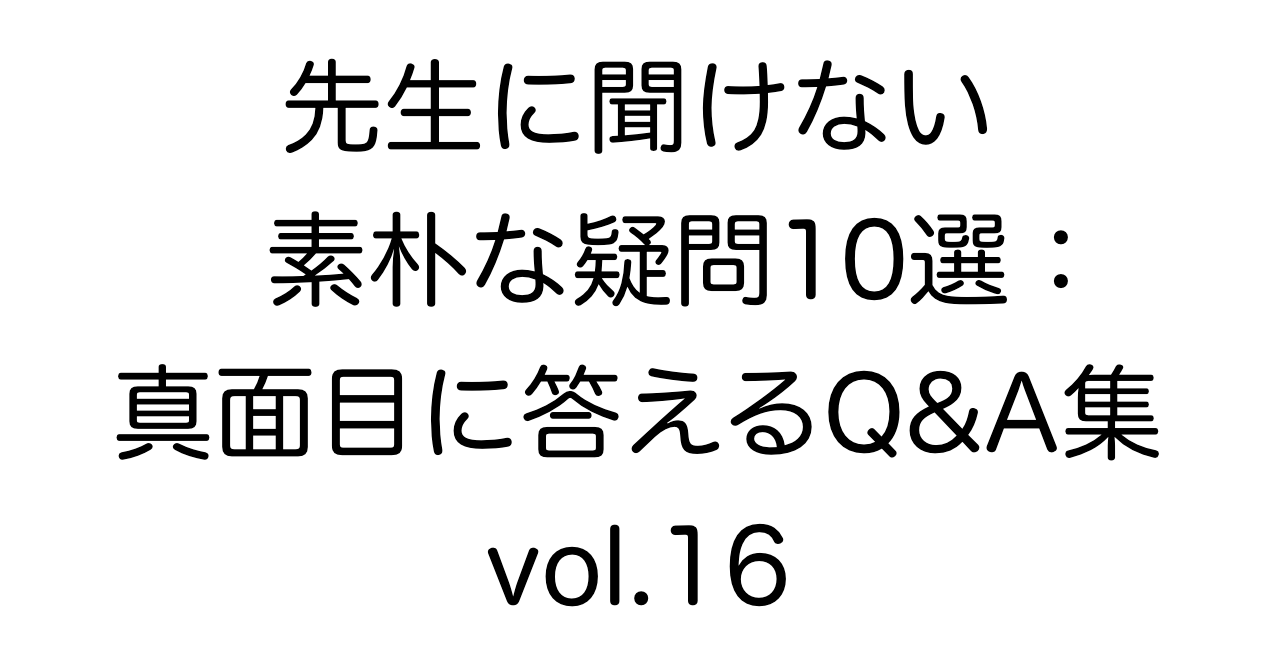
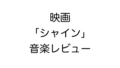
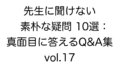
コメント