【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. 黒鍵と革命、結局どっちが難しい?
結論:一般的には「革命」だが、適性による差が大きい
この質問は、ショパンのエチュードにまだ到達していないけれど、先生に内緒で練習したいという方に多いものです。
一般的には「革命のほうが難しい」と言われることが多い印象です。ただし、速く動かすという意味だけで言うと、黒鍵は右手、革命は左手に課題があるので、どちらが弾きやすいかは人によるとしか言いようがありません。
踏まえておくべきなのは、「黒鍵も革命も、最後の1ページが最も技術的に難しい」という事実です。どちらを選んでも、後半をきちんと弾けるようにすることが課題となります。
演奏会でどちらかを選ぶ必要があるなら、楽曲として好きなほうを選んで構いません。難易度に大差はないので、モチベーションが維持できる曲を選ぶことが成功への近道です。
‣ Q2. デジタル vs 振り子メトロノーム、どっちを買うべき?
結論:実用性重視ならデジタル
単純にピアノ練習で活用するという意味では、以下の点でデジタルメトロノームをおすすめします:
デジタルメトロノームのメリット
・ネジ巻き不要で練習に集中できる
・音量調整が簡単
・テンポを1単位で細かく変更できる
・製品によってはイヤフォンでも練習できる
・コンパクトで場所を取らない
・水平な場所でなくても使える
もちろん、無料アプリ(Pro Metronome など)も便利ですが、すぐに取り出してサッと使える実機の利便性は格別です。
推奨製品: SEIKO セイコー デジタルメトロノーム 薄型 ブラック DM71B
おすすめポイント:
・超コンパクト設計(8.6×5.4×1.2cm)
・最小限の機能で迷わない
・前世代の製品から数十年の使用実績がある定番商品
メトロノームとしての最小限の機能とコンパクトさを望む方には迷わずおすすめできる実機です。
・SEIKO セイコー デジタルメトロノーム 薄型 ブラック DM71B
振り子メトロノームが向いているケース
以下のような学習者には振り子メトロノームも有用です:
・ソルフェージュのリズム打ち学習(視覚的に打点を予測できる)
・「練習している実感」を味わいたい
・アナログの質感や温かみが好き
・インテリアとしても楽しみたい
‣ Q3. 毎日弾けないとき、週1回3時間 vs 週3回1時間?
結論:週3回1時間(分散学習が効果的)
分散させることをおすすめする理由:
1. 身体的な負担が少ない
一度に3時間弾くと、手や腕への負担が大きく、腱鞘炎などのリスクも高まります。
2. 習慣化しやすい
決まった曜日に練習することで、ピアノが日常に組み込まれます。習慣は継続の鍵です。
3. 記憶の定着が良い
認知心理学の「分散効果」により、短時間の学習を複数回に分けたほうが、長時間の一回集中よりも記憶に定着しやすいことが知られています。
習慣づけのコツ
適当に週3回練習するのではなく、曜日を固定することが重要です。例えば「月・水・金の20時から」と決めてしまうことで、ピアノのためのスペシャルな時間があらかじめ確保されます。
やむを得ず週1回3時間になる場合
その3時間を複数の短いセッション(30分×6回)に分け、休憩を挟みましょう。集中力も維持でき、身体への負担も軽減されます。
‣ Q4. 発表会の選曲、先生の提案と自分の希望が違うときの対処法
結論:一旦先生の提案を受け入れた後に、意見を出す
この問題は本当に悩ましいことでしょう。しかし、まずは先生の提案に乗っておくのが賢明です。
先生の提案を優先すべき理由:
1. 先生は生徒を客観視している
先生は生徒の状態を見抜いている可能性が高いでしょう。反対意見を投げる前に、まずは、なぜ先生がその選曲を提案するのかを考え、場合によっては聞き出す必要があります。
2. プログラム全体のバランスを考慮している
例えば、同じ楽曲で複数人が演奏してしまうと、生徒に余計なプレッシャーを与えてしまう可能性があります。こういったことを先生が考えて、先に決定した生徒の選曲を優先している可能性もゼロではありません。
別の方向を提案したいときのコツ
・一旦相手の意見に乗っかっておく
・そして、同調する意思があると示したうえで、次回以降少しづつ提案していく
同調するフリをしてすぐに反論するのではなく、「今回の選曲では何も反論しない」ということです。そして、次回以降に柔らかく提案していきます。
組織で新しい提案をするときと同じ考え方です。真っ向から反対意見を述べるのではなく、一旦相手を受け入れて、最低限の信頼を得ておきましょう。そのうえで、その環境の中に居ながら少しづつ言いたいことを提案するのです。
理想的なストーリー
「今回は先生の提案に乗る → 成功させる → 演奏力が向上する → 次回、念願の曲に挑戦 → より良い演奏ができる」
次回また意見がズレたら、「前回は先生のご提案を演奏しましたので、今回は私の弾きたい曲を…」と主張する材料にもなります。
例外:価値観の違いが大きい場合
「クラシックを提案されたけど、どうしてもポップスが弾きたい」など、根本的な価値観の違いなら、正直に相談しましょう。良い先生なら、妥協案を見つけてくれるはずです。
‣ Q5. YouTubeに演奏アップ、先生に報告すべき?
結論:報告したうえで、あまり周りの目を気にせずに発信を続ける
報告するメリット:
・先生自身も発信している場合、撮影環境や見せ方についてアドバイスがもらえる可能性
・コラボレーションや拡散の機会が生まれる可能性
・「先生に見られている」という適度な緊張感
報告するデメリット:
・完璧主義の先生だと、公開に否定的なことも
・指導方針と違う曲をアップする際に気を遣う
・逆に過度なプレッシャーを感じることも
推奨方法
報告したうえで、あまり周りの目を気にせず発信を続けることをおすすめします。
もし先生から否定的な意見があっても、自分の学びのスタイルは自分で決めて良いのです。ただし、先生の指導そのものや、レッスン内容を無断で公開するのは避けましょう。
‣ Q6. 自分の演奏、録音して聞くとヘタ過ぎて凹む問題をどうするか?
結論:譜読みの早い段階で録音を習慣化し、現実を受け入れる
自分の演奏を客観的に聴けるようになっていない限り、初めて録音したときは大抵ショックを受けます。それなら、練習の早い段階で録音を経験しておくほうがいいでしょう。
落ち込むのは、もうかなり弾けるようになっていると思ってから録音するからです。日頃の練習に組み込んで譜読みから録音してしまうくらいの勢いで構いません。まだ上手に弾けていないということを理解したうえで、改善点を見つけて練習すればいいのです。
‣ Q7. 家で弾けたのに、レッスンでミス連発…凹む問題をどうするか?
結論:家の状態をデフォルトだと思わないこと
多くの人が陥る誤解があります。それは、自宅での演奏が自分の実力だと思い込むことです。
自宅での演奏環境:
・自宅のリラックスした空間
・聴いている人がいない空間
・いつも慣れているピアノでの演奏
・何度でも弾き直せる安心感
レッスン・本番での環境:
・自宅ではない緊張感のある空間
・誰かに聴かれている空間
・週1回程度しか触らない慣れないピアノ
・一発勝負のプレッシャー
考えてみてください。発表会や演奏会は、すべて後者の条件で行われます。つまり、レッスンでの演奏こそが、より本番に近い状態なのです。
対策
自宅でも本番を想定した練習を取り入れる:
・通し練習(弾き直し禁止)
・録音・録画
・家族や友人に同じ部屋で読書していてもらう
レッスンを「実力確認の場」として捉え直す:
・ミスを恐れず、今の実力を正直に見せる
・ほとんどの先生はミスを責めるのではなく、改善点を見つけるために聴いている
‣ Q8. 先生に差し入れ、何を選ぶ?
結論:荷物にならず、消える日持ちするお菓子
ファーストレッスンやファイナルレッスン、スポットレッスンなどで差し入れを考える場合の対処法です。
前提として
余程のスペシャルなタイミングでない限り、手土産は不要です。習慣化すると、お互いに負担になることもあります。
おすすめ:お菓子・スイーツ(消えもの)
選ぶ理由:
・荷物にならない
・日持ちする
・先生の家族も喜ぶ
・甘いものは「気持ち」を伝えやすい
選び方のコツ:
・常温保存可(生菓子は避ける)
・個包装(シェアしやすく、保存もきく)
・有名店やブランド(安心感がある)
・賞味期限が最低1ヶ月以上
・予算:1,200〜3,000円程度
例:
・ヨックモックのシガール(定番中の定番)
・ゴディバのクッキーアソート
・帝国ホテルの焼き菓子
・地元の有名店の銘菓
筆者は、「困ったらシガール」と決めています。嫌いな人をほとんど見たことがないからです。
避けるべきもの:
・生ケーキ・生菓子(当日中に食べる必要がある)
・香りの強いもの(キャンドル、入浴剤など)
・消えないもの(雑貨、食器など)
・場所をとるもの、重いもの(ワインなど)
・趣味が分かれるもの
大切なこと
先生は「金額」より「気持ち」を見ています。高価である必要はありません。「ありがとうございます」「気にかけています」「大切に思っています」という感謝の気持ちが伝わることが何より大切です。
また、先生が他の生徒に一部シェアしたと後日知っても、決して腹を立てないようにしましょう。それも差し入れの役割です。
‣ Q9. ワンレッスン制の相場はどれくらい?
結論:5,000〜10,000円(60分)が一般的
・「月謝制じゃなくて、都度払いで習いたい」
・「でも、相場が分からない…」
という悩み、実は多いのです。
一般的な相場(60分レッスン)
標準的な相場:5,000〜10,000円
ただし以下の要因で変動します:
・先生の経歴・実績:音大教員、音専教員、演奏活動が活発なアーティストの場合は10,000円以上も
・地域:都市部は高め、地方は比較的安めの傾向
・レッスン内容:通常レッスンか、専門的な指導か
筆者自身、ワンレッスン30,000円という先生に習っていた時期もあります(音楽家としての活動実績が豊富な方でした)。
月謝制とワンレッスン制の違い
月謝制・サブスク制(月3〜4回):
・メリット:1回あたりが割安、定期的に通える、先生との関係が深まる
・デメリット:休むと損、スケジュール固定、退会を伝える心理的ハードルが高い
ワンレッスン制(都度払い):
・メリット:自分のペースで通える、休んでも損しない、気軽に始められる
・デメリット:1回あたりが割高、継続意思が必要、予約が取りにくい場合も
注意点:
1. スタジオ代が別の場合がある
「レッスン料8,000円+スタジオ代1,500円」などといったパターン。事前確認が必須です。
2. キャンセルポリシー
「前日キャンセル:50%」「当日キャンセル:100%」など、先生によって異なります。最初に確認しましょう。
3. 月謝制より「割高」は当然
フレキシブルさへの対価です。また、演奏活動などで多忙な先生はワンレッスン制のみの場合が多く、相場も高めです。
ワンレッスン制度のおすすめの使い方:
・月謝制で別の先生に習いながら、ワンレッスンで専門的な指導を受ける(普段の先生への許可取り必須)
・発表会前の集中レッスンとして活用
・独学の補完として利用
推奨記事:【ピアノ】ピアノレッスン代の上手な渡し方:失礼にならず、自然に
‣ Q10. 楽曲分析(アナリーゼ)、演奏に活きてる実感ない問題
結論:長期的視点で捉え、理解の深まりを楽しむ
楽曲分析により以下のような恩恵が得られます:
1. 音楽的理解によるテクニック面の改善
2. 練習効率の向上
3. 音楽的表現の幅の拡大
詳しくは、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
【ピアノ】楽曲分析学習との向き合い方:演奏力向上への長期的視点
ただし注意点
分析で得た知識は、必ずしもすべてが演奏のための直接的な指示というわけではありません。「楽曲理解を深めるための手段」としても捉えましょう:
・見つけた特徴を自身の解釈に取り入れる過程を楽しむ
・同じ作曲家の他の作品でも同様の分析を試みる
・作曲家特有の手法を探求する楽しみを見つける
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
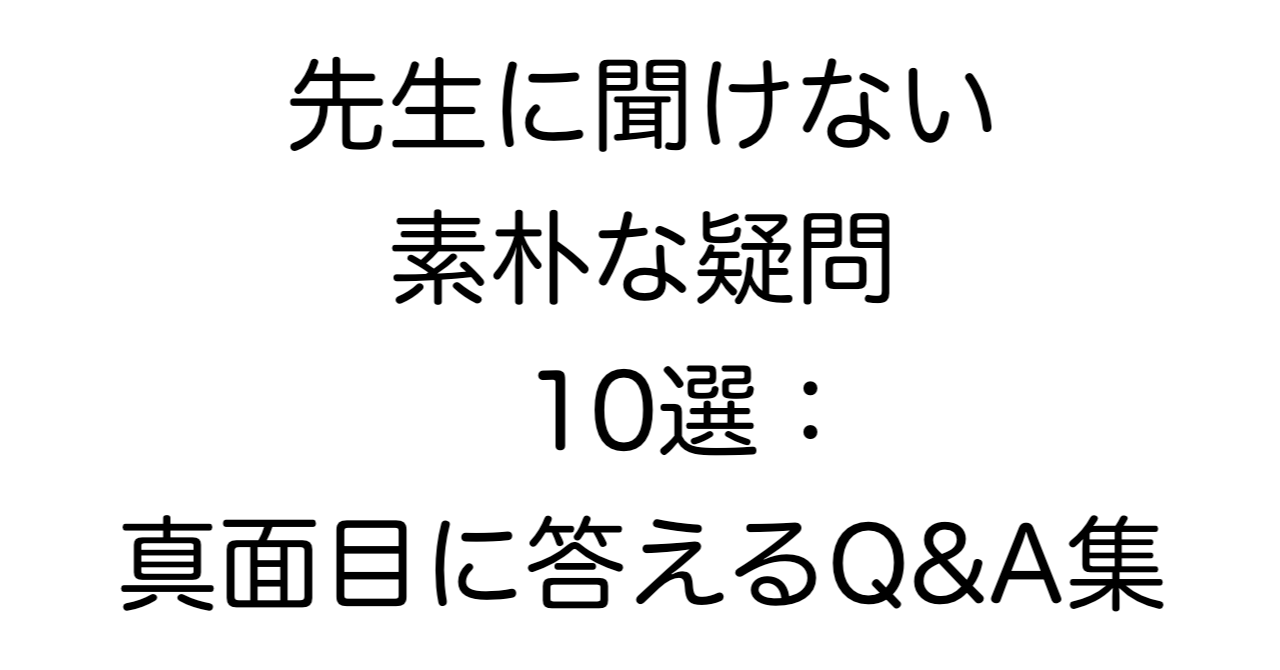

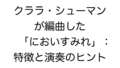
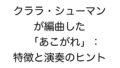
コメント