【ピアノ】マルグリット・ロン三部作 完全ガイド:ドビュッシー・フォーレ・ラヴェル
► はじめに
20世紀を代表するピアニスト、マルグリット・ロン(1874-1966)が遺した音楽界への貴重な証言録。ロン=ティボー国際コンクールの設立者として知られる彼女が、ドビュッシー、フォーレ、ラヴェルという3人の巨匠と直接交流した体験をもとに綴った三部作は、20世紀フランス音楽を理解するうえで欠かせない一次資料です。
これらの書籍を通読することで、単に個々の作曲家についての知識を得るだけでなく、20世紀フランス音楽の全体像と、ロンの音楽観の変遷を理解することができます。それぞれの作曲家との関係性や時代背景の違いが、ロンの視点の変化として反映されており、音楽史的に極めて価値の高い記録となっています。
► 三部作
‣ 第1巻:ドビュッシーとピアノ曲
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:1969年
・ページ数:新版 144ページ 旧版 166ページ
・対象レベル:中級~上級者
· 本書の特徴と価値
三部作の第1巻となる本書は、ドビュッシーとの深い師弟関係から生まれた貴重な証言録です。作曲家本人から直接、徹底的な指導を受けた演奏家による回想録という点で、音楽史的価値は計り知れないものがあります。
ドビュッシーがロンに託した言葉「私がこの世にいなくなったときに、わたしの思っていたことを正しく知っている者がのこることになるのだからね」からも、彼が自らの音楽の正しい伝承者としてロンを信頼していたことが分かります。
· 内容のポイント
直接伝授された演奏法の記録
ドビュッシー自身が教えた演奏技法や解釈が詳細に記されている
作曲の背景や意図の解明
各作品が生まれた状況や、作曲家の意図が明らかにされている
ドビュッシーの人間像
私生活や性格、人間関係まで含めた全人格的な記録
印象派という誤解の訂正
ドビュッシー自身が「自分は印象派ではない」と断言していたことなど、一般的な誤解を正す記述
特にドビュッシーの身体的特徴についての言及や、「喜びの島」における作曲家がすすめた極端に左手の指の間を開く運指法(譜例付き)は、演奏解釈に直結する貴重な情報です。
・新版 ドビュッシーとピアノ曲―天才が名演奏家に直接託した技法と「こころ」の希有な記録 著: マルグリット・ロン 訳:室淳介 / 音楽之友社
‣ 第2巻:回想のフォーレ―ピアノ曲をめぐって
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:2002年
・ページ数:188ページ
・対象レベル:中級~上級者
· フォーレとの関係や作曲家の真意
フォーレとロンの関係は、ドビュッシーとのそれとは異なる印象を感じ取れます。
フォーレが日常的に口にしていた「ニュアンスをこめて。でも動きは変えないで。」という言葉や、「僕たちにとって、バス声部は重要だ。」という発言は、楽譜からは読み取れない作曲家の真意を伝えています。
· 構成と内容
本書は全11章で構成され、大きく3つの部分に分けられます:
第1部(第1章~第7章):人物像と交流の記録
フォーレとの出会いから関係の深まり、そして彼を取り巻く音楽界の人々との関係まで、まさに「回想」の名にふさわしい体験が語られます。
第2部(第8章):演奏家としての視座
ロンが自身のピアニストとしての意見を展開。練習方法、メトロノームについての考え、演奏時の心理状態など、興味深い内容が含まれています。
第3部(第9章~第11章):作品論や音楽観、まとめ
フォーレの具体的な作品について、舟歌、夜想曲、ヴァルス・カプリス、即興曲、バラード、ドリー、主題と変奏、前奏曲集、そして室内楽曲まで、ロンの深い洞察が語られます。
· 本書の魅力
「フォーレは短くて息をのむような『クレッシェンド』や『ディミヌエンド』を好んでいました。」などの具体的な音楽観についての記述は、フォーレの音楽を理解するうえで非常に有用です。また、「フォーレの逆説的な性格に、私はよくひっかかりました。彼は極端に伝統を尊重するかと思えば、自分自身の作曲に関しては、頑固ではないといった態度を示すのです。」という記述からは、創作者としてのフォーレの複雑な内面が垣間見えます。
・回想のフォーレ―ピアノ曲をめぐって 著:マルグリット・ロン 訳:遠山菜穂美 / 音楽之友社
‣ 第3巻:ラヴェル―回想のピアノ
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:1985年
・ページ数:194ページ
・対象レベル:中級~上級者
· 当事者だけが知る生の証言
三部作の最後を飾る本書は、ロンがラヴェルと過ごした時間の中で実際に見聞きした体験情報が豊富に提供されています。作曲家の人間性と音楽観を間近で観察した演奏家の証言として、音楽史上貴重な記録となっています。
· 印象的なエピソード
「左手のためのピアノ協奏曲」の初演者ヴィットゲンシュタインとラヴェルが激しく対立したエピソードなど、このような場面に居合わせたロンだからこそ語れる生々しい証言は、ラヴェルの音楽に対する真摯な姿勢と、同時に人間としての繊細さを浮き彫りにしています。
· 作曲家と演奏家の関係性
本書が提起する重要なテーマの一つが、作曲家と演奏家の関係性です。ラヴェルの有名な言葉「私は、私の曲を自分なりに解釈してほしいとは思わない。ただ演奏してほしいと思うだけである」を軸に、具体的なエピソードを通して両者の緊張関係が描かれています。
· 個別楽曲への実践的アプローチ
「水の戯れ」「ソナチネ」「鏡」「夜のガスパール」「クープランの墓」といった代表作について、作曲家本人から直接聞いた話と、ロン自身の演奏経験を織り交ぜた解説は、実際に演奏に取り組む方にとって実用的な価値を持ちます。
・ラヴェル―回想のピアノ 著:マルグリット・ロン 訳:北原道彦、藤村久美子 / 音楽之友社
► 三部作を通して見える20世紀フランス音楽の全体像
時代の変遷と音楽観の発展
ドビュッシー(1862-1918)、フォーレ(1845-1924)、ラヴェル(1875-1937)という3人の作曲家は、それぞれ異なる世代に属しながらも、20世紀フランス音楽の黄金時代を築いた巨匠たちです。ロンの証言を通して、これらの作曲家たちの音楽観の相違点と共通点を理解することができます。
ロンの音楽観の変遷
三部作を通読することで、ロン自身の音楽観の変遷も追うことができます。ドビュッシーとの交流、フォーレとの交流、そしてラヴェルとの知的な対話は、それぞれ異なる音楽的体験を彼女に与えました。
演奏解釈への示唆
3人の作曲家それぞれが持つ演奏に対する考え方の違いは、現代の演奏者にとっても重要なヒントになります。特にラヴェルの客観的な完成度への拘りははっきりと描かれていますが、それぞれの美学を理解することで、より深い演奏解釈が可能になります。
► 活用のヒント
関連書籍との併読
ラヴェルについては、同じく直接師事したヴラド・ペルルミュテールによる「ラヴェルのピアノ曲」との併読をおすすめします。両書は補完的な関係にあり、ロンの回想録的な視点とペルルミュテールのより技術的な解説が相互にヒントを与えてくれます。
書籍「ラヴェルのピアノ曲」については以下の記事でレビューしているので、あわせて参考にしてください。
【ピアノ】ラヴェルの弟子が語る「ラヴェルのピアノ曲」:演奏解釈の決定版
実践的な使い方:
・まず三部作を通読して、20世紀フランス音楽のキーパーソンやロンの考え方を把握する
・各作曲家の作品を演奏したり分析する際に、該当部分を参照する
・音楽史的な背景を理解するための一次資料として活用する
► 留意点
これらの書籍は回想録という性格上、客観的な音楽分析書ではありません。ロンの主観的な視点に基づいた記述が中心となっているため、学術的な研究においては他の資料との照合が必要となります。しかし、それゆえに持つ人間的な温かみと生々しさこそが、これらの書籍の魅力でもあります。
► 終わりに
マルグリット・ロンの三部作は、20世紀フランス音楽の黄金時代を生きた証言者による貴重な記録です。ドビュッシー、フォーレ、ラヴェルの音楽を深く理解したい方にとって、これらの書籍は必読と言えるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
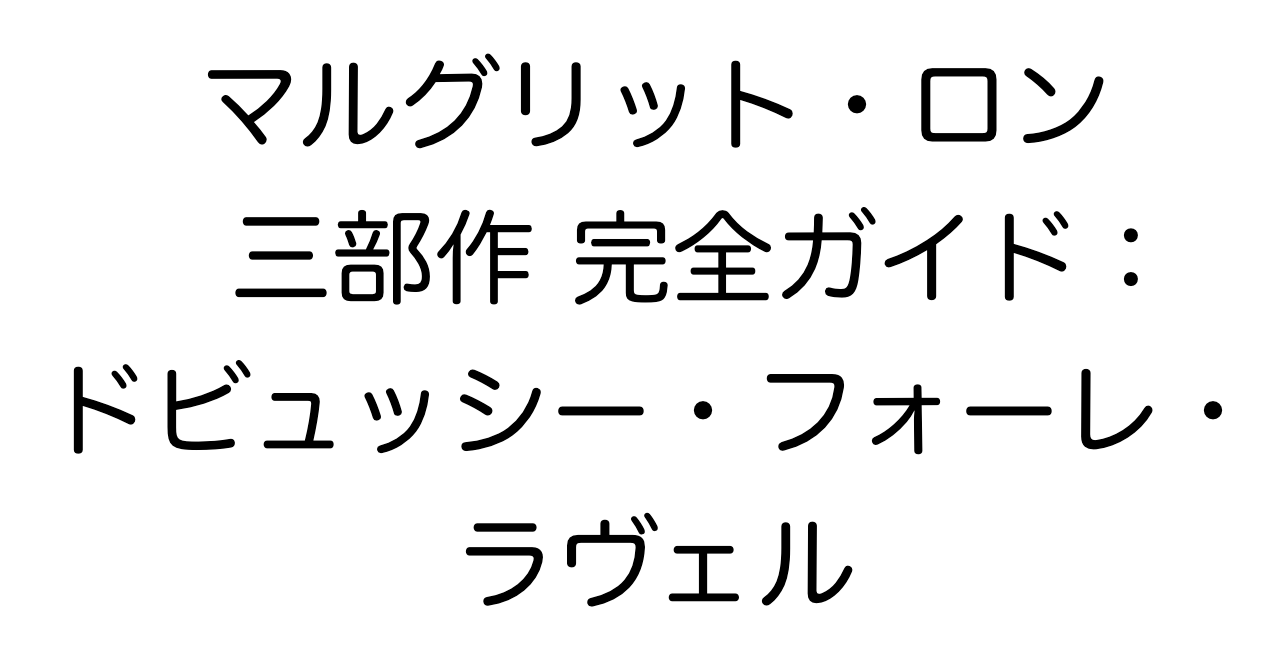



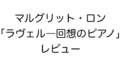
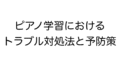
コメント