【ピアノ】映画「哀愁のトロイメライ」レビュー:ピアノで読み解くクララ・シューマン物語
► はじめに
映画「哀愁のトロイメライ(Frühlingssinfonie)」は、19世紀ロマン派音楽界の巨匠たち―クララ・ヴィーク(後のクララ・シューマン)とロベルト・シューマンの結婚までを描いた作品です。
本記事では、ピアノ的視点から、この映画の魅力と特に注目すべき楽曲の使われ方について詳しく解説します。
・公開年:1983年(ドイツ)/ 1985年(日本)
・監督:ペーター・シャモニ
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
用語解説:状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
一方、外的に付けられた通常のBGMは「状況外音楽」となります。
‣ 本作が同系統の映画2作と異なる部分
クララが描かれた映画でよく知られているものは以下の3作です:
愛の調べ(Song of Love)
・公開年:1947年(アメリカ)/ 1949年(日本)
・監督:クラレンス・ブラウン
哀愁のトロイメライ(Frühlingssinfonie)
・公開年:1983年(ドイツ)/ 1985年(日本)
・監督:ペーター・シャモニ
クララ・シューマン 愛の協奏曲(Geliebte Clara)
・公開年:2008年(ドイツ)/ 2009年(日本)
・監督:ヘルマ・サンダース=ブラームス
本記事で取り上げる「哀愁のトロイメライ」が他の2作と大きく異なる部分を紹介します。
ロベルトとクララが結婚するまでが描かれている
本作では、青年ロベルトが11歳のクララと出会うところから始まり、クララとロベルトが結婚するまでが描かれており、その後の生活はラストの5分のみです。他の2作では、結婚後の生活におけるクララとロベルトとブラームスの関係などが主に描かれています。
主要登場人物以外の作品がいくつか使われている
本作では、クララがショパンのエチュードを練習していたり、脇役のメンデルスゾーンの音楽が使われたりと、主要登場人物以外が作曲した音楽も使われています。他の2作では、クララとロベルトとブラームスの音楽で演出されています。
ピアノアンサンブルの場面の多さ
他の2作では、ピアノ協奏曲でオーケストラとクララがアンサンブルする場面を除き、多くがピアノソロの状況内音楽です。一方本作では、クララが父親に連れられて様々なところで演奏活動する子供時代が中心に描かれているため、あらゆる編成での室内楽演奏をする場面も多く含まれています。
作曲過程の説明
本作では、ピアノ曲やオーケストラ曲についてロベルトが他者にその作りを説明する音楽的な場面が数箇所含まれています。例えば本編32分頃には、「謝肉祭 Op.9 より 10. A.S.C.H.-S.C.H.A 踊る文字」でどうやってそれぞれの音を選んでいるのかを楽しそうに話す様子が描かれています。
‣ ロベルトとクララの演奏技術の逆転
本編11分頃、クララが作曲した「4つのポロネーズ より 第1番 Op.1-1」を、まずロベルトが弾き、直後にクララが弾きます。すでにクララは才能があるという設定でしたが、このときには明らかにロベルトのほうが上手に聴こえるように演奏されています。
一方、本編57分頃、ロベルトが作曲した「交響的練習曲 Op.13 より Etüde XII」をまずロベルトが弾き、直後にクララが弾きます。このときには明らかにクララのほうが上手に聴こえるように演奏されています。
「クララがピアニストとして成長して演奏技術が逆転したことを、その演奏内容で対照的に表現している」と考えていいでしょう。
時代考証:
・映画の設定上、この時点でクララは最低でも16歳を超えている
・「交響的練習曲 Op.13」の作曲は、1834-1837年
・ロベルトと結婚したのは、1819年生まれのクララが20歳のとき
したがって、クララがおおよそ10代後半頃のことになります。
‣ その他の印象的な音楽演出
気持ちの焦りを表現した状況内音楽
本編前半部分で、ロベルトが指に錘をつけて練習したり手を痛めてしまっている様子が描かれています。ここでロベルトが練習しているのは、自身が作曲した「トッカータ ハ長調 Op.7」や「謝肉祭 Op.9 より 9.パピヨン」などの速くて技巧的な作品。これは、ロベルトの技術傾向の気持ちとその焦りを表現しているかのようです。
「トロイメライ」の使用によるロベルトの作曲方針の柔軟さ
「哀愁のトロイメライ」という映画タイトルですが、「トロイメライ」は本編76分頃に一度使用されるのみです。それをロベルトの演奏で聴いたクララは「出版社や一般の方に喜ばれるわ」と言います。これまでの場面で、ロベルトは「この難解な作品では楽譜が売れない」と出版社から突き返されてそれに反発している場面も描かれていることから、ロベルトの作曲方針の柔軟さに変化が見れるシーンとなっています。
カットアウトによる現実への引き戻し
本編78分頃、ロベルトとクララの結婚に大反対しているクララの父親の目を盗んで、2人が情熱的なキスをします。このときにはロベルトの「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 第1楽章」が情熱的に流れます。しかしその直後、この音楽がバッサリとカットアウトされ、クララと父親の場面へ。急激にカットアウトすることで、2つの場面の時間軸が異なることと、束縛してくる父親がいる現実に引き戻されたことが強調されています。
「献呈」の使用による状況説明
本編97分頃、ロベルトが作曲した歌曲集「ミルテの花」の第1曲として知られる「献呈」が流れ、結婚式会場が映し出されます。2人の様子が映し出されるのは少し後ですが、「献呈」はロベルトがクララとの結婚時に彼女に捧げた特別な作品だという音楽史を知っている方であれば、すぐに結婚の場面まで飛んだことが理解できます。
‣ 留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているクララの音楽史の内容と異なる点もあります。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。
► 終わりに
「哀愁のトロイメライ」は、クララ・シューマンの生涯を描いた3つの映画の中でも、特に彼女の少女時代から結婚に至るまでの成長過程に焦点を当てた貴重な作品です。演奏シーンの細やかな演出や音楽的な解説が織り込まれた構成は、ピアノ学習者にとって興味深いものとなっています。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
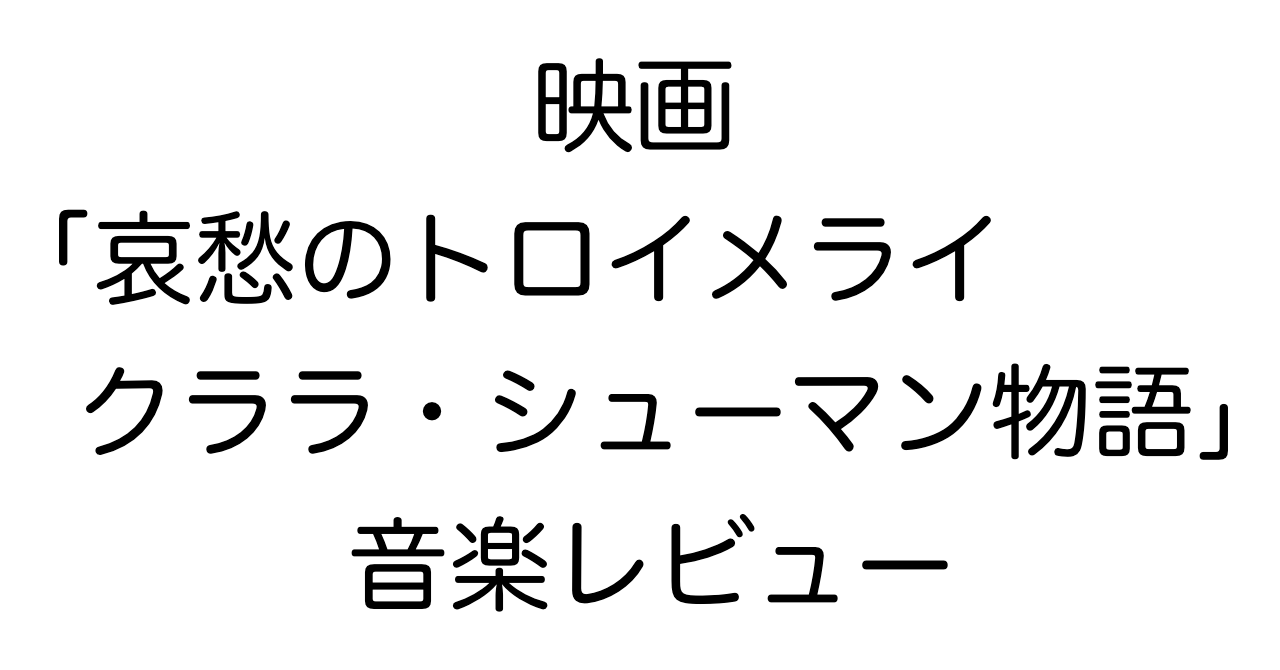
![哀愁のトロイメライ/クララ・シューマン物語 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51R0S9HAYAL._SL160_.jpg)
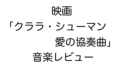
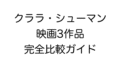
コメント