- 【ピアノ】本番を成功させるための48のポイント:本番前から本番後まで
- ► はじめに
- ► A. 本番前の全知識
- ‣ 1. 本番1週間前に多少ガタガタでも何とか間に合わせる方法
- ‣ 2. 本番3日前なのに何とかなっていない場合の対処法
- ‣ 3. 本番前に仕上がっているためのちょっとしたコツ
- ‣ 4. 本番直前に新しい練習方法を始めない
- ‣ 5. プログラム提出では、絶対に曲名を適当に扱ってはいけない
- ‣ 6. 演奏曲名を勝手にいじられたときは問い合わせよう
- ‣ 7. 爪の音がうるさいと演奏が台無しになる
- ‣ 8. 目の前の本番に全力をあげるコツ
- ‣ 9. 本番までのカウントダウンを楽しむコツ
- ‣ 10. ピアノ演奏におけるステージ不安克服法
- ‣ 11. 失敗しない、譜めくり者のたて方
- ‣ 12. 共演者の精神的なサポートもピアノ奏者の役割
- ‣ 13. 本番会場のピアノのソステヌートペダルをチェック
- ‣ 14. 内部奏法の落とし穴:事前確認の重要性と注意点
- ‣ 15. 発表会における服装選びの落とし穴
- ► B. 本番当日の全知識
- ‣ 16. 本番当日の必須アイテム:忘れてはいけない3つの準備品
- ‣ 17. 想定外に備える:本番に持参すべき予備のアイテムたち
- ‣ 18. 本番当日の防寒対策
- ‣ 19. 当日、自宅で一度指を動かしておく
- ‣ 20. 控え室での心得:本番前に避けるべき行動と注意点
- ‣ 21. お手洗いでの「手洗い」に注意
- ‣ 22. なぜ、当日会場リハに顔を出すことが大事なのか
- ‣ 23. 会場リハでピアノの状態と椅子の形態をチェック
- ‣ 24. 会場リハで譜めくり者の椅子の音もチェック
- ‣ 25. チェック用レパートリーの重要性
- ‣ 26. ステージ脇へ行くタイミング
- ‣ 27. ステージ脇での注意点
- ‣ 28. ステージ上では3拍子で歩こう
- ‣ 29. ステージでピアノ椅子を引きずらなくする方法
- ‣ 30. 印象が激変するお辞儀の仕方
- ‣ 31. 演奏中、男性のスーツボタンは外す
- ‣ 32. 本番でフーガのテンポ設定を間違えないコツ
- ‣ 33. プレリュードとフーガの間で、手を拭かない
- ‣ 34. 失敗したときの苦笑いをやめよう
- ‣ 35. 演奏後の立ち上がり方
- ‣ 36. ステージ脇への戻り方
- ► C. 本番後の全知識
- ► D. 音楽家の知恵袋:追加のヒント
- ► 終わりに
【ピアノ】本番を成功させるための48のポイント:本番前から本番後まで
► はじめに
ピアノの本番は、練習の成果を発揮する最高の瞬間であり、同時に多くの演奏家が不安を感じる大切な機会です。
本記事では、本番前から本番当日、そして本番後までのすべての段階について、実践的なアドバイスを48のポイントにまとめました。本番を成功させるために必要な全知識です。
► A. 本番前の全知識
‣ 1. 本番1週間前に多少ガタガタでも何とか間に合わせる方法
本番1週間前に通し練習をした結果、ガタガタしていて焦ることはあります。何とか間に合わせたくても、今までのやり方をしていては上手くいきません。それは、今の状態が証明しています。
提案はただ一つです。今すぐに、弾けるところばかり気持ち良く弾くのを辞め、そしてその出来た時間で、ガタガタしているところの集中工事に全力をあげましょう。
結局、昔の筆者も含めて多くの学習者は、弾けるところを気持ち良く弾くことに時間を使い過ぎです。そんなことをしている時間はもうありません。それをやっていた時間を使って、やばいところの立てなおしをするべきです。
最終的な仕上げにあたって全体の練習は必要です。しかし、大切なのは力配分。練習割合の配分を、よく弾けるところからやばいところへと移動させるのが、とにかく何とか間に合わせる方法です。
‣ 2. 本番3日前なのに何とかなっていない場合の対処法
「本番3日前に何とかなっていない」など、もっとやばい場合はどうすればいいのでしょうか。
対処法としては、大きく3つです:
・明らかに弾けていないのであれば、テンポを落とす
・バロック期の作品であれば、装飾音符の省略を検討する
・暗譜が問題なのであれば、本番でも楽譜を見て弾く
対処法の一つは、まずはやはり、テンポを落とすことです。
自分で速く弾いていることすら分かっていないのであれば、テンポを落ち着かせる前に、一旦、気持ちを落ち着かせてください。
トラックが120キロで走って半分くらい荷物を落としている状態は、避けなければいけません。70キロで走って、見事に荷物を落っことさずに届ける。しかも、へこんだりしていない綺麗な状態で。
・「荷物を届ける」というのが、音を拾うこと
・「へこんだりしていない綺麗な状態で」というのが、雑にならず表現が伴っていること
とりあえず、これで披露しましょう。別の本番の機会に70キロ以上を目指せばいいのです。
一番苦手な部分がきちんと弾けるテンポで全体を弾くのが、目安です。
以下の2つのパターン、どちらのほうが印象が良いと思いますか。
・弾けるところはテンポが上がっていて、苦手なところで遅くなっている
・全体のテンポはゆっくりめで、苦手なところも事故なく弾けている
印象がいいのは当然、後者です。全体のテンポを少しゆっくりめに設定したとしても、苦手なところで明らかに遅くなってしまったようには聴かせないようにする。そのほうが全体の完成度は高く聴こえます。
加えて、荒技的に感じるかもしれませんが、バロック作品に取り組んでいて装飾音がうまく弾けないのが足を引っ張っているのであれば、その装飾音、今回は取っ払ってしまってください。
詳しい解説は専門書にゆずりますが、バロックの装飾音は一部の例外を除き、書かれていないところにつけるのも、書いてあるものを省略してしまうのも、どちらも自由とされていました。その点は、今の時代よりも演奏家の裁量に任されていたわけです。
このことについては、バロック音楽の専門書の他、以下のピアノ専門書籍などで解説されています。
・ピアノが上手になる人、ならない人 著 : 小林 仁 / 春秋社
その他、暗譜がやばいのであれば、一部の巨匠ですらやっているように、本番でも楽譜を見て弾きましょう。本番の環境的にそれが無理なのであれば、今すぐにこの記事を閉じて暗譜をすることに全力をあげるしかありません。
大きくは、これら3点です。とにかく、残り3日のできる限りの時間を投下して、一点集中で取り組んでください。
今回やばい思いをしたのであれば:
・選曲
・練習計画の立て方
・練習方法
などのどこに問題があったのかを突き止めて反省しましょう。
言い方は良くありませんが、問題を引き起こす原因は、大抵の場合、自信過剰にあります。新年の抱負などを思い出してみると分かるように、我々は自分が思っている以上に自信過剰です。余程スムーズに学習が進む場合でない限り、大抵、計画崩れになってしまいます。
こういったことも、一つ一つの本番から分かってくる学びの一つです。
‣ 3. 本番前に仕上がっているためのちょっとしたコツ
本番前に仕上がっているためには、計画的な練習が必要なのは言うまでもありません。加えてもう一つ、仕上がっている状態へ近づけるコツがあります。
中級者以上の方はいくつかの本番を抱えることもあるかと思いますが、「これくらいの本番数なら、何とかこなせるかな」という感覚でスケジュールを組まないでください。それだと、十中八九一杯一杯になります。
前項目でも書いたように、我々は自分が思っている以上に自信過剰です。余程スムーズに学習が進む場合でない限り、大抵、計画崩れになってしまうでしょう。
「本番の数は、余裕があるくらいで丁度いい」と考えて計画を立てておきましょう。そうすると、本番前に仕上がっている可能性は高くなります。
くれぐれも、「焦って切羽詰まっているほうが自分は学習できる」などと勘違いしないでください。それは、内容が伴っていないはずです。音楽は心に余裕があるときにしかできません。
‣ 4. 本番直前に新しい練習方法を始めない
本番直前になって焦る気持ちは分かりますが、原則、直前に新しい練習方法を始めるのは控えるようにしましょう。
やることを増やし過ぎるのが良くないだけでなく、慣れないことをやると、感覚が乱されて今まで出来ていた部分が急に弾けなくなる可能性が高いからです。
本番直前では、新しいアプローチの練習方法は取り入れずに「今までずっと取り組んできた弾きこみのやり方」を継続するようにしましょう。
今まで通りのアプローチだと心配になるかもしれません。しかし、ここで焦って練習方法を変えても、わずかの時間でいきなりうまくなることはありません。それであれば、今までのやり方で安定させておくほうがいい結果になるのです。
こういった「弾きこみ面」に関してはもちろん、「本番直前に、今まで聴いていなかったピアニストの音源を聴いてしまうこと」も避けるべきです。
何か新しいことを取り入れたいのであれば、せめて少し前から始めるようにしましょう。目安としては、2週間くらいは欲しいところです。本番が立て続けにある場合は、取り入れたい新しいことをまだ本番が先にある別の楽曲で取り入れるといいでしょう。
‣ 5. プログラム提出では、絶対に曲名を適当に扱ってはいけない
以前に、今は閉鎖されたとある国際的な日本人音楽家のHPを見ていたら、他者の作品名やアーティスト名の記載に間違いがヤマのようにあり、ひっくり返りそうになりました。
たまに誤字を入力してしまうことは筆者にもあります。しかし、うっかり誤字にしてしまったわけではなく:
・英題でしか公になっていない楽曲名をカタカナ読みしてカタカナのまま書いてしまっていたり
・アーティスト名のひらがな部分をカタカナで書いていたり
などと、明らかにいい加減な記載だったのです。
ピアノを弾いていると、演奏会に出演するときなどにプログラム提出をする機会がありますが、作曲をする立場から言わせてもらうと、どうか、他人の作品名や名前を大切にして正しく提出して欲しいと思っています。
筆者にも昔、他人の作品名を雑に扱ってしまった経験があります。
ライネッケ「左手のためのピアノソナタ ハ短調 Op.179 第4楽章」を弾いたときに、楽章抜粋ではなくて単曲を弾いているような印象を与えたかったので、
というタイトルにしてプログラム提出してしまいました。
「まあそうなんだけど、それじゃダメでしょ」ってやつです。今となっては反省しています。
また、本Webメディアの記事の中で、「YouTube」のことを「Youtube」と書いてしまったことがあります。
どちらでもいいわけなく、このたった一文字の「T」が大文字であることに対して、ブランド主には相当な想いがあるはずです。他者のブランドを大切にしていませんでした。
作品名やアーティスト名をはじめ、他者のブランド名を大切にしようと思ったのは、これらのような失敗と反省がきっかけでした。
筆者は音楽活動はすべてカタカナ名義で行なっているのですが、名字と名前の間に勝手にスペースを入れられてしまってガッカリすることがあります。また、音楽のプロジェクトのことで連絡をしているにも関わらず、わざわざどこかで調べた本名の漢字で名前を書いてメールが送られてくると、もっと残念な気持ちになります。
‣ 6. 演奏曲名を勝手にいじられたときは問い合わせよう
大なり小なり出演する各種演奏会では事前に演奏曲目提出をするはずです。
ところが、プログラムが出来上がってきたときに、提出した曲名が勝手に変えられていることを経験したことはありませんか。ささいなことで言えば、「スペースの入れ方を変えられている」とかです。
筆者は昔、ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3」を提出したら、プログラム冊子に「狩」という副題が付け加えられていて、少し残念な気持ちになりました。
この反発したい感覚、分かってもらえる方もいるのではないでしょうか。
作曲者名や曲名というのは様々な表記が出回っているものなので、演奏会の主催のほうで統一基準を設けている場合であれば仕方ありません。例えば、とある企業は会社ルールで「ベートーヴェン」ではなく「ベートーベン」に統一しています。
しかし、明らかに何となくでいじられた感じがする場合は、事務局に問い合わせてみてください。その結果、すでに出来上がったプログラム冊子自体は変更できなくても、本番でのアナウンスで希望通りに読み上げてもらえる可能性はあります。
演奏曲名はもちろん、コメントなど、音楽を伝えるうえでの「言葉」というものに、もっとこだわっていきましょう。
‣ 7. 爪の音がうるさいと演奏が台無しになる
本番の経験がまだ浅い場合、「こんなことまで意識できていなかった」というような失敗が起きる可能性があります。
その代表格は、「爪が鍵盤にあたる音がうるさ過ぎて、演奏の邪魔になった」というものです。特に独学の方は、日ごろ指摘してくれる方がいないので、自宅で一人で練習しているとそこまで気が回らないこともあるでしょう。
爪の音がうるさいと演奏が台無しになってしまいます。本番のようなよく響く会場で弾いたり、ましてや、録音を聴き直したりすると、驚くほどカチカチ音が気になるものです。
爪の長さによって、騒音面だけではなく演奏のしやすさにも影響があるからか、音楽雑誌で「ピアニストの爪のお手入れ特集」などを目にすることさえあります。最低限の手入れはやっておきましょう。本番前にだけやろうとするのではなく、ピアノを学習している以上、日ごろから定期的に手入れするのが得策です。
騒音面以外についても言うと、「爪を伸ばすことと、正しい奏法は両立できない」ことを踏まえておきましょう。
爪が長いと、どうしても指をベタッと伸ばして演奏することになってしまうので、出したい音によって様々な指の角度が必要になるピアノ演奏には不向きなのです。こういった指先の使い分けは、特に中級以上になると避けて通れません。初級段階の方も、指の角度が限定されてしまうような爪の長さにしておくべきではないでしょう。
お手入れの目安としては:
・伸ばしっぱなしなのは論外
・一般的に「深爪」と言われるほど短くなければ、通常の感覚で切ってしまってOK
・ピアノへ向かってみて、必要であれば、気になるところのみヤスリで削って調整する
爪を切っておかなかったばかりに、たくさん練習してきた努力が台無しになるのだけは回避しましょう。
「爪という些細な部分に少し気を回せるか」が、演奏に「少し」ではなく大きく影響するのです。
‣ 8. 目の前の本番に全力をあげるコツ
はじめて人前で演奏したときのことを今でも覚えていますが、緊張しながらも、楽しみで興奮していたのを記憶しています。もちろん、その当時なりに準備にも時間をかけていました。
「慣れ」というのは良くも悪くも影響があり、本番というイヴェントに慣れたことで:
・目の前のそれへ向けてガッツが入らなかったり
・選曲を無難なものばかりで楽して回したり
なんてこともあるでしょう。
こういった状態を抜け出して目の前の本番に全力をあげるためには、本番の数を制限して、チャレンジングな本番のみを残すようにするしかありません。
よく、「ピアニストはどんな本番でも意識を持ってステージに立っている」という話を耳にします。確かにそうなのでしょう。しかし、踏まない本番を決めているのも確か。そのうえでのことなのです。
それぞれの本番に優劣をつけたいわけではありません。しかし、慣れもあるとすべての本番を新鮮に感じるのには、正直、無理があります。
慣れには良い面とそうでない面があるので、その扱い方を考えてうまく付き合っていかないといけません。
本番は成長の大きな機会になりますが:
・もし入れ過ぎていると思ったら、少し調整してみる
・自分にとってチャレンジングなものだけを残すようにしてみる
この2つを意識すると、全力をあげられるようになるはずです。
今までで一番気合いの入った本番は何だったのかを思い出してみて、それに近しい本番の機会を探してみるのもいいでしょう。
‣ 9. 本番までのカウントダウンを楽しむコツ
本番などの大事な予定が決まっているとき、その日までストレスをためながら過ごしてしまうケースは多いようです。気持ちは分かるのですが、「本番までのカウントダウンを楽しむ」というつもりで過ごせるように持っていけるとベターです。
例えば筆者は、重要な作品発表を控えているときには:
・「あと○日だ、ちょうど○日前って何をやっていたっけ」などと考えたり
・毎日、iPadでカレンダーの日付にバッテンをいれていったり
このようにして楽しんでいます。
あらゆる本番は、本番日が大切なだけでなく、その日を迎えるまでの期間も同じく大切です。ドキドキしたり、ワクワクしたり、ウロウロしたり、その期間を丸ごと楽しんでみましょう。
楽しむためのコツを一つだけ挙げるとすると、とにかく、少し早めに準備を進めておくことです。
本番の3日前なのに、演奏がガタガタだったり作曲が終わっていなかったりすると、楽しめるわけありません。少し日にちを残した状態で、「ここまでできていれば大きく崩れることはないだろう」という段階までやりこんでおいてください。そうすれば、「はやく本番を迎えたい」と思うようになります。
この気持ちの状態で中々カウントダウンが進まないからこそ、その期間がちょっとじれったくも本当に楽しい日々になるわけです。
‣ 10. ピアノ演奏におけるステージ不安克服法
本番に「慣れ」はなくて、新しいステージになれば、またそのときに新たな緊張感が出てきます。しかし、良い緊張感はむしろあったほうが良く、だからこそ、弾き終えて緊張から解放されたときのハイな感覚や充実感を得ることができるわけです。
「ノー練習」よりも少し練習すると「練習不足による嫌な緊張感」がある状態に達し、さらに練習すると「ワクワクを含んだ緊張感」になります。
この3段階を意識して練習し、第3段階目まで押し上げておけば緊張しても全く問題ないと理解しましょう。
「練習不足による嫌な緊張感がなければよいと割り切る」
これを踏まえると、あがり・緊張をふっきることができます。
以下、もう少し細かく見ていきます。
【ステージで楽譜を見る場合】
ソロで楽譜を見る場合というのは、本番までにそれほど余裕を持って準備できないケースが多いでしょう。
しかし、目標として「楽譜を見る場合でも、一応暗譜している」というところを目指してください。暗譜をしているけれども一応楽譜を置いているのと、楽譜にかじりついているのとでは、全く心理的状況が異なります。
「嫌な」緊張感を減らすためには、心理的な余裕を持てなくてはいけません。
【ステージで楽譜を見ない場合】
楽譜を見ない場合は、文字通り暗譜していることが前提ですが、その暗譜が危なくなったときに参考にできるものがないわけです。
「嫌な」緊張感を減らすためには、楽譜に代わる復帰のための保険をかけておくといいでしょう。例えば、以下のようなものです:
・危ないところの周辺では、各段の一番左から弾き始められるようにしておく
・「1拍ずつ速く弾く練習法」をやり込んで、各拍の頭の音を覚えておく
演奏面で工夫できることを紹介しましたが、他にも:
・当日リハーサルでピアノの椅子やペダルの不安点を確認しておいたり
・ステージ上での歩く経路を決めておいたり
など、頭をよぎるであろう演奏以外の一切の不安を消しておくことがステージ不安克服法のさらなるポイントです。
プロの音楽家でもみんな、一か八かやっています。「嫌な」緊張感さえなければ、適度な緊張感は歓迎しましょう。そのようにして思い切って弾くことが、ステージでの不安克服につながります。
心構え:
・みんな「一か八か」でやっている
・適度な緊張感は歓迎
・思い切って弾くことが大切
緊張感について:
・何回やっても本番に完全に「慣れる」ことはない
・新しいステージでは新たな緊張感が生まれる
・良い緊張感はあったほうが、演奏後の解放感や充実感を味わえる
楽譜を見る場合:
・できるだけ暗譜を目指す
・暗譜をしているうえで楽譜を置くと心理的な余裕ができる
・完全な暗譜が必要
楽譜を見ない場合:
・「復帰のための保険」を準備する
・危ないところは各段の左から弾き始められるようにしたり
・「拍頭止め」練習で各拍の頭の音を覚える など
その他の準備:
・リハーサルでピアノの椅子やペダルを確認するなど、 演奏以外の一切の不安要素をなくしておく
‣ 11. 失敗しない、譜めくり者のたて方
伴奏をするときはもちろん、場合によってはピアノソロであっても、本番の譜めくりを依頼することがあるでしょう。そんなときに「誰に頼むのか」というのは大事な観点です。
譜めくり者はとても重要な役割ですが、ステージにおいては黒子です。原則、目立ってはいけません。言い方は良くありませんが、あらゆる意味で自分よりも目立つ人物には依頼しないことです。例えば:
・どうしても派手な格好が好きな人物
・直前にステージへ出て顔が知られている出演者
・自分よりも極端に身長が高い人物
これを、見た目で人を判断しているという悪い意味に捉えないでください。自身のステージにとってどんな譜めくり者が適切なのかは、何となくイメージがついているはずです。
当然、譜めくり者との打ち合わせも重視しましょう。ごくまれに、ステージを去る順番を間違えられて、どちらが主役なのか分からなくなるときがあります。譜めくりの位置が早過ぎることもあります。その他も含め、あらゆるトラブルは事前の打ち合わせである程度防げます。
例えば、以下のことを確認しておきましょう:
・お互いの衣装について
・ステージの出入りについて(手順、歩き方など)
・譜めくりする位置について
・譜めくり者が座る位置の距離感について
・譜面の持ち運びについて
・合図の出し方について
「慣れている譜めくり者」というのは意外と少ないので、細かなことも確認しておくことをおすすめします。
「備えあれば・・・」というのは、演奏面だけのことではありません。譜めくり者とのコミュニケーションにも言えます。そして、逆に譜めくりを頼まれたときには、演奏者とのやりとりを丁寧に行なうようにしましょう。
‣ 12. 共演者の精神的なサポートもピアノ奏者の役割
共演者というのは:
・他のソロ演奏者
・自分の譜めくりをしてくれる共演者
・2台ピアノ作品を弾く場合の共演者
・連弾ピアノ作品を弾く場合の共演者
はもちろんですが、本項目では:
・自分がピアノ伴奏をする場合の共演者
・室内楽作品で一緒に演奏をする場合の共演者
について見ていきましょう。
ピアノ奏者には「共演者の精神的なサポートまでする」という大きな任務があり、演奏において共演者に完全に信頼してもらう必要があります。そのために、相手のパートがどうなっているかということを事細かに把握しておかなければいけません。
ピアノパートの演奏者が共演者のパートを知り尽くしているかは、演奏を聴けばすぐに分かってしまいます。初級レベルの演奏者でも、相手の心が自分に向いていないことはすぐに感じ取ります。
だからこそ、「共演者のパートのことを共演者以上に詳しく知っておく」くらいの気概で事前準備しておくようにしましょう。
例えば、「山田耕筰の歌曲の伴奏」をするとしましょう。
山田耕筰は歌曲に深い造詣があったので、歌のパートにもたくさんのニュアンスが書いてあります。こういったことをつぶさに勉強し、伴奏者もピアノを通して一緒に寄り添ってあげなくてはいけないのです。
その他の面でも、「この人はこれだけ詳しいから、万が一、本番中におちてしまっても対応してくれるだろう」と安心させてあげる必要があります。
つまり、共演者のパートを知りつくすことは「精神的なサポートまでする」ということです。
自分のパートを一生懸命読むことから始めるはずなので、大きく次の4段階の到達度が出てくるでしょう:
1. 自分のパートすらよく理解できていない
2. 自分のパートは深く理解している
3. 自分のパートは深く理解しているが、相手のパートはよく理解できていない
4. 自分のパートも相手のパートもよく理解できている
この「4」の段階まで自分を引き上げてからリハーサルへ臨めるように、過勉強して欲しいと思います。
そうして全体理解の段階まで達していると、音楽の深いレヴェルでアンサンブルやディスカッションできるので、共演者を暗い顔させる可能性はありませんし、音楽的に充実したリハーサル時間を過ごすことができるでしょう。
アンサンブルのリハーサルへは、とにかく、過勉強で万全準備をして臨むに限ります。
‣ 13. 本番会場のピアノのソステヌートペダルをチェック
「ソステヌートペダル(3本あるうち、真ん中のペダル)」は、結構大きなホールのグランドピアノでも平気で故障したままになっていることがあります。うまく効かない状態で放置されていたりします。当日の調律では、多くの場合そこまでチェックをしてくれません。
ソステヌートペダルが故障していることに当日会場リハで気づいて、すぐにその場にいる調律師に伝えても、構造上すぐに直せないことがほとんどです。
したがって、ソステヌートペダルを使用する作品を弾く方は、必ず会場への事前チェックを入れるのが得策です。
習っている「ピアノの講師」が主催の演奏発表会の場合、マナーという意味でも、必ず講師を通して確認してもらってください。無断で直接ホールとやりとりをしてしまうと、先生はきっといい思いをしないはずです。
‣ 14. 内部奏法の落とし穴:事前確認の重要性と注意点
現代作品でよく出てくる「内部奏法」ですが、ほとんどの会場は禁止しています。
最近のホールは、大元が委託して管理者を雇っているケースも多いので、ホールに問い合わせても、「禁止しています」と、相手側としてもとりあえず断っておくしかないのです。
会場を探すときに「個人が管理しているサロンやホール」などだとOKが出る場合もありますが、当て布を義務付けられたりと制約がつくのが大半です。
この問い合わせをせずに本番でいきなりやってしまったのが確認されると大変です。以前に、とある小さなサロンでのことでしたが、問い合わせをせずに本番でいきなり内部奏法をして、個人だけでなくその団体全員が出禁になったという事例も知っています。
内部奏法は、ピアノの弦など「内部」を触ることになるので、たとえ「当て布」をしたとしても会場としては遠慮して欲しいのが一般的。汗で弦のサビにつながってメンテナンスが必要になる可能性や、弦が切れたりと損傷の可能性もあるからです。
もし、内部奏法を使用する楽曲を弾く場合は、必ず事前に確認するようにしましょう。と言いますか、それでは遅いくらいなのです。
・会場が決まっている場合は、会場に確認してから選曲するか
・演奏楽曲を選曲してから、会場をとる
むしろ、これくらいの気持ちでいないと、思うようにいかないことのほうが多いと思っておいてください。
‣ 15. 発表会における服装選びの落とし穴
発表会での「服装」は男女問わず悩みどころでしょう。
男女問わずよく問題として耳にするのが、「カジュアルな服装」についてです。発表会の趣旨自体がそういったものであれば問題ないのですが、そうでない場合は「なるべく正装に寄せた格好」をしておいたほうが得策です。
というのも、クラシックの発表会や演奏会は、聴衆の多くが「ご年配の方」なのです。
発表会では、出演する子供の親御さんが聴きにくる割合も多いですが、それでも一部を除けば最低ラインは30代、多くの聴衆はそれ以上の年齢と考えていいでしょう。
そういったときに、いきなり周りの出演者とかけ離れた「カジュアルな服装」で登場すると、それまで面識のない方に対してでさえクレームを入れる方が実際にいるのです。
また、譜めくりで参加する方は主役よりシンプルな格好をしたり、伴奏者はソリストよりもシンプルな格好をするのが一般的です。こういったことは当たり前のようではありますが、うっかりすると当日汗かくなんてことにもなりかねません。
► B. 本番当日の全知識
‣ 16. 本番当日の必須アイテム:忘れてはいけない3つの準備品
1つ目の、当日会場に持っていく準備品として欠かせないものは、「ICレコーダー」です。
自分の本番は必ず録音するようにしてください。そして、本番で緊張するとどんな演奏になるのか(なってしまうのか)をチェックしておきましょう。本番毎に録音チェックをして状態を把握しておくことは、今後さらに大きな本番を踏む際の糧になります。
2つ目の、当日会場に持っていく準備品として欠かせないものは、「手を温めるカイロ」です。
当然と思いませんでしたか。しかし強調したいのは、「冬だけではない」ということです。
人間の手は、緊張をすると冷たくなります。身体を暖かくしていても、普段では想像もつかないくらい手が冷たく感じたことは経験があると思います。つまり、「それほど寒くはない春や秋の本番」でも、念のために未開封のものを持っていく必要があるのです。
3つ目の、当日会場に持っていく準備品として欠かせないものは、ふざけているわけではありませんが、「演奏会用の靴」です。
本番当日は会場に着いてから着替える方がほとんどなので、家を出るときには「普段の靴」を履いていますね。そのせいか、会場に着いてから「演奏会用の靴」を忘れてきたことに気づいた経験をした方が、筆者の知り合いだけでも何人かいるのです。笑い話のようで、本当に何度も起こった笑えない話です。
その他、衣装はもちろん、自分にとって絶対に必要だけれども家を出るときには身につけていないものには要注意です。
‣ 17. 想定外に備える:本番に持参すべき予備のアイテムたち
筆者が昔言われてずっと守っていることがあります。
それは、「大切な本番では、今日は不要かもと思うちょっとしたものでも一応持っていく」ということ。
例えば:
・冬場以外でもカイロ
・筆記用具
・暗譜している楽曲の楽譜
・ティッシュペーパー
・降水確率がわずかでもあれば折り畳み傘
など、他にももしかしたら必要になるかもしれないと思うものは、とりあえずみんな連れていってください。必要にならなかったらそれはそれでいいのです。
多少荷物は増えたとしても、大事な本番ではできる限りの万全の準備をしたうえで、自信をもって臨んでください。
‣ 18. 本番当日の防寒対策
防寒をおろそかにしてしまい、「本番で指が動かなかった…」なんてことになってしまったら大変です。
緊張すると身体が冷えることは、専門家も指摘しています。そこに加えて、季節的な寒さによる冷えも重なるわけなので、それなりの対策が必要です。
注意しなければいけないのは、「会場によっては、屋内であってもあまりエアコンが効いてないケースもある」という点です。
会場につけば暖かいと思い込んでいると、大変なことになる可能性があります。暖かくても寒くても対応できるように先読みしておかなければいけません。
日常生活で経験があるかと思いますが、手が冷え切っていると、チャックを開け閉めするのも一苦労です。そんな状態でピアノなんて弾いたら、冗談抜きに力の1割も出せません。以前の筆者も、痛い目にあった経験があります。
【手と上半身の防寒】
「手」に関して注意しなければいけないのは、「気温一桁以下の時期の場合、毛糸手袋1枚では防寒としては足りない」ということです。
だからといって、わざわざ「電気手袋」を買う必要はありません。ピッタリ手にフィットする毛糸手袋であれば「ドラッグストア」でも買えますし、すでに自宅にある方も多いはずです。それをつけた後に、厚手の手袋を重ねましょう。
「上半身」に関しては、とにかく恥ずかしがらずに着込むことです。着込んだままステージに出るわけではないのですから。本番を成功させるためです。特に男性はステージ衣装を自宅から着てくる方も多いようなので、とても冷えやすいと言えるでしょう。
随分前のことですが、共演者のとある男性がスーツのみで会場入りしていて、スーツ用のコートも着ていないので「冷えませんか?」とたずねてみたことがあります。「コートを着るのが恥ずかしいから、いつもこのスタイル」と返答されて、驚いたことがあります。
カイロは「貼らないタイプ」よりも「貼るタイプ」のほうがずっと暖かい印象です。「ステージ脇待機」のために貼らないタイプを持っていくのはいいですが、「基本は、貼るタイプで防寒する」と思っておきましょう。
【下半身の防寒】
下半身の防寒については見落としがちです。下半身が冷えると、腰より上をどんなにあたたかくしていても、元の木阿弥。再び手も氷のような冷たさに戻りますので注意しましょう。
下半身の防寒対策に関しては、ステージ衣装によっては難しいですが、会場入りして着替えるまでの防寒は怠らないのが重要です。
男女問わず、演奏家仲間の間で定番なのは「タイツ」です。タイツは会場入りしてから脱げますが、男性はタイツを履いた上にスーツパンツを履いて、そのまま本番をこなす方もいるようです。筆者自身もそうした経験はあります。
「靴や靴下に貼るタイプのカイロ」は使っても大丈夫ですが、会場リハの前には必ずはがしてください。
わずかの厚みだけですが、ペダルを踏む感覚に大きな影響を与えます。したがって、うっかりはがし忘れて会場リハをやった後にはがして本番を迎えると、感覚の変化に戸惑うはずです。
どんな本番でも足元の感覚は統一しておいたほうがいいので、寒い時期の本番だけカイロを入れたまま演奏するのはおすすめできません。
‣ 19. 当日、自宅で一度指を動かしておく
防寒とともに、関連事項としてお伝えしたい内容です。
とあるスポーツ選手の発言で知ったことなのですが、多くのスポーツでは、試合当日、試合前に一回息をあげておくそう。「肩で息をするくらい一度あげておくことで、試合本番で激しく動いても体力が続く」とのことです。
ピアノでも「指慣らし」という言葉がありますが、会場リハに頼らず、本番当日、自宅で一度指を動かしておくことは必須です。一度「指慣らし」をしてあるかどうかで、「指の動きや感覚」に好影響があるのは、筆者自身、身をもって経験しています。
もちろん、その後の防寒対策はしっかりと行いましょう。
‣ 20. 控え室での心得:本番前に避けるべき行動と注意点
当日控え室でやってはいけないことは、机鍵盤で演奏することです。
控え室での待ち時間に、イヤフォンで録音を聴きながら机の上で指を動かしている方を見ますが、筆者はあまりおすすめしていません。というのも、「机」と「鍵盤」では感触があまりにも違うので、本番前に違う感触を体感することはむしろマイナスになると思っているからです。
当日までに十分練習してきたのであれば、もう一か八かで思い切ってやるしかありません。当日に悪いクセがついてしまわないように気をつけましょう。
控え室では「リラックスをする時間に充てる」とか、どうしても不安なら、せめてイメージ練習をするほうがいいでしょう。
‣ 21. お手洗いでの「手洗い」に注意
会場入りしてからお手洗いへ行くことは何度かあるはずですが、会場によってはお湯が出ないので、キンキンの水で手を洗わなければならない可能性があります。
「通常の手洗い」くらいであれば割と短い時間で済みますが、「油性の整髪剤」などがついた手はハンドソープでよく洗わないと落ちません。そういったことも考えると、男女ともに、会場入りしてからヘアメイクを行うのは危険です。その後、手洗いで手を冷やす恐れが高いからです。
会場でのヘアメイクは、「直し」程度で済むようにしておきましょう。
‣ 22. なぜ、当日会場リハに顔を出すことが大事なのか
習いにいっている方の教室の演奏発表会や、独学の方であれば自主申し込み参加型の各種演奏発表会などに参加することはあるはずです。そういったイベントで、毎回、絶対に当日会場リハに顔を出さない参加者がいると思いませんか。
会社勤めの大人の参加者で、どうしても自分の本番にしか間に合わない場合はともかく、毎回同じ人物がいなかったりして、明らかに顔を出すのを控えているであろうケースもあります。
筆者は、もし間に合うのであれば、リハには絶対に顔を出すべきだと考えています。会場のピアノに慣れておいて云々というのもありますが、言いたいのはもっと前の段階の理由です。
なぜ、顔を出すべきなのかというと、「自分一人の経験やストックにしたいのではなく、一緒に一つのイベントを作りますよ」という意思表示になるからです。もっと極端な言い方をすれば、「敵ではありません」という意思表示になるからです。
また、もっと細かなことまで言ってしまいましょう。
演奏会の場合、習っている先生や知っている目上の出演者がいることも多いはず。それなのに、出せる顔を出さずにわざと挨拶を遅らせていること自体がマナー違反なのです。
自分の本番でのステージというのは、そういったことが済んだ後。目上の人物に対してステージ上ではじめて自分の姿を見せるのは、タイミングが違います。
‣ 23. 会場リハでピアノの状態と椅子の形態をチェック
当日会場リハではピアノを触れますが、このときにやっておくべきことがあります。
一番重要なのは、会場のピアノはどこまで弱音を出せるかのチェックです。
「弱音までしっかりと出てくれるピアノ」があれば、「ある程度の弱音になると音がすっぽ抜けて、鍵盤が下りても音が出ないピアノ」もあります。怖いのは後者。「鍵盤が下りたのに音が出なかった」というのは、ミスタッチと同じくらいもったいないミスです。
基本的には楽器を持ち運ばないピアノ奏者は、「会場のピアノ」を使うしかない宿命なので、当日にそのピアノに合わせて打鍵のコントロールを調整しなければいけません。ホールのピアノであっても、状態の良くないものはたくさん存在します。つまり、自分自身の演奏で対応して本番を成功させないといけないのです。
気持ちよく「通しリハ」をするだけでなく、少しでも「弱音のチェック」の観点でピアノを触ってみる時間を作りましょう。
また、当日会場リハでは「ピアノ椅子の形態」についてもよくチェックしておきましょう。
特に注意が必要なのは、「回して高さを調整するタイプ」のピアノ椅子。時々「逆向き」に椅子が置かれていることがあります。そうすると、普段自宅で回している方向と逆になるわけですが、ある程度回さないと上がったのか下がったのか分からないので、本番で逆に回してしまって戻したりすると、とても見栄えが悪くなってしまいます。
リハで確認しておけばこのミスは防げます。
「聴衆は見た目でも演奏を聴く」と言いますが、これは演奏中のことだけでなく、演奏直前のステージ動作のことでもあるのです。
‣ 24. 会場リハで譜めくり者の椅子の音もチェック
アンサンブルでステージへ出る場合をはじめ、場合によってはピアノソロであっても譜めくりをお願いすることがあるかと思います。
困ったことに、いざ本番を迎えてみて、その椅子のギシギシ音が思わぬトラブルとして挙げられることも多々あります。
よく注意して意識していないと譜めくり者が自分では気づかないこともあるので、リハの段階でまずいと思ったら伝えてあげてください。そして、会場スタッフにも伝えて、即刻交換してもらいましょう。同種の椅子であればまだしも、本番でいきなり椅子の種類が変わっていると譜めくり者が焦る可能性もあるので、両者に伝えるのがポイントです。
演奏上のアクシデントはともかく、椅子の音などのチェックしておけば防げるトラブルについては原則ゼロにすることを前提に準備しましょう。
‣ 25. チェック用レパートリーの重要性
「チェック用レパートリー」とは、熟知した「リファレンス楽曲」のことです。新しいピアノに触れるとき、いつも慣れていて熟知している楽曲を弾くことで、そのピアノのコンディションを正しく把握できます。
コンディションチェックに失敗すると:
・弱奏で鍵盤が下りても音が出ずにすっぽ抜けたり
・強奏でタイミングが合わずに鳴り損なったり
などといったトラブルの原因になります。
リハーサルなどでピアノに触れる時間が極端に短い場合は、その日に演奏する楽曲を弾くことがほとんどでしょう。しかし、本番の回数が増えれば増えるほど、当日初めて出会うピアノのコンディションチェックに頭を悩ますことになります。そういったときに、チェック用レパートリーが力を発揮します。
チェック用レパートリーは、すでにある自身のレパートリーの中から選ぶのでも構いませんが、その中でも:
・弱奏と強奏の両方が出てくる
・短めの楽曲
これらの条件を満たしている作品から選曲しましょう。
‣ 26. ステージ脇へ行くタイミング
人間が落ち着くにはある程度の時間が必要です。演奏をするには集中しなければいけません。したがって、ステージ脇で「出番待ちの椅子」に座ってから最低でも「5分」、できれば「10分」の時間を確保できると望ましいでしょう。
それに、自分と出番が近い他の出演者が欠席している可能性もあり、いきなり一人分とんだりすることも日常茶飯事。想像以上に自分の出番が早く回ってくることも十分に考えられるので、万が一間に合わなければ、周りの出演者や聴衆に迷惑をかけてしまいます。「欠席者が出たから」などというのは、特に聴衆にとっては関係がないことなのです。
「10分前にはステージ脇で待機を開始するのがベスト」でしょう。ステージ脇に置かれている椅子には数に限りがあるので、あまりにも早く行き過ぎると椅子が余っていません。
‣ 27. ステージ脇での注意点
ステージ脇では絶対に喋らないようにしましょう。理由は以下の3つです:
・集中には時間が必要だから
・ステージ脇の会話は、小さい声であっても会場の前方にザワザワ聴こえているから
・演奏中の奏者がステージ脇で録音している可能性が高いから
仮に前後の出演者に知り合いがいてステージ脇で会っても、あいさつだけしたら座り、集中して目をつぶってしまえばOKです。落ち着いて集中するには時間が必要です。次の出番の方は、あなたが演奏している間に集中できるので気楽なわけですが、あなた自身は違います。ギリギリまで喋っていて30秒前にいきなり集中することなんて、プロでもそうそうできません。
また、ステージ脇の会話は小さい声であっても会場の前方に聴こえています。内容を聴き取れなくてもザワザワしているのが伝わります。最悪のケースではクレームにもなりかねませんし、ステージ脇にいる他のすべての方にも迷惑です。
さらに、演奏中の奏者は多くの場合、ステージ脇でICレコーダーを使って録音しています。客席では、「タイマー機能」でも使わない限りは頼める人がいないと録音できませんし、不安要素もあるので、ステージ脇で自分で録音するケースが圧倒的です。
脇で録音している場合は、喋っている声をICレコーダーが確実に拾ってしまうことを踏まえておきましょう。録音された会話内容がずっと残ることになるのです。
‣ 28. ステージ上では3拍子で歩こう
本番では、演奏のことで頭がいっぱいかもしれません。しかし、うっかりペンギンみたいな歩き方にならないように、ステージの出入りにも少し意識を向けられるといいでしょう。
筆者がおすすめするステージ上での歩き方は3拍子で歩くことです。
「12 12 ペタペタ ペタペタ」などと2拍子で歩くと、何だか鈍臭く見えてしまいます。「123 123 トントントン トントントン」と3拍子で歩くと、聴衆から見て好印象にうつります。
3拍子の歩き方は、検索をすれば様々なやり方がでてきますが、筆者は「少しだけ速歩き気味で、3拍子の意識をもって歩く」だけでも十分だと考えています。あまり色々と考えると、かえってギクシャクしてしまいますから。
‣ 29. ステージでピアノ椅子を引きずらなくする方法
本番で、弾き始める直前や直後にピアノ椅子を引きずる音を立ててしまうと、白けてしまいます。
引きずらなくする方法はシンプルで、とにかく、座ったままの状態では前後に動かさないことです。宙に浮かせて移動させるのが原則で、ちょっとだけ後ろへ下げる場合でも立つようにしましょう。セッティングで再度立つのはダサいように感じるかもしれませんが、引きずる音のほうがずっと恥ずかしいものです。
また、少し持ち上げた椅子を置くときに、ガンと音を立てないように気をつけてください。たった1秒急いでも何も変わらないので、ステージ上では焦らず落ち着いて行動しましょう。
‣ 30. 印象が激変するお辞儀の仕方
お辞儀の仕方は印象に大きく影響します。
まず、お辞儀をする場所まで歩いて行ったら、必ず一度前を向くこと。これをせずにいきなり頭を下げてしまうとだらしなく見えてしまいます。
また、前を向いたときには「まっすぐ偉そうに立つこと」が重要です。
・「首だけ前に出てしまっていませんか?」
・「肩が前に出て背中が丸まっていませんか?」
・「手の位置はそこで大丈夫ですか?」
牛乳を飲む人みたいに胸を張ってください。
・一度前を向いたら頭を下げ、決して首先だけにならないように腰から深くお辞儀する
・頭を下げた状態で少し維持してから上げる
・上げてからも必ず、一度前を向く
この一連の動作が速過ぎると印象が良くありません。
譜面を持ってステージに出る場合は、必ずお辞儀をしてから楽譜を譜面台に置いてください。先に置いてしまうと観客に失礼になってしまいます。
演奏後の注意点も基本的には同様です。
‣ 31. 演奏中、男性のスーツボタンは外す
男性の方でスーツ正装をする方は、腹部でスーツのボタンを1つ締めてステージに出ていきますが、このボタンをかけっぱなしにしたまま演奏してしまうと、窮屈で演奏に差し支えることがあります。
筆者が実践していて、かつ、聴衆として見ている中で一番スマートに感じるのは、ピアノ椅子に座った後にさりげなく「片手で」外すやり方です。
演奏後は、立ちながらさっとはめるか、さっとはめた後に素早く立ち上がるのが自然に見えます。ボタンをかけるのに苦戦している様子は印象が良くないので、練習しておくといいでしょう。
はめるときには両手を使って問題ありません。
‣ 32. 本番でフーガのテンポ設定を間違えないコツ
フーガ、特にJ.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集」のフーガを弾くときに不安要素となるものの一つが、「テンポ設定」です。「堂々と主題を弾き始めたけど、途中で細かな音符が出てきたら速過ぎた」などといったトラブルが起きて汗をかいたことがあるかもしれません。
テンポ設定のコツは、「16分音符の部分をイメージしてから弾き始める」ことです。
フーガにもよりますが、「主題は長めの音価が中心、嬉遊部(きゆうぶ)などで16分音符が目立つ」ように出来ている場合が多いのです。したがって、楽曲の始めに16分音符の部分をイメージしておけば、全体のテンポ設定を誤る可能性は減ります。
部分的に「32分音符」なども出てくるかも知れません。しかし、32分音符を基準にすると、カウントが細かくなり過ぎてギクシャクします。
テンポ設定の基準としては、多くのフーガでは「16分音符」が適切なので自身が弾く作品で確認しておきましょう。
例外的な音価が多発するフーガに関しては、上記でいう16分音符に準ずる音価、つまり、「その楽曲を全体で見た場合に、大振り過ぎず、細か過ぎずの音価」を判断してそれを基準にすればOKです。
‣ 33. プレリュードとフーガの間で、手を拭かない
J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集」では、プレリュードとフーガがセットになっていますが、このようにひとつながりで演奏すべき場合の曲間では、手を拭いたり長いインターヴァルはとらないようにしましょう。
聴覚的にあまりにも時間が空いてしまうのは避けるべきですし、視覚的にも聴衆側の緊張感が切れてしまうような見え方を避けたいのです。
ソナタなどの各楽章間も同様です。
反対に全く別の作品との曲間では、時間を少しだけ長めにとったりと工夫することで、プレリュードとフーガのようなセットで演奏する作品との差を演出することができるでしょう。
こういった工夫は、聴覚的な観点と視覚的な観点の両方で気をつけるのがポイントです。
‣ 34. 失敗したときの苦笑いをやめよう
時には、本番のステージ上でちょっとした演奏トラブルが起きてしまうこともあるかもしれません。
そんなときに特に初心者の方に気をつけてもらいたいのが、苦笑いをしないようにすることです。
トラブルが起きたことは聴衆が分かってもいいのです。そんなことはどうでもよくて、演奏者がそこで「間違えました」と認めてしまうのは避けるべきです。
苦笑いをするのは舌を出すのと同じで、その瞬間に聴衆の立場が上になってしまいます。演奏者は、聴衆に感謝しつつも、ステージ上ではキングでいてください。
ちなみに、著名なピアニストでもしょっちゅう演奏中にトラブっていますが、みんな、本当に知らん顔して先へ進みます。少なくとも表情だけは、あたかもそういう曲であるかのように装っています。
これは初心者でもできるので、実行してください。そうすれば、たとえテクニックはそのままでも、少しステージが上がります。
‣ 35. 演奏後の立ち上がり方
演奏後に「下」を向きながら立つのは少し鬱陶しく見えます。女性の方はドレスでの足元のこともありますが、基本的には「斜め上」を向いて立つほうが見栄えはいいでしょう。
また、「立ち上がり方は曲の終わりの雰囲気に一致させる」というのが一つの演出として使えます。例えば:
・静かに余韻を聴き取るように楽曲が終わった場合はゆっくりと思案げに立つ
・勢いよく終わる楽曲は立ち上がりもスピーディに
一つの方法として参考にしてみてください。
‣ 36. ステージ脇への戻り方
アンサンブルの場合の注意点です。
共演者がいる場合は、複数人いる人物がどのような順序でステージ脇に戻ればいいのでしょうか。以下の3つが挙げられます:
1. 譜めくり者よりも先に退出する
2. ピアノ伴奏の場合は、ソロの人をたてて、ソロの人よりも後に退場する(相手の方が年下であっても)
3. 連弾や2台ピアノの場合は関係性による
最後の項目は少し判断に悩むこともあります。「プリモが先に退出する」とする例も多いようですが、「基本的には人物同士の関係性による」と考えていいでしょう。
ピアノが編成に入った室内楽の場合も同様です。オーケストラでは基本的に退場する順番が「楽器の種類」で定番化していますが、室内楽の場合は特に決まりはありません。
ポイントは、ステージに上がる時点で、すでに順序を話し合っておくことです。ステージ上でまごついている様子は観客に見せないようにしましょう。
► C. 本番後の全知識
‣ 37. 学びの機会:他の演奏から得られる貴重な洞察
自分の出番が終わったら、他の参加者の演奏を聴くようにしましょう。
「自分と同じくらい、もしくは自分より少しうまいくらいの演奏」を聴くことは学びにつながります。
プロの演奏ばかりを聴いても、それをどう表現するかが分からないと自分の演奏には反映されません。一方、「自分と同じくらい、もしくは自分より少しうまいくらいの演奏」を聴くことで、良いところも反省すべきところもはっきりと見えます。自分のレヴェルとかけ離れているわけではないので、そういったことを理解することができるのです。
もちろん、純粋に音楽を聴いて楽しむことも大事です。ピンときた方がいたら後ほどロビーなどで声をかけてみるのもいいでしょう。いい刺激を与えあえる音楽仲間ができるかもしれません。
‣ 38. 思い出作りの落とし穴:写真撮影時の注意点
全員の演奏が終わるとステージ上で写真撮影が行われることも多いと思います。このときに起こりがちな失敗は大きく2つあります:
1. 出番が終わって安心してしまい、正装を汚してしまっている
2. みんなを待たせて遅刻してしまう
自分の出番が終わっても、安心して正装のまま食事をしてしまわないようにしましょう。女性の方でドレスで出歩く方は流石にいないと思いますが、控え室などで軽食をとるだけの場合も細心の注意を払わなければいけません。
「自分の出番」から「写真撮影まで時間」が大きく開く場合は、いったん着替えておくのが得策です。最近は、写真がデジタルデータ配布されることも多く、一生残る写真になりますので、ちょっとしたシワなどにも注意したほうがいいでしょう。
また、写真撮影で遅刻していくのは最悪です。いったん着替えておいた場合も、「写真撮影はステージ衣装で行うのが原則」なので、写真撮影の5~10分前にはステージに戻れるように用意し直す必要があります。
‣ 39. タイムリーなお礼メールの重要性
終演後、「指導者」や「知り合いになった参加者」にお礼のメールを入れるケースもあるはずです。
サンキューメールは速攻送らないと意味がありません。終演後、3日もしてから送られてくると熱感が変わってしまっています。指導者自身はお礼のメールが欲しいわけではありませんが、受け取るのであればすぐに届いたほうが気持ちがいいのは確かです。
内容はシンプルでOKです。相手にとって負担にならない程度の文量で心を込めて書きましょう:
・相手に返信を促すような疑問形を使った内容は入れない
・相手から話題を出してこない限り、自分の演奏の感想を求めない
・シンプルに感謝の気持ちだけを伝える
‣ 40. オーガナイズする立場になるために
本番後、帰宅してから必ずやって欲しいのが、「会場と会場のピアノについての使用感触をメモする」ということです。
これを本番毎に積み重ねておくことで、もし今後に演奏会を「企画者としてオーガナイズする立場」になったときの会場選びに大きく役に立ちます。
ホールの中には事前にピアノを触らせてもらえないケースもありますし、控え室も事前には見せてもらえないことがあります。そこで、一参加者としての「会場と会場のピアノについての使用感触」を都度記録しておくことは大きな資料になります。
参加者の会場への不満は企画者への不満にもなりかねません。オーガナイズする立場になったら「自身の経験に基づいた情報」をもとに最善の会場を選んでいく必要があるのです。
‣ 41. 本番演奏の反省は帰宅してからにしよう
本番演奏は必ず録音しておき、帰宅してからチェックしましょう。人間は失敗してしまった箇所を気にしてしまう傾向があるので、自分の出番が終わってからすぐに録音を聴いてしまうと、会場で居合わせた方とネガティブな会話になりがちだからです。
必ず「帰宅してから」初めて聴くようにしてください。
本番の録音を忘れてしまうと、二度と来ない大事な勉強の機会を一つ失ってしまったことになるので気をつけましょう。録音を聴きながら、良かった点も反省点も踏まえて、今後の演奏にとって何を活かせるのかをじっくり考えます。
ピアノ教室に通われている方は、発表会後のレッスンは必ず先生と話す時間をとりましょう。
「10回のレッスンよりも1回の本番」などと言われることもありますが、それくらい本番の演奏経験は学習者にとって飛躍のタネなのです。その本番の内容についてレッスンで話し合うことで必ず発見があるはずです。
この際に、本番演奏の録音をしっかりと聴いておくと、会話がスムーズで先生から金言をもらえる可能性も高まります。先生との関係性にもよりますが、場合によっては、録音を持参して一緒に聴いてもらうのもいいでしょう。
‣ 42. 失敗と成功の公平な振り返り
1998年のアメリカ映画「ジョー・ブラックをよろしく」の中で、登場人物であるジョー・ブラック(ブラット・ピット)がスーザン・パリッシュ(クレア・フォーラニ)へ投げかける、以下のような発言があります。
簡潔に言うと、「君の想い出の中にいる僕は、今の僕ではないけれども、その想い出は、君しかもっていないかけがえのないものだ」というニュアンス。
このような考え方は、音楽生活の中においても言えることです。
我々はどうしても、何でもかんでも完璧主義になってしまうことが多いように感じます。例えば:
・本番中、ある一部分で失敗したので、その日の演奏はすべて良くなかったと思ってしまう
・譜読み途中に挫折したから、その楽曲へ取り組んだこと自体を完全な黒歴史にしてしまう
しかし、以下のような幸せも経験しているはずです:
・新たな作品の楽譜を開いて譜読みを始めるワクワクを感じた
・本番までの期間に新たな作品が弾けるようになったことに大きな喜びを感じた
・本番で新たなピアノに触る喜びを感じた
先ほどのジョー・ブラックの発言のように、「君があのとき見つけたのは君のもの」と思ってみるのはどうでしょうか。
自身が経験した上記のような喜びは、これまでの経験などの積んできたことをすべて踏まえたうえで感じているものなので、全く同じ経験を他者がすることはできません。しかも、その経験や想い出がなくなることはありません。喜びはずっと自分の中にしまっておけばいいと考えています。
音楽学習でも何でも、一つの上手くいかなかったことだけに目を向けてしまって、他の良かったことまで黒歴史にしない、ということを踏まえておきましょう。
・ジョー・ブラックをよろしく (字幕版)
‣ 43. 失敗した自分の許し方
筆者が10代の頃、海老名でとある本番があったのですが、見事に大失敗しました。帰りに駅へ向かう途中、随分と落ち込んだのを覚えています。しかし、今考えてみたら、本番への楽しみや期待があったからこそだと感じます。
必ずうまくいくと決まっていたら、毎日の学習の楽しみや意味が一気になくなってしまうと思いませんか。
・ガタガタになったらどうしようとか
・ここは好きなパッセージだから弾くのが楽しみだとか
・聴衆に誰々がいるから背筋を伸ばして頑張るだとか
そういった様々な感情の中で、本番へ向けて取り組む過程も含めて楽しむことが、楽器演奏の醍醐味となります。
失敗したら反省と改善は必要ですが、必要以上に自分を責めなくてもいいというのが、最近の考えです。それが甘いと思う方は、他人に結果を決められてしまう場面にばかり身を置いていないかを、一度振り返ってみてください。
‣ 44. 本番で初めて経験したミスは気にしなくていい
本番という緊張の中では、様々な演奏面におけるアクシデントが発生することは、可能性として避けられません。
まず、演奏面におけるアクシデントのうち初めて経験した “突発的な” アクシデントは、「次は気をつけよう」 と思う程度にして気にし過ぎる必要はありません。理由はシンプルで、予測できないからです。
今までの練習でアクシデントになっていたことをできる限り改善できていればいいのです。それが1回限りにならず再発してしまった場合は、理由を追求してください。
次に、ステージ回りの身のこなしや本番準備などの演奏面以外でのアクシデントは、予測できるできないに関わらず、とにかく、1回限りにしてください。こういうのは、意識さえすれば大抵再発しないからです。
昔、同じ演奏会に出ていた方が楽屋で「演奏のときに履く靴を忘れた」と騒いでいたという、笑い話のような実話があります。また、「主催であるピアノの先生を通さないで、発表会で使うピアノについて会場に探りを入れた」などといったマナー違反も時々耳にします。
このようなアクシデントというか不注意や不義理は、1回で終わらせるようにする。そうすると、みんなが幸せになりますし、演奏そのものへもっと集中できるようになります。
‣ 45. 微妙だった演奏の感想を求められたときの対処法
演奏会の後などに出演者から感想を求められることもあるでしょう。しかし、正直微妙だった場合は返事に困るはずです。決して上からものを言いたいわけではないのですが、良くあるのです。
そういったときには無理に嘘をついてお世辞を言わずに:
・「プロコ初めてじゃない?」
・「おめでとう!」
などと、演奏の評価を加えずに高めのテンションで対応するようにしましょう。
人間の会話は、誇張とかちょっとしたジョークみたいな部分がないと相当殺伐とします。だからと言って、嘘をついてまで「最高の演奏でした」なんて言えません。これは、冷たいのではなく、誰でもそうすることには抵抗があるはずです。だからこそ、演奏の評価を加えずに盛り上げてください。
それでももし、突っ込んで演奏の感想をきかれたら:
・「えっ、カッコ良かったよ」などと、個別の部分には触れないようにしたり
・「今日はみんなすごかったから」などと全体評価をする
このように対応すればOKです。
こういったときに、間違ってでも良くなかったところを指摘しないことが重要です。
おそらく、感想をきいてくる方の90%以上は、褒めて欲しいのです。アドヴァイスと思って何かを言っても、それはただのマウンティングになってしまいます。
その代わり、次にその相手が本当に良い演奏をしたときには、心の底から良かったということを伝えましょう。
► D. 音楽家の知恵袋:追加のヒント
‣ 46. コンクールで予選を2回受けられるのは良い制度
パリオリンピック2024では、初戦で敗退してしまいながらも、とある条件から3位決定戦へ進めることになり銅メダルを獲得した日本人選手が話題となりました。
この話題を耳にして真っ先に思い出したのが、日本でとても知られているピアノコンクールにおける、予選を2回まで受けられる制度です。
予選で1回失敗してしまいながらも、もう1回の予選を通過し、その後のラウンドも通過して全国大会ファイナルで上位入賞した知り合いがいます。上手くいかなかった予選では「エチュードを失敗しちゃった」と言っていましたが、ファイナルで上位入賞できる力があっても、ちょっと調子が合わないと予選で上手くいかないこともあるのです。
もちろん、ファイナルで2回のチャンスがある必要はありませんが、一番はじめの予選で2回のチャンスがあるのは、筆者は良い制度だと思っており、そういったコンクールがさらに増えてもいいと考えています。
ただし、この制度をつくる前提条件として「参加者が相当多いコンクールでないと設けられない」という、予選通過者の人数や予算的な部分からくる現実もあります。その代わりではありませんが、比較的新設のコンクールの中には:
・実演審査
・動画審査
というの2つの予選チャンスが用意されているものもあり、ここ近年は特にコンテスタントにとって幅広い可能性があるのは確かでしょう。
‣ 47. 得意なレパートリーをもっと得意にする方法
すでに得意なレパートリーをもっと得意にする方法があります。
その作品を、その作品ではまだ経験したことがないもっと緊張する場へ持っていってみてください。
例えば、不特定多数の人に聴かれるのに弱い方はストリートピアノで弾いてもいいですし、コンクールのような順位のつくような場をあえて利用してみるのでもいいでしょう。
・その作品ではまだ経験したことのない緊張する場を通してみる
・それを録音&チェックして学習する
この積み重ねで、さらに得意なレパートリーになります。あらゆる高い緊張感に慣れるうえ、「不慣れな場での録音」という最高の教材を使って、さらに演奏をブラッシュアップできるからです。
仮に緊張し過ぎて失敗しても何の問題もありません。それがきっかけで演奏が下手になるわけではありませんので。
本当に得意な作品というのは、ただ単に上手く弾ける作品というだけでなく、あらゆる場を一緒に過ごした作品のことです。何かを失うと思わずに、どんどん、緊張する場へ持っていきましょう。
‣ 48. なぜ、本番機会の多い人は上達するのか
本番機会の多い学習者には、上手な方が比較的多いと思いませんか。また、あまり舞台に出る経験をしていなかった学習者が本番の数を増やしたらいきなり伸びたりする例も、目の当たりにしてきています。
「100回のレッスンよりも、数回の本番から得られるもののほうが多い」などと言われることがあります。
では、この「得られるもの」とは何なのでしょうか。
例えば、以下のようなものだと考えています:
・人前に立つ緊張感が当たり前になること
・初めて触るピアノの数が増えること
・本番に迫られて、必ず練習する習慣がつくこと
・競争心が芽生えること
これらはどれも、一人で自宅でさらっているだけでは経験できません。こういったことが自分の中に浸透していった結果、あるタイミングで力が伸びるのです。特に、本番で力を発揮できる確率が飛躍的に上がります。
ある根本的な課題を克服したいときには、一時的に舞台から遠ざかるほうが効果的な場合もあります。しかし、今までの自分では考えられなかったほどの多くの本番を経験してみる時期を作るのも、飛躍のためには絶対に欠かせません。
自身の状況と照らし合わせて、もし、「今は舞台を経験するべき時期だ」と思ったならば、意識的に本番の数を増やしてみるのも選択肢の一つです。
► 終わりに
ピアノ演奏における本番は、自己成長の機会であり、音楽を表現する瞬間です。失敗を恐れず、ステージを踏む機会を大切にしましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
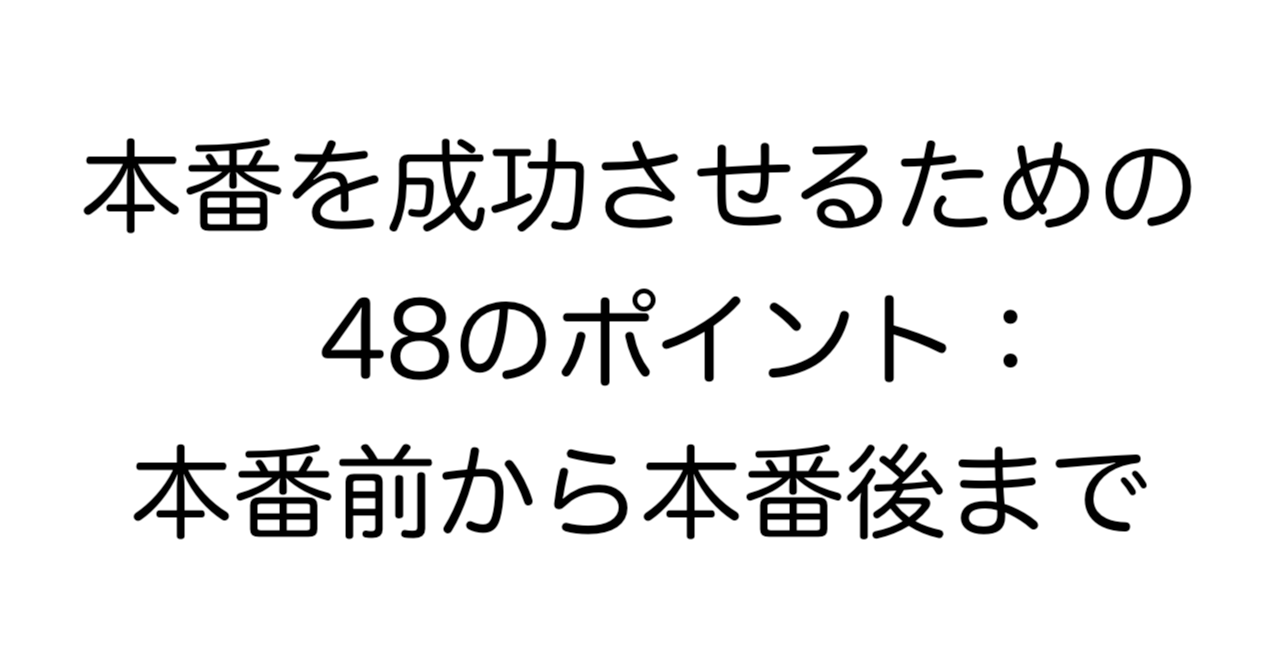


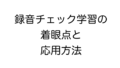
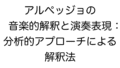
コメント