【ピアノ】2週間で学ぶ「ピアノ音楽史事典」活用ロードマップ:効率的な音楽史入門法
► はじめに:本記事の対象者
本記事の対象者(どれか一つでも当てはまれば対象です):
・ピアノ音楽史を学ぶべきだと、とうとう観念した方
・浅過ぎない、難し過ぎない入門を希望している方
・「ピアノ音楽史事典(千蔵八郎 著)」を持っている、もしくは購入予定の方
・こちらの記事で、ピアノ音楽史における43ページの要点学習を済ませた方
・他の書籍でも応用できる学習方法を知りたい方
ピアノ音楽史の学習については、ピアノを学習していくうえで重要だと分かっていながらも、中々腰が上がらないのではないでしょうか。
ピアノ音楽史を深く学んでいくための前提的な部分を押さえるための良いアプローチとして紹介したのが、上記の記事でした。その記事では「最新ピアノ講座」解釈シリーズの中に含まれるわずか43ページのピアノ音楽史の解説を使って基礎を学ぶ方法を紹介しました。しかし、この学習方法が合わない方や、更に一歩進んで学習したいという方もいることでしょう。そこで本記事では、「ピアノ音楽史事典」を中心に良質な学習を進めるヒントをまとめました。
► 具体的な進め方
‣ 一日一章ずつ
序章と終章を合わせると「全11章」なので、一日一章ずつ学習するペースで進めていくと、2週間程度で一巡できます。
ハードスケジュールに感じるかも知れませんが、後述するように、間引くポイントがあるので、1日1-2時間程度を確保出来れば学習可能です。
全674ページと厚い書籍ですが、意外とあっさり一巡出来るので、安心してください。
‣ 進め方と間引くポイント
まず、その日に取り組む章を開き、はじめに書かれているその時代の特徴などを正確に理解してください。その後に作曲家別の解説が続きますが、以下のように取り組んでみましょう:
・作曲家の概略を読む
・作品分野の特徴を読む(「この作曲家のソナタの特徴」など)
・具体的な作品は、一人の作曲家につき3曲聴く
具体的な作品の解説が意外とページ数をとっているだけで、その部分を間引きながら読むと、一日一章ずつも意外と容易です。
一人の作曲家につき、掲載曲を3曲聴き、その作品の解説部分は読んでください。出来る限り知らない作品をピックアップするようにします。作曲家によっては3曲以下の作品数しか解説されていないので、その場合は全曲聴いてください。
机上の座学で終わらせないためにも、この「耳から学ぶ」という過程を絶対にすっ飛ばさないようにしましょう。
‣ 最後まで学習できたら
一日一章ずつ進めると、2週間程度でひととおりの学習が終了します。最後まで学習できたら、アンダーラインを引いたところを中心に復習しながら、まだ聴いていない残りの作品を聴き、解説を読んでいきましょう。この場合にも、「一人の作曲家につき、追加で3曲」などと基準を決めておくといいでしょう。作曲家によっては膨大な作品が解説されているからです。
一度最後まで読了出来ていると、気持ち的に余裕があって、こういった追加学習を気持ち良く進められるでしょう。
►「ピアノ音楽史事典」を使った学習の注意点
難しい書籍の場合は、読み方に完璧主義になると挫折の原因になります。しかし、この書籍はピアノ音楽史の基礎を扱っており、内容自体は決して高度ではありませんし、文体もとても読みやすいものです。したがって、一つ一つの登場する用語についていちいち調べながら先へ進んだほうが、結果的に良い基礎学習が出来ます。
例えば、「この傾向はギャラント・スタイルと平行しながら〜」などと書かれていて、「ギャラント・スタイル」の意味が怪しかったら、分からないまま先へ進まないようにしましょう。
また、この書籍の「まえがき」は必ず読んで下さい。 音楽史学習で捉えるべき5つの重要な要素について解説されている他、本編の扱い方についても解説されています。
► さらに学びたい方のための追加教材
‣「ピアノ音楽史事典」内容をざっとまとめて理解し直す教材
最新ピアノ講座(7)(8)
同じ著者によるピアノ音楽史の解説が、43ページに凝縮されて解説されています。本来は「ピアノ音楽史事典」よりも先にファーストステップとして学習すべき内容ですが、事典で学習した内容をざっとまとめて理解し直すようなつもりで通読するといいでしょう。同じ著者による内容なので、整合性を保ったまま学習出来ます。
・最新ピアノ講座(7) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ / 音楽之友社
・最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ / 音楽之友社
‣ 翻訳書も取り入れながら、さらに豊富な知識を得たい方
ピアノ音楽史について書かれた翻訳書はいくつかありますが、以下の2冊は内容がまとまっており、特におすすめ出来ます。
・ピアノ音楽史 著 : ウィリ・アーペル 訳 : 服部幸三 / 音楽之友社
・鍵盤音楽の歴史 著 : F.E.カービー 訳 : 千蔵八郎 / 全音楽譜出版社
これらの書籍に関しては以下の記事で解説していますので、あわせて参考にしてください:
· 9-1 ピアノ音楽史 著 : ウィリ・アーペル 訳 : 服部幸三 / 音楽之友社
· 9-2 鍵盤音楽の歴史 著 : F.E.カービー 訳 : 千蔵八郎 / 全音楽譜出版
► 終わりに
ピアノ音楽史の学習もピアノ練習と同じく基礎が重要です。いきなり難し過ぎる書籍や論文などに手を伸ばすのではなく、本記事を参考に土台を固めることから始めましょう。
正直、ピアノ音楽史事典の内容をしっかりと理解するだけでもかなり知識が高まり、ピアノ音楽を新たな視点で眺めることが出来るようになるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
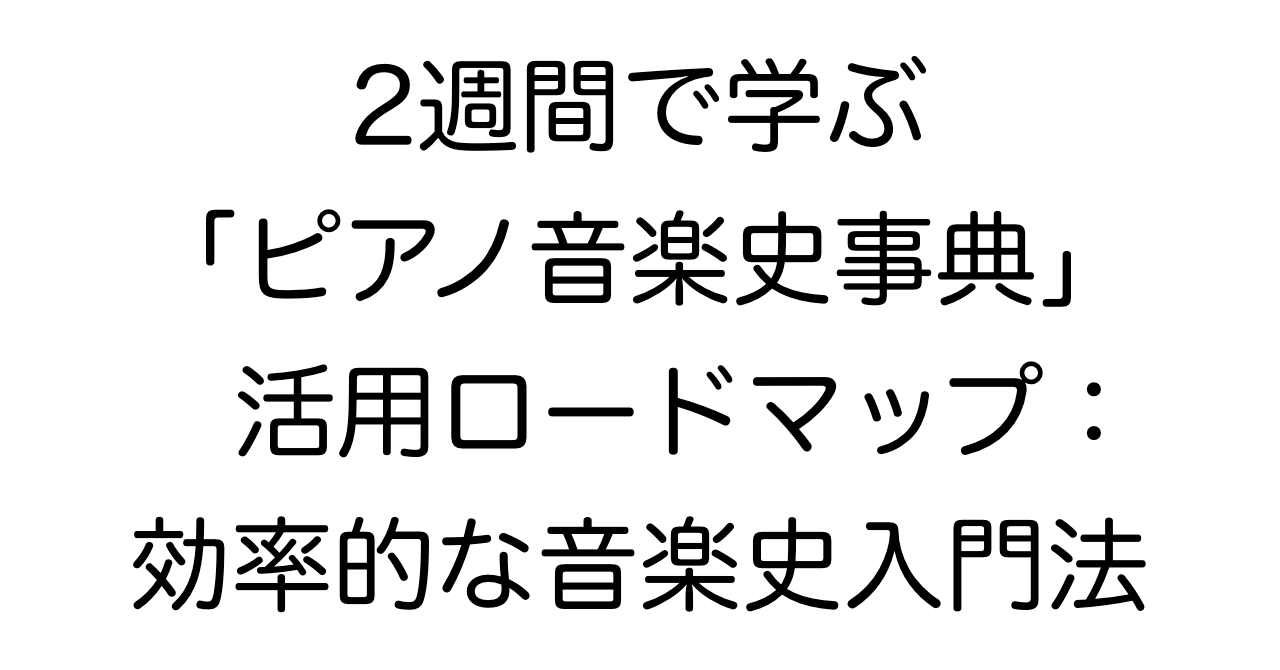


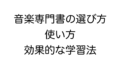
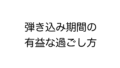
コメント