【ピアノ】43ページの要点学習とピアノ音楽史事典を併用した体系的音楽史学習法
► はじめに
ピアノ音楽史の学習において、多くの方が以下のような課題を抱えています:
・音楽史の参考書の選び方が分からない
・知識を体系的に整理する方法が分からない
本記事では、「最新ピアノ講座」シリーズにおける千蔵八郎氏(1923-2010)によるピアノ音楽史部分(合計43ページ)を基礎とし、同じ著者による「ピアノ音楽史事典」で補完する学習法を提案します。同一著者によるこれら2つの資料を組み合わせることで、整合性のとれた体系的な音楽史学習が可能になります。
► 推奨書籍の特徴と概要
‣ 基礎学習用の書籍:最新ピアノ講座(7)(8)
これらは本来、演奏解釈のための参考書ですが、千蔵八郎氏による音楽史の要点がコンパクトにまとめられています。全てのピアノ音楽史部分を合わせても43ページと非常にコンパクトで、必要最低限の知識を効率よく学べます。
・最新ピアノ講座(7) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ / 音楽之友社
・最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ / 音楽之友社
‣ 補完・発展学習用の書籍:ピアノ音楽史事典
総ページ数:674ページ
初版:1996年
特徴:時代背景の解説と個別作品解説の両方を網羅
構成:序章から第9章までの時代順構成、終章で現代ピアノ音楽の考察
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
► 段階的学習プラン
‣ ステップ1:基礎知識の習得(43ページ学習)
時代順の通読:
・最新ピアノ講座(7)(8)の音楽史部分を連続して読む
・各時代の主要な特徴、作曲家、作品をチェック
時代別の整理:
以下の流れで各時代の特徴を把握する
・バロック期:チェンバロからピアノへの移行期
・古典派:ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの様式的特徴
・ロマン派:性格的小品の発展、ショパン、シューマン、ブラームスの重要性
・近現代:国民楽派、印象派、新古典主義の流れ
演奏解釈との連携:
・各時代の音楽史を学んだ後、対応する演奏解釈の章を読む
・自分のレパートリーに関連する作品を重点的に学習
このステップ1の段階から様々な作品の名前が挙がってくるので、必要に応じて「ピアノ音楽史事典」で調べて補足情報を入れましょう。「ピアノ音楽史事典」は、とにかく出したままにしておくことが稼働率を上げるコツです。
‣ ステップ2:「ピアノ音楽史事典」による知識の拡充
最新ピアノ講座で基礎を固めた後、ピアノ音楽史事典をさらに活用して知識を深めます:
作曲家別の深掘り:
・興味を持った作曲家について事典の該当箇所を参照
・生涯と作品の傾向をより幅広く理解
作品知識の拡大:
・自分のレパートリーに含まれる作品の解説を読む
・同じ作曲家の他の作品もガンガン調べて視野を広げる
レファレンス的使用:
・演奏会やCDを聴く前に、関連作品の解説をチェック
・未知の作品との出会いのきっかけとして活用
► 終わりに
「最新ピアノ講座」の43ページのピアノ音楽史概説と「ピアノ音楽史事典」を併用することで、効率的かつ体系的な音楽史学習が可能になります。この方法の利点は:
・同一著者による資料を用いることで、情報の整合性が高い
・短時間で基礎的な全体像を把握した後、必要に応じて詳細を学べる
・短時間で一旦一通りのことが把握出来るので、「進んでいる感」「充実感」がある
・演奏解釈に直結する形で音楽史を学べる
・個人の興味やレパートリーに合わせて学習を深められる
何と言っても、「同一著者による資料の併用」というのは、学習における大きなメリットです。事典で調べた内容を43ページのピアノ音楽史概説部分にガンガン書き込みながら、両書をリンクさせつつ学習を進めてみましょう。
各書籍についてもっと詳しく知りたい方は、以下のレビュー記事を参考にしてください:
・【ピアノ】「最新ピアノ講座」演奏解釈シリーズのレビュー
・【ピアノ】「ピアノ音楽史事典」(千蔵八郎 著)レビュー
・最新ピアノ講座(7) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ / 音楽之友社
・最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ / 音楽之友社
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこち
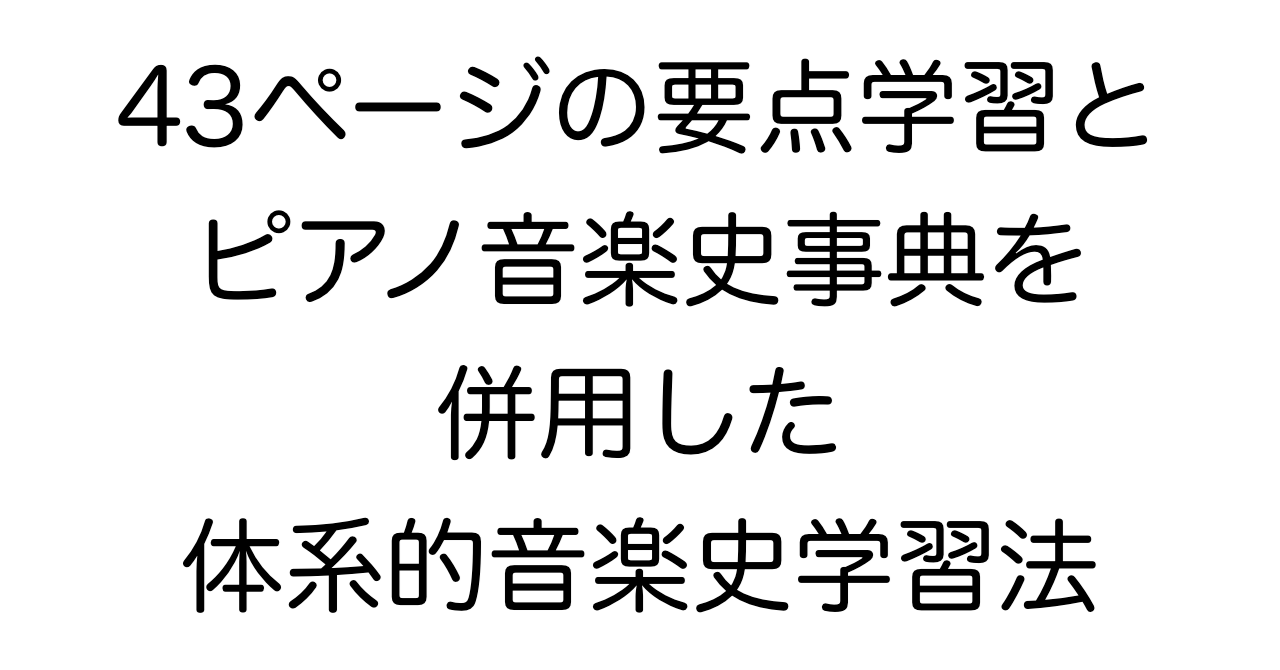



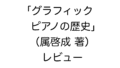
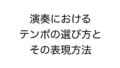
コメント