【ピアノ】難易度表記との付き合い方:表記の問題点と効果的な活用方法
► はじめに
ピアノを学ぶ際、「この曲は自分に弾けるだろうか?」という疑問は誰もが持つものです。楽譜や教材に付けられた難易度表記は、そんな疑問に答える重要な指標として活用されています。
しかし、難易度表記には様々な課題があるのも事実です。出版社によって基準が異なったり、ジャンルによって「上級」の意味が変わったりと、学習者にとって混乱の元となることも少なくありません。
本記事では、ピアノの難易度表記が抱える問題点と、それらとの上手な付き合い方について、実体験を交えながら解説します。難易度表記を理解し、効果的に活用することで、より充実したピアノ学習を進めていきましょう。
► 難易度づけの難しさ
選曲をする際に難易度の目安を参考にすることは多いと思います。本Webメディアでも楽曲紹介系の記事では難易度も併記するようにしていますが、その都度、難易度づけの難しさを痛感しています。
「初級・中級・上級」と言っても幅がありますし、単にメカニック面のことだけで判断するのかなど、複雑な要素が絡み合っているからです。
本Webメディアで使用している学習レベルの目安:
初級:バイエル修了~程度
初中級:ツェルニー30番入門~程度
中級:ツェルニー40番中盤~程度
上級:ツェルニー50番中盤~程度
難易度づけで重視している観点
表現面も難しさの要素ですが、読者の方が知りたいのはおそらく次の点でしょう:
・概ね弾けるまでに必要な時間の推測
・そもそも取り組めそうなのか
したがって、筆者自身はこの視点を重視して難易度づけをしています。
もし表現や楽曲のコンセプトの理解まで難易度の指標に含めてしまうのであれば、全音ピアノピースで難易度Cに分類されているサティ「3つのジムノペディ 第1番」は、最難関曲に分類せざるを得ない状況になるでしょう。
► 難易度との付き合い方
‣ ジャンルによって異なる「上級」という難易度ワード
クラシックの場合
クラシック分野での難易度というと、何と言っても全音ピアノピースの難易度分類が知られています。ショパンの作品はシンプルなものでも難しめに難易度が付けられている傾向があったり、古くから話題になりがちな「ラ・カンパネラが難易度Eなのはなぜか」という興味深い点はありますが、基本的にこの難易度表は学習者が参考にしても問題ない信頼できる指標になるものです。
ポピュラーピアノの場合
ポピュラーピアノの分野になると、難易度はあってないようなもので、クラシック以上に出版社によって難易度表記のギャップが大きくなります。
初級はクラシックでもポピュラーでも初級なのですが、問題は「上級」です。とある出版物では、ツェルニー30番中盤程度で上級に分類されています。さらに、ただ「上級」とだけ書いてあることが多く、その内容は楽譜を見て判断するしかありません。
ポピュラーピアノで難易度を判断するコツ
・実際に楽譜のサンプルを見てみる
・「ツェルニー30番中盤程度」などと具体的な表記があるものを参考にする
このように、楽曲比較で考えるのがベターです。
‣ 書籍やピアノ曲事典の中には難易度表記があるものも
以下のものを複数所持し、比較しながら使用するのもおすすめです。
新訂 ピアノの学習 著:長岡敏夫 / 音楽之友社
15段階の難易度を示した、百科事典的な一冊です。テクニックだけでなく「芸術的な密度」も考慮した難易度評価が特徴です。
ピアノ・レパートリー事典 著:高橋淳 / 春秋社
作品別の難易度を15段階のグレードで示しています。豊富な楽曲データベースとして活用できます。
最新ピアノ講座(5) ピアノ実技指導法 / 音楽之友社
第3章「15段階によるピアノの学習」では、初級(E)、中級(M)、上級(H)それぞれ5段階ずつの詳細な学習プログラムを提示。各レベルでの具体的な指導方針が明確に示されており、特に指導者にとって実用性の高い内容となっています。
ピアノ学習ハンドブック 著:千蔵八郎 / 春秋社
以下の教材についての詳細な情報が掲載されています:
・教則本30種
・エチュード58種
・曲集67種
・J.S.バッハ「インヴェンションとシンフォニア」の版23種
各教材について「どれくらいの学習段階で使用するものなのか」が明記されているため、自分の現在のレベルに適した教材を知ることができます。他のピアノ曲事典であまり取り上げられていない教則本やエチュード系の情報が充実しているのが特徴です。
► 初級者の多さの再認識による考えの変化
‣ 初級者の多さという現実
どんな習い事でもそうですが、ピアノに関しても一番多いのは初級者の方です。理由として以下が挙げられます。
・始める方、始めたい方、再開したい方が多い
・初級段階で辞めてしまう方も多く、再開したときは初級段階からスタート
筆者自身、ソナチネアルバムを弾いていたときに先生が変わったのですが、初めてコンタクトを取ったときに「今まで習っていたのはバイエルですか?」と言われたのを今でも覚えています。「ソナチネアルバム1です。」と答えると、「ごめんなさい、よその教室からうちに来る生徒はバイエルをやっているケースが多くて。」と返ってきました。
上級者しかレッスンしない指導者も時々いますが、基本的には、初級層の多さはどんな時代でもどんな地域でも共通なのです。本Webメディアの記事も、一番読んでいただいているのは、やはり初級者用の記事です。
そのため、一般的に初中級あたりに分類される「ツェルニー30番」を弾いているというと、かなり続けていて上達したイメージを持たれるのです。
‣ 筆者自身の考え方の変遷
筆者自身は、以前は難易度づけを否定していました。表現と切り離して音楽的でないように感じていたからです。しかし、本Webメディアの運営を始めてから、初級者の多さを改めて実感し、読者の方にとって使いやすい記事とは何かを考えました。その結果、「難易度」は必要だと考えが変わりました。
毎日たくさんやることがある方がピアノを練習するにあたって、以下を知りたいのは当然です。
・概ね弾けるまでに必要な時間の推測
・そもそも取り組めそうなのか
また、筆者自身も、難易度表を眺めては次に何を弾こうかワクワクしていた学習初期の時代があり、それがあったからこそ楽しくピアノを続けられたとも思っています。
► 終わりに
難易度表記には完璧な基準は存在しません。しかし、それぞれの特徴を理解し、複数の情報源を参考にすることで、より適切な選曲が可能になります。
重要なのは、難易度表記を参考にしつつも縛られ過ぎず、自分の現在のレベルと目標を見据えながら、楽しく学習を継続することです。時には少し背伸びをした曲に挑戦することで、新たな成長を感じられるかもしれません。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
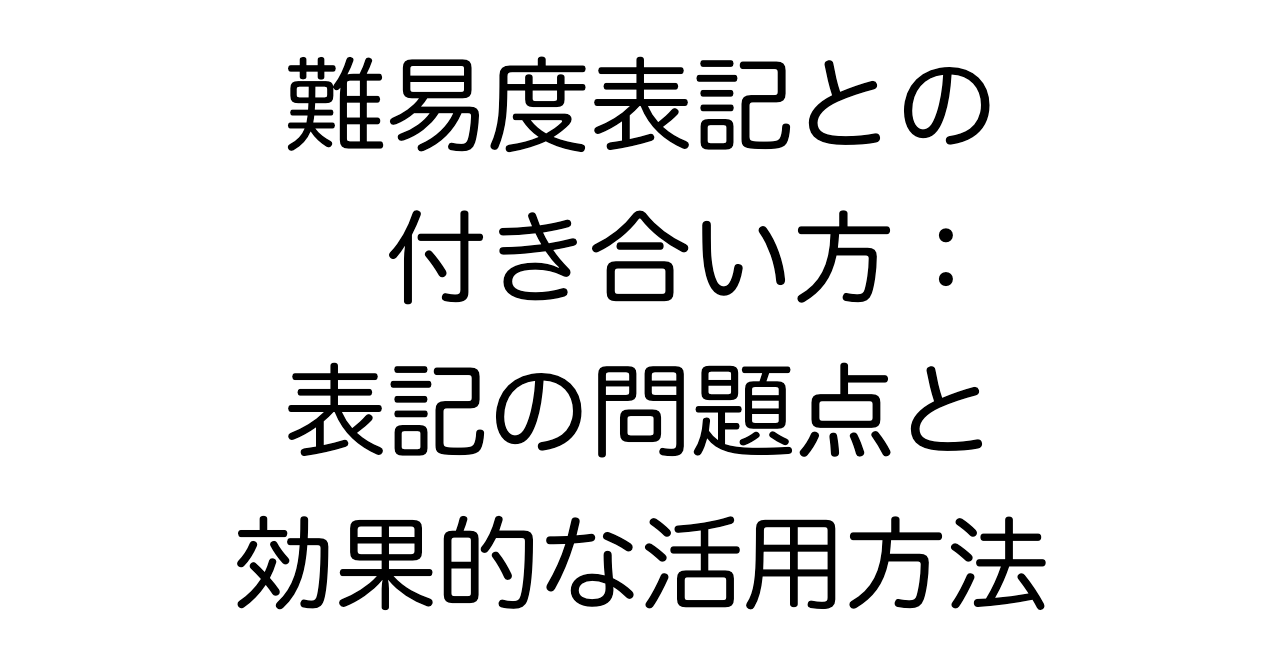
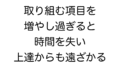
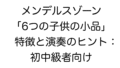
コメント