【ピアノ】映画「敬愛なるベートーヴェン」レビュー:音楽的魅力と楽曲演出の分析
► はじめに
「敬愛なるベートーヴェン(Copying Beethoven)」は、ベートーヴェンの晩年に焦点を当て、架空のコピスト(写譜師:作曲家が書いた楽譜を浄書する)であるアンナとの交流を通して、天才作曲家の内面世界と第九交響曲誕生の裏側を描いた作品です。
本記事では、特に音楽の使われ方に注目し、ベートーヴェンの楽曲がどのように物語と融合しているのか、また映画全体の音楽的構造について掘り下げていきます。
・製作国:イギリス、ハンガリー
・公開年:2006年(カナダ)/ 2006年(日本)
・監督:アニエスカ・ホランド
・ピアノ関連度:★★☆☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。本記事では、曲名は一部俗称を用いています。
‣ 本編で使用されるピアノ曲
物語自体は第九交響曲が軸になっているのでピアノ曲自体はそれほど多く出てきませんが、ベートーヴェンとアンナの会話の中で様々なピアノ音楽の話題が出る他、以下のようなピアノ曲は実際に使われます:
・ピアノソナタ 第5番 Op.10-1 第3楽章
・ピアノソナタ 第32番 Op.111 第2楽章
・ディアベッリのワルツの主題による33の変奏曲 Op.120
・エリーゼのために
ピアノ曲も含め、本映画の中で使用された楽曲の一覧や演奏者情報は、エンドクレジットに表示されているので、興味のある方は確認してみてください。
‣ 音楽演出の卓越した使い方
‣ 息を引き取るシーンの音声
物語のはじめに、まずベートーヴェンの死去のシーンを描き、過去に遡るようにして物語がスタートします。この息を引き取るシーンに一切音楽は無く、「鳥の声」という自然音のみを背景音とした中で息を引き取るのが印象的です。これは本編中でベートーヴェンが「音楽において、無音における間(ま)が重要」だと発言したこととリンクしていると考えていいでしょう。
‣ 完成前の第九の効果的な使用
初演前に何度も流れる第九の意味:
第九の初演を4日後に控えたベートーべンのもとに、コピストのアンナがやってきて写譜をしますが、その段階で、写譜中の第九の第4楽章がBGMとして何度も使われます。これは、初演前の「未来の音楽」であり、初演前に何度も流れる第九というのは、「理想、夢」の象徴と考えられます。音楽をただの背景音楽として使うのではなく、物語のテーマと結びつけています。
状況を表現した第九:
写譜シーンでは、第九の第4楽章が以下のような状況とともに効果的にBGMとして使用されます:
・851小節目からのPresto部分の急速なBGMが、本番が迫った写譜の忙しさを表現
・916小節目からのMaestoso部分の緩やかなBGMが、ベートーヴェンが睡魔に襲われているのを表現
このように、楽曲の持つテンポや印象を活用して、登場人物の心理状態や場面の緊張感を描き出しています。それも、第九を使ってそれを表現していることには着目すべきでしょう。
目的地へ導く状況内音楽:
アンナが初めてベートーヴェンの自宅へ行く際、その集合住宅の階段を登り始めます。「状況内音楽」(ストーリー内で実際にその場で流れている音楽)として、上階の方からベートーヴェンがピアノを弾きながら歌う第九の第4楽章の一部が聴こえてきます。しかし、この時点でアンナは受け取っていた原稿の一部を写譜済みであり、楽曲を知っていました。知っている楽曲に導かれるように階段を上がって行くこのシーンは、「目的地へ導く状況内音楽」の見事な活用例と言えるでしょう。
音楽が物語を進行させる重要な役割を担っているのです。この演出は、アンナがベートーヴェンの音楽世界へと足を踏み入れるという象徴的な意味合いも持っているようにも感じます。
‣ 音楽史的視点から見た留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているベートーヴェンの音楽史の内容と異なる点もあります。例えば、アンナという女性コピストの存在自体がフィクションであり、実際のベートーヴェンの第九交響曲初演の準備過程とは異なります。しかし、これらの脚色は芸術作品としての映画の魅力を高めるためのものです。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。
► 終わりに
映画の中でベートーヴェンが語る「音楽家は神に最も近い存在だ」という言葉が象徴するように、本作は伝記映画を超えて、芸術創造の本質に迫る問いかけも含んでいます。また、アンナとの関係性を通して、創作の孤独と協働の喜びという相反する感情も表現されており、伝記映画を超えた深みを持つ作品となっています。
ベートーヴェンを描いた他の映画作品についても本Webメディアではレビューしています。それぞれの描き方の違いを比較することで、より深い鑑賞体験が得られるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
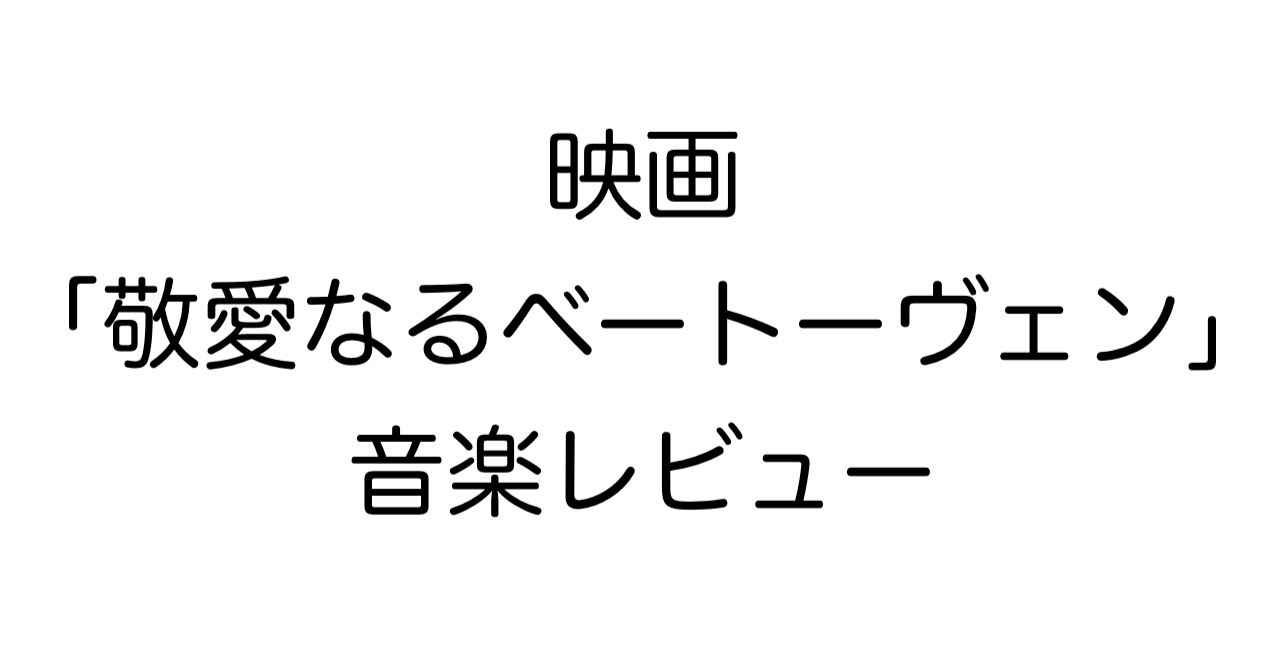
![敬愛なるベートーベン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uj8WYQHAL._SL160_.jpg)
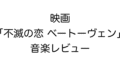
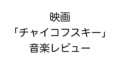
コメント