【ピアノ】映画「ショパン 愛と哀しみの旋律」レビュー:ピアノ曲の使われ方と伏線表現
► はじめに
ショパンの生涯と音楽を描いた映画「ショパン 愛と哀しみの旋律(Chopin. Pragnienie miłości)」は、ただの伝記映画ではなく、彼の楽曲がどのように物語と感情を表現するために使われているかを体験できる作品です。
本記事では、「ピアノ曲の使われ方」と「伏線表現」に焦点を当て、音楽的視点から作品の魅力を掘り下げていきます。
・公開年:2002年(ポーランド)/ 2011年(日本)
・監督:イェジ・アントチャク
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 場面で統一された音楽設定
·「転換音楽」のような位置付けのエチュード
本映画では、ある程度場面で統一された音楽設定になっています。例えば、屋外を大きく移動するシーンでは、ショパンのエチュードが流れます:
・エチュード Op.25-11 木枯らし(オープニング音楽を兼ねる)
・エチュード Op.25-6
・エチュード Op.25-1 エオリアンハープ
・エチュード Op.10-4
・エチュード Op.10-6
楽曲が短く使われて切り取られて終わるので、中には疑問に思う方もいるかも知れませんが、これは、一種の「転換音楽(場面と場面の繋ぎを担う音楽)」のような位置付けだと考えるといいでしょう。
· ジョルジュ・サンドのテーマ
「ワルツ(遺作) イ短調 KK.IVb-11」は、ジョルジュ・サンドのテーマと言っても過言ではありません。何度も使われるのですが、この楽曲が流れる時は、必ずジョルジュ・サンドが関連している場面となっているのです。これも、場面で統一された音楽設定と言えるでしょう。
また、このワルツは本来ピアノソロで演奏されますが、本映画ではオーケストラによる伴奏が付けられたアレンジで使われます。本映画ではソロ演奏をしている楽曲が多く出てくることもあり、オーケストラによる伴奏が付けられたことでBGM感が少し高まっていることに着目しましょう。オーケストレーター名や演奏者名は、映画中のクレジットに記載されています。
‣ 音声による「伏線」の表現
· 伏線とは
伏線とは「その後に起こることを予めほのめかしておく手法」であり、「映像表現+”音”の表現」として伏線をはることもできれば、「音楽表現(純粋な音楽)」として示すこともできます。
· 本映画で見られる伏線表現
マヨルカ島での一場面で大きな「雷」が鳴りますが、これは後に起こることの伏線となっています。そのすぐ後に、ショパンの身に以下のようなことが起こりました:
・悪夢を見る
・進行の速い肺結核が見つかる
・別荘の立ち退き命令をされる
・崖から落ちそうになる
また、別の場面では、「ピアノの弦が切れたような不吉な音」がして、そのすぐ後に、ショパンとサンドとの大喧嘩がありました。この不吉な音も伏線です。
本映画では、「映像表現+”音”の表現」としては以上のような伏線を確認できました。一方、オープニング音楽から不吉な「エチュード Op.25-11 木枯らし」が流れていたことにも伏線を感じます。この音楽自体が「音楽表現(純粋な音楽)」としての伏線であり、全体的に暗い印象でまとめられた映画本編に対する暗示だったのでしょう。
‣ 鑑賞上の留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているショパンの音楽史の内容と異なる点もあります。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。また、本映画には感情表現が激しいシーンや緊張感のある場面が含まれているので、その点もご承知おきください。
本映画の中で使用された楽曲の一覧や演奏者情報は、エンドクレジットに表示されているので、興味のある方は確認してみてください。
► 終わりに
ショパンの生涯を描いた本作は、ピアノ曲の使い方において興味深い工夫がなされています。特に、エチュードを場面転換に挿入する手法や、特定の曲をキャラクターのテーマとして一貫して使う手法は、音楽と物語を効果的に結びつけています。
本作の魅力はショパンの伝記的側面だけでなく、彼の音楽が映画の演出とどのように融合しているかを体験できる点にあります。音楽史との相違点や一部の劇的な脚色はあるものの、ショパンの音楽の魅力を再認識させてくれる作品と言えるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
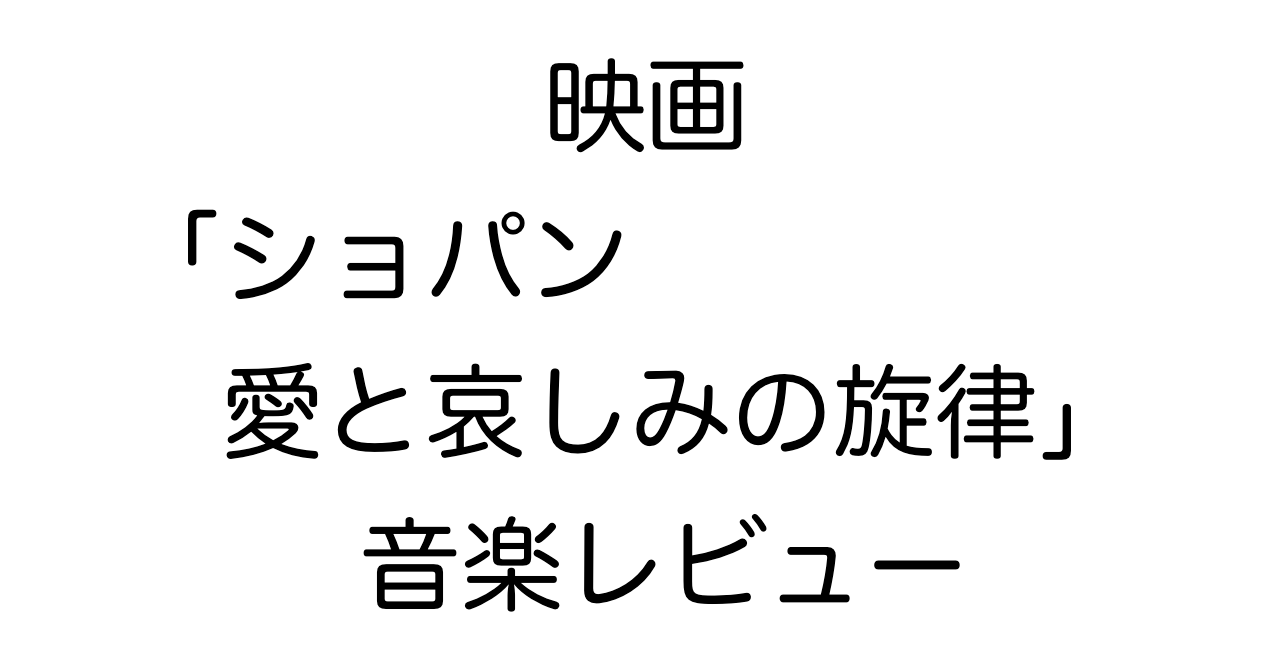
![ショパン 愛と哀しみの旋律 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ttEAlSvcL._SL160_.jpg)
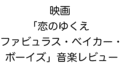
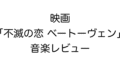
コメント